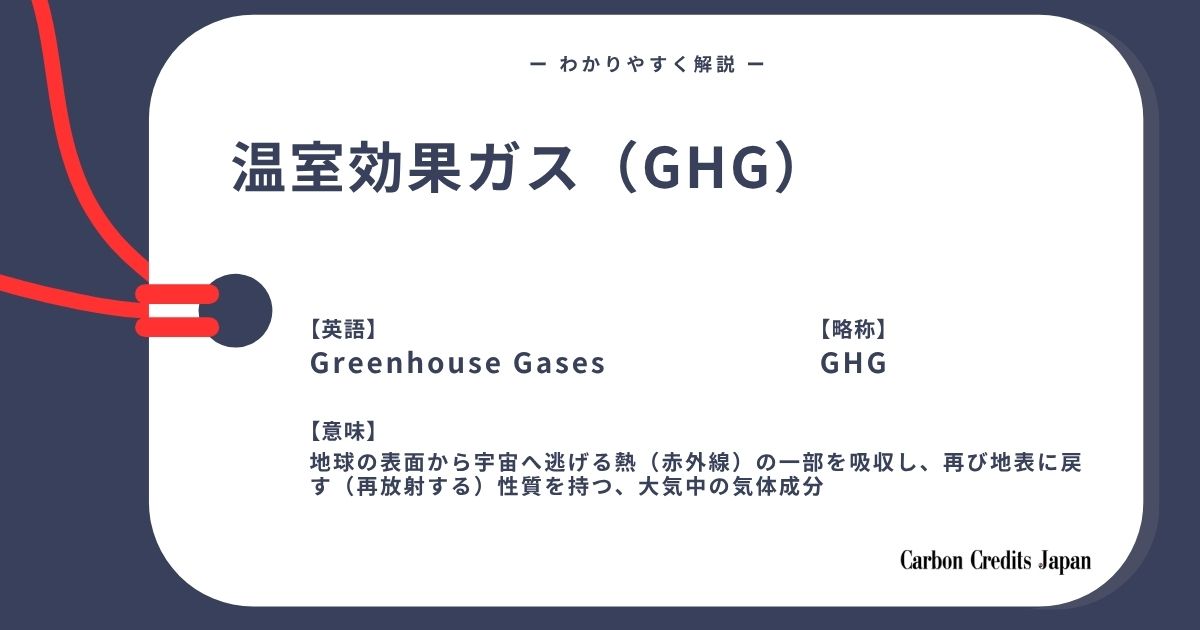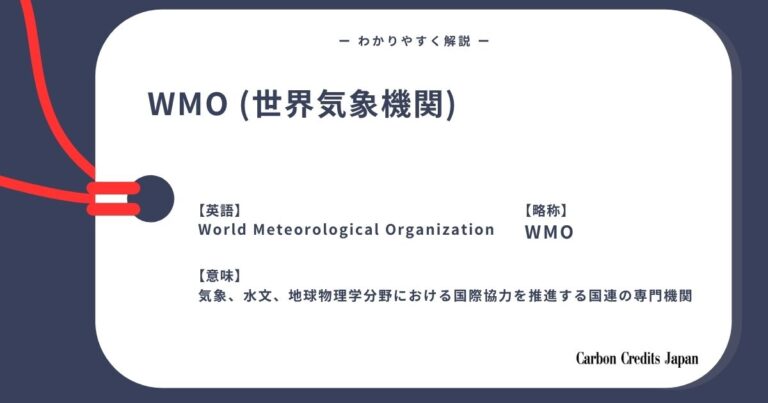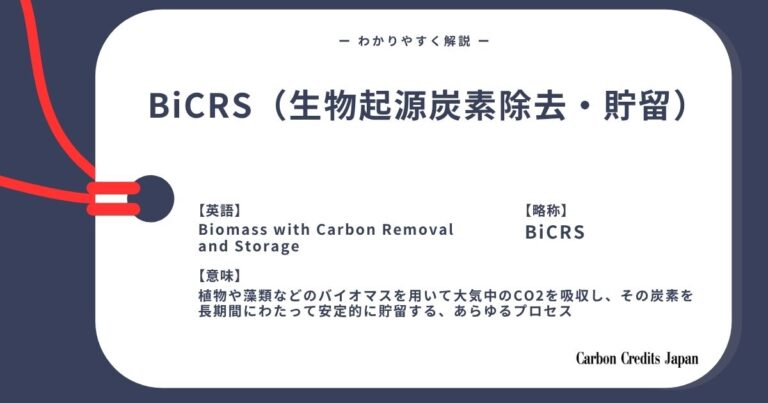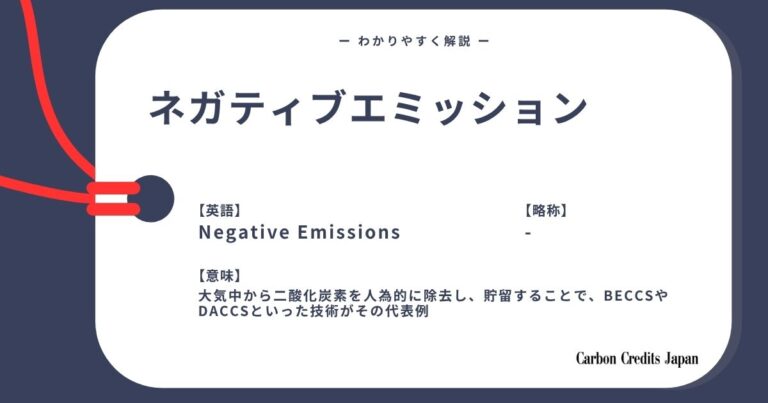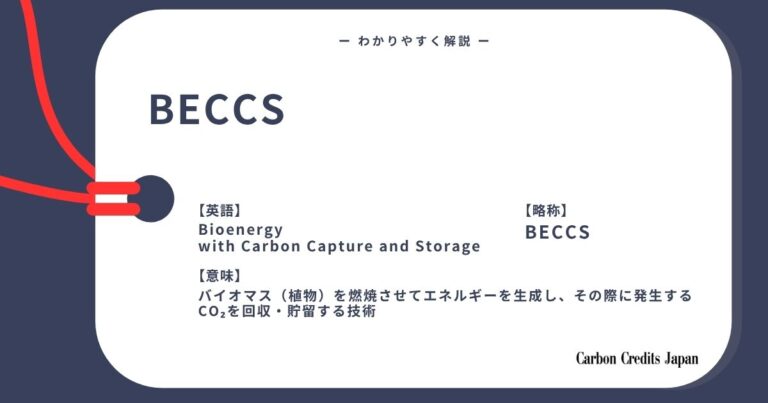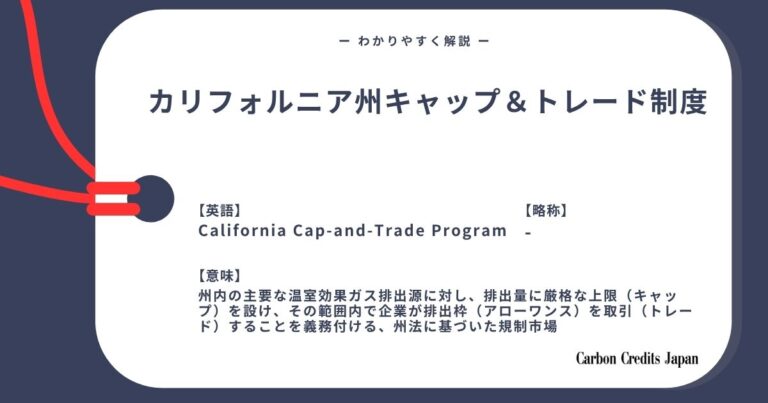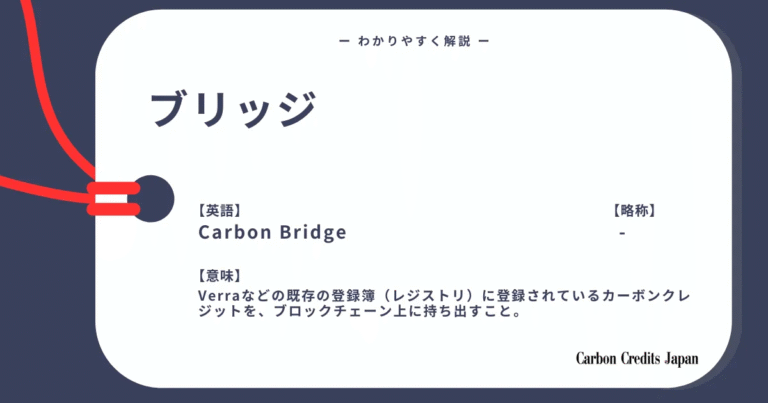地球が生命にとって快適な温度に保たれているのは、大気中に存在する温室効果ガスが、地球を包む「透明な毛布」のような役割を果たしているためである。しかし、人間活動によってこの毛布が必要以上に厚くなり、地球が過剰に暖められてしまう。これが、地球温暖化の基本的なメカニズムである。
本稿では、全ての気候変動の議論の出発点である「温室効果ガス(Greenhouse Gas, GHG)」について、その正体と種類、そしてなぜその管理が人類共通の課題となっているのかを解説する。
温室効果ガスとは
温室効果ガスとは、一言で言えば「地球の表面から宇宙へ逃げる熱(赤外線)の一部を吸収し、再び地表に戻す(再放射する)性質を持つ、大気中の気体成分」である。
このプロセスは温室効果と呼ばれ、自然な状態では、地球の平均気温を約14℃という生命に適した温度に保つために不可欠である。しかし、産業革命以降、人間活動によって大気中の温室効果ガスの濃度が急激に増加したことで、この「毛布」が厚くなりすぎ、地球全体の気温が上昇する地球温暖化が引き起こされている。
なぜGHGの管理が重要なのか
温室効果ガスは、現代の気候変動を理解し、対策を講じる上での、最も基本的なキーワードである。
地球温暖化の主要因
IPCCは、近年の温暖化が人間活動による温室効果ガスの増加に起因することを、科学的に「疑う余地がない」と結論付けている。GHGの排出量を削減することが、温暖化対策の根幹である。
全ての気候変動政策の対象
パリ協定のような国際条約から、各国の法律、そして企業の削減目標に至るまで、全ての気候変動対策は、この温室効果ガスの排出をいかにして減らし、大気中から除去するかに焦点を当てている。
多様なガスと共通の指標
温室効果ガスには複数の種類があり、それぞれ発生源や温暖化への影響度(温暖化能力)が異なる。この異なるガスの温暖化能力を比較するため、二酸化炭素(CO2)を「1」とした場合の温暖化能力を示す「GWP(地球温暖化係数)」という指標が用いられ、全ての排出量は「CO2換算(CO2e)」という共通の単位で計算される。
国際交渉の対象となる主な温室効果ガス
京都議定書やパリ協定の下で、国際的に排出量の算定・報告・削減の対象となっているのは、主に以下の7種類のガスである。
二酸化炭素(CO2)
最も排出量が多く、温暖化への影響が最大の温室効果ガスである。主に化石燃料(石炭、石油、天然ガス)の燃焼や、セメントの生産、森林減少などによって排出される。
メタン(CH4)
CO2の次に影響の大きなガスである。家畜(牛のゲップなど)や水田、天然ガスの採掘時の漏洩、廃棄物の埋め立てなどから発生する。大気中の寿命はCO2より短いものの、短期的な温室効果は数十倍強力である。
一酸化二窒素(N2O、亜酸化窒素)
主な発生源は、農用地に施用された窒素肥料や、工業プロセス、燃料の燃焼などである。大気中の寿命が非常に長く、温暖化能力もCO2の200倍以上と強力である。
Fガス類(フロンガス類)
自然界には存在しない、人間が作り出した化学物質であり、極めて強力な温室効果を持つ。大気中に数千年以上にわたって留まるものもある。
- ハイドロフルオロカーボン類(HFCs):主にエアコンや冷蔵庫の冷媒として使用される。
- パーフルオロカーボン類(PFCs):半導体の製造プロセスなどで使用される。
- 六フッ化硫黄(SF6):電力設備などで絶縁ガスとして使用される。
- 三フッ化窒素(NF3):半導体や液晶パネルの製造プロセスで使用される。
GHGという概念を理解するメリットと課題
メリット
- 気候変動の根本原因を、科学的に明確に理解できる。
- 排出源を特定することで、効果的な対策を講じることができる。
- 「CO2換算」という共通の物差しにより、国や企業、プロジェクトの垣根を越えて、削減努力を比較・評価できる。
課題
- 温室効果ガスは無色・無臭で、その影響がすぐには現れないため、問題の緊急性が社会に認識されにくい。
- 排出が、エネルギー、食料、輸送、工業生産といった、私たちの生活のあらゆる側面に深く組み込まれており、その削減には社会経済システム全体の大きな変革が必要である。
まとめ
温室効果ガス(GHG)は、地球を暖かく保つ自然の「毛布」でありながら、人間活動によってその濃度が過剰になり、地球温暖化を引き起こしている、気候変動の根本原因である。
GHG排出量の算定・報告は、全ての気候変動対策の出発点であり、この科学的真実に基づき、いかにして迅速かつ公正に、社会経済システム全体を脱炭素化させていくかが、人類に残された最大の課題である。