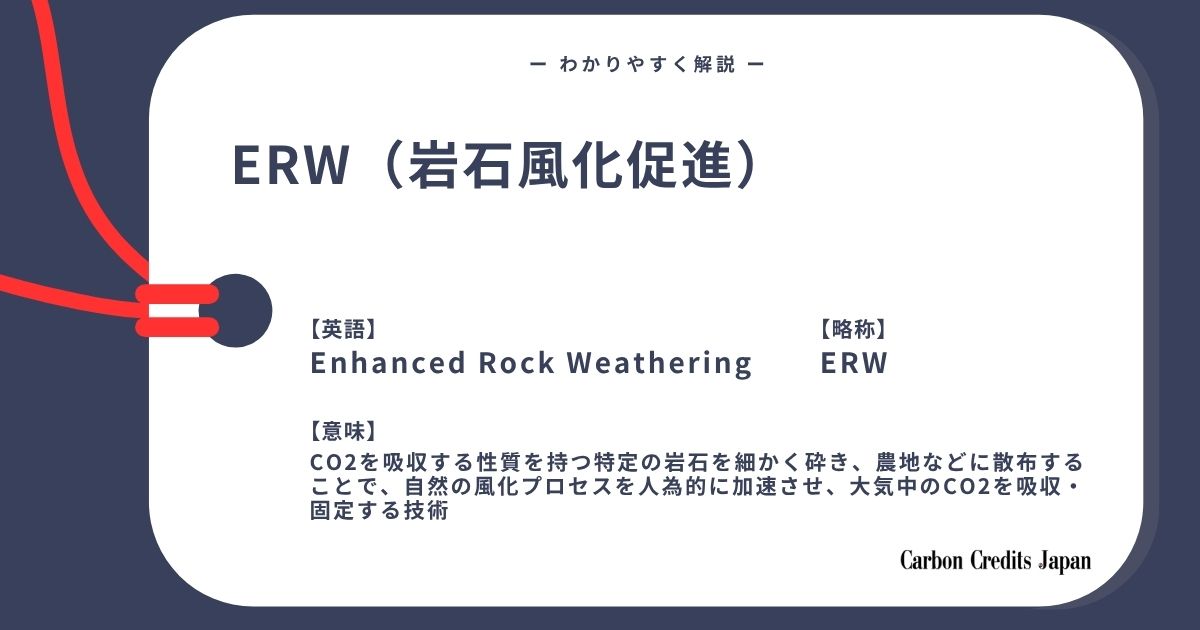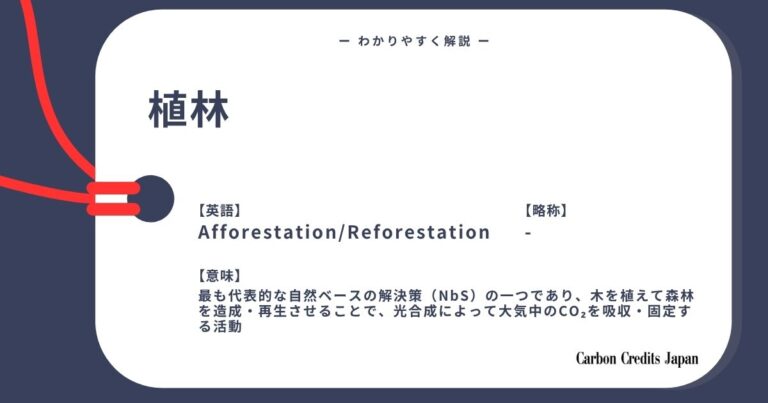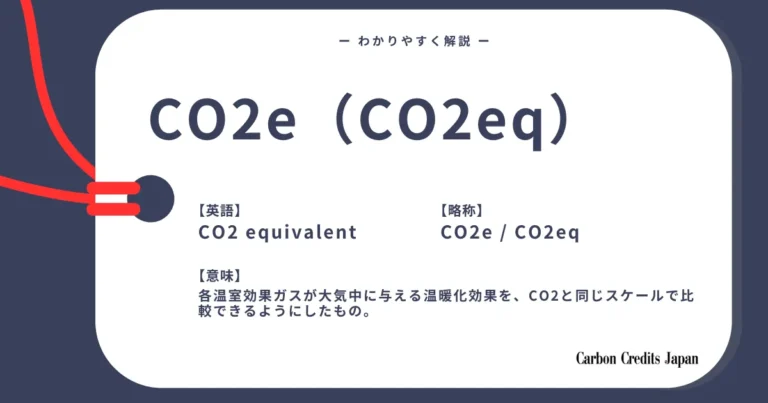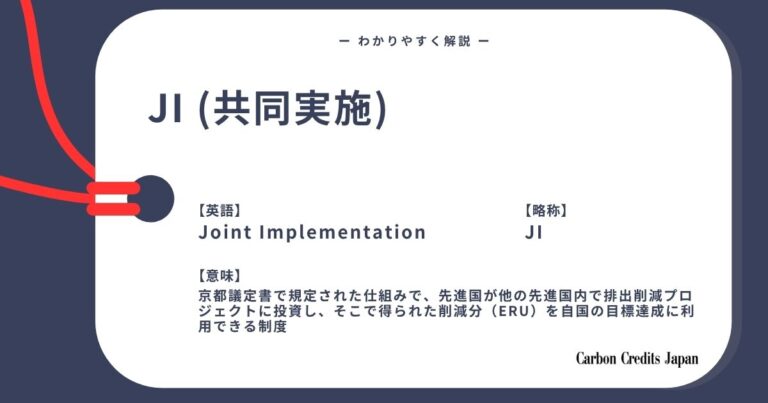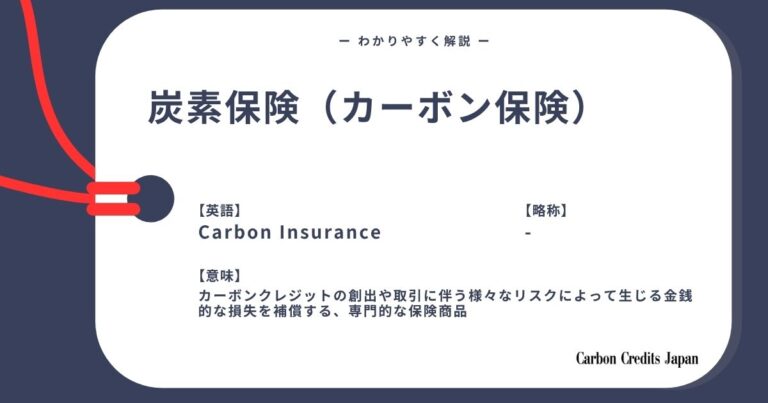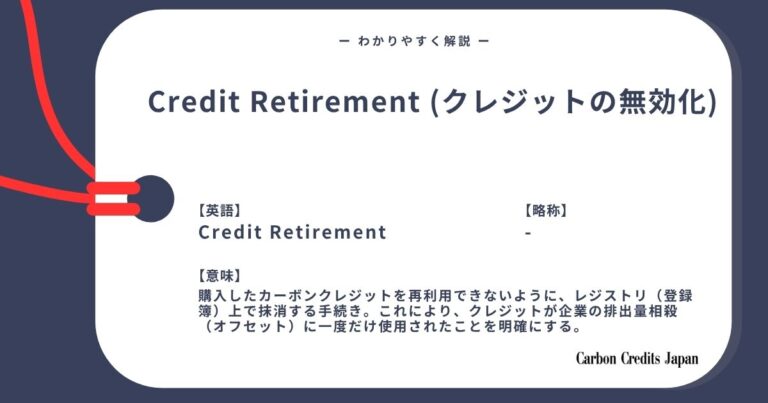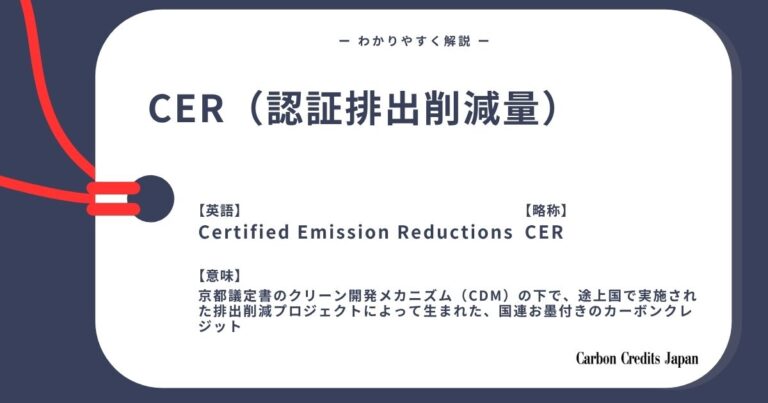岩石風化促進(ERW:Enhanced Rock Weathering)は、地球が何億年もかけて行ってきた自然の炭素循環を人為的に加速させ、大気中の二酸化炭素を吸収し長期的に貯留する除去系の技術である。
本解説では、ERWが単なるCO2除去技術にとどまらず、いかにして開発途上国の農業生産性向上という強力なコベネフィットを生み出し、カーボンクレジット市場を通じて資金動員を促す可能性を秘めているのかを、国際開発と気候変動ファイナンスの視点から解説する。
ERWの定義
ERWとは、玄武岩などのアルカリ性岩石を細かく砕き、農地などの土壌に散布することで、岩石が自然に風化する化学反応を加速させ、大気中のCO2を吸収・固定する二酸化炭素除去(CDR:Carbon Dioxide Removal)技術である。
CO2吸収のメカニズム
- 自然の風化
- 自然界では、岩石が雨水(弱酸性)に触れると、非常にゆっくりと化学反応を起こす。
- この反応により、大気中のCO2が炭酸水素イオンという形で水に溶かし込まれる。
- このイオンは最終的に海に流れ着き、貝殻やサンゴの骨格(炭酸カルシウム)として半永久的に固定される。
- ERWによる加速
- ERWは、岩石を粉末状にすることで表面積を劇的に増加させる
- これにより、自然のプロセスが数十年から数百年のスケールにまで加速されるのである。
制酸剤による中和の比喩
このプロセスは、「制酸剤で胃酸を中和する」ことに例えられる。CO2が溶け込んだ雨水は地球にとっての軽い「酸性化」であり、アルカリ性の「制酸剤」(砕いた岩石)を土壌に撒くことで中和反応が起こる。その化学反応の過程で、原因物質であるCO2が安定した物質に変わり、大気中から除去されるのである。
ERWの重要性
ERWは、気候変動対策と持続可能な開発を両立させる大きなポテンシャルを秘めている。
ギガトン級のCO2除去ポテンシャル
理論上、ERWは世界で年間数十億トン(ギガトン)規模のCO2を除去できる可能性があり、パリ協定の1.5℃目標達成に必要な大規模なCDRの選択肢の一つとして期待されている。
農業生産性向上という強力な共同便益
玄武岩などの岩石には、カリウム、カルシウム、マグネシウムといった、植物の成長に不可欠なミネラルが豊富に含まれている。
ERWを農地に適用すると、土壌の酸性度が改善され、これらのミネラルが供給されるため、化学肥料の使用量を減らしつつ、作物の収穫量を増やす効果が期待できる。これは、食料安全保障が課題である開発途上国にとって極めて大きなメリットである。
新たな資金動員
ERWによるCO2除去量を正確に測定・報告・検証(MRV)できれば、それを高品質な「除去系」カーボンクレジットとしてボランタリーカーボンクレジット市場で販売できる。これにより、プロジェクト実施のコストを賄い、途上国の農家に新たな収入源をもたらすことで、民間資金を動員する道が開かれる。
永続性の高い炭素貯留
一度、炭酸水素イオンとして海洋に流れ着いた炭素は、数万年以上のスケールで安定的に貯留される。森林火災などで再びCO2が放出されるリスク(リバーサルリスク)が極めて低い、永続性の高い除去方法である点は大きな魅力である。
仕組みと具体例
ERWプロジェクトのプロセスは比較的シンプルである。
原料調達と粉砕
- 原料調達
玄武岩やかんらん岩といった、風化しやすくミネラルが豊富なケイ酸塩岩を採石場から調達する。これらの岩石は世界中に豊富に存在する。 - 粉砕
専用の施設で、岩石を砂粒ほどの細かさ(直径100マイクロメートル以下)に粉砕する。この粉砕プロセスが、ERW全体のコストとエネルギー消費の大部分を占める。
農地への散布と反応
- 散布
粉砕された岩石の粉末を、既存の農業機械(肥料散布機など)を使って農地に散布する。土壌に混ぜ込むことで、雨水や土壌中の微生物との反応が始まる。 - 化学反応とCO2吸収
土壌中で、岩石の粉末が雨水(炭酸)と反応し、CO2を溶かし込んだ重炭酸イオンを生成する。
モニタリングとクレジット化
土壌サンプルや水質を分析し、化学反応の進行度を測定することで、CO2除去量を算定する。この検証済みデータに基づき、カーボンクレジットが発行される。
具体例、米国のスタートアップ企業 Lithos Carbon
米国のスタートアップ企業であるLithos Carbonは、同国の農家と提携し、農地に玄武岩の粉末を散布する大規模な実証プロジェクトを展開している。農家は無償で土壌改良材(岩石粉末)を得られる一方、Lithosはそれによって生まれるカーボンクレジットを販売することで収益を上げている。
メリットと課題
ERWは大きな可能性を秘めているが、実用化に向けては多くのハードルが存在する。
| メリット | 課題 |
| 大規模な除去ポテンシャルと永続性 理論上の除去ポテンシャルが大きく、固定した炭素の貯留期間が非常に長い。 | 高コストとエネルギー消費 採掘、輸送、そして特に粉砕プロセスに大量のエネルギーを要し、コストが高い。ライフサイクル全体での純除去量の厳密な評価が必要である。 |
| 農業生産性向上という強力なコベネフィット 食料増産と土壌改良に貢献し、途上国の開発課題解決に直結する。農家にとって導入のインセンティブが高い。 | MRV(測定・報告・検証)の難しさ 広大な農地で、ゆっくりと進む化学反応によるCO2除去量を、正確かつ安価に測定する技術がまだ確立されていない。これがクレジットの信頼性を左右する。 |
| 既存インフラの活用 | 環境への潜在的影響 |
| 散布には既存の農業機械が使えるため、新たな大規模インフラ投資が不要である。 | 岩石に含まれるニッケルやクロムといった重金属が、土壌や地下水に溶け出すリスクが指摘されており、長期的な生態系への影響評価が不可欠である。 |
まとめと今後の展望
岩石風化促進(ERW)は、地球の自然な炭素循環システムを利用して気候変動に立ち向かう、野心的かつ有望なCDR技術である。特に、CO2除去と食料安全保障という、人類が直面する二つの大きな課題に同時に貢献できる可能性は、他の技術にはない大きな魅力である。
- ERWは、砕いた岩石を土壌に撒き、自然の風化プロセスを加速させて大気中のCO2を除去・固定する技術である。
- CO2除去だけでなく、土壌改良による農業生産性向上という強力なコベネフィットを持つ。
- 除去ポテンシャルと永続性に優れるが、高コストとMRV手法の確立が実用化への大きな課題である。
- 途上国にとっては、気候変動対策と食料安全保障を両立させ、カーボンクレジットを通じて新たな収入源となりうる。
ERWが気候変動対策の主要な柱の一つとなるためには、技術革新による粉砕コストの抜本的な削減と、信頼性の高いMRVプロトコルの確立が急務である。今後は、衛星リモートセンシングや機械学習を組み合わせた新しいモニタリング技術の開発が進むと予測される。また、どのような岩石を、どのような土壌や気候条件で利用すれば、CO2除去と農業への便益を最大化できるのか、世界各地での実証試験の積み重ねが重要となる。ERWは、まさに「一石二鳥」を地で行く技術として、サステナブルな未来への道を切り開く可能性を秘めている。