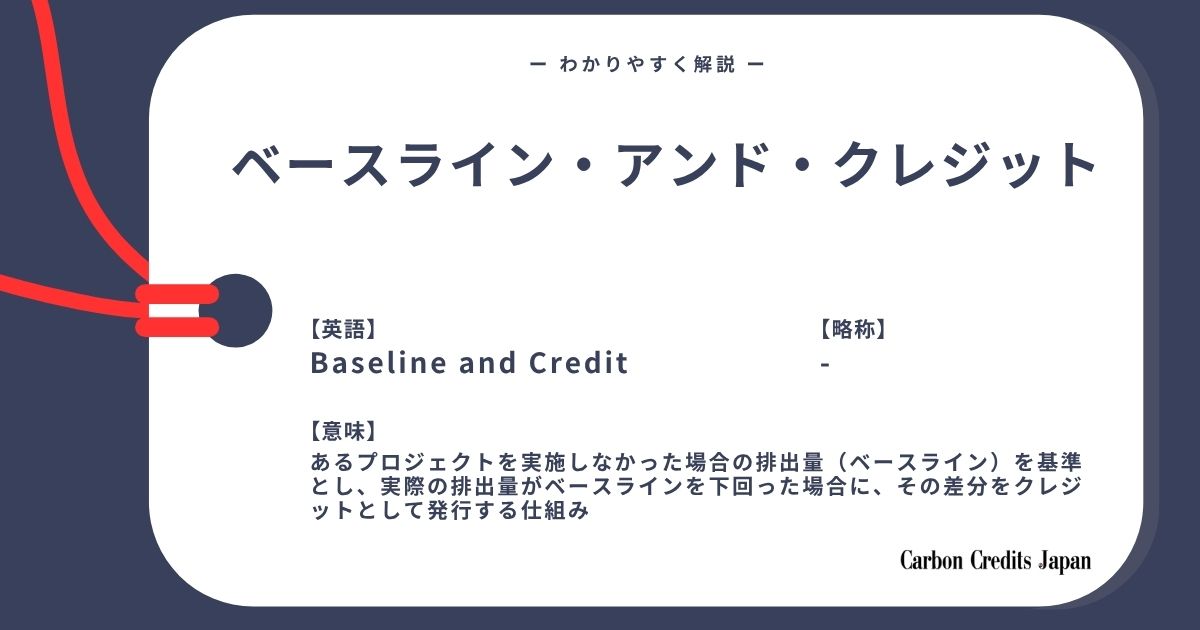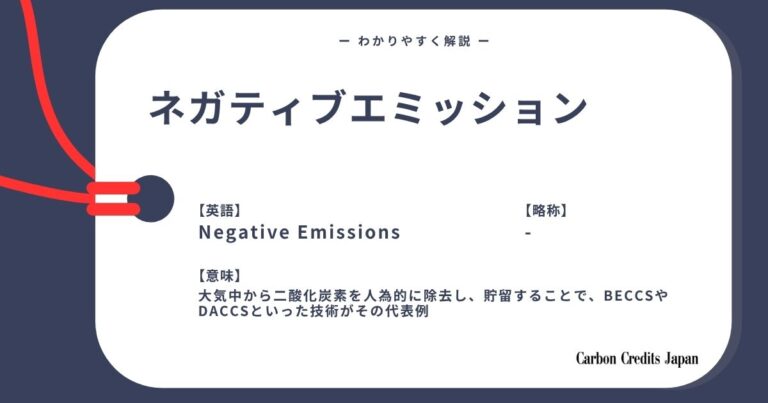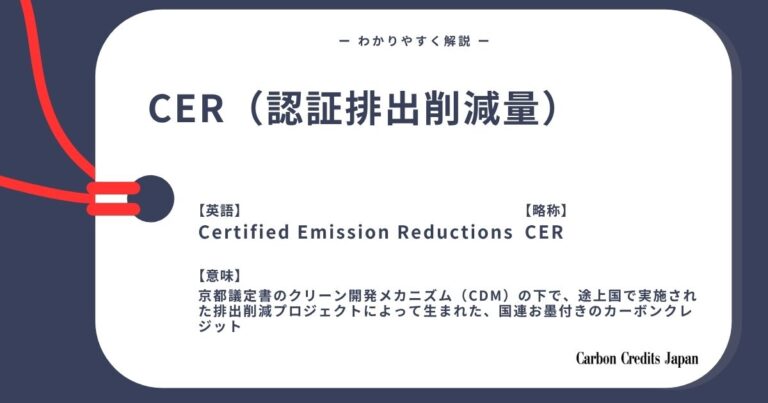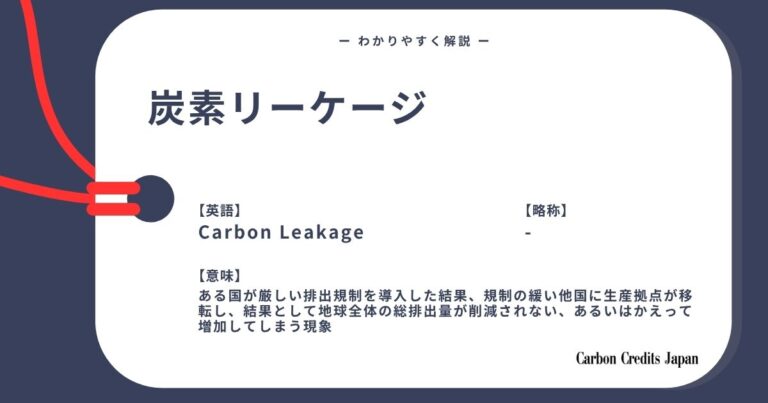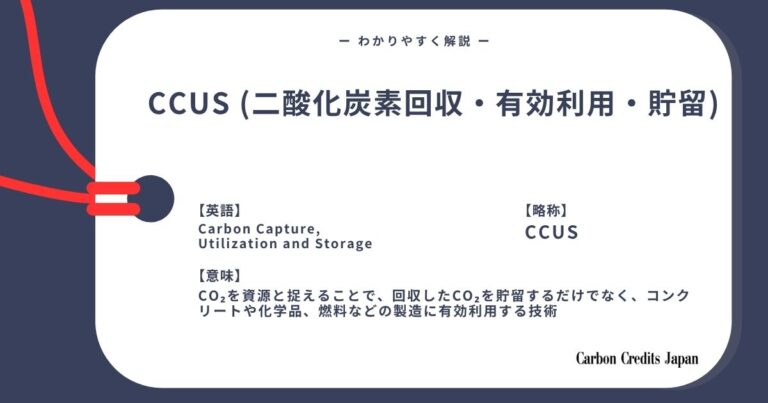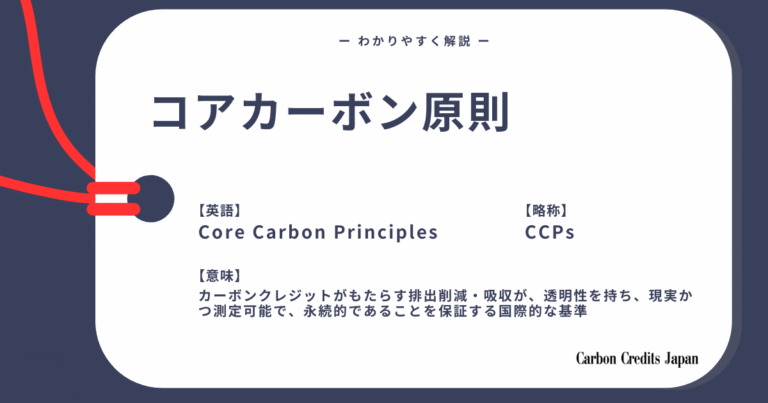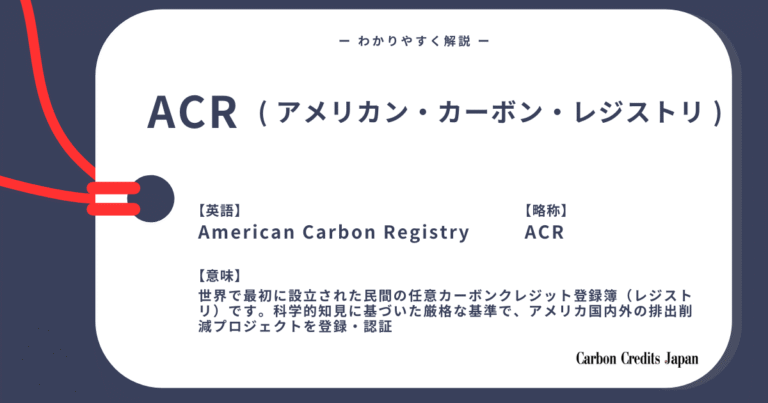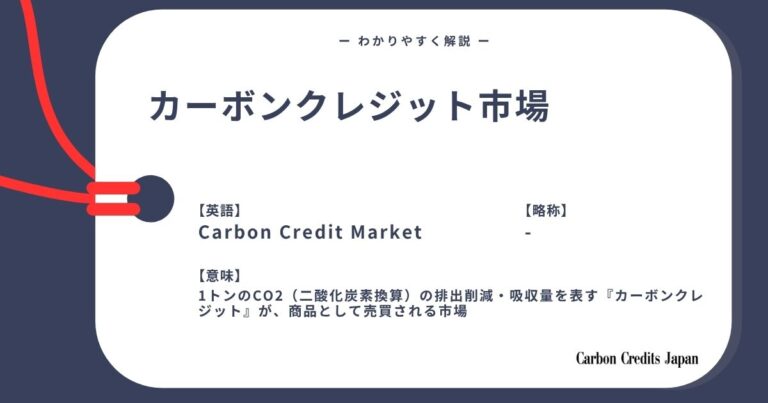気候変動対策の金融メカニズムにおいて、キャップ&トレード型の排出量取引制度(ETS)と双璧をなす重要な概念が「ベースライン&クレジット制度」である。これは、特定のプロジェクトやセクター単位で排出削減を促す際に用いられる、より柔軟でボトムアップ的なアプローチだ。
本稿では、「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から、この制度の本質を解説する。制度の生命線であるベースライン設定の信頼性確保や、途上国における脱炭素プロジェクトへの資金動員、そして地域社会への便益といった観点を中心に、キャップ&トレードとの違いを明確にしながらその仕組みと役割を詳述する。
ベースライン&クレジットとは
一言で表現すれば、「対策を講じなかった場合に想定される排出量(ベースライン)を設定し、そのベースラインを下回る削減を達成した場合に、その差分をクレジットとして発行する制度」である。
排出量に絶対的な上限(キャップ)を設けるトップダウン型のETSとは異なり、個々の活動の「パフォーマンス」に着目する点に特徴がある。「本来であればこれだけ排出していたはず」という基準線からの改善度合いを評価し、その努力の成果を取引可能な価値(クレジット)へと転換するボトムアップ型の仕組みである。
ベースライン&クレジットの重要性
本制度の重要性は、国全体での厳格なキャップ設定が難しい状況であっても、個別具体的な排出削減活動に対して直接的な経済的インセンティブを付与できる点にある。
このアプローチは、温室効果ガス(GHG)削減に寄与する先進技術の導入や、森林保全活動といった個別プロジェクトへの資金動員に極めて有効である。特に、経済成長段階にあり、国全体の排出量に厳しい上限を設けることが政治的・経済的に困難な途上国において、その効果を発揮する。再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の改善といった優良なプロジェクトを個別に促進し、そこへ先進国からの民間投資を呼び込むための重要な金融ツールとなるからである。
制度の仕組み
ベースライン&クレジット制度の信頼性は、その根幹である「ベースライン」をいかに設定するかに依存する。具体的なプロセスは以下の通りである。
ベースラインの設定
これは最も重要かつ困難なプロセスである。「もし、このプロジェクトが実施されなかったら、どれだけのGHGが排出されていたか」というシナリオ(Business as Usual, BaU)を、科学的かつ客観的な方法論に基づいて設定する。この設定が甘い場合、実質的な削減とは言えないものまでクレジット化される「ホットエア」の問題が発生し、市場の信頼性を著しく損なうこととなる。
モニタリングと報告
プロジェクト実施後の実際の排出量を、定められた方法に従って継続的に監視・測定し、報告を行う。
検証とクレジット発行
報告された実績値と、事前に設定したベースラインとの差分(削減量)について、第三者機関が厳格な検証を行う。検証を経て承認された削減量が、クレジットとして認証・発行される。
ETS(キャップ&トレード)との比較
両者の主な違いは以下の通りである。
| 特徴 | ベースライン・アンド・クレジット | 排出量取引制度(ETS) |
| アプローチ | ボトムアップ(プロジェクト単位) | トップダウン(国・地域全体) |
| 排出枠 | 排出削減実績に応じて創出(クレジット) | 総量の上限内で配分(アロケーション) |
| 環境効果 | 全体の排出削減量は保証されない | キャップにより全体の排出総量が保証される |
| 主な用途 | J-クレジット、JCMなど、ボランタリーカーボンクレジット市場全般 | EU-ETSなど |
具体例
二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism, JCM)
日本が持つ優れた低炭素技術をパートナー国(主に途上国)に提供する事例が挙げられる。例えば、エネルギー効率の高いボイラーを導入するプロジェクトでは、ベースラインを「現地で一般的に使われている旧式のボイラーを使い続けた場合の排出量」と設定する。実際に高効率ボイラーを導入して達成できた排出削減分がクレジットとして発行され、日本とパートナー国とで分配される。これは、途上国への技術移転と資金動員を具体化する典型例である。
ボランタリーカーボンクレジット市場のプロジェクト
途上国で大規模な太陽光発電所を建設する場合、ベースラインは「その発電所がなければ、化石燃料中心の既存の電力網から供給されていたであろう電力の排出係数」に基づいて計算される。クリーンな電力を供給することで削減できた排出量がクレジットとなり、世界中の企業等へ販売される。
日本における活用事例
日本はこの仕組みを国内外で積極的に活用している。
J-クレジット制度
国内における省エネ設備導入や森林管理などによる排出削減・吸収量を認証する、典型的なベースライン・アンド・クレジット制度である。
JCM(二国間クレジット制度)
日本の国際貢献の柱として、途上国と共にこの仕組みを用いたプロジェクトを世界中で展開している。
メリットと課題
柔軟性が高い制度である一方で、その信頼性の確保には常に困難が伴う。
メリット
- 導入のしやすさ
- 国全体の排出上限を設けるよりも、特定のセクターや技術に絞って導入しやすいため、カーボンプライシングの第一歩として有効である。
- プロジェクトへの直接的インセンティブ
- 具体的な行動(例:再エネ導入)と経済的リターンが直結するため、民間資金を特定のプロジェクトに動員しやすい。
- 経済成長との両立
- 絶対的な排出上限がないため、経済成長を阻害するとの政治的抵抗を受けにくい側面がある。
課題
- ベースラインの信頼性(最大のリスク)
- 「もし〜だったら」という反実仮想のシナリオを証明することは本質的に困難である。ベースラインが不適切に設定されると、実態のないクレジットが乱発され、制度全体への信頼が失われる。
- 環境十全性の不確実さ
- 個々のプロジェクトが排出削減を達成しても、制度の対象外で排出量が増加すれば、社会全体の排出量は増え続ける可能性がある。つまり、排出総量の削減は保証されない。
- 複雑な方法論
- プロジェクトの種類ごとに異なるベースライン算定方法論が必要となり、その開発・適用・検証には高度な専門性とコストを要する。
まとめと今後の展望
ベースライン&クレジットは、気候変動対策の選択肢を広げ、特にプロジェクト単位での資金動員を可能にする極めて重要な金融メカニズムである。「もし〜だったら」というベースラインからの削減実績を評価するボトムアップ型の制度として、途上国でのプロジェクト実施や企業の自主的取り組みを促す上で高い柔軟性と有効性を持つ。
一方で、制度の成否は、いかに客観的で信頼性の高いベースラインを設定できるかにかかっている。排出総量の削減を保証するものではなく、キャップ&トレード制度とは補完的な関係にあることを理解する必要がある。
今後、制度の信頼性を高めるために、新技術を活用したモニタリングやベースライン評価の高度化が進むことが予想される。国際開発の文脈では、この仕組みを通じて生まれる資金が、単に排出削減だけでなく、現地の生物多様性保全や雇用創出といった、公正な移行に資する「コベネフィット」をいかに最大化できるかが、重要な評価軸となっていくであろう。