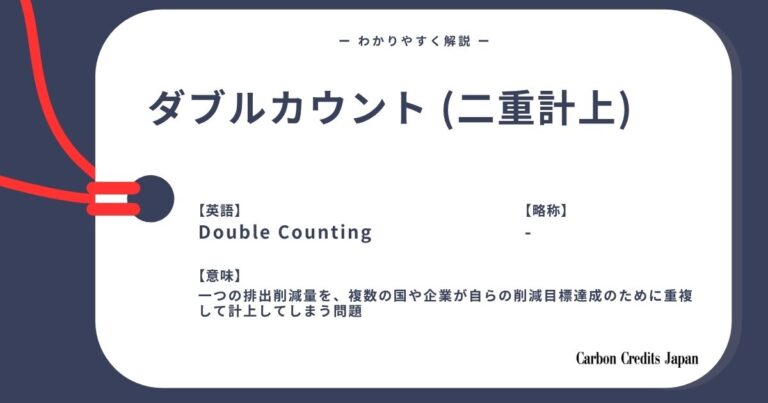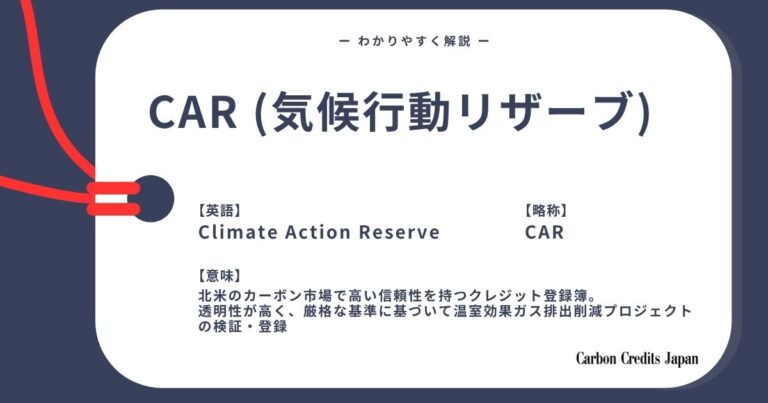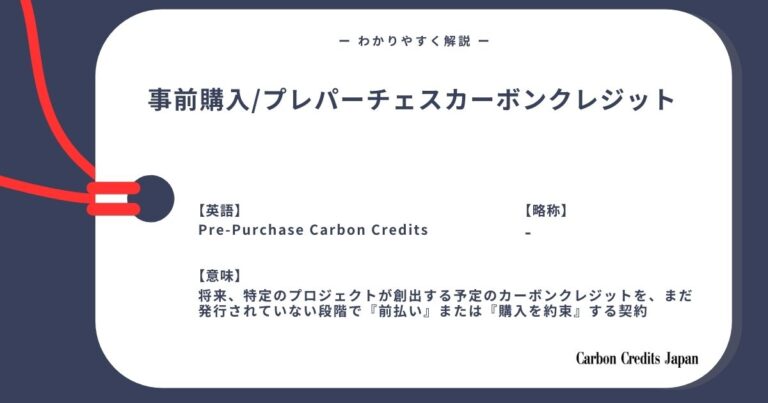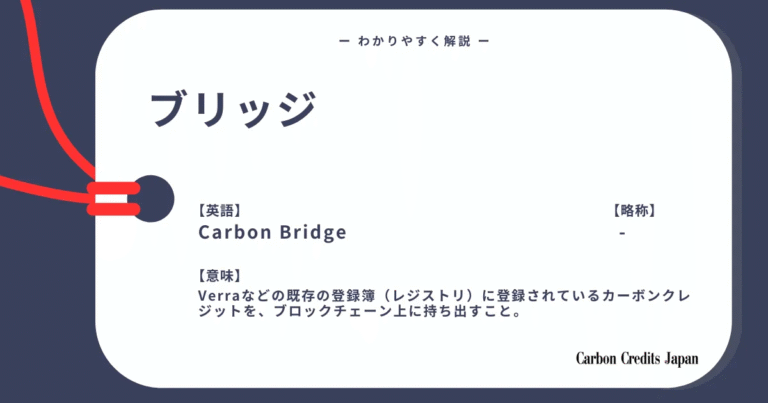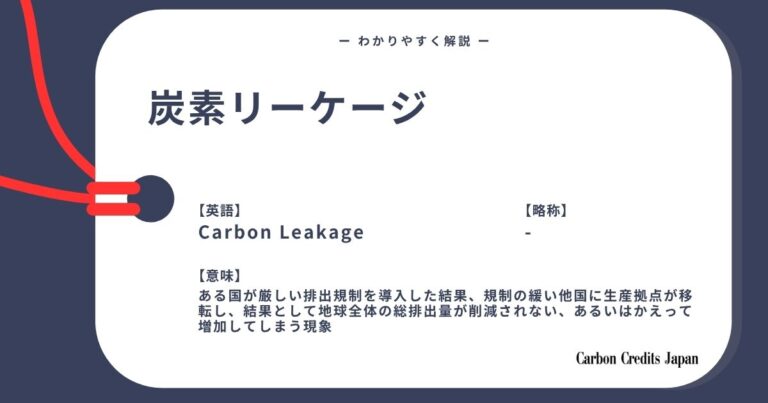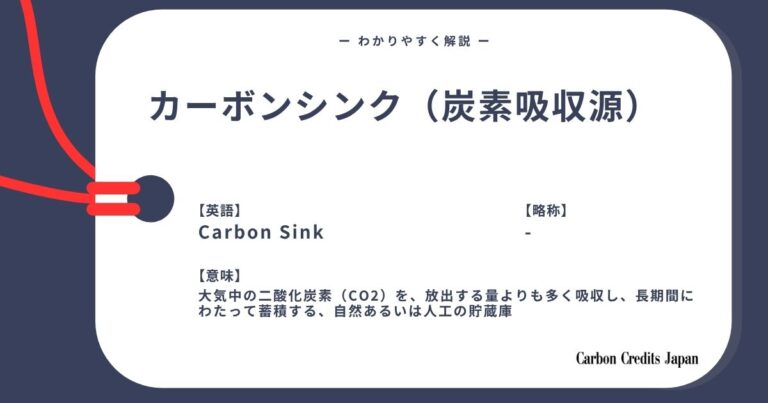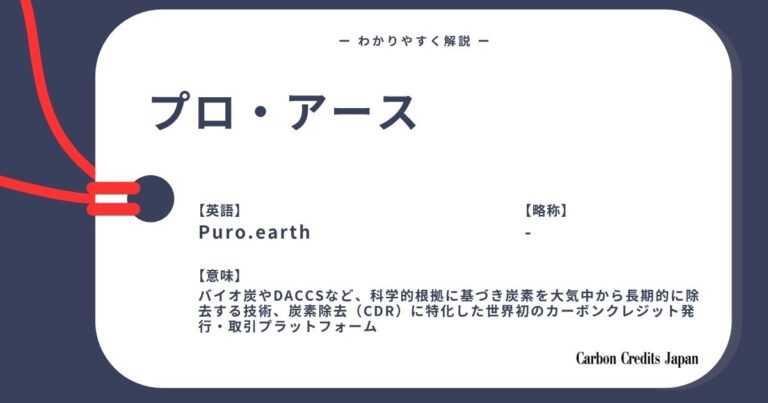CDRクレジットとは、炭素除去(CDR: Carbon Dioxide Removal)によって創出されるカーボンクレジットを指す。つまり、単に排出を削減するだけでなく、大気中から実際に二酸化炭素(CO2)を取り除いた成果をクレジット化したものである。
CDRクレジットとは
従来のカーボンクレジットは、再生可能エネルギーの導入や省エネ設備の導入など、CO2排出の回避・削減に基づくものであった。これらは回避系カーボンクレジットや削減系カーボンクレジットと呼ばれる。
これに対しCDRクレジットは、森林吸収、バイオマス利用、直接空気回収(DAC)などの技術を用い、大気中のCO2を「マイナスにする」行為を対象とする。
CDRクレジットの主な種類
CDRの方法は多岐にわたるが、大きく自然ベースと技術ベースの二つに整理できる。
自然由来のCDR
自然由来のCDRプロジェクトには、例えば、植林・再植林(ARR : Afforestation, Reforestation)、生物起源炭素除去・貯留(BiCRS : Bio-based Carbon Removal and Storage)、海洋炭素除去(mCDR : marine CDR)などが挙げられる。
これらのプロジェクトは比較的コストが低い一方で、除去した炭素の永続性の確保や、食糧生産のための土地利用との競合といった課題がある。
技術由来のCDR
技術由来のCDRプロジェクトには、例えば直接空気回収・貯留(DACCS : Direct Air Capture and Carbon Storage)、バイオエネルギー炭素回収・貯留(BECCS : Bioenergy with Carbon Capture and Storage)などが挙げられる。
これらのプロジェクトはCO2除去の確実性は高い一方で、現時点ではコストが非常に高く、商用規模の展開には時間を要する。
CDRクレジットの課題
CDRクレジットの普及には、以下のような複数の課題が指摘されている。
- 除去量の測定・報告・検証(MRV)
特に自然由来のCDRにおいて、正確な除去量を把握し、透明性をもって報告することが困難である。 - 除去の永続性担保
クレジットの価値を維持するためには、除去したCO2が長期間にわたって大気中に再放出されない保証が必要である。 - コスト
現時点では、特に技術由来のCDRにおいて、1トンあたり数百〜数千米ドルに達するケースもあり、広く利用するにはコストダウンが求められる。 - 国際的な基準整備が途上
例えば、パリ協定の第6条との整合性を図るなど、グローバルな市場としての信頼性を高めるためのルール作りが進行中である。
まとめ
CDRクレジットは、脱炭素社会を実現するための「最終ピース」として位置づけられる。
これまで主流であった回避系カーボンクレジット、削減系カーボンクレジットが「炭素の増加を抑える」ものであるのに対し、CDRクレジットは「炭素を減らす」仕組みである。今後、信頼性の高いMRV基準と市場メカニズムの整備が進むことで、CDRクレジットはグローバルな炭素市場の中核的存在となることが期待される。