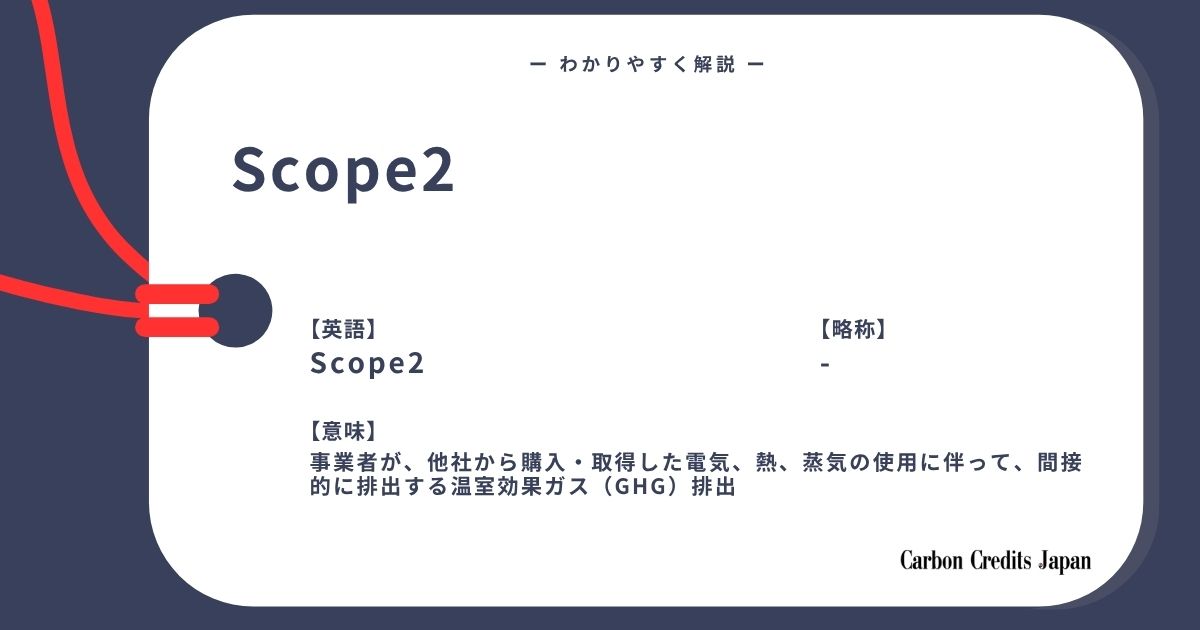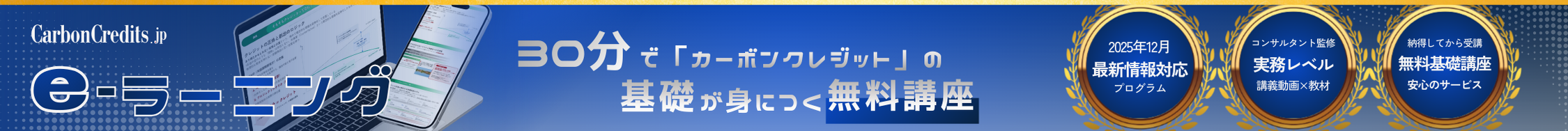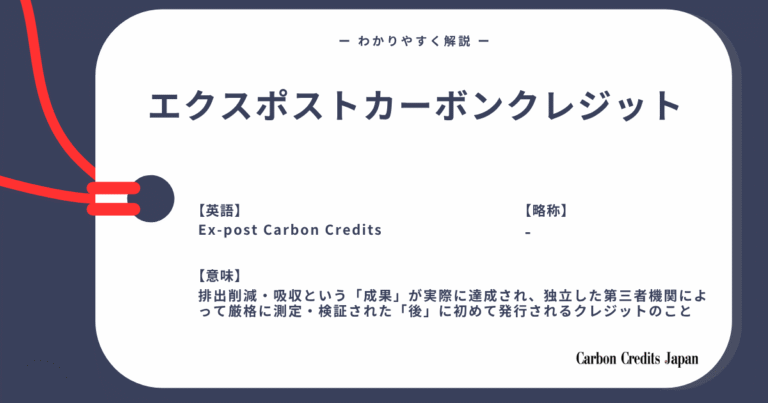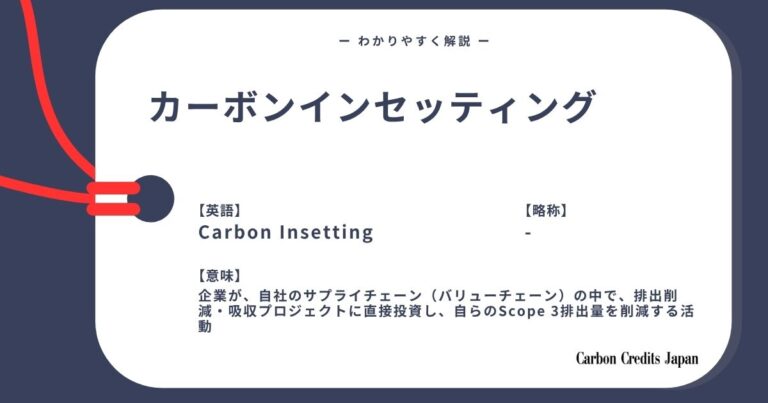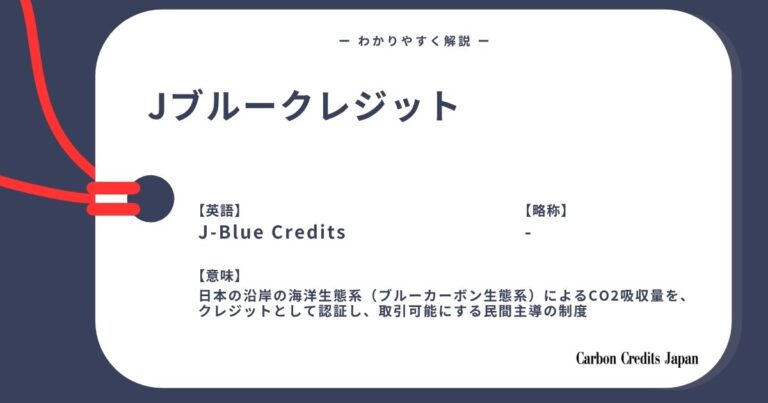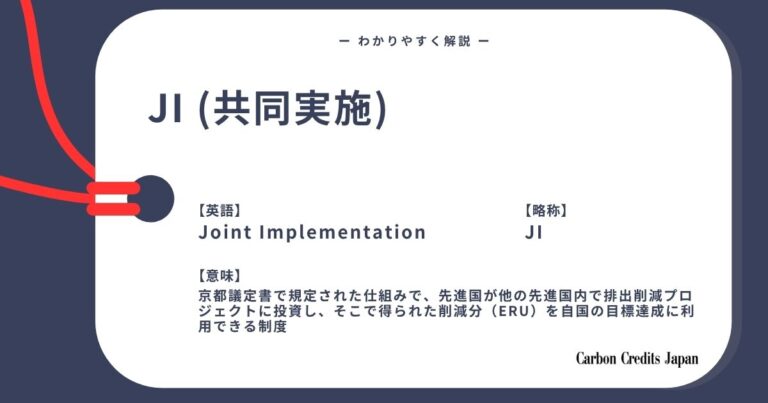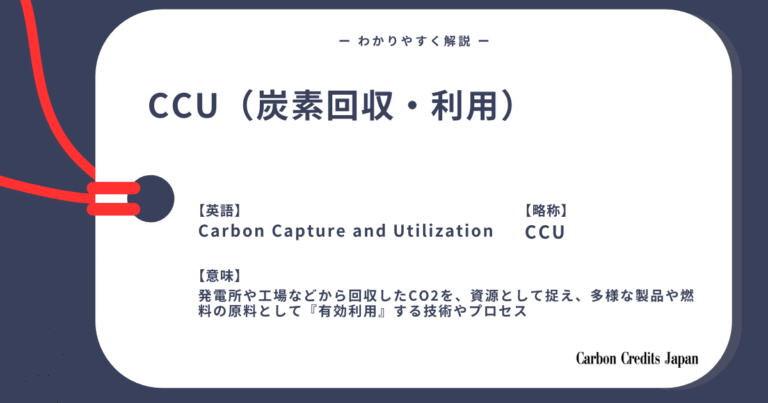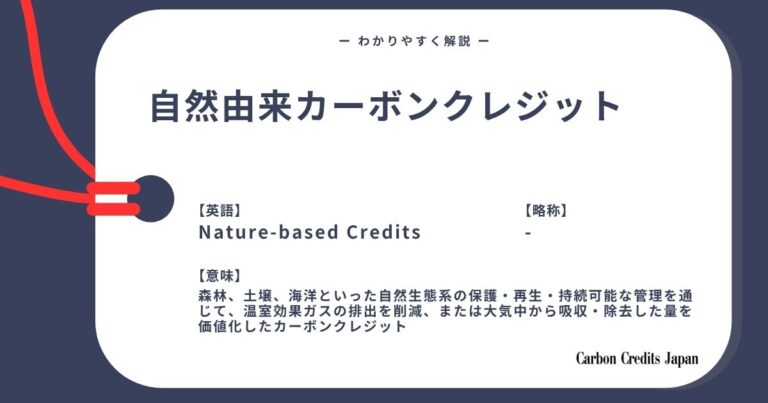企業の気候変動対策を理解する上で、自社の直接排出(Scope1)と並び、その事業活動を支えるエネルギーの選択を問う極めて重要な指標が「Scope2(スコープ2)」排出量である。
これは、他社から購入した電気、熱、蒸気の使用に伴う間接的な排出を指し、特にオフィス業務が中心の非製造業にとっては、最大の排出源となることも少なくない。
本記事では、Scope2の管理が、いかにして企業のエネルギー調達戦略を通じ、国全体の再生可能エネルギーへの投資、すなわち資金動員を加速させるのか。そして、企業の選択が開発途上国のエネルギーインフラ転換や、公正な移行にどのような影響を与えるのか。その基本的な概念から本質的な重要性までを掘り下げる。
Scope2とは
Scope2排出量とは、「事業者が他社から購入して使用した電気、熱、蒸気の生成に伴い、間接的に排出される温室効果ガス(GHG)」のことである。
これは、GHGプロトコルによって定められた「間接排出」の一種だ。自社のボイラーで燃料を燃やす(Scope1)のではなく、電力会社が運営する発電所で燃やされた燃料に由来する排出を、電気を購入した事業者が自社の排出量として計上するという考え方である。
Scope1、Scope3との違い
- Scope1(スコープ1): 自社が所有・管理する排出源からの直接排出(例:社用車のガソリン燃焼)。
- Scope2(スコープ2): 購入したエネルギーの生成に伴う間接排出(例:購入した電力)。
- Scope3(スコープ3): Scope1、2以外のサプライチェーン全体からの、その他の間接排出(例:原材料の輸送、従業員の出張)。
Scope2の重要性
Scope2の重要性は、企業のエネルギー調達という具体的な購買行動を通じ、社会全体のエネルギーシステムへ直接的な影響を与え得る点にある。これは、マンションの住人による電力選択に例えることができる。
- Scope1
自室のガスコンロで料理をする際のガス排出。これは住人の直接的な責任である。 - Scope2
部屋の照明やエアコンを使うための電気。この電気は、マンション全体で契約している電力会社が遠くの発電所で作っている。住人は発電所を直接コントロールできないが、「どの電力会社から電気を買うか」という選択を通じ、間接的に発電方法(火力か、再生可能エネルギーか)へ影響を与えることができる。
多くの企業、特に金融、IT、サービス業といった非製造業にとって、Scope2はGHG排出量全体の大部分を占める。そのため、企業が化石燃料由来の電力から再生可能エネルギー由来の電力へと購入契約を切り替えることは、極めて強力な脱炭素化のアクションとなる。
この企業の需要は、「再生可能エネルギーにはこれだけの市場価値がある」という明確なシグナルを社会に送り、新たな風力発電所や太陽光発電所の建設への投資を促す。これは、エネルギーインフラの転換が急務である開発途上国において、特に重要な意味を持つ。
算定の仕組み
Scope2排出量の算定には、GHGプロトコルによって2つの異なるアプローチが定められている。
ロケーション基準(Location-based)
電力を消費した地域の電力系統(グリッド)全体の、平均的なCO2排出係数(例:1kWh発電するのに、平均何kgのCO2が排出されるか)を用いて算定する方法である。
これは、その地域で事業を行うことによる物理的な排出への影響を反映する。同じ量の電力を使用していても、石炭火力発電の割合が高い電力網の地域にある工場は、水力発電の割合が高い地域の工場よりも、ロケーション基準でのScope2排出量が多くなる。
マーケット基準(Market-based)
事業者が結んだ電力の購入契約の内容を反映して算定する方法である。
再生可能エネルギー由来の電力であることを証明する証書(再エネ証書)の購入や、再生可能エネルギー発電事業者との直接契約(コーポレートPPA)などを通じ、排出係数をゼロとして計上することが可能だ。企業が自社の使用電力に相当する量の証書を購入することで、マーケット基準におけるScope2排出量を実質ゼロと報告することができる。
企業の選択がもたらす市場への影響
Scope2排出量の削減、すなわち再生可能エネルギー電力への転換は、グローバル企業の気候変動対策において基本的な要件となりつつある。
国際的なイニシアチブ等を通じ、事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が増えている。こうした企業が世界中のサプライヤーに対しても同様の取り組みを求めることは、開発途上国における再生可能エネルギー市場の創出と拡大を牽引する強力なドライバーとなる。
つまり、企業のScope2削減努力が、途上国のエネルギーインフラへの直接的な気候変動ファイナンスとして機能する構造になっているのである。
メリットと課題
Scope2の管理は企業のエネルギー戦略の中核であるが、その手法にはいくつかの論点がある。
Scope2管理のメリット
- エネルギー契約の切り替えという比較的明確なアクションにより、排出量を大幅に削減できる可能性がある。
- 再生可能エネルギーへの需要を創出し、国全体のエネルギー転換を後押しするシグナルとなる。
- 長期のPPA契約などを通じて変動の激しい化石燃料市場から独立し、電力コストを長期的に安定させる効果も期待できる。
管理における課題
- 証書の「追加性」の問題
再エネ証書の購入が、必ずしも新しい再生可能エネルギー発電所の建設(追加性)に繋がっているわけではないという、信頼性に関する指摘がある。単なる権利の移転にとどまらず、実質的な再エネ増加に貢献しているかが問われる。 - 途上国における選択肢の欠如
多くの開発途上国では、再生可能エネルギーを企業が直接選択して購入するための制度やインフラが未整備であり、Scope2削減の選択肢が限られているのが現状である。 - 24/7 CFEへの移行
より先進的な課題として、年間での電力使用量と再エネ調達量を帳尻合わせするだけでなく、24時間365日、常にカーボンフリーな電力で事業を運営する「24/7 Carbon-Free Energy」への移行が求められ始めており、これはより高度な挑戦となる。
まとめと今後の展望
Scope2排出量は、企業の内部努力(Scope1)と、外部の社会システム(電力網)とを結ぶ重要な結節点である。
Scope2は購入したエネルギーの生成に伴う「間接排出」であり、多くの企業にとって主要な排出源だ。再生可能エネルギー電力への切り替えは、企業の排出量を削減する最も効果的な手段であると同時に、国全体のエネルギー転換を促す力を持つ。
今後の展望として、企業のScope2管理は、単なる排出量の会計報告から、より能動的で戦略的な「エネルギー調達戦略」へと進化していくだろう。それは、自社の事業運営を支えるエネルギーが、いつ、どこで、どのように作られているかを常に把握し、最も信頼性が高く、かつ社会・環境への貢献度が大きい方法を選択していくという経営判断である。この企業の賢明な選択こそが、世界中の、特に開発途上国におけるクリーンで公正なエネルギーへの移行を加速させる原動力となるはずだ。