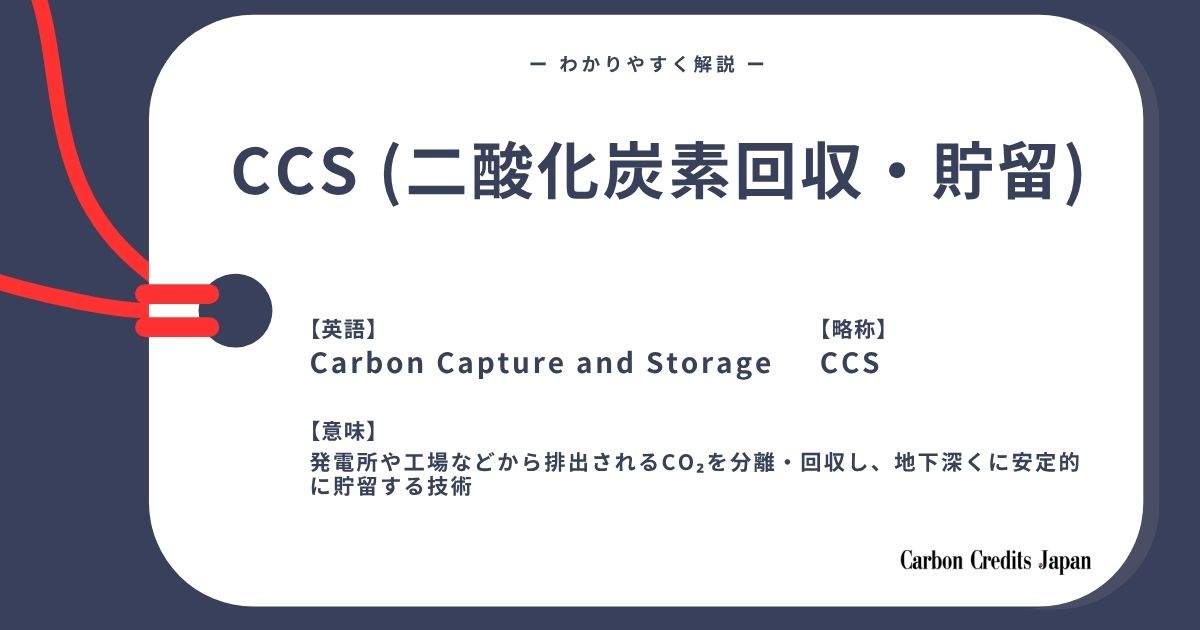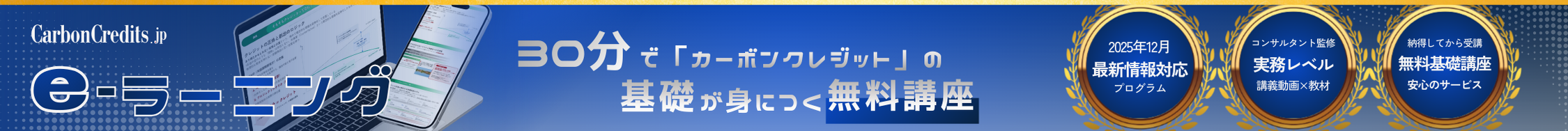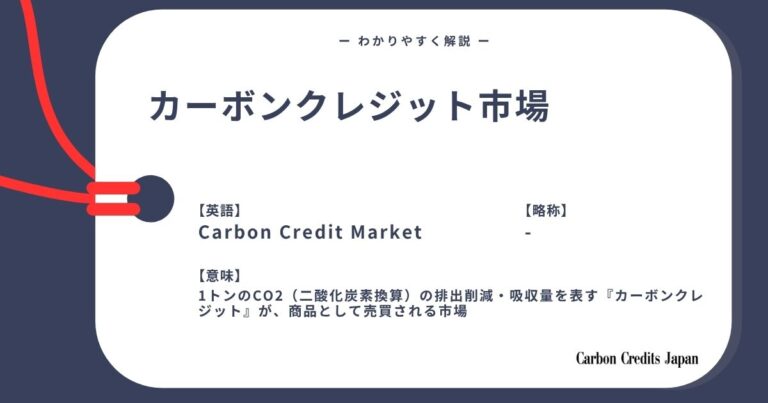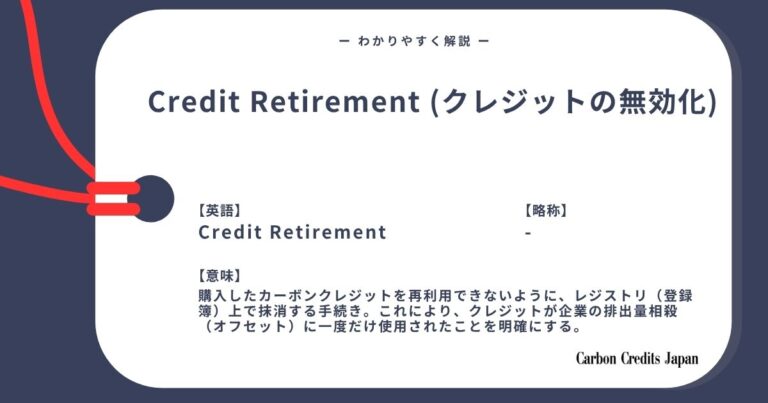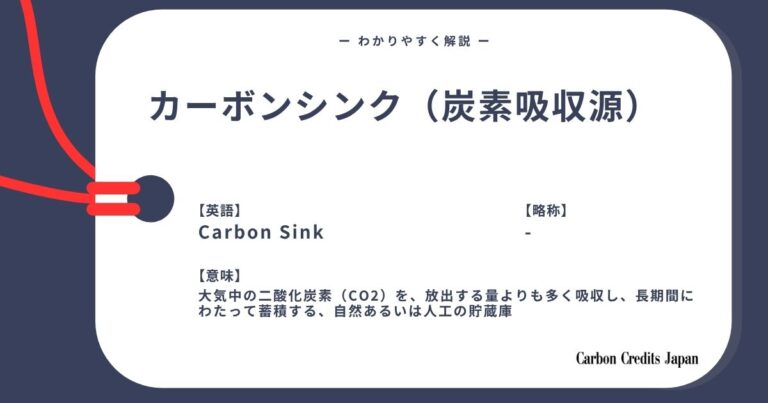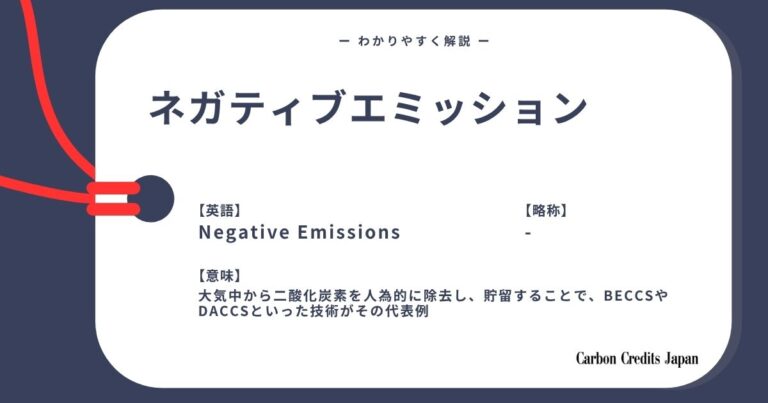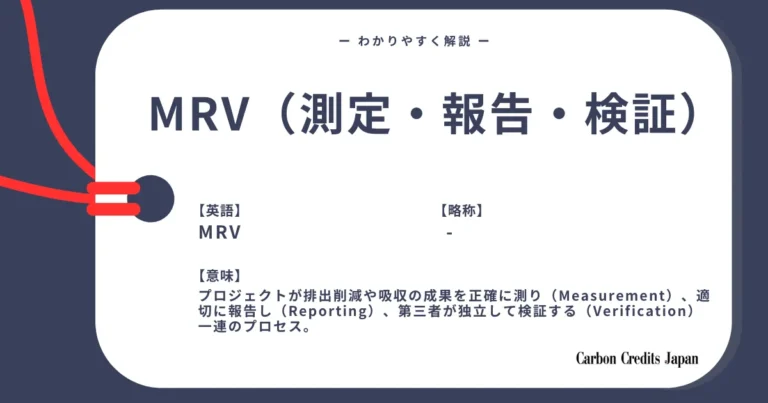パリ協定が掲げる野心的な気候目標の達成に向け、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの推進と並び、特定の産業分野で不可欠な技術として期待と議論を集めているのが、「CCS(Carbon Capture and Storage)」、すなわち「二酸化炭素の回収・貯留」技術である。これは、発電所や工場などから排出されるCO2を大気放出前に分離・回収し、地中深くに安定的に貯留するという、いわば「炭素の地中隔離」技術である。
本記事では、このCCSを「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から深く分析する。CCSがいかにして、脱炭素化が困難なハード・トゥ・アベイト(削減困難な)セクターの切り札となり得るのか。その莫大なコストを賄うための資金調達の課題、そして、貯留した炭素の永続性をいかに担保するかという市場の信頼性の問題について、多角的に解説する。
用語の定義とCCSの仕組み
CCSとは
一言で言うと、CCSとは「産業活動から排出される二酸化炭素(CO2)を、大気に放出される前に分離・回収し、地中深くに長期間にわたって安定的に貯留する一連の技術」の総称である。
関連用語との違い
CCSとしばしば関連付けて語られる用語との違いを理解することが重要である。
- 炭素回収・利用(Carbon Capture and Utilization, CCU)
回収したCO2を、コンクリートや化学製品、燃料などの製造に「利用」する技術である。CCSとCCUを組み合わせた総称がCCUSである。 - 炭素除去(Carbon Dioxide Removal, CDR)
CCSが、特定の排出源からのCO2を「減らす」技術であるのに対し、CDRは、すでに大気中に存在するCO2を直接「除去する」技術である。CCSをバイオマス発電と組み合わせたBECCSや、大気から直接CO2を回収するDACCSは、CDRに分類される。
CCSのプロセス
CCSのプロセスは、大きく「分離・回収」「輸送」「貯留」の3つのステップで構成される。
- 分離・回収(Capture)
排出源からCO2を分離する方法には、主に三つの方式がある。- 燃焼後回収(Post-combustion)
既存の発電所などで、排出される排ガスの中から化学吸収液などを用いてCO2を分離する方式である。既存設備への後付けが可能な点が利点である。 - 燃焼前回収(Pre-combustion)
化石燃料を燃焼させる前にガス化し、CO2と水素(H2)に分離する方式である。CO2を回収し、水素を燃料として利用する。 - 酸素燃焼(Oxy-fuel combustion)
空気ではなく、純酸素で燃料を燃焼させ、高濃度のCO2ガスを発生させて回収を容易にする方式である。
- 燃焼後回収(Post-combustion)
- 輸送(Transport)
回収したCO2を、パイプラインや船舶を用いて、貯留地まで輸送する。 - 貯留(Storage)
輸送されたCO2を、地上800メートル以上深くの地中にある、隙間の多い地層(帯水層や、採掘を終えた石油・ガス田など)に圧入する。CO2は、その上を覆う、ガスの通さない固い地層(遮蔽層)によって、数千年以上にわたって安定的に封じ込められる。
CCSの重要性と対象産業
削減困難セクターへの現実的な解決策
CCSの重要性は、再生可能エネルギーへの転換だけでは脱炭素化が極めて困難な、特定の産業分野に「現実的な解決策」を提供する点にある。
これは、気候変動対策における省エネや再エネ導入を最優先しつつも、どうしても排出されてしまうCO2を安全に最終処分する「CO2の最終処分場」の役割を担うことを意味する。
ハード・トゥ・アベイト(削減困難な)セクター
特に、以下の「ハード・トゥ・アベイト(削減困難な)」セクターにとって、CCSは不可欠な技術と見なされている。これらの産業なくして現代社会は成り立たず、多くの開発途上国にとって、その役割は決定的である。CCSは、これらの産業活動と脱炭素化を両立させるための、重要な架け橋となり得る。
- セメント: 製造過程の化学反応で、原料の石灰石からCO2が必然的に発生する。
- 鉄鋼: 製鉄プロセスでコークスを使用するため、大量のCO2が排出される。
- 化学: 同様に、化学反応を伴うプロセスが多い。
- 化石燃料発電: 再エネの出力変動を補うための調整電源として、火力発電が必要となる場合がある。
メリットと課題
CCSは大きな可能性を秘める一方で、その導入には経済的、技術的、社会的な課題が山積している。
メリット
- 削減困難セクターの脱炭素化
他に代替手段の少ない産業の排出削減を可能にする。 - 低炭素水素(ブルー水素)の製造
天然ガスから水素を製造する際に排出されるCO2を回収することで、クリーンな水素を大量に供給できる。 - 既存インフラ・雇用の活用
化石燃料産業の既存のインフラや、地質学の専門知識を持つ人材を活用できる可能性がある。
課題
- 莫大なコストとエネルギー消費
CCS設備の建設・操業には巨額の投資が必要である。また、回収プロセス自体がエネルギーを消費するため、発電所の効率が低下する(エネルギーペナルティ)。 - 貯留の安全性と長期的な責任
CO2が将来にわたって漏洩しないことを保証するための、厳格なモニタリング・測定・検証(MMV)が不可欠である。万が一漏洩した場合の、数百年後までの長期的な責任の所在が不明確である。 - 「モラルハザード」のリスク
CCSが存在することで、本来進めるべき化石燃料からの脱却や再生可能エネルギーへの転換が遅延する、いわゆる「延命措置」として利用されるリスクがある。 - 途上国における導入の困難さ
資金、技術、ガバナンスの全ての面で、多くの途上国にとって自力での導入は極めて困難である。
まとめ
CCSは、気候変動対策の「銀の弾丸(特効薬)」ではないが、特定の分野においては、他に代えがたい重要な選択肢の一つである。
- CCSは、発電所や工場から排出されるCO2を回収し、地中深くに貯留する技術の総称である。
- セメントや鉄鋼といった「削減困難セクター」の脱炭素化に不可欠な役割を果たすと期待されている。
- 莫大なコスト、貯留の長期的な安全性、そして化石燃料依存を延命させかねないモラルハザードが大きな課題である。
- その真価は、バイオマス発電(BECCS)や大気直接回収(DACCS)と組み合わせ、単なる排出削減から「炭素除去(ネガティブ・エミッション)」へと進化する点にある。
今後の展望として、CCSの普及の鍵は、技術革新による抜本的なコスト削減と、CO2貯留の長期的な安全性と責任に関する、国際的な法的枠組みの構築にかかっている。
そして最も重要なのは、CCSを、再生可能エネルギーへの移行を遅らせるための「言い訳」としてではなく、どうしても避けられない排出に対処するための「最後の砦」として、厳格な条件下でのみ活用するという、社会全体の賢明な合意形成である。この技術が、真に公正で持続可能な未来への移行に貢献できるかは、私たちの賢明な選択にかかっている。