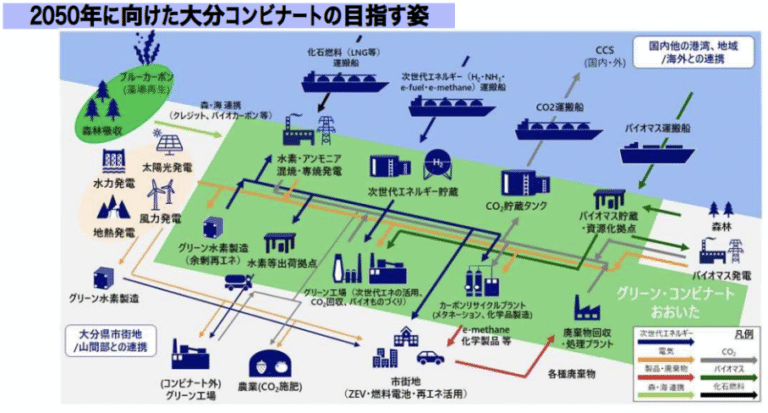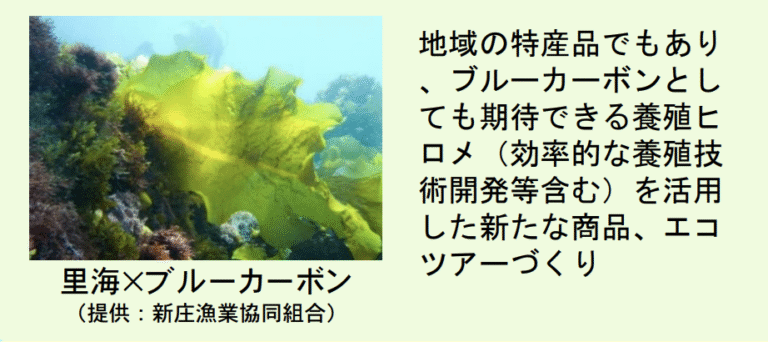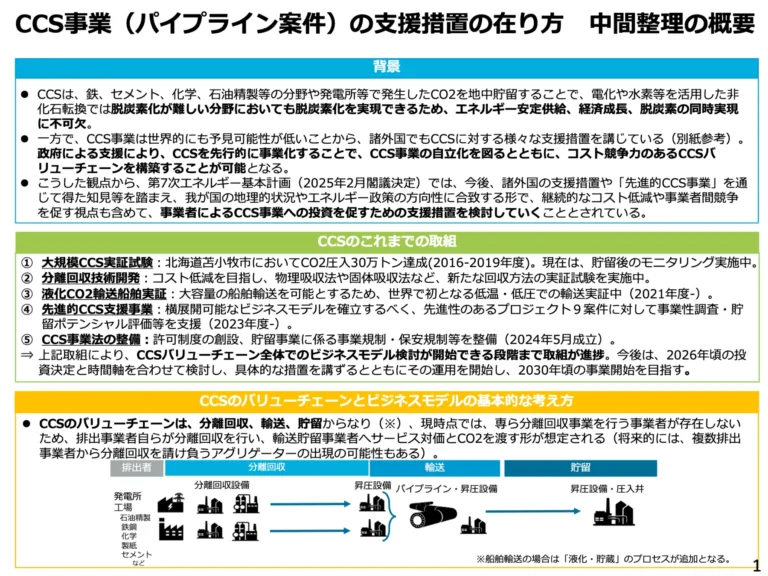産官学連携プラットフォームである瀬戸内渚フォーラムは、藻場再生を伴う二酸化炭素(CO2)吸収価値の「ブルーカーボンクレジット」取得を目標に掲げ、活動フェーズを現状把握の「診断」から、具体的な「対策」へと移行した。フォーラムを運営するイノカが11月14日に発表したもので、新たに今治造船、共英製鋼、福山市、玉野市など、多様な業種・自治体が新規参画し、第2期「対策」フェーズを本格始動した。
同フォーラムは、深刻化する瀬戸内海の藻場消失に対応するため、環境保全をコストではなく、ブルーカーボンを活用した地域経済を活性化させる「事業」として確立することを目指している。第2期では、初年度の科学的調査結果に基づき、「再生した藻場によるCO2吸収価値をブルーカーボンクレジットとして取得するための取り組みに挑戦する」ことを主要な行動計画の一つに明確に位置づけた。
科学的根拠に基づき「海域ごと」の課題に対応へ
フォーラムは初年度の調査で、香川県三豊市、岡山県玉野市胸上、広島県三原市の3海域において統一手法による比較調査を実施した。その結果、藻場再生における課題は海域によって「全く異なる」という科学的知見を導き出し、「画一的な解決策は存在しない」ことを実証した。
- 香川・三豊エリア:海底からの硫化水素発生がアマモ(海草の一種)の生育を阻害している可能性。
- 岡山・胸上エリア:環境変化により、アマモが他の藻類との生存競争に敗れている可能性。
- 広島・三原エリア:激しい潮流に適応したアマモが生育しており、特殊環境下での再生モデルとなりうる可能性。
この結果を受け、第2期「対策」フェーズでは、各海域の固有の課題(硫化水素、食害、生存競争など)に応じた解決策を実装するため、フィールドでの実証実験を引き続き推進し、CO2吸収源の再生活動の計画・実行・評価を行う枠組み構築を加速する。
鉄鋼・造船も参画、クレジット化へ技術と知見を結集
第2期では、新たに6団体が参画し、産官学連携を強化した。特に電炉メーカーである共英製鋼株式会社は、製造過程で生じる電炉スラグに着目し、「藻場創出という新たな価値の可能性を探る技術開発を進めている」と表明した。同社の取り組みは2024年度に環境省の環境技術実証(ETV)事業の実証対象技術として選定されており、産業副産物を活用したブルーカーボン創出の試みとして注目される。
今治造船は、「海と地域の価値をつなぎ、新しい連携と創造が生まれる本フォーラムに加わることは大きな誇りだ」と参画の意義を述べた。また、自治体からは玉野市と福山市が加わり、漁獲量の減少や藻場の減少といった地元の深刻な課題解決のため、「本フォーラムに参加する他の団体と知見を交わし、瀬戸内海全体で水産資源及び漁場改善等に繋げていきたい」と福山市がコメントを寄せた。
同フォーラムは今後、藻場再生のCO2吸収量をブルーカーボンクレジットとして取得することに加え、活動地を国の「30by30目標」に貢献する「自然共生サイト」へ登録することを目指し、環境と経済の持続可能な両立を追求する方針だ。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000047217.html