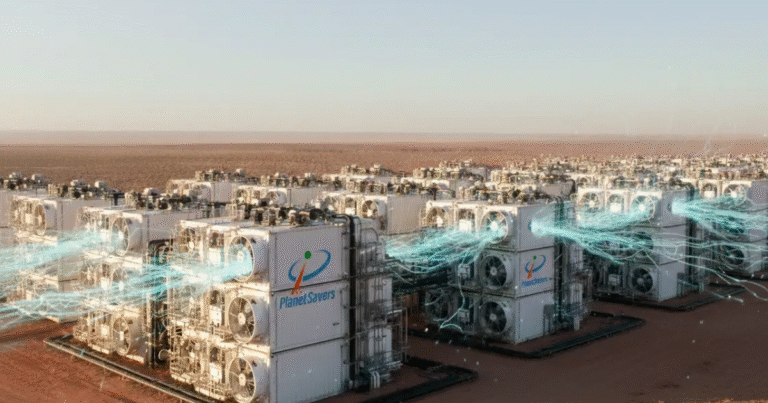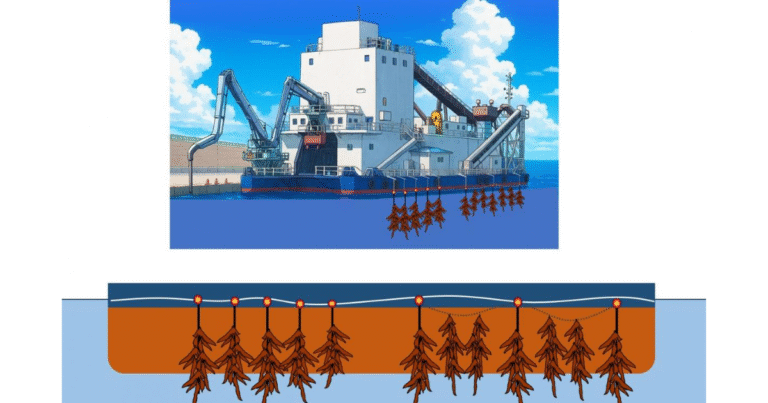マツダは11月15〜16日、ENEOSスーパー耐久シリーズ2025第7戦(栃木県)で、車載型CO2回収システム「Mazda Mobile Carbon Capture」を初めて公開実証した。多孔質ゼオライトを用いた装置で排気ガス中のCO2を直接吸着し、カーボンニュートラル燃料のHVO(水素化植物油)と組み合わせることで、走行距離に比例して大気中CO2を削減する可能性を検証した。2035年に「走るほどCO2が減る」モビリティの実現を掲げる同社にとって、重要な技術検証となった。
マツダは、日本モビリティショー2025で示した「The Joy of Driving Fuels a Sustainable Tomorrow(走る喜びがサステナブルな未来をつくる)」というビジョンの下、内燃機関を活かした低炭素モビリティの実像を探っている。今回の試験では、レース車両「MAZDA SPIRIT RACING 3 Future Concept(55号車)」に同システムを搭載した。
装置は多孔質ゼオライトをCO2吸着材として用い、排気流からCO2を直接回収する仕組みである。高温・高負荷のレース環境においてCO2吸着が確認されたことは、車載型CDR(炭素除去)の実用化に向けた初のフィールド検証となる。
車両は欧州で商用化されているカーボンニュートラル燃料HVOを使用した。燃料調達段階で排出されるCO2を原料由来で相殺しつつ、排気段階でもCO2を回収することで、マツダは「カーボンニュートラル燃料×車載CO2回収」の完全ループが成立するかを検証した。内燃機関を継続利用する領域、特に長距離輸送・高出力用途において、電動化と並行する代替的なGHG削減策として位置付ける。
マツダは次シーズンのスーパー耐久シリーズでも実証を継続し、CO2回収率や熱マネジメント、重量・エネルギー統合の最適化を進める方針だ。担当者は「吸着材や装置構成を高度化し、モビリティに適したCO2回収のかたちをさらに追求する」と述べた。
同社は2035年に向けて、車載型CDR車両の実現可能性を探りつつ、将来のカーボンマイナス型モビリティの構築を目指す。次の節目は2026年シーズンの追加実証となり、回収効率の数値検証が焦点となる。
参考:https://newsroom.mazda.com/en/publicity/release/2025/202511/251117b.html