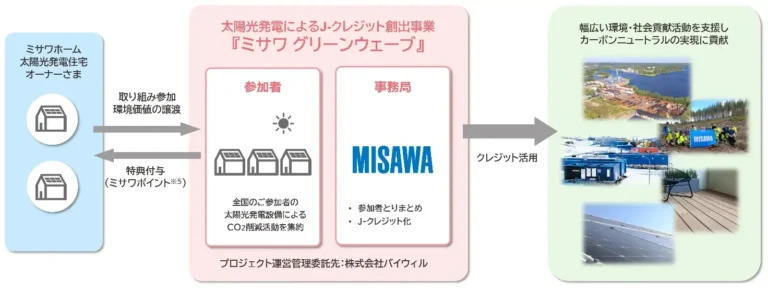国際標準化機構(ISO)と温室効果ガスプロトコル(GHGプロトコル)は9月9日、温室効果ガス(GHG)排出量の算定と報告に関する基準を統一し、新しい国際基準を共同で開発すると発表した。これにより、企業や投資家、政府が共通のルールを使えるようになり、カーボンクレジットや炭素除去(CDR)の信頼性が大きく高まる見通しだ。
今回の提携では、ISOが持つ「ISO 1406Xシリーズ」とGHGプロトコルの「企業会計・報告基準」「スコープ2・3基準」を一本化し、共通ロゴ付きの国際標準として発行する。また、製品ごとのカーボンフットプリント基準も共同で策定し、サプライチェーン全体の排出量データを可視化することで、企業の脱炭素戦略を後押しする。
ISOのセルヒオ・ムヒカ事務局長は「気候行動を簡単にし、すべての関係者の負担を減らす新しい時代の幕開けだ」と語った。GHGプロトコル運営委員長のジェラルディン・マチェット氏も「企業や製品、プロジェクトの算定基準を一つにすることで、ユーザーの混乱をなくす」と強調した。
これまでGHG排出量の基準は複数存在し、範囲や検証方法が異なっていたため、企業や投資家は対応に苦労してきた。今回の統一は、主要7カ国(G7)に意見を届ける「B7」や、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が求めていた方向性とも一致する。
ISSBのエマニュエル・ファベール議長は「投資家にとっては、世界共通で比較できるカーボンデータが資本配分の判断に不可欠だ」と歓迎した。また、COP30のハイレベルチャンピオンであるダン・イオシュペ氏は「統一基準がネットゼロへの移行を加速させる」と述べた。
ISOとGHGプロトコルはすでに国際的に広く使われており、ISOは各国の法規制の基盤、GHGプロトコルは自主的な情報開示の基準として参照されている。今後の統一基準は、政策的な妥当性と技術的な厳密さ、そして実務的な使いやすさを兼ね備えることで、国境を越えたカーボンクレジット市場の信頼性を高めることになる。
両組織は今後、専門家による共同作業を通じて基準を整備し、2026年にも最初の成果を公表する予定だ。11月に開かれるCOP30でも、この統一基準が大きな焦点となる見込みである。
参考:https://ghgprotocol.org/blog/release-iso-and-ghg-protocol-announce-strategic-partnership-deliver-unified-global-standards