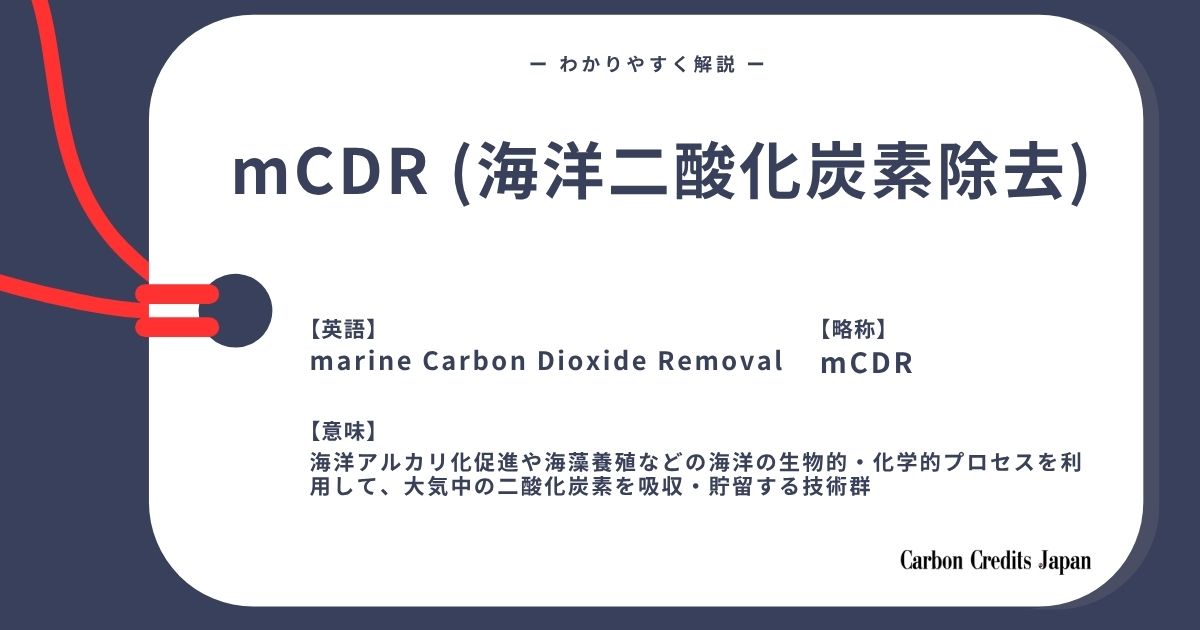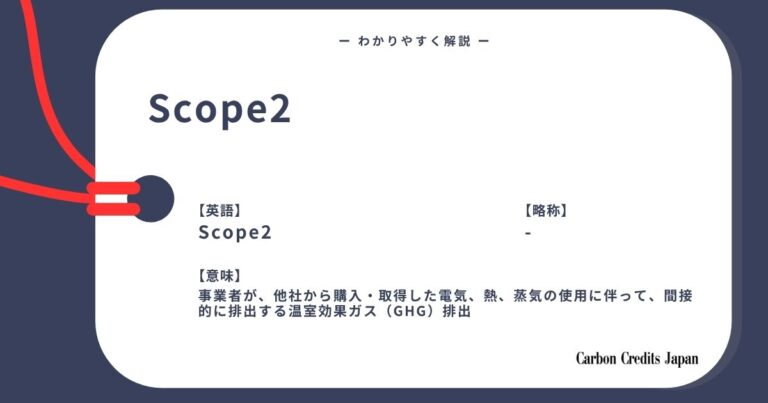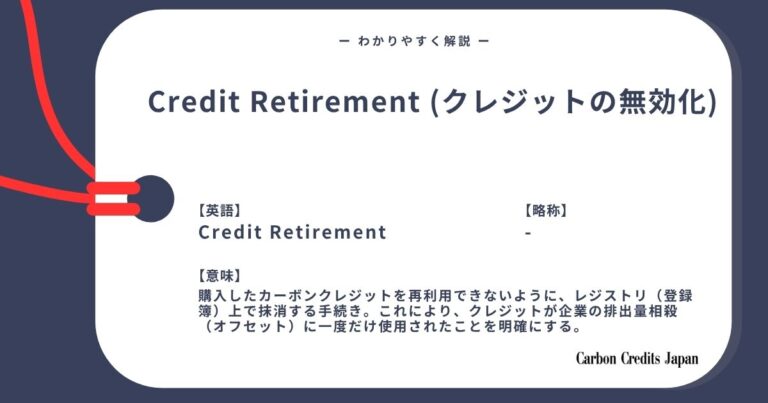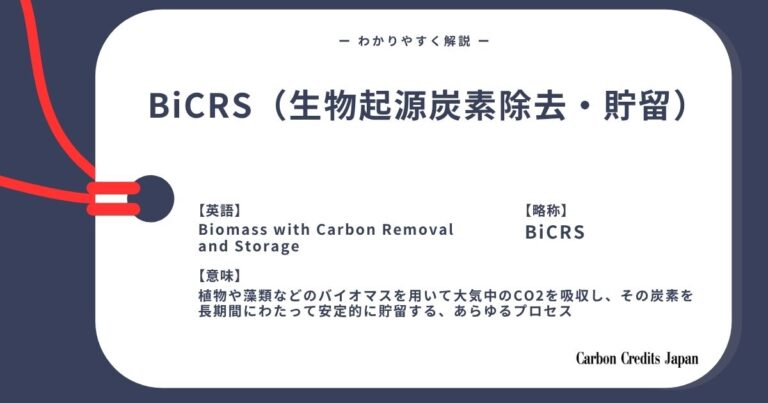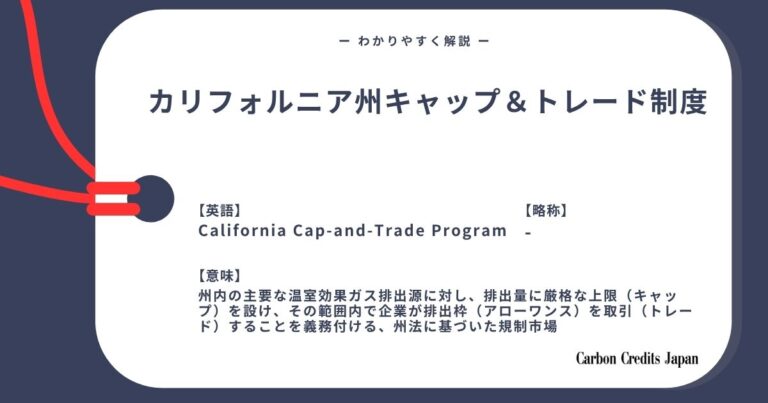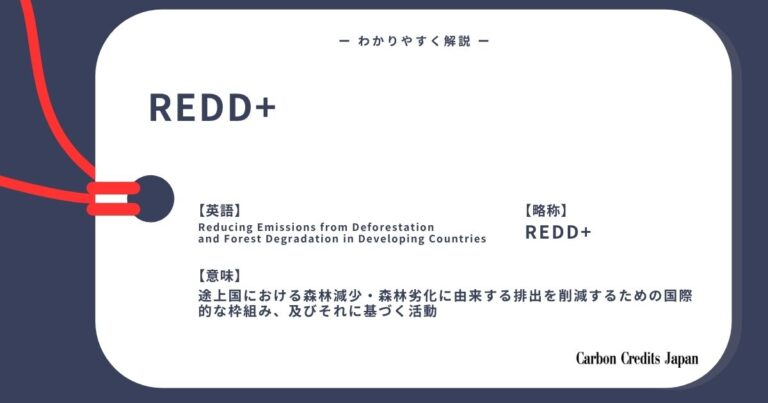はじめに
地球の表面積の約7割を占める海洋は、人類が排出した二酸化炭素(CO2)の約4分の1を吸収してきた、最大の炭素貯蔵庫です。この海の巨大なポテンシャルを、気候変動対策のためにさらに活用しようとするアプローチが**mCDR(海洋二酸化炭素除去、marine Carbon Dioxide Removal)**です。これは、陸上のCDRだけでは追いつかない大規模なCO2除去を実現するフロンティアとして、大きな期待と同時に未知のリスクを秘めています。本記事では、「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から、mCDRの主な手法、それが持つ計り知れない可能性、そして海洋生態系やそれに依存する途上国への影響、国際的なガバナンスといった、乗り越えるべき課題について解説します。
用語の定義
一言で言うと、mCDRとは**「海洋の生物学的・化学的・物理的なプロセスを人為的に促進または改変することで、大気中のCO2を海洋に吸収させ、長期間にわたって貯留する技術やアプローチの総称」**です。
海洋は、大気中のCO2と常にガスの交換を行っており、自然の状態でバランスを保っています。mCDRは、このバランスを意図的に変化させ、CO2の吸収量を排出量よりも多くする、つまり海洋をより強力な「CO2の吸収源」に変えることを目指します。
この概念を**「炭酸飲料」で例えてみましょう。グラスに注がれた炭酸飲料は、時間が経つと炭酸(CO2)が抜けていきます。これは、グラスの中のCO2濃度が、空気中の濃度よりも高いために起こる自然なプロセスです。mCDRは、これとは逆の反応を意図的に起こします。様々な手法を用いて海水の”炭酸濃度”(専門的にはpCO2)を下げる**ことで、大気という巨大なペットボトルから、海水というグラスへ、より多くのCO2が溶け込むように促すのです。
重要性の解説
mCDRは、まだ研究開発の初期段階にありますが、その議論は気候変動対策の未来を左右するほど重要です。
- 圧倒的な規模(スケール)の可能性: 海洋の巨大さを考えれば、mCDRが持つ理論上のCO2除去ポテンシャルは、陸上のどのCDR手法よりも大きいとされています。ギガトン単位の除去を実現するためには、海洋の活用が不可欠となる可能性があります。
- 海洋酸性化の緩和という共同便益: 一部のmCDR手法(特に海洋アルカリ化増強)は、CO2を吸収するだけでなく、CO2の溶け込みによって進む海洋酸性化を直接的に緩和する効果が期待されます。これは、サンゴ礁や貝類といった海洋生態系を保護することに繋がります。
- 市場の信頼性(Integrity)とMRVの究極的課題: 広大で常に変動する海洋の中で、「どれだけのCO2が、どれくらいの期間、確実に貯留されたか」を測定・報告・検証(MRV)することは極めて困難です。信頼性の高いカーボンクレジットを創出するためには、このMRV手法の確立が最大のハードルとなります。
- 国際ガバナンスと公正な移行: 海は国境を越えて繋がっています。ある海域でのmCDRの実践が、他の国の漁業や沿岸コミュニティに予期せぬ影響を与える可能性があります。国際的なルール作りや、特に海洋資源への依存度が高い開発途上国や島嶼国の声を反映した、公正なガバナンスの構築が不可欠です。
仕組みや具体例
mCDRには、生物の力を借りるものから、化学的なアプローチまで、様々な研究が進められています。
- 海洋アルカリ化増強(Ocean Alkalinity Enhancement, OAE):
- 仕組み: カンラン石などのアルカリ性の鉱物を細かく砕いて海洋に散布したり、海水を電気分解したりすることで、海水のアルカリ度を高めます。これにより、海水がCO2を吸収する化学的な能力が向上します。岩石風化促進(ERW)の海洋版とも言えます。
- 特徴: CO2除去と海洋酸性化の緩和を同時に行える可能性がありますが、生態系への影響や鉱物の大規模な採掘・輸送が課題です。
- 大型海藻(昆布など)の養殖と沈降:
- 仕組み: 沿岸域や外洋でコンブやワカメといった大型の海藻を大規模に養殖します。成長した海藻は光合成によって大量の炭素を体内に固定します。これを収穫せずに、重りをつけるなどして深海に沈めることで、炭素を数百年から数千年にわたって隔離します。
- 特徴: 生物ベースのアプローチで、生態系への影響が比較的少ないと考えられていますが、養殖の規模や沈降の効率、深海生態系への影響評価が課題です。
- 電気化学的手法(Direct Ocean Removal, DOR):
- 仕組み: 海水に電気を流すことで化学的な処理を行い、海水に溶けているCO2(炭酸水素イオンなど)を直接、気体や固体の形(炭酸カルシウムなど)で分離・回収します。CO2が取り除かれて”空腹”になった海水は、再び大気からCO2を吸収します。
- 特徴: 閉鎖的なシステムで除去量を正確に測定できる可能性がありますが、莫大な電力が必要であり、コストが非常に高いです。
国際的な動向と日本の状況
国際的な動向
mCDRは、科学的・倫理的な不確実性が大きいことから、その研究開発や実証は極めて慎重に進められています。
- ロンドン条約・議定書といった海洋投棄を規制する国際的な枠組みが、mCDRをどう位置づけるかについての議論を進めています。無秩序な実証実験は厳しく制限されており、科学的調査が優先されています。
- **全米科学・工学・医学アカデミー(NASEM)**などが、mCDRの研究開発に向けた大規模なロードマップを提言し、米国政府も研究資金を投じ始めています。
- 民間では、Stripeなどが支援するCDRの買い手連合Frontierが、有望なmCDRスタートアップ(例: Running Tide)のクレジット事前購入を行うなど、技術革新を後押しする動きも出てきています。
日本の状況
四方を海に囲まれた日本にとって、mCDRは大きなポテンシャルを秘めた分野です。
- **海洋研究開発機構(JAMSTEC)**などの研究機関が、海洋アルカリ化増強やブルーカーボンに関する基礎研究を進めています。
- 日本が推進するCCS(二酸化炭素回収・貯留)の貯留先として、海底下の地層が有望視されており、海洋を利用した気候変動対策への関心は高いと言えます。しかし、外洋での大規模な実証はまだ行われておらず、国際的なガバナンスの動向を注視している段階です。
メリットと課題
mCDRは、気候変動対策の「究極の切り札」となる可能性と、「パンドラの箱」となるリスクの両方を内包しています。
| メリット | 課題 |
| ✅ 圧倒的な除去ポテンシャル: 地球最大の炭素吸収源である海洋を利用するため、理論上のCO2除去規模は陸上の手法を大きく上回る。 | ⚠️ 生態系への予期せぬ影響: 海洋の化学的性質や生物プロセスを人為的に変えることは、プランクトンから魚類、海洋哺乳類に至るまで、食物網全体に予測不可能な影響を及ぼすリスクがある。 |
| ✅ 土地利用との競合がない: 陸上の植林やバイオマス生産のように、食料生産用地と競合することがない。 | ⚠️ MRV(測定・報告・検証)の極度の困難さ: 広大で複雑な海洋環境において、追加的に吸収・貯留されたCO2量を正確に測定し、自然変動と区別することは、現在の技術では極めて難しい。 |
| ✅ 海洋酸性化の緩和: 特にOAEは、CO2除去と同時に、海洋生態系を脅かす酸性化問題を緩和できる可能性がある。 | ⚠️ ガバナンスの欠如と社会的合意: どの国が、どの海域で、どのような手法を、どれくらいの規模で実施する権利を持つのか。国境を越える影響をどう管理するのか。国際的なルールや社会的な合意形成が全く追いついていない。 |
まとめと今後の展望
mCDRは、気候変動という地球規模の危機に対し、海洋という地球最大のシステムを用いて立ち向かう、壮大なスケールの挑戦です。そのポテンシャルは計り知れませんが、人類がまだ完全に理解していない海洋生態系に介入することの責任は、それ以上に重大です。
要点の整理
- mCDRは、海洋のプロセスを人為的に活用し、大気中のCO2を海洋に吸収・貯留するアプローチの総称である。
- 海洋アルカリ化増強(OAE)や大型海藻の養殖・沈降などが研究されているが、まだ初期段階にある。
- 圧倒的な除去ポテンシャルを持つ一方で、生態系への影響、MRVの困難さ、国際ガバナンスの欠如という巨大な課題を抱える。
- 気候変動ファイナンスの対象となるには、科学的理解の深化と、透明性の高い国際ルールの構築が不可欠である。
今後の展望
mCDRの未来は、性急な大規模展開ではなく、「責任ある研究開発」にかかっています。まずは、閉鎖系や沿岸域での小規模な実験を通じて、その有効性と安全性を慎重に見極め、生態系への影響を徹底的に監視することが最優先です。国際社会は、予防的原則に基づき、透明性の高い科学的評価とガバナンスの枠組みを構築しなければなりません。mCDRは、人類が海洋との新たな関わり方を学ぶ、長期的な探求の始まりであり、その舵取りには、科学、倫理、そして国際協調のすべてが問われることになるでしょう。