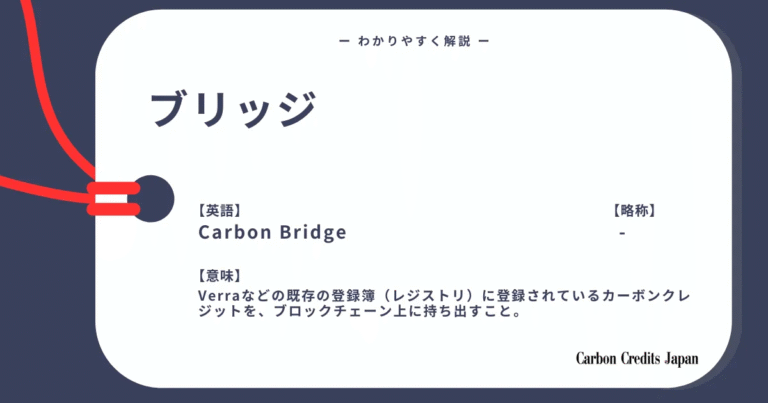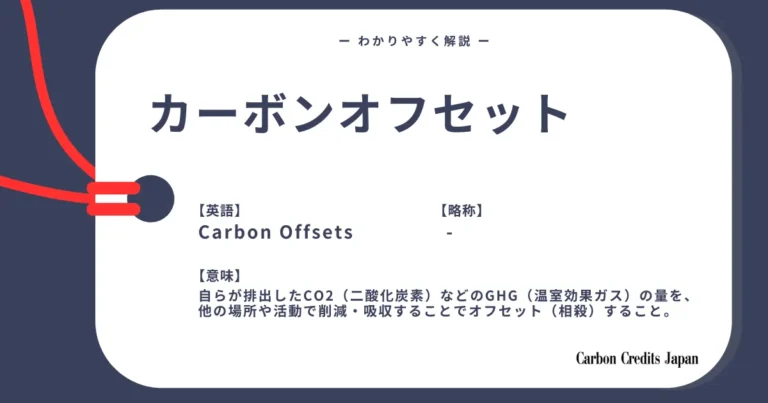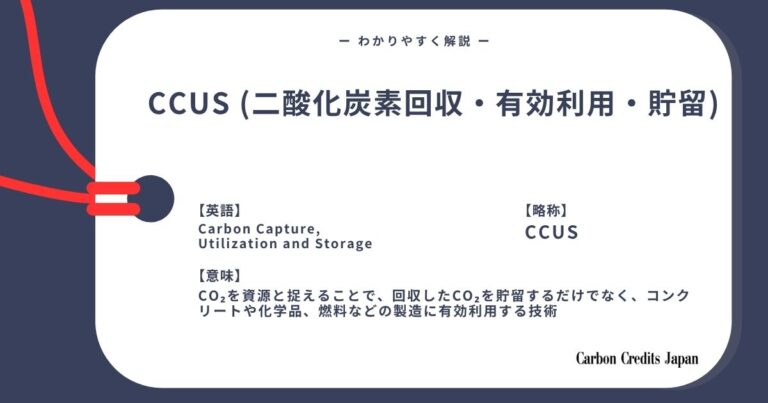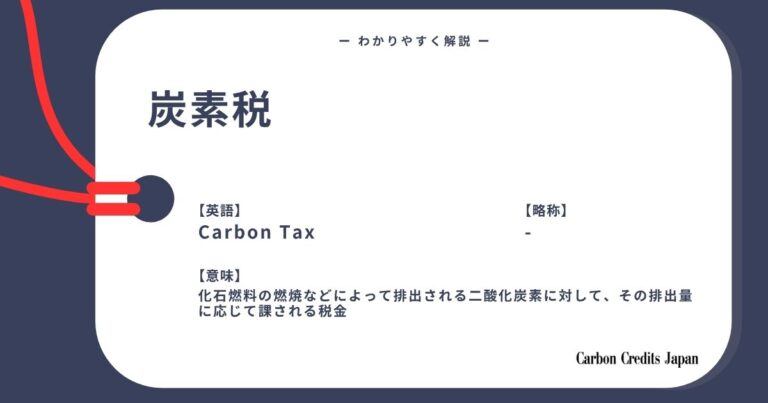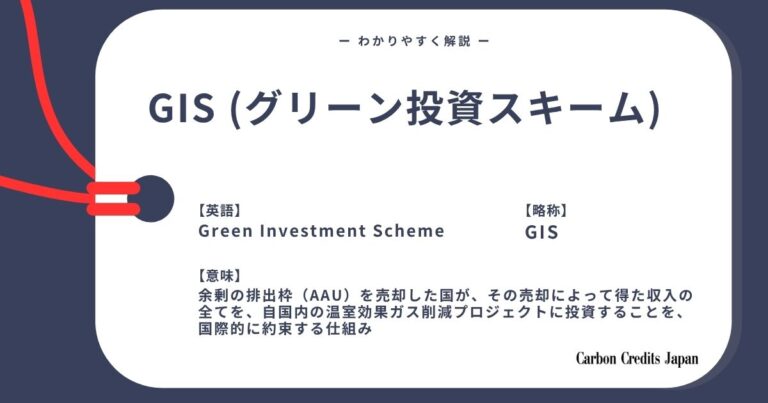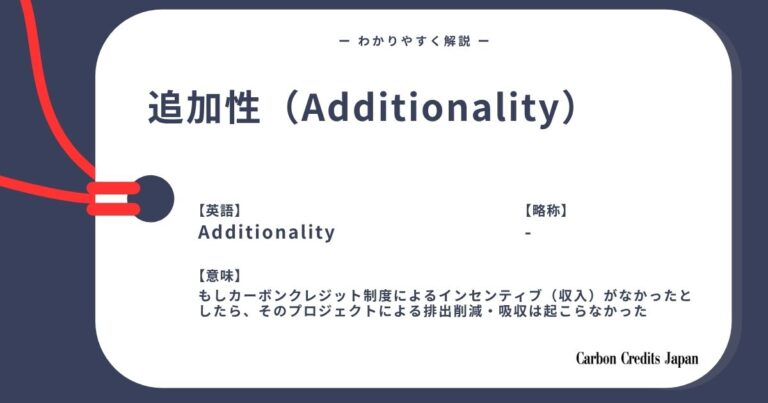大気中の二酸化炭素(CO2)を直接回収するDAC(Direct Air Capture)が陸上の主要な排出削減策であるのに対し、直接海洋回収(Direct Ocean Capture, DOC)は、地球最大の炭素吸収源である海洋の力を活用しようとする最先端の技術群である。
DOCは、海洋が自然に行っているCO2吸収プロセスを人為的に加速・増強することで、大気中からCO2を除去(Remove)しようとする技術を指す。この技術は、その計り知れないポテンシャルと、海洋生態系への影響という深刻なリスクの両面から、気候変動対策と気候変動ファイナンスの世界で注目を集めている。
直接海洋回収(DOC)とは
直接海洋回収(DOC)とは、「海洋の化学的・生物学的なプロセスに働きかけることで、海洋が大気中からCO2を吸収・貯留する能力を高める、一連の革新的な炭素除去(CDR)技術」のことである。
DOCは海洋CDR(Ocean-based Carbon Dioxide Removal)とも呼ばれる。このアプローチは、主に海水の化学的な性質を変化させ、CO2が溶け込みやすい環境を作り出すことを目指す。大気中のCO2を直接回収するDACとは異なり、地球の表面積の約7割を占める広大な海面そのものを、巨大な「CO2コレクター」として利用する考え方である。
DOCの仕組みと具体的なアプローチ
DOCの技術はまだ研究開発段階にあり、主に以下のようないくつかのアプローチが検討されている。
海洋アルカリ化(Ocean Alkalinity Enhancement, OAE)
海洋アルカリ化は、かんらん岩などのアルカリ性の鉱物を細かく砕いて海に散布する手法である。これにより、酸性化した海水を中和し、海洋のアルカリ度を高める。
海洋のアルカリ度が高まると、化学平衡を回復しようとする自然のプロセスを通じて、海洋は大気中からより多くのCO2を吸収できるようになる。これは、海洋酸性化という深刻な環境問題の直接的な解決策となり、サンゴ礁などの生態系を保護する可能性がある。
電気化学的手法(Electrochemical Approaches)
電気化学的手法は、再生可能エネルギーを用いて海水に電気を流し、電気分解のプロセスを利用する。
この手法では、海水から酸(塩酸)を取り除き、アルカリ化された海水を海洋に戻すことでCO2吸収を促す。取り除かれた酸は、別のプロセスで処理されるか、回収されたCO2と結合させて地中貯留される。大量のクリーンな電力が必要となるが、除去プロセスをより精密に制御できる可能性がある。
海洋施肥(Ocean Fertilization)
海洋施肥は、海洋の特定の領域に鉄などの栄養塩を散布し、植物プランクトンのブルーム(大発生)を促す手法である。
プランクトンは光合成によってCO2を吸収し、死んだ後に深海に沈むことで炭素を隔離する。生態系への予期せぬ影響(例:酸欠のデッドゾーン形成)のリスクが非常に高く、多くの科学者や国際条約(ロンドン条約)によって、現在は大規模な実施が厳しく制限されている。
メリットと課題
DOCは、究極の解決策となる可能性と、未知のリスクが同居する「諸刃の剣」である。
メリット
- 圧倒的なスケール
地球の海洋が持つ、理論上のCO2吸収・貯留ポテンシャルは、他のどのCDR技術よりも大きい。 - 高い永続性(Permanence)
海洋に吸収・貯留された炭素は、数百年から数千年にわたって大気から隔離される。 - 共同便益の可能性
海洋アルカリ化は、海洋酸性化の直接的な解決策となり、サンゴ礁などの生態系を保護する可能性がある。
課題
- 生態系への未知のリスク(最重要課題)
海洋の化学的性質を人為的に大規模に改変することが、海洋生物や食物連鎖にどのような予期せぬ影響を与えるか、まだほとんど分かっていない。 - 測定・報告・検証(MRV)の困難さ
広大で常に変動する海洋の中で、「追加的に」どれだけのCO2が、いつ、どこで吸収されたのかを正確に測定し、クレジットとして認証することは、技術的に極めて困難である。これは市場の信頼性を確保する上での最大の障壁である。 - 国際ガバナンスの欠如
ある国が大規模な海洋アルカリ化を行った場合、その影響は国境を越えて広がる可能性がある。こうした活動を誰が許可し、誰が監視し、万が一の悪影響に誰が責任を負うのかといった、国境を越える影響を管理するための国際的なルールや責任体制が存在しない。 - コストとエネルギー
特に電気化学的手法は、大量のクリーンな電力を必要とするため、コストとエネルギー効率が課題となる。