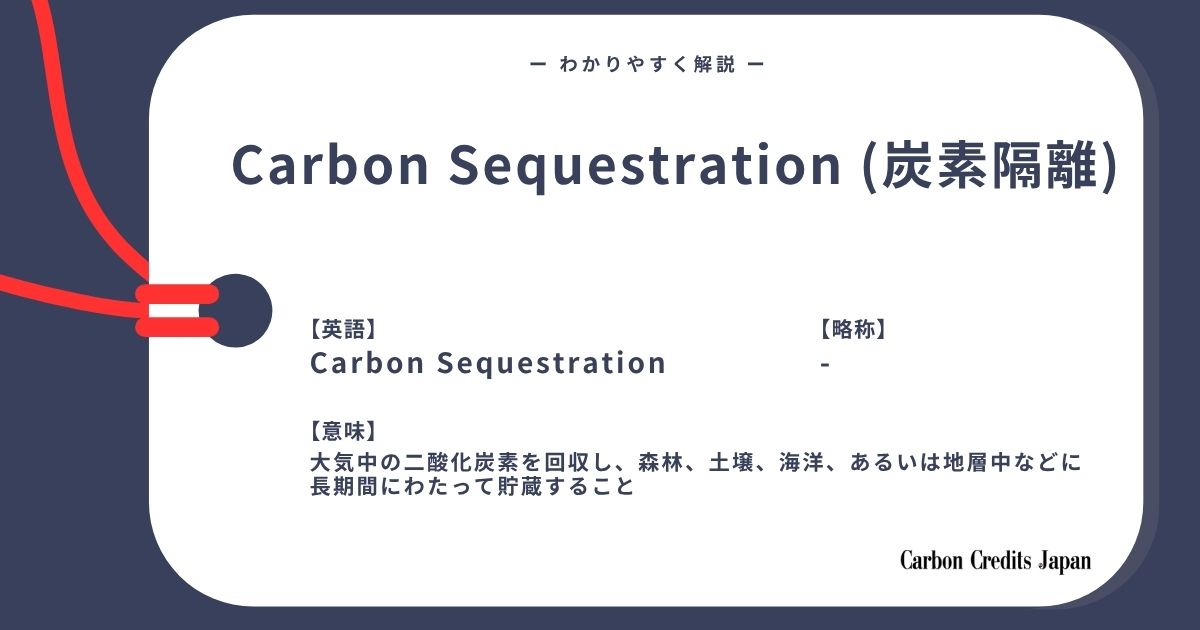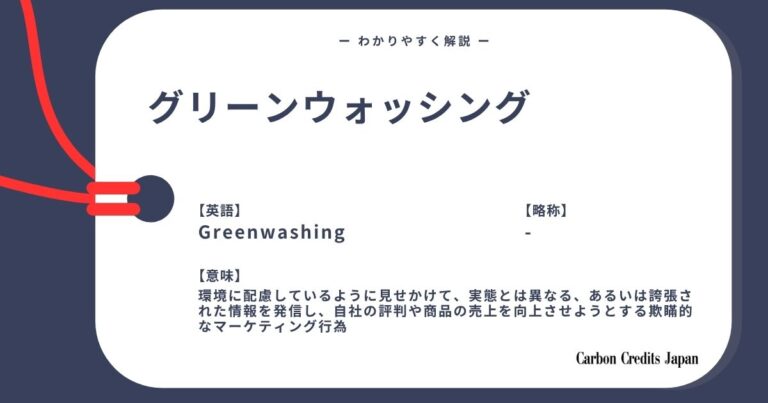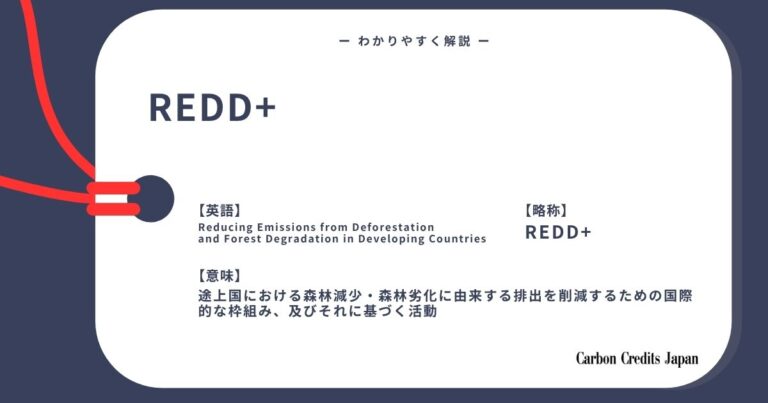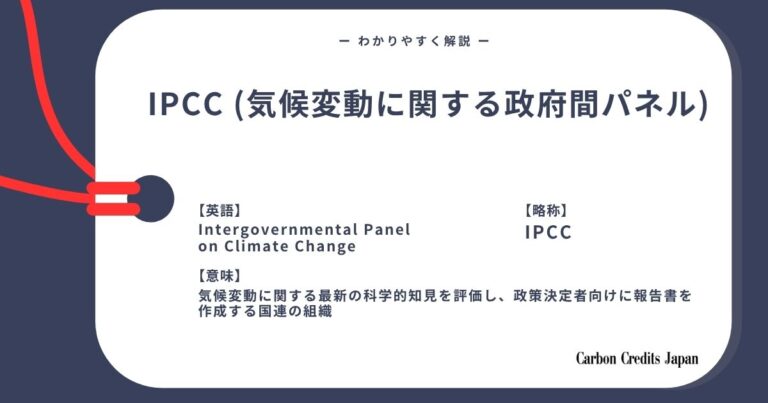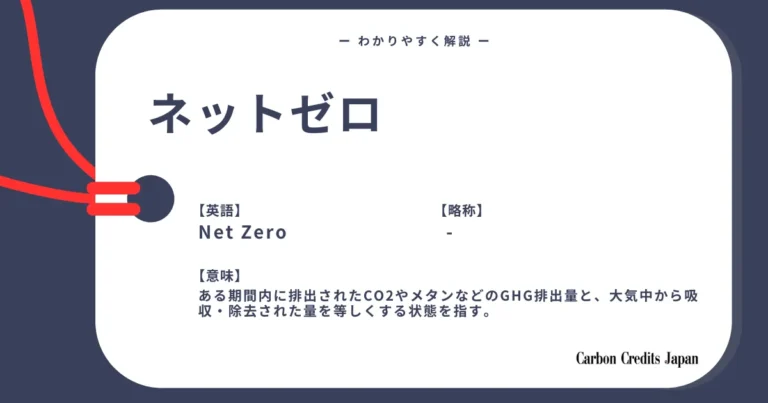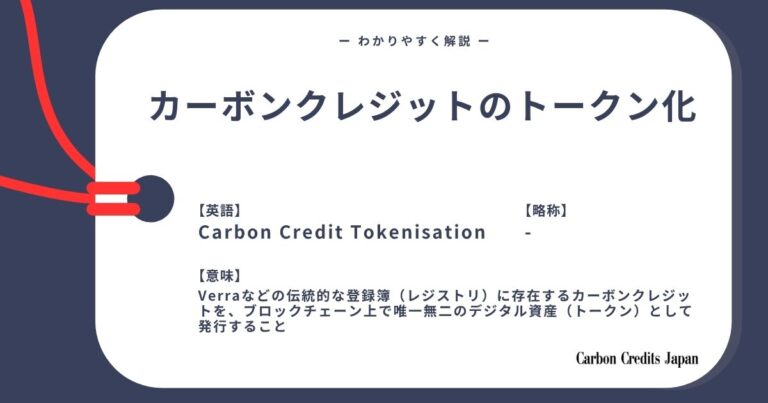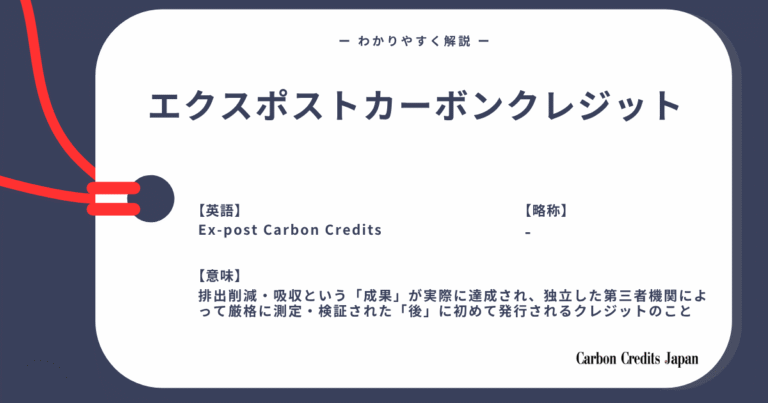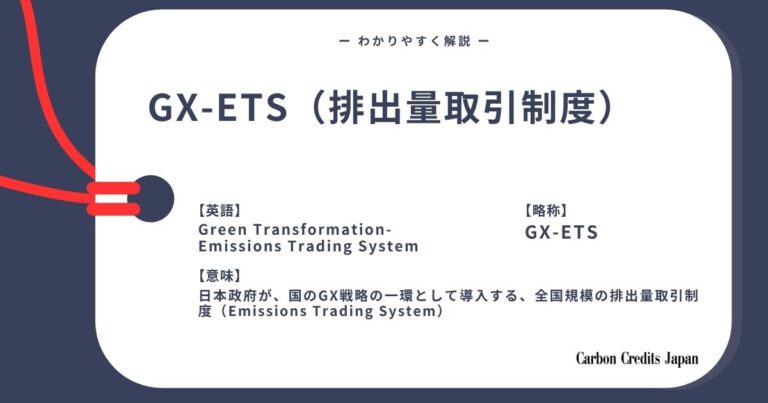気候変動対策は、温室効果ガスの「排出を減らす(緩和)」ことと、すでに大気中にある二酸化炭素を「取り除く(除去)」ことの両輪で進める必要がある。「ネットゼロ」を達成するためには、後者の「除去」したCO2を再び大気中に漏れ出さないよう、安全に長期間貯蔵するプロセスが不可欠だ。この重要なプロセスが炭素隔離である。
本記事では、国際開発と気候変動ファイナンスの視点から、炭素隔離の様々な手法、それが市場の信頼性や資金動員にどう関わるか、そして特に開発途上国における機会と公正な移行の課題について解説する。
炭素隔離とは
炭素隔離とは「大気中の二酸化炭素(CO2)を回収し、地中、海洋、あるいは森林や土壌といった生態系の中に、長期間にわたって安定的に貯留すること」である。
これは、CO2を貯めておく「貯蔵庫(リザーバー)」に移動させ、閉じ込めておくイメージに近い。炭素隔離は、二酸化炭素除去(Carbon Dioxide Removal, CDR)の一部であり、その最終段階の「貯留」を指すものである。
炭素隔離の重要性
炭素隔離は、パリ協定の目標達成に向けたシナリオにおいて、避けては通れない重要な戦略とされている。その理由は主に以下の4点に集約される。
ネットゼロ達成の必須条件
農業や一部の重工業など、排出を完全にゼロにすることが困難な分野(Hard-to-abate sectors)がどうしても残る。それらの残余排出量を相殺するためには、同量のCO2を大気から除去し、確実に隔離する必要があるためだ。
市場の信頼性の根幹
カーボンクレジット市場、特に除去系クレジットの価値は、そのCO2がどれだけ永続的に隔離されるかによって大きく左右される。隔離の期間が長く、モニタリングが確実であるほど、カーボンクレジットの信頼性と価格は高まる傾向にある。
開発途上国の新たな機会
多くの開発途上国は、広大な森林、豊かな土壌、マングローブ林といった、炭素隔離のポテンシャルを持つ自然資本に恵まれている。これらを活用したプロジェクトは、カーボンクレジットを通じて新たな収入源を生み出し、国の経済開発と気候変動対策を両立させる道を開く可能性がある。
資金動員の対象
永続性の高い炭素隔離技術(例:地中貯留)や、コベネフィットの大きい自然ベースの隔離プロジェクトは、インパクト投資を求める民間資金や、国際的な気候変動基金からの投資を呼び込む魅力的な対象となり得る。
仕組みや具体例
炭素隔離は、その貯留場所やメカニズムによって、大きく3つのタイプに分類される。
生物学的隔離
光合成のプロセスを利用して、生態系の中に炭素を固定する方法である。
- 森林
- 植林・再植林によって、樹木や森林土壌に炭素を貯留する。最も一般的で実績のある方法である。
- 土壌
カバークロップや不耕起栽培といった、リジェネラティブ農業を通じて、土壌中の有機物として炭素を貯留する。 - ブルーカーボン
マングローブ林、塩性湿地、海草藻場といった沿岸生態系に炭素を貯留する。単位面積あたりの炭素吸収速度が非常に速いのが特徴である。
地中貯留
回収したCO2を、地下深くの安定した地層に圧入し、封じ込める方法である。数千年以上の極めて長期的な隔離が可能とされる。
発電所や工場から排出されるCO2を分離・回収し、パイプラインなどで輸送した後、地下800m以上にある帯水層や、枯渇した石油・ガス田に圧入する。上部を泥岩などの硬い層(キャップロック)が覆っているため、CO2の漏出を防ぐことができる。CCSや、バイオマス発電と組み合わせたBECCSの中核をなす技術である。
技術的・鉱物的隔離
特定の技術を用いてCO2を化学的に安定した状態に変え、貯留する方法である。
- 岩石風化促進(ERW)
玄武岩などの粉末を散布し、化学反応を通じてCO2を重炭酸イオンに変え、最終的に海洋で鉱物化させる。 - コンクリートへの固定
CO2をコンクリート製品の製造過程で内部に注入し、鉱物として固定する技術も開発されている。
メリットと課題
炭素隔離は不可欠な戦略だが、その手法ごとに異なるメリットと課題を抱えている。
メリット
- ネットゼロ達成に不可欠
残余排出量を相殺する手段として、気候目標達成の鍵を握る。 - 大きなコベネフィット
生物学的隔離は、生物多様性の保全、土壌の健康改善、地域コミュニティへの貢献など、多くのプラスの副次効果を生む。 - 新たな経済・雇用の創出
新しいCDR技術の開発や、自然資本を活用したクカーボンレジット創出は、グリーンな産業と雇用を生み出す可能性がある。
課題
- 永続性の問題
生物学的隔離は、森林火災や病害、土地利用の変化によって、貯留した炭素が再び大気中に放出される「リバーサルリスク」を抱えている。 - 高コストとエネルギー消費
CCSやDACといった技術的・地中貯留アプローチは、設備投資や運転コストが高く、大量のエネルギーを必要とする場合が多い。 - 社会的・環境的リスクと公正な移行
大規模な植林や地中貯留サイトの建設は、地域の土地利用や水資源を巡る対立、先住民の権利侵害、生態系への予期せぬ影響といったリスクを伴う。利益が地域に公正に分配される仕組みが不可欠である。
まとめ
炭素隔離は、気候変動との闘いにおいて、攻撃(排出削減)だけでなく、防御(除去・貯留)の役割を果たす重要な戦略である。どの隔離手法が唯一の正解ということはなく、それぞれの長所と短所を理解し、適材適所で組み合わせていく「ポートフォリオ・アプローチ」が求められる。
今後は単にCO2を隔離するだけでなく、その永続性の長さ、MRV(測定・報告・検証)の堅牢さ、そして生物多様性や地域社会への貢献といったコベネフィットを統合的に評価することが重要となる。技術革新によるコスト低減と、人権や環境への配慮を両立させながら、高品質な炭素隔離を社会に実装していくことが、気候変動対策の鍵となるだろう。