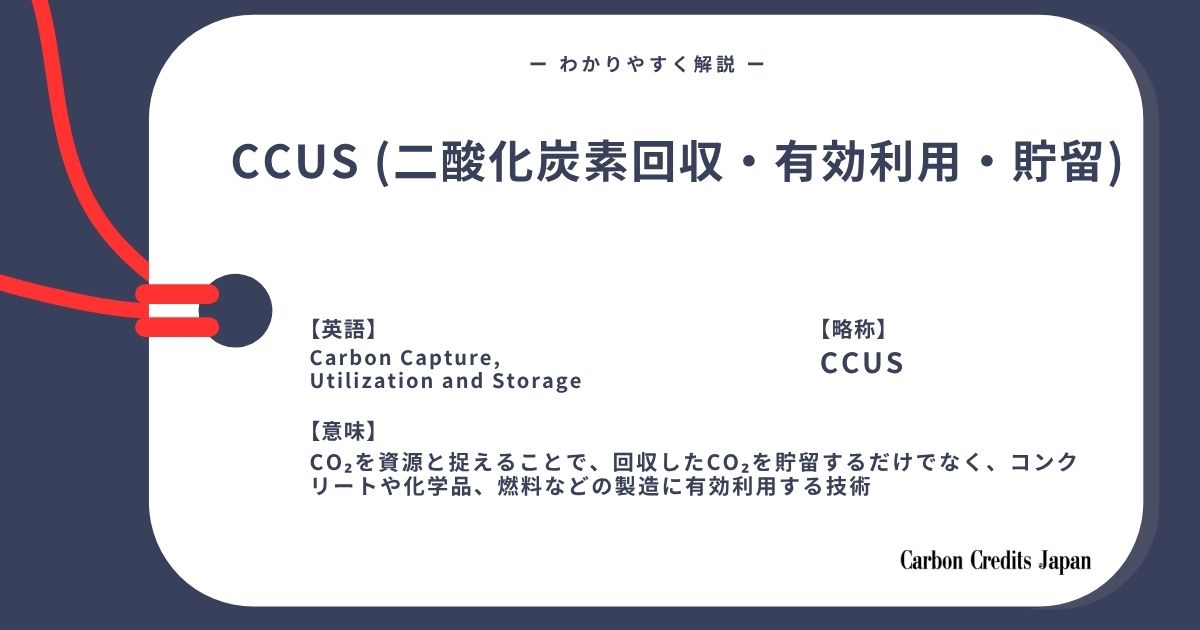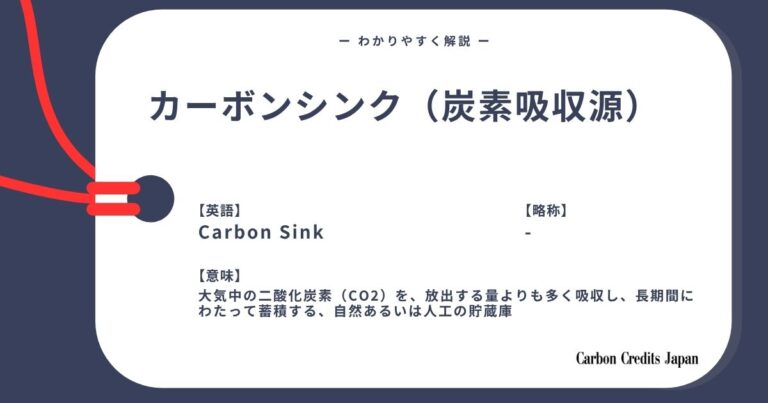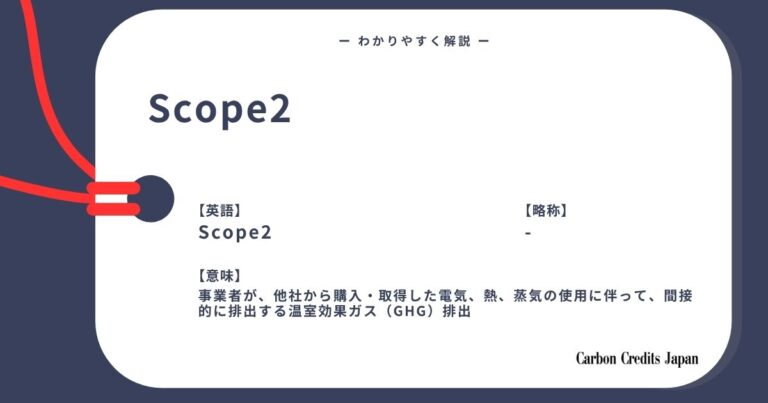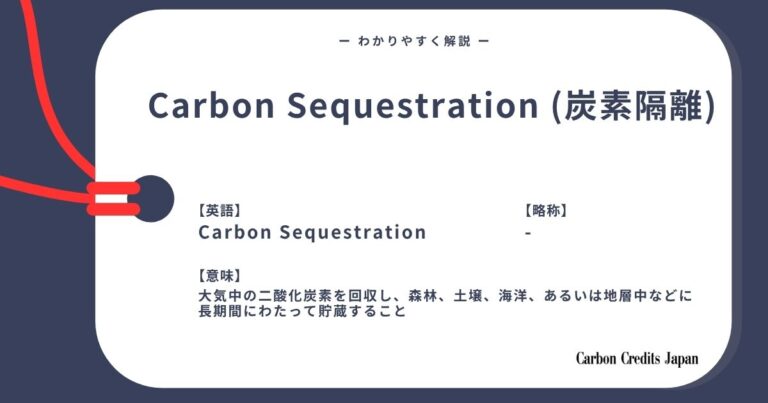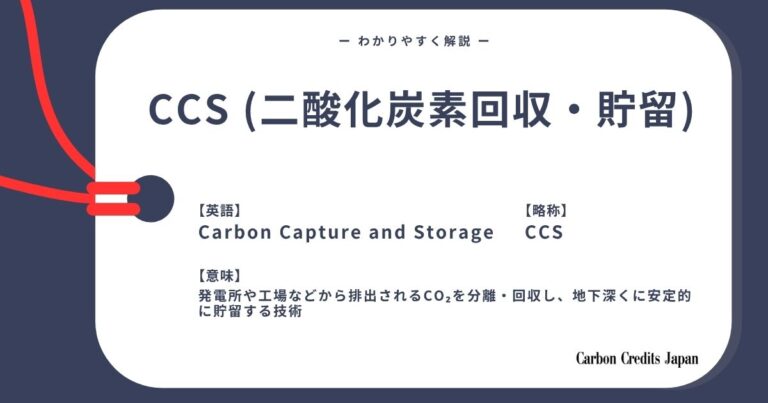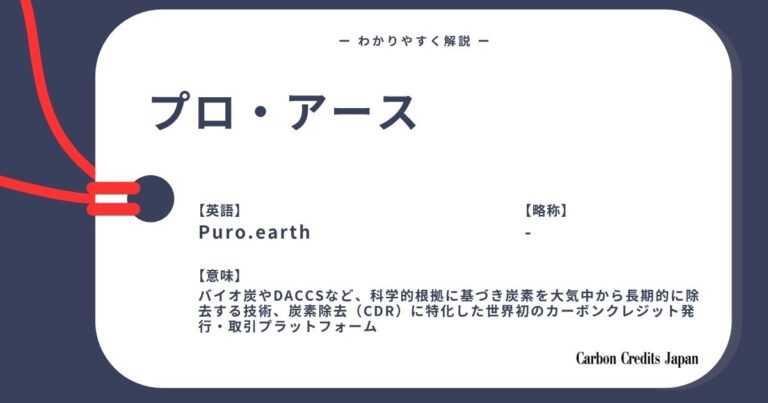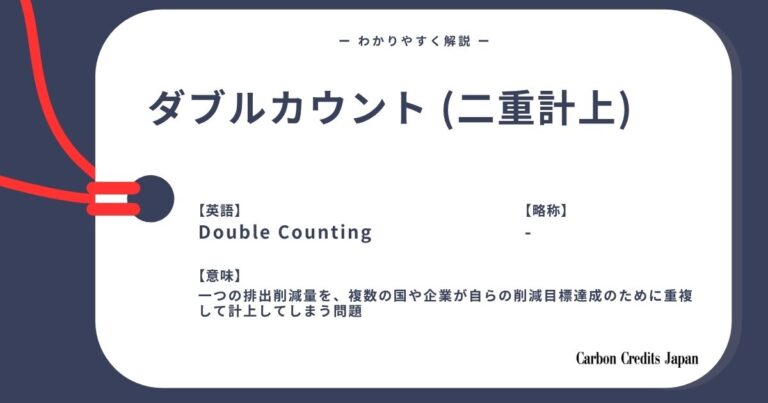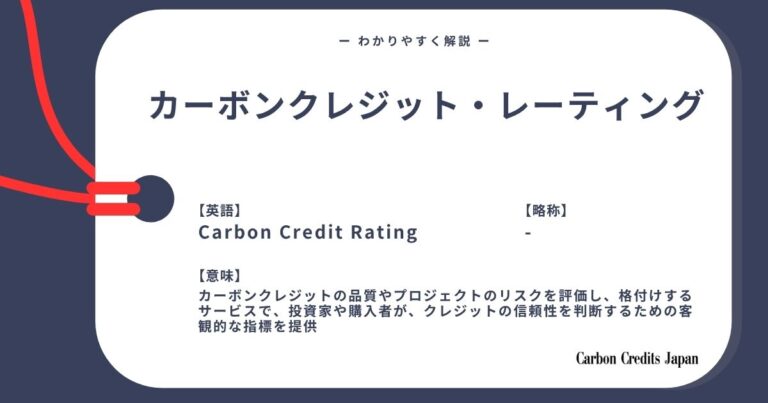CCS(炭素回収・貯留)が、排出された二酸化炭素(CO2)を地中に「埋めて処分する」技術であるのに対し、そのコンセプトをさらに一歩進めるアプローチが、「CCUS(Carbon Capture, Utilization, and Storage)」、すなわち「二酸化炭素の回収・利用・貯留」である。この技術は、CO2を単なる廃棄物ではなく「資源」として捉え直し、気候変動対策と経済活動を両立させる「サーキュラー・エコノミー」の実現に向けた、鍵となる技術として期待されている。
本記事は、CO2の「利用(Utilization)」という要素がいかにしてプロジェクトの経済性を向上させ、新たな民間資金を呼び込むのか、そしてこの新しい炭素循環産業がどのような可能性をもたらすのかを包括的に解説する。
CCUSとは
CCUSとは、「産業活動から排出されるCO2を分離・回収し、資源として『利用』するか、それが難しい場合は地中深くに『貯留』する一連の技術」の総称である。
CCUSは、CCS(Carbon Capture and Storage)の概念を内包し、それにCCU(Carbon Capture and Utilization)という選択肢を加えたものだ。すなわち、「C(回収)」した後のCO2の行き先として、「S(貯留)」という「ごみ処理場」だけでなく、「U(利用)」という「リサイクル工場」のルートを新たに設けた、より統合的なアプローチと言える。この「U」の部分は、日本では特にカーボンリサイクルと呼ばれ、国家戦略の柱の一つとして位置づけられている。
経済性がCCUSの重要性を高める
CCUSの重要性は、CO2回収という行為に、コストだけでなく「収益を生む可能性」を与えることで、その経済的なハードルを劇的に下げる点にある。
これは、廃棄物管理の進化に例えることができる。かつて、廃棄物は単に埋め立てる(=CCS)だけのコストセンターであった。しかし、そこから有価物を取り出してリサイクルし、新しい製品として販売する(=CCUSの「U」)ことができれば、廃棄物処理事業そのものが、収益を生むビジネスへと転換する可能性がある。
CCUSは、まさにこの「CO2の資源化・有価物化」を目指すものである。回収したCO2から燃料や化学製品、建材といった価値のある商品を生み出すことができれば、その販売収益によって、莫大なコストがかかるCO2回収設備の投資回収を早めることが可能となる。この経済的インセンティブは、これまで公的資金や補助金に大きく依存してきたCCSプロジェクトの事業性を根本から変え、純粋な民間投資を呼び込むための強力なドライバーとなり得る。
革新をもたらす「利用(U)」の技術
CCUSのプロセスにおける「C(回収)」と「S(貯留)」の部分は、基本的にCCSと同じである。その革新性は、新たに加わった「U(利用)」の多様な技術経路にある。
「U」の技術は、CO2を様々な産業分野の原料として活用する。
- 燃料・化学製品への転換回収したCO2と水素を組み合わせて、ガソリンやジェット燃料(SAF)、あるいはプラスチックの原料となるメタノールなどを合成する。この合成燃料はe-fuelとも呼ばれる。
- 鉱物化による建材への利用CO2をセメントやコンクリートといった建材と反応させ、安定した炭酸塩として固定する。この技術は、CO2を長期間、大気中に戻さない形で固定できる点に特徴がある。
- その他の活用農業分野でのCO2施用や、ドライアイスなどへの利用も含まれる。
メリットと課題
CCUSは、気候変動対策と経済成長を結びつける技術として期待される一方で、その実現には高いハードルが存在する。
メリット、経済的自立と資源循環の促進
CCUSの導入は、CO2排出削減の努力に経済的な合理性を付与する。
- 経済性の向上回収したCO2から有価物を生み出すことで、CO2回収事業の経済的自立を促し、民間投資を呼び込みやすくする。
- 新たな産業と雇用の創出カーボンリサイクルという新しいグリーン産業を創出し、特に途上国において新たな発展の機会となり得る。
- 化石資源への依存低減燃料や化学品の原料を、化石資源からCO2へと転換することで、資源の循環利用を促進する。
課題、コストと規模の限界、そして信頼性の評価
技術的なハードルや、気候変動への貢献度を評価する際の課題が残る。
- 莫大なエネルギー消費とコスト多くのCCUプロセス、特にグリーン水素の製造には、安価で大量の再生可能エネルギーが必要不可欠であり、現時点では製造コストが非常に高い。
- 規模(スケール)の限界現在、技術的に可能なCO2の「活用」量は、世界で排出されるCO2の総量に比べてごく僅かであり、大規模な排出削減のためには、依然として「貯留(CCS)」が主要な選択肢となる。
- 信頼性の評価活用方法によってCO2の固定期間が大きく異なるため、その気候便益をライフサイクル全体で評価(LCA)し、市場で適切に価値評価するための、統一された基準がまだ存在しない。特に、燃料として再利用される場合、燃焼時にCO2が再び大気中に排出されるため、CO2貯留のような永続性(Permanence)を持たない点に注意が必要である。
まとめ
CCUSは、CCSの概念を拡張し、人類がCO2を「敵」から「味方(資源)」へと捉え直す、パラダイムシフトを促す技術である。
- CCUSは、CO2を回収し、「利用(Utilization)」または「貯留(Storage)」する技術の総称である。
- 「有効活用」は、プロジェクトに新たな収益源をもたらし、経済的自立を促すことで、民間資金の動員を加速させる可能性がある。
- その気候便益は、活用方法によって大きく異なり、信頼性の高い評価ルールの確立が最大の課題である。
CCUSが真に気候変動対策の主流となるためには、技術革新による抜本的なコストダウンと、そのエネルギー源となる再生可能エネルギーの爆発的な普及が大前提となる。そして、国際社会は、その多様な活用方法がもたらす気候便益を、永続性という厳格な物差しで評価し、信頼できる市場を構築しなければならない。
CCUSが描く「炭素循環社会」の未来は、単なる技術開発だけでなく、それを支えるエネルギーシステムと、賢明な市場ルールの設計にかかっている。