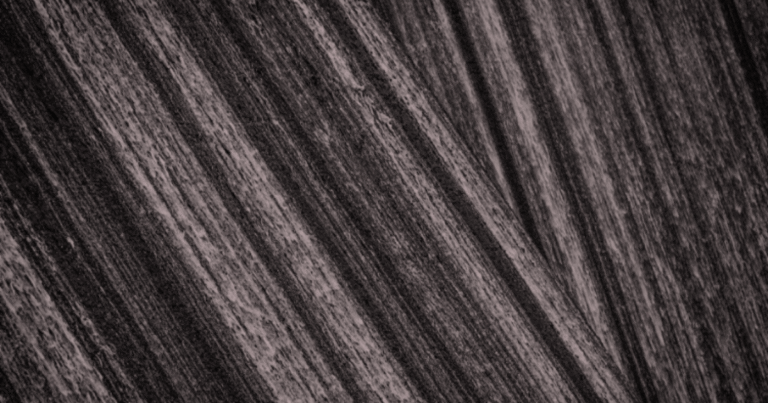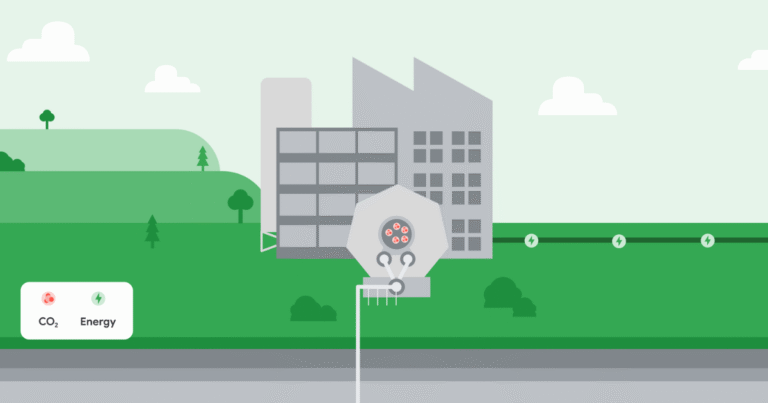マイクロソフトは、アメリカの森林再生を手がけるスタートアップLiving Carbonとの間で、140万トン分のCDRクレジットの購入契約を締結した。対象となるのは、アパラチア地域の廃鉱地2.5万エーカーにおよぶ広大な土地での再植林事業だ。
Living Carbonは、鉱山採掘で劣化した土壌に合わせた樹種を選定し、土壌改良から植林までを一貫して実施する。多くの廃鉱地では侵食や重金属汚染、外来種の繁殖により自然回復が困難だが、同社の技術により炭素隔離と生態系回復の両立が可能になるという。
このプロジェクトで生成されるCDRクレジットは、気候影響と科学的透明性の厳格な基準を掲げる「Isometric」の認証を受ける予定であり、従来の森林系オフセットと異なり、技術主導でカーボンリーケージの防止やライフサイクル全体を可視化する点が評価されている。
マイクロソフトの気候ポートフォリオにまた1社
マイクロソフトは、近年、様々なCDR企業との提携を強化しており、FidelisのBECCS施設「AtmosClear」や、DAC技術を持つTerradotなどとも大型契約を締結している。そして今回のLiving Carbonのようなネイチャーベースのアプローチも積極的に取り入れている。
マイクロソフト エネルギー&CDR担当上級ディレクターのブライアン・マーズ氏は「このプロジェクトは、単に炭素を除去するだけでなく、地域社会への経済的還元や生物多様性の保全といった副次的な価値も提供してくれます。」とコメントしている。
産業遺産から「再生の森」へ
Living Carbonの共同創業者でCEOのマディ・ホール氏は、「鉱山跡地は気候変動対策における未開拓のフロンティア」と述べ、再生による“トリプルボトムライン(環境・経済・社会)”の創出を目指すとした。米国には中央アパラチアだけで400万ac超の廃鉱地が存在しており、このスケール感は他の自然系CDRにはない強みとなる。
今後のCDR市場は「オフセット」から「インセット」、そして「再生型投資」へと進化していく中、Living Carbonのような企業の台頭はその象徴的存在といえるだろう。