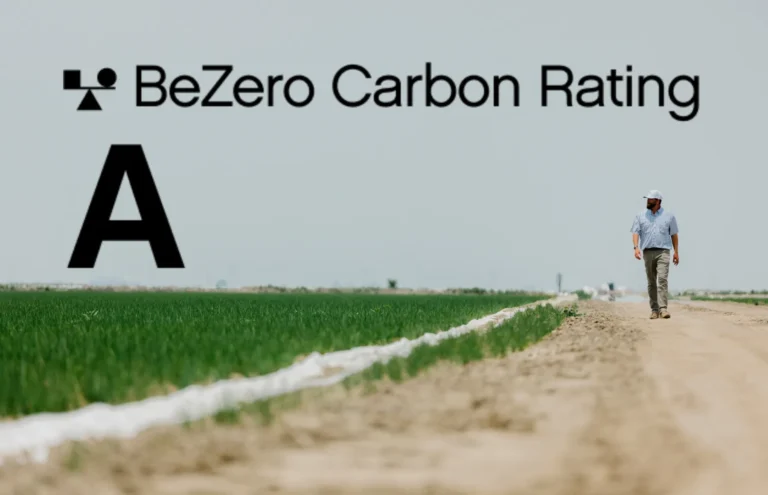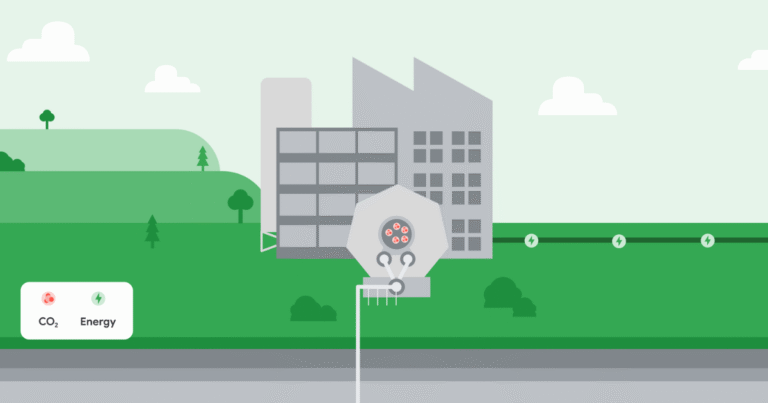米国の非営利団体カーボン180(Carbon180)は、海洋炭素除去(mCDR)の社会実装に向け、地域主導の取り組みを支援する「メイキング・ウェーブス沿岸地域リグラント・イニシアチブ(Making Waves Coastal Community Regranting Initiative)」の初回助成先を発表した。アラスカ、ハワイ、プエルトリコの3団体に対し、それぞれ10万ドル(約1,500万円)、総額30万ドル(約4,500万円)を拠出する。
カーボン180は、陸域や技術主導のCDRが注目を集める中で、海洋が持つ吸収能力を活かしたmCDRの実現を目指している。同団体は「海洋が地球表面の7割を占める以上、CDRの戦略も海に見合う規模であるべきだ」としており、今回の支援は沿岸地域と先住民コミュニティの知見を政策形成の初期段階から反映させる狙いがある。
カーボン180はこれまで、全米6地域で環境団体への助成を通じ、地域組織がCDR政策に関与できる仕組みを構築してきた。同団体の再助成(リグラント)プログラムは、単に資金を分配するだけでなく、技術支援と教育カリキュラムを通じて「地域が自ら判断する力」を高めることを目的とする。
今回選定された3団体は、mCDRの展開が予想される地域で、文化的・生態学的視点からの協議と政策提言を担う。
アラスカ湾を拠点とする「コミュニティ・リーダーズ・アンド・mCDR(CLaM)プロジェクト」は、アラスカ海洋酸性化ネットワークやエヤク先住民村、地元漁業者団体などが連携する。原油流出など環境被害を経験した地域で、漁業者や科学者、先住民が共同で円卓会議を開催し、mCDRの影響とガバナンスの在り方を討議する。
プロジェクト関係者は「mCDRはやがてアラスカに到来する。今こそ地域が理想のかたちを描き、主導権を握るべき時だ」と語った。
モロカイ島に拠点を置く非営利団体ʻĀina Momonaは、古代ハワイの魚池(フィッシュポンド)や流域管理の再生に取り組んできた。今回の助成では、ハワイ全土でmCDRに関する認知度調査や意見交換を実施し、漁業者や文化実践者、若年層の声を反映させる。
同団体は声明で「これまで外部からの政策決定に防戦してきたが、今回は自ら未来を設計する攻勢に出る。地域が主体的に判断できる仕組みづくりが必要だ」と述べた。
プエルトリコの社会生態学研究所(ISERカリブ)は、サンゴやウニの養殖を通じて海洋生態系の回復を進めている。今回の資金でセイバ拠点にマングローブ苗の育成施設を設け、地域住民を対象にブルーカーボン教育を行う計画だ。
同研究所は「マングローブとサンゴ礁の生態的相互作用を強化し、長期的な気候緩和効果と地域の回復力を高める」と説明した。
近年、mCDRは米連邦政府の研究資金や民間投資の流入によって注目度を高めている。カーボン180は、こうした動きを「地域の合意形成が追いつかないまま技術が先行するリスク」と指摘し、今回の助成で「mCDRの社会的正当性を確立する第一歩」と位置づける。
今後、3団体はカーボン180と共同で現地視察や共同学習プログラムを進め、得られた知見をmCDR政策提言に反映させる予定だ。
同団体は「沿岸地域が専門性を持ち、自らの海を守る政策に参加する未来こそ、真に持続可能な海洋炭素除去の鍵である」と強調している。