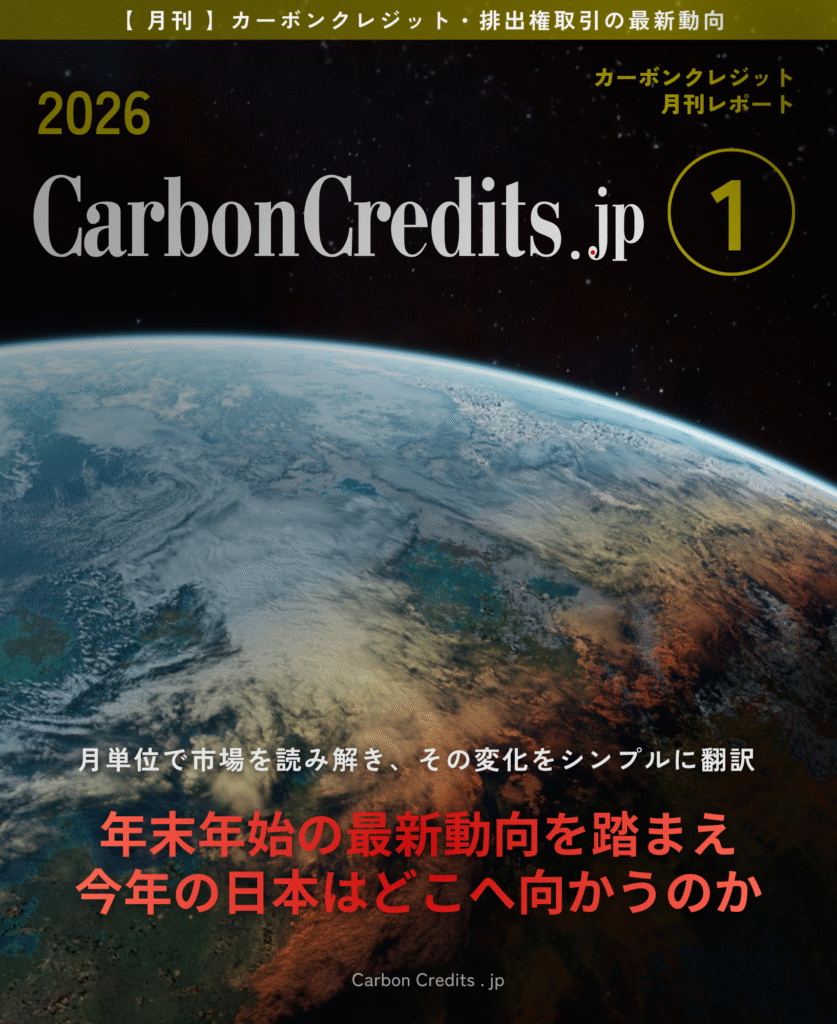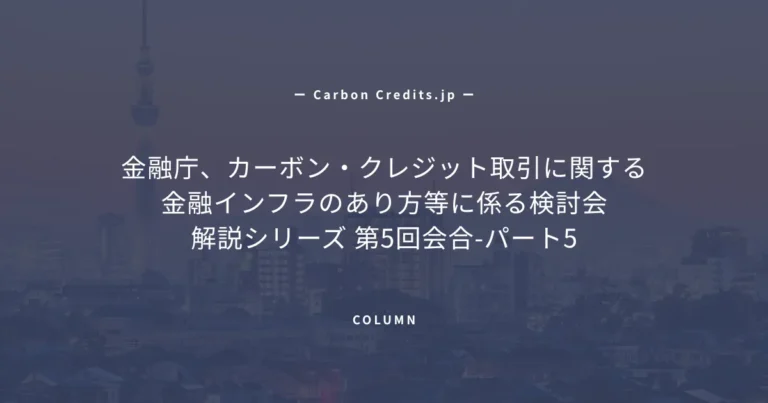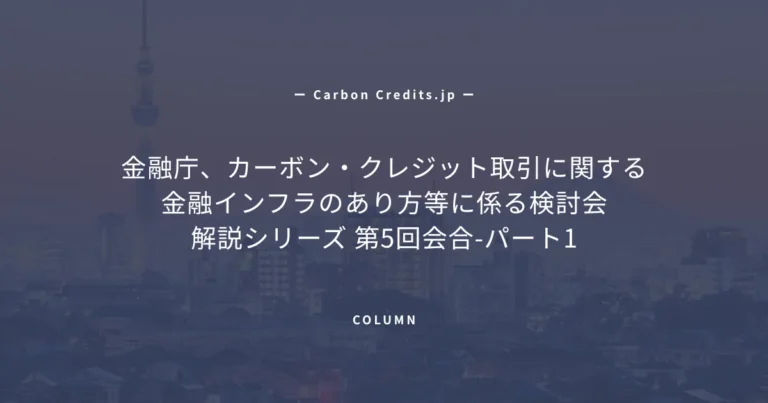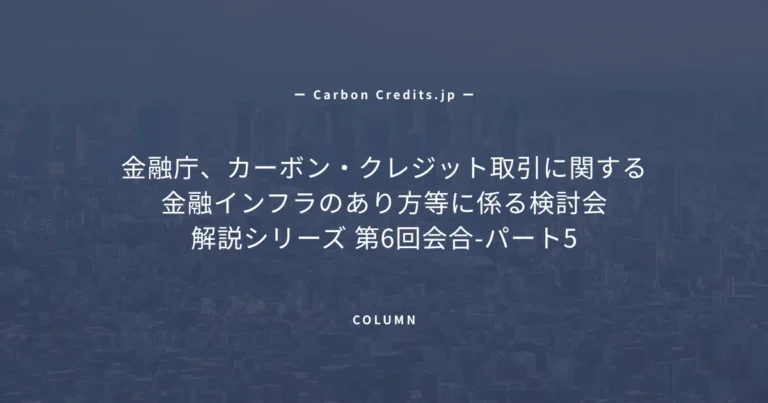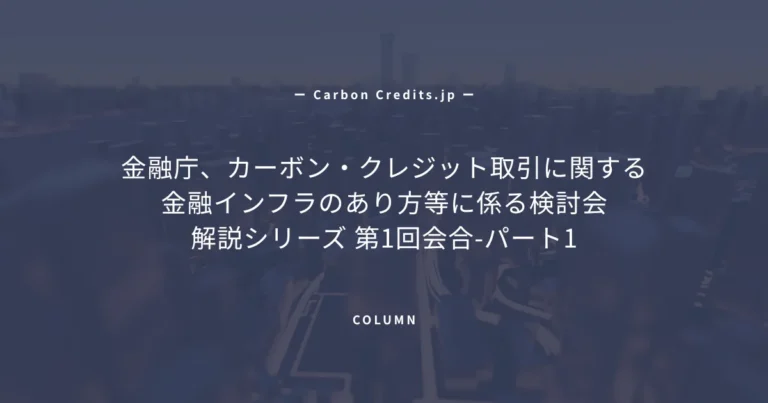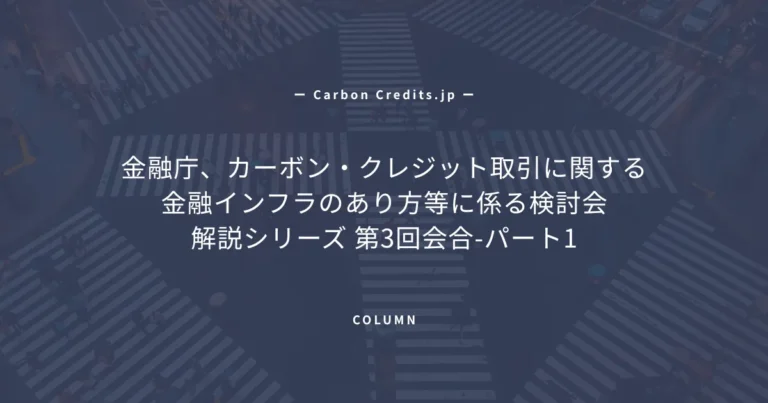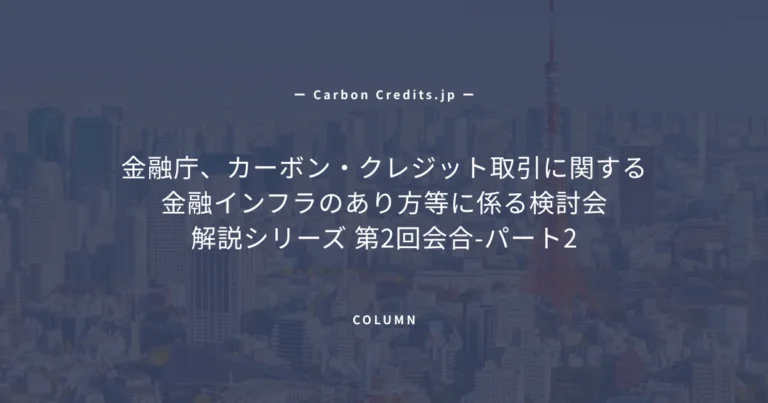「植物を乾燥させて地面に埋めるだけでは、いずれ腐ってメタンガスが出てしまうのではないか」という疑問は、非常に鋭い視点である。しかし、米国のスタートアップ企業であるグラファイト(Graphyte)が開発したカーボン・キャスティング(Carbon Casting)は、単なるゴミの埋め立てとは根本的に異なる。
結論から言えば、この技術は微生物が活動するために不可欠な「水」を物理的に奪い、特殊なシートで外気から遮断することで、数百年間にわたって「腐敗という現象そのもの」を停止させる手法である。
本記事では、既存の二酸化炭素除去(CDR)技術であるバイオ炭などと比較しながら、なぜこの方法が科学的に信頼され、かつ効率的なのかを解説する。
微生物を「活動不能」にする,乾燥と密閉の科学
バイオマスが腐るのを防ぐ鍵は、微生物が動けない環境を物理的に作り出すことにある。微生物が有機物を分解して二酸化炭素(CO2)やメタンを出すには、一定以上の水分と酸素が必要である。
グラファイトのプロセスでは、まずバイオマスを徹底的に乾燥させ、含水率を10%以下まで下げる。米国農務省(USDA)のデータによれば、木材を腐らせる菌は、水分が少なくなると活動が急激に鈍くなり、特定の数値を下回ると事実上停止する。これは、干物が腐りにくいのと同じ理屈である。
さらに、乾燥させたバイオマスを機械で強く圧縮してブロック状にし、特殊な不透水性ポリマーシートで隙間なく包み込む。これが「キャスティング(封入)」と呼ばれる工程である。このシートが、好気性分解に必要な酸素を遮断し、雨水や地下水の浸入を完全に防ぐ。水分も酸素もない環境下では、たとえ地中であっても微生物は活動できず、メタンが発生するリスクを根底から取り除くことができるのである。
「焼却」しない強み、バイオ炭を上回る炭素回収率
現在、脱炭素の手段として注目されているバイオ炭は、バイオマスを蒸し焼き(熱分解)にして炭にする手法である。しかし、この熱分解の過程では、原料に含まれる炭素の約半分がガスとして空気中に逃げてしまう。
一方、グラファイトの手法は「燃やさない」ことが最大の特徴である。
植物が光合成によって蓄えた炭素を、ほぼ100%に近い状態で維持したまま封じ込める。ライフサイクルアセスメント(LCA)の観点で見ても、グラファイトの炭素残存率は約90%以上と極めて高い。
コスト面でも大きな差が出る。
バイオ炭を作るには大規模な加熱設備が必要だが、カーボン・キャスティングは乾燥と圧縮、そして埋設という既存の土木技術の組み合わせで実現できる。1トンあたりの二酸化炭素除去コストは、バイオ炭が22,500円から45,000円程度かかるのに対し、グラファイトは15,000円(100ドル)未満という低価格を目指している。
地中の「炭素貯蔵庫」を守る高度な監視体制
「一度埋めてしまったら、後でどうなっているか分からない」という懸念に対しては、最新のデジタル技術で対応している。グラファイトは、プロ・アース(Puro.earth)の基準に準拠した、厳格な計測・報告・検証(MRV)体制を敷いている。
具体的には、地中の埋設ピットに多くのIoTセンサーを設置し、湿度やガスの組成をリアルタイムで監視する。万が一、シートが破れて水が入り込んだり、わずかでもガスが発生したりすれば、即座に検知できる仕組みである。さらに、すべてのブロックには個別のIDが付与され、どこから来たバイオマスがどこに埋まっているかがデジタル上で管理される。
もしセンサーが異常を検知した場合には、該当する箇所を掘り起こして再度封入し直すことも可能である。
こうした透明性の高い管理が、アメリカン航空(American Airlines)のような大企業が同社のカーボンクレジットを早期に購入する決め手となっている。
まとめ
グラファイトのカーボン・キャスティングは、複雑な化学工場を建てるのではなく、「乾燥させて包む」という物理の基本を徹底した、合理的な解決策である。エネルギー消費を最小限に抑えつつ、自然が蓄えた炭素をそのまま地中に戻すこの手法は、2050年のネットゼロ達成に向けた「最も安価で現実的な選択肢」の一つと言えるだろう。
一見シンプルに見える「埋設」という行為の裏側には、微生物学と土木工学、そして最新の監視技術が融合した、堅牢な科学的根拠が隠されているのである。