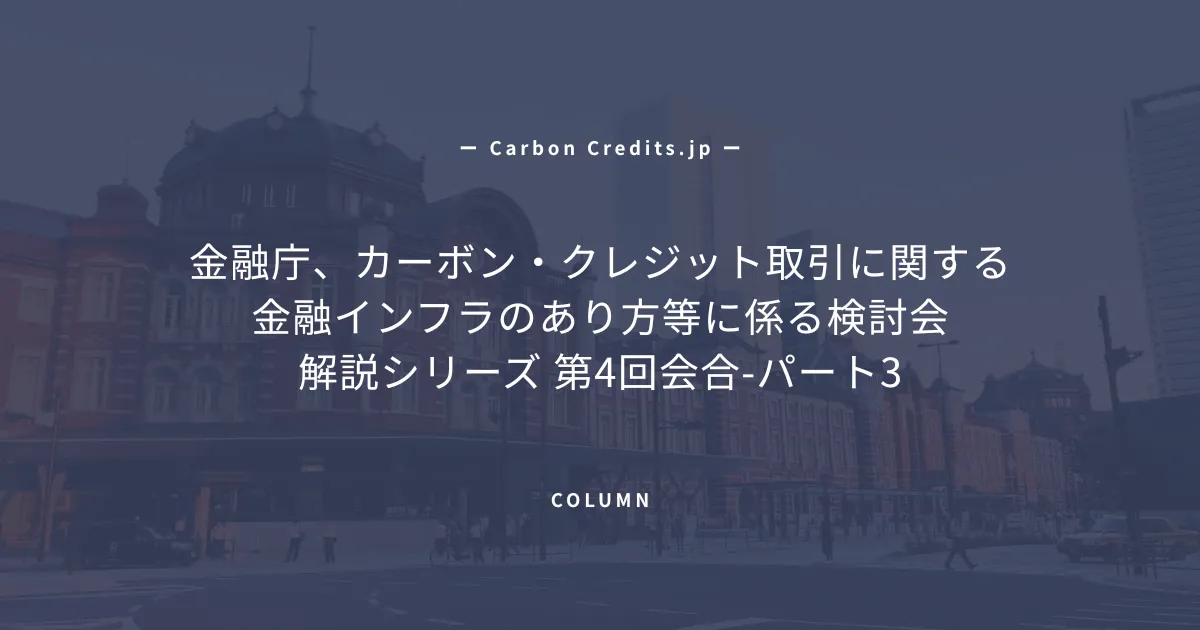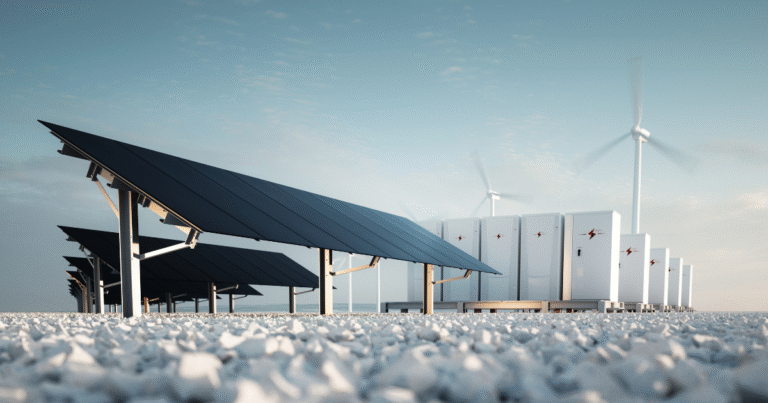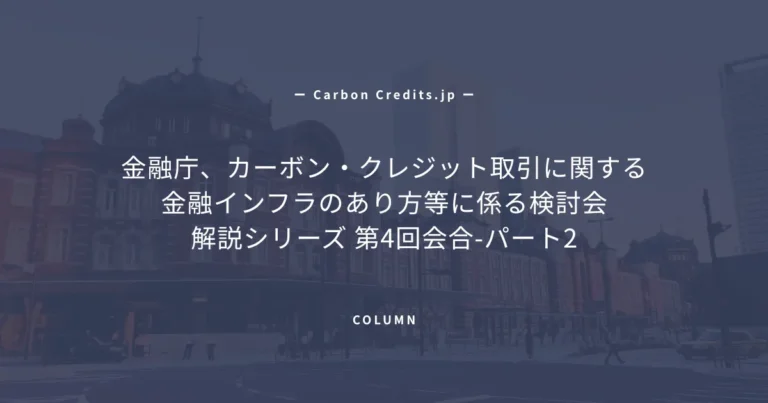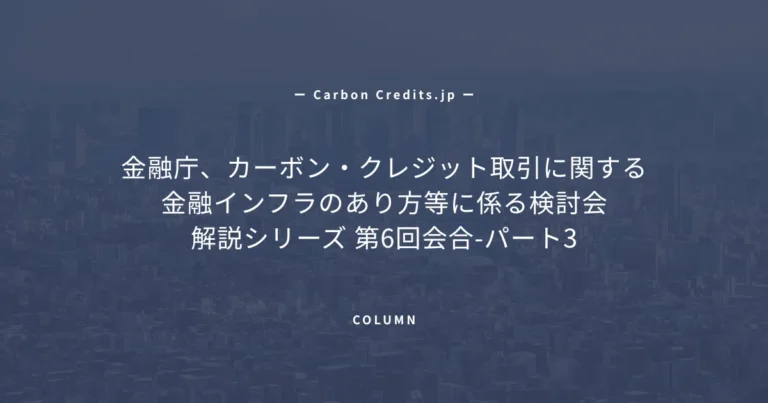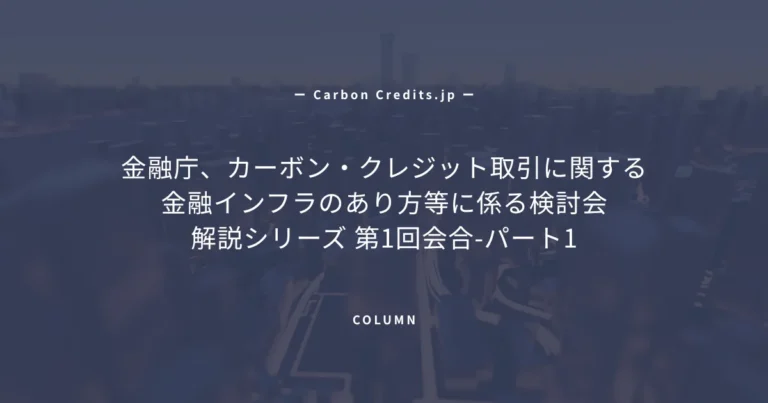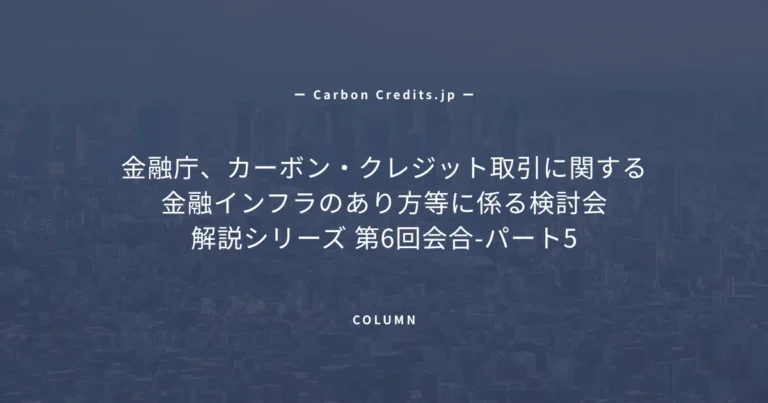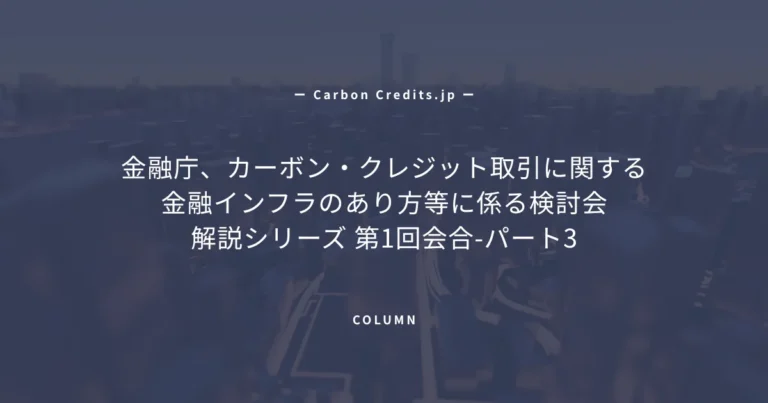金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第4回パート3
金融庁「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会(第4回)」パート3では、メンバーによる自由討議が行われた。
議論は「取引活性化に向けた発行量と価格指標の整備」と「利用者保護・ガバナンスの実効性」の二本柱に集中し、排出枠とボランタリーカーボンクレジットを分けた制度設計と、登録簿(レジストリ)API接続によるリアルタイム決済・情報開示の標準化が喫緊の課題として浮かび上がった。
二つの大きな論点軸
メンバーからは「発行量の絶対的不足」があらためて強調された。
J-クレジット累計認証量は1,075万トン、JCMクレジットは8万トンに過ぎず、年間11億トン規模の国内排出量と比べれば、取引活性化の前提が欠けると指摘する。創出手続きのデジタル化でコストと期間を圧縮し、量を一気に増やす必要があるという主張だ。
またGX-ETS第2フェーズではJ-クレジットとJCMのみに限定せず、条件付きでボランタリーカーボンクレジットを適格対象として残すべきだとし、同時に価格指標の整備が、先物・デリバティブ導入の基盤になるとの主張がなされた。
また「需要家が求める情報の透明性」を優先事項にすべきという意見も挙げられた。
プロジェクトの具体的内容や創出地域が選定理由になるケースが多いにもかかわらず、取引所取引では個別情報がマスキングされやすい点を指摘。マーケットプレイス型では詳細を吟味した取引が可能であることから、取引所と相対市場の補完関係を維持しつつ、取引所側も情報公開ルールを再構築すべきだと提言された。
討議で浮かび上がった主要論点
自由討議では、まず排出枠とその他のカーボンクレジットを分けて議論する必要性が指摘された。つまり、コンプライアンスカーボンクレジット市場とボランタリーカーボンクレジット市場を明確に区分した上で議論すべきという主張だ。
コンプライアンスカーボンクレジット市場における排出枠(Allowance)は価格の公正性が重視され「取引所集中義務」を課す制度設計が既に進んでいる。一方で、ボランタリーカーボンクレジット市場は価格が一物一価にならず、複数プラットフォームの共存が現実的だという整理である。
インテグリティ確保
商社の立場であるメンバーからは「インテグリティ確保」を最優先視した提案が挙げられた。グリーンウォッシング批判を回避するため、取引関係者全体で品質管理を徹底し、第三者格付けなどを活用して一定水準以上の商品だけを扱う自主規律が欠かせないとした。
韓国ETSの事例を引き、マーケットメイカーに経済インセンティブを与えれば低流動市場でも価格形成が進むと提案された。
証書系商品の拡大
またメンバーは、非化石証書やSAF証書など証書系商品の拡大に触れ、制度差が価格や流動性に与える影響を整理すべきだと述べた。
これに対し、enechainは「レジストリAPIが非公開なため移転・決済がマニュアル処理となり、取引の自動化に制約がある」と課題を共有し、API公開が実現すれば海外並みのリアルタイムDVP(Delivery-versus-Payment)が可能になると説明した。さらに、JCEXでは信託銀行を介した倒産隔離スキームで元本リスクを排除する枠組みを設計中と紹介した。
横断的に見えた三つの喫緊課題
議論を総覧すると、第一に「発行量と価格指標の同時拡大」が必要である。創出加速と価格の見通しが両立しなければ、需要は腰折れし、将来の先物やオプション取引も根付かない。
第二に「APIベースのエンドツーエンド決済」が鍵を握る。レジストリと銀行APIを連携し、クレジット移転から資金決済までをリアルタイム化できれば、取引コストとリスクを同時に削減できる。
第三に「情報開示の標準化とレイヤード設計」が避けて通れない。排出枠市場では統一的な価格公示と厳格な監視を、ボランタリーカーボンクレジット市場ではプロジェクト詳細やSDGs貢献度など多様なメタデータの公開を求める声が強い。
今後の検討会が焦点を当てるべきポイント
短期的には、登録簿API公開のロードマップと情報開示テンプレートの素案づくりが急務となる。
中期的には、価格指数の算定手法やマーケットメイカー制度への具体的インセンティブ設計を詰める必要がある。
長期的には、先物・オプションなどデリバティブ市場を視野に入れた事業者保護スキームの法制化、AIによる市場監視の実装などが論点に浮上するだろう。
まとめ
第4回の討議によって、カーボンクレジット流通インフラの次の改良フェーズは「量・質・透明性の三位一体改革」に帰着することが明確になった。
排出枠市場の公正性とボランタリーカーボンクレジット市場の多様性をどう両立させるか。
その鍵は、API接続を核としたデータと決済のリアルタイム化、そして統一的な情報開示基準の策定である。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第4回)議事録.令和7年1月28日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第4回)議事次第.令和7年1月28日