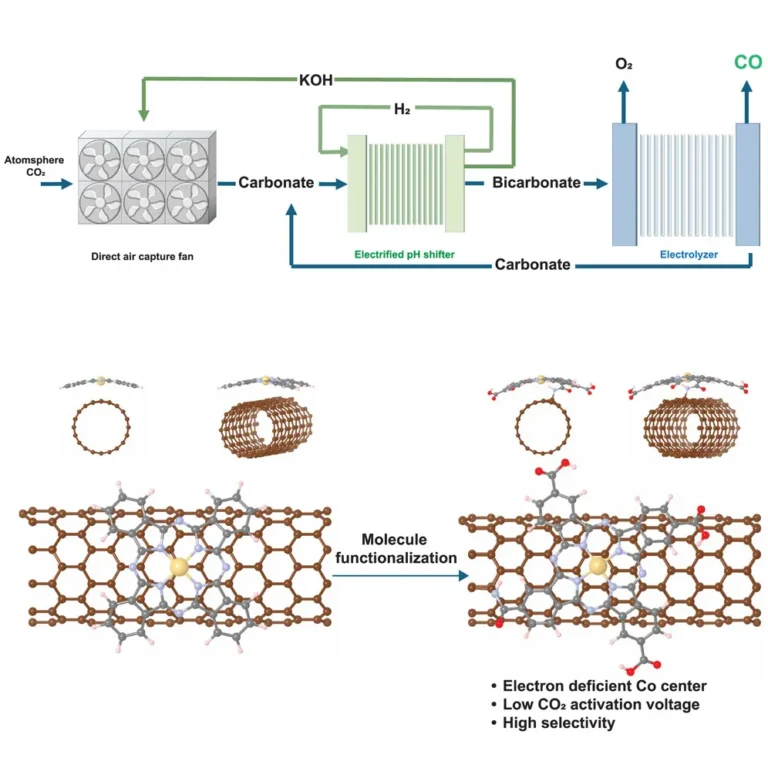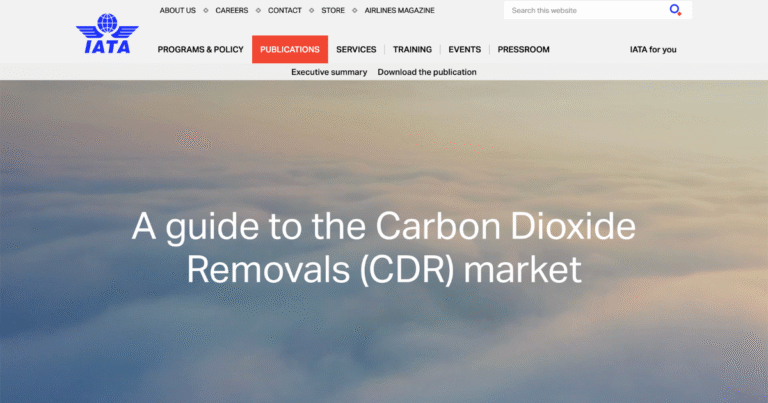英国のオックスフォード大学(University of Oxford)やインペリアル・カレッジ・ロンドン(Imperial College London)などの研究チームは2026年2月9日、将来の炭素除去(CDR)に過度に依存する気候変動対策が、国際法に抵触する恐れがあるとする最新の研究結果を発表した。
気候変動目標の達成において、実現可能性が不透明な将来のCDRを即時の排出削減の代替手段として扱うことは、国家に課せられた「相当の注意(デュ・ディリジェンス)」義務に違反し、パリ協定の1.5度目標を危険にさらすと結論づけている。
本研究は、2025年7月に国際司法裁判所(ICJ)が出した「気候変動に関する勧告的意見」に基づき、国家が負う法的義務の観点からCDRの利用を分析したものである。ICJの意見では、気候システムへの重大な害を防止するために、国家には「厳格かつ要求水準の高い」行動基準が求められることが示された。研究チームは、将来の除去を前提とした目標設定が、短期間での大幅な排出削減を怠る口実となっている現状に強い懸念を示している。
オックスフォード大学法学部のラバニャ・ラジャマニ(Lavanya Rajamani)教授は「不確実な世界において、一部の国家は野心的な近期的削減策の代わりに、将来のCDR技術の展開に賭けている」と指摘した。同教授はさらに「近期的排出削減と実現可能なCDR戦略の追求は、単なる倫理的責務ではなく、法的要件である」と述べ、国家の裁量には法的な「ガードレール」が必要であると強調した。
研究では、法的な基準を満たすための具体的な「ガードレール」として、除去よりも排出削減を優先することや、炭素除去のアプローチが技術的・社会的に実現可能であることを求めている。また、多くの国家がネットゼロ目標において、直接的な排出削減量と除去量を区別せずに公表している現状を批判し、透明性の確保を求めた。実際に、ネットゼロ目標を掲げる国の31%が目標年における総排出量の推計値を示しておらず、その中には日本、中国、インド、デンマークなどが含まれている。
本研究は、国際的なカーボンクレジットへの依存を抑制し、国内での直接的な削減と透明性の高いCDR計画を両立させることが、法的リスクを回避する唯一の道であると結んでいる。
現実的な落とし所
今回のオックスフォード大学の研究は、CDRへの過度な依存が招く法的リスクに焦点を当てている。しかし、現実問題として、パリ協定の目標達成にCDRが必要不可欠な選択肢である事実は、科学的にも法的にも認められている。
課題はその「バランス」にある。
法的な制約を軽視した無計画な依存は将来の訴訟リスクを招くが、一方で経済成長と脱炭素の「落とし所」を見出さなければ、現実的な政策として各国で機能しない。この極めて困難な均衡点を探ることこそが、脱炭素を前進させる鍵となる。
企業や政府は、法的要件を遵守しつつ、経済的合理性との両立をいかに図るかという、高度な戦略的判断が求められている。
参考:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2025.2599861