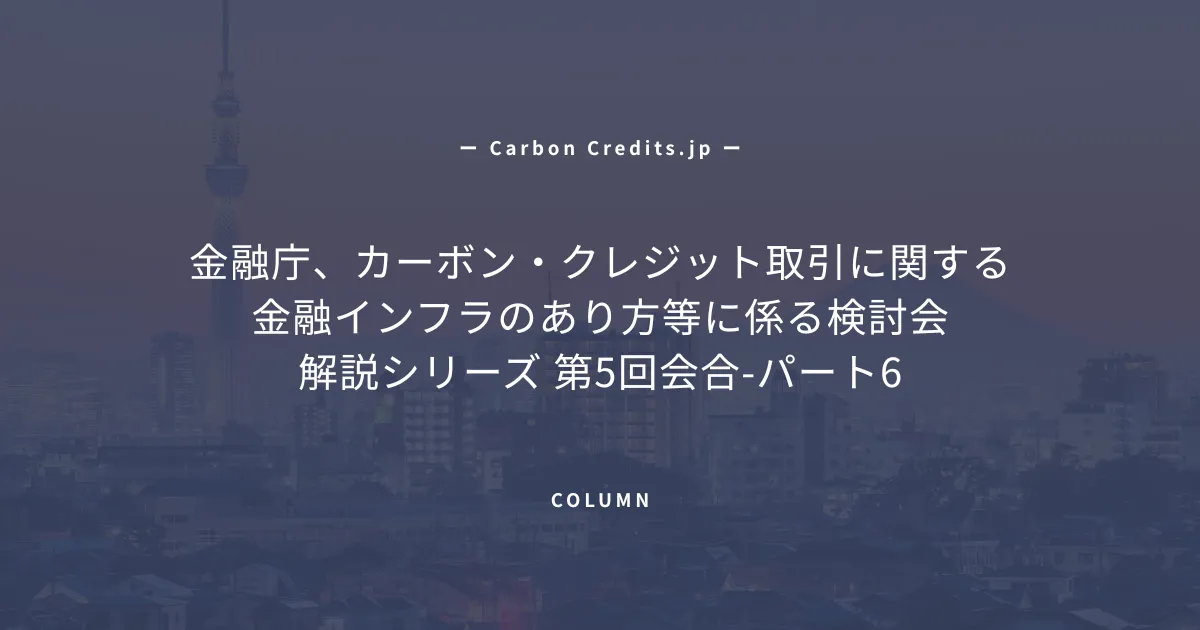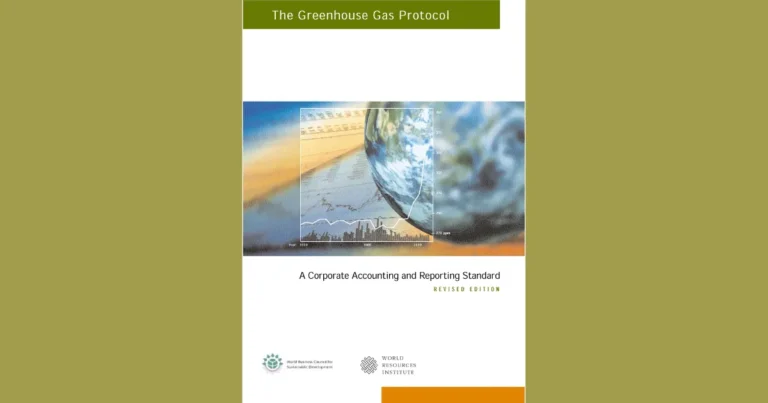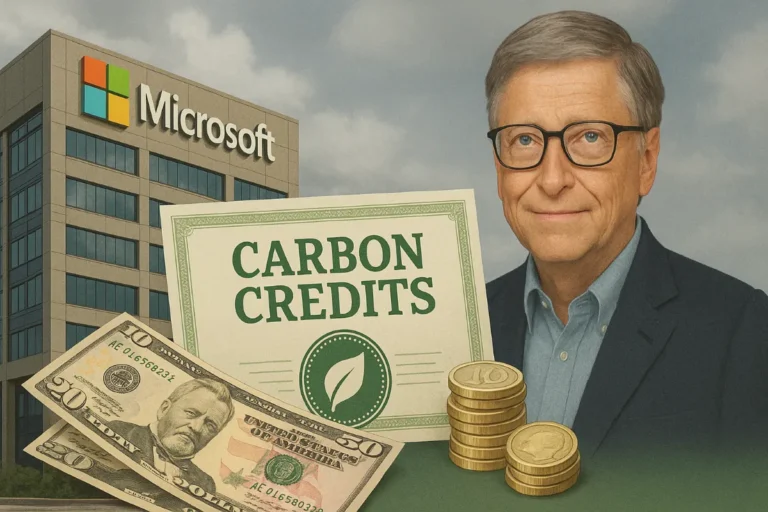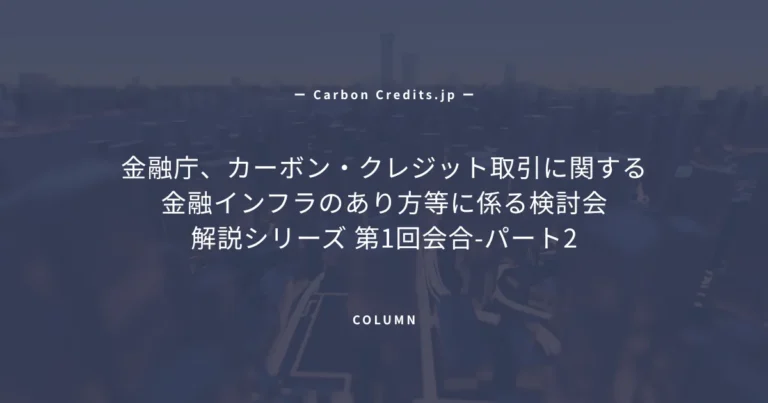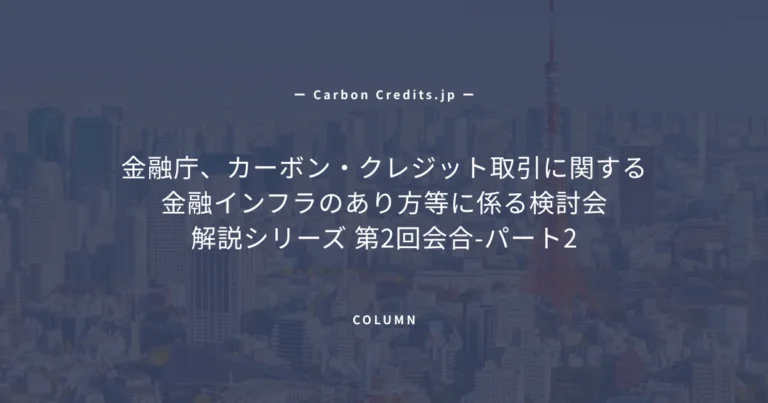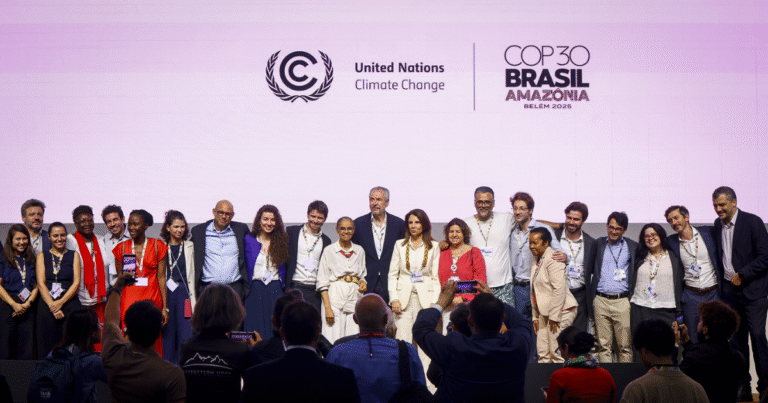金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第5回パート6
2025年春に開催された第5回「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」では、カーボンクレジット取引の契約実務と市場インテグリティ(誠実性)の確保が主要テーマとなった。
本パート6では、ISDAマスター契約の普及状況や、買手・売手双方が直面する品質評価・情報開示の課題、さらに国内制度設計に向けたグッドプラクティス収集の必要性について、各メンバーが示した論点をまとめる。
ISDAの浸透
メンバーは「ISDA(国際スワップ・デリバティブ協会)のマスター契約が実際にどの程度利用されているのか」と質問した。これに対しISDAは、金融機関間では「ほぼ100%」が同契約を締結していると説明し、最近は外資系を中心に事業法人や機関投資家にも利用が広がっていると補足した。
ISDAマスター契約は金利・為替デリバティブ取引で標準化を進めてきた枠組みであり、カーボンクレジット分野でも契約リスクを平準化できる点が注目されている。
メンバーは併せて、ボランタリーカーボンクレジット市場向けにはIETA(国際排出権取引協会)が早くから売買契約のひな形を公表している事実を指摘し、国内プレーヤーが参照し得る契約フォーマットの選択肢を確認した。ISADはIETAフォーマットも依然利用可能であるとし、複数の国際テンプレートが並存する現状を説明した。
買手・売手の実務課題
議論は買手・売手の実務課題へと移る。メンバーは「脱炭素の潮流で需要は伸長するが、売手には追加性や恒久性などプロジェクト信頼性の確保が不可欠」と強調。
一方で買手企業は、カーボンクレジットの品質評価に加え、グリーンウォッシュ批判やレピュテーションリスクを避けるための情報開示が重要になると訴えた。
カーボンクレジット活用の情報開示
情報開示の在り方については、購入したカーボンクレジットの種類や認証機関、使用目的を明示し、カーボンクレジット活用が企業の削減努力を補完する位置づけであることを明確化すべきとの意見が複数のメンバーから挙がった。
GX-ETS(排出量取引制度)との接続を念頭に「企業事例を収集したグッドプラクティス集の整備」が提案された。
金融庁が公表する「記述情報の開示の好事例集」のような形で、カーボンクレジット情報開示事例を提示する意義も指摘された。
さらに、「買手の気候戦略の中でカーボンクレジットをどう位置づけるか」を明示する必要性を説き、VCMIの4ステップ指針やIOSCO・英国原則がいずれも自社削減の上乗せとしてのカーボンクレジット活用を求めている点を紹介。
市場流動性を高める鍵として価格情報と開示方法の統一を挙げ、既存の環境省ガイドラインとの調整を要望も挙げられた。
まとめ
最後に、「国内市場は黎明期であり、過度な規制よりも最低限のガバナンスと論点整理を優先すべき」と総括。
将来的な規制選択肢を視野に入れつつも、現段階では取引拡大と多様化を促す柔軟な制度設計を求めた。
本パート6では、国際標準契約の適用状況と市場インテグリティ向上の取り組み、そして国内制度整備に向けた情報開示・グッドプラクティスの重要性が浮き彫りになった。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事録.令和7年2月25日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事次第.令和7年2月21日