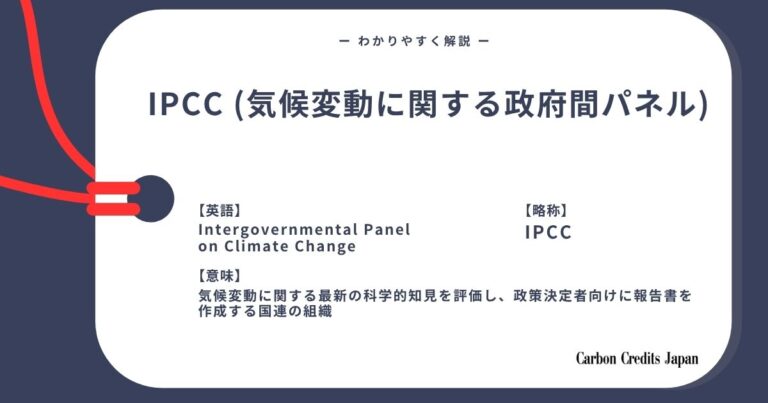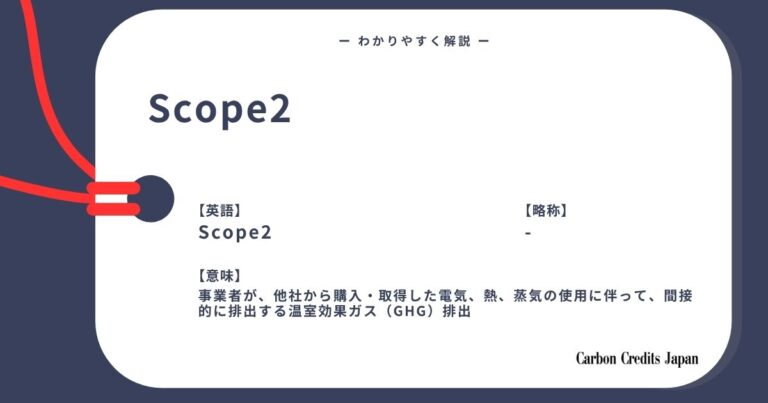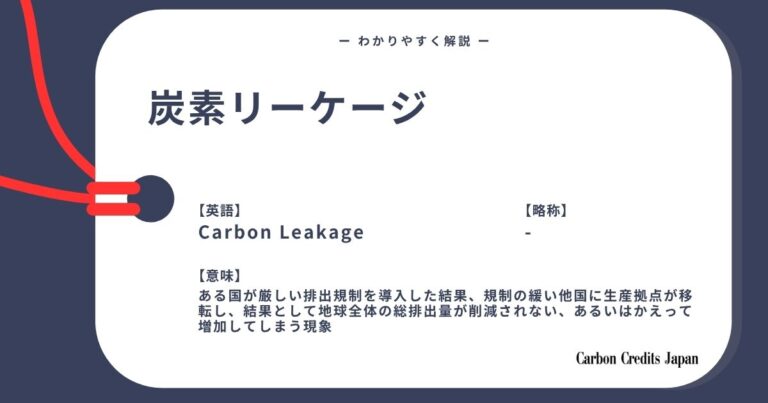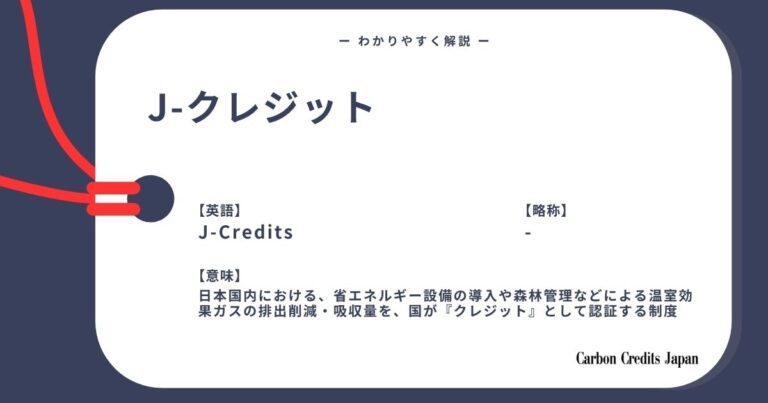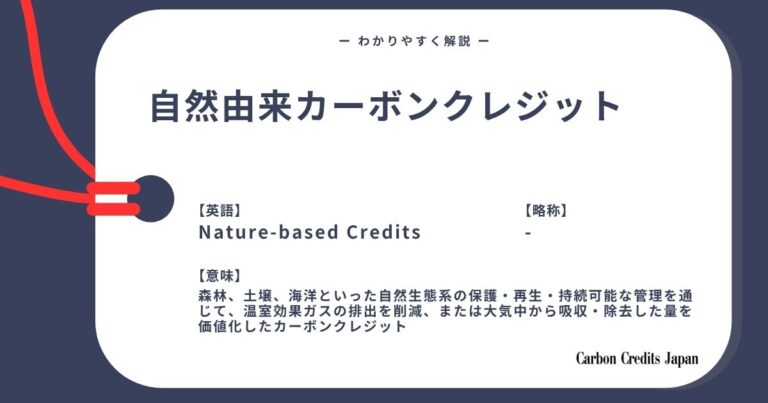はじめに
地球の気候システムを安定させる上で、熱帯林が果たす役割は計り知れません。しかし、多くの開発途上国では、農業や鉱業開発のために森林が失われ続け、それが地球全体の温室効果ガス排出量の約1割を占めています。この危機的な状況に立ち向かうため、国際社会が生み出した最も重要かつ野心的な枠組みが、「REDD+」です。
本記事では、このREDD+を「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から、その核心に迫ります。REDD+がいかにして「生きている森林」に経済的価値を与え、その保全に民間および公的資金を動員(Finance Mobilization)しようとするのか。そして、その成功が、市場の信頼性(Integrity)の確保と、森林と共に生きる先住民や地域コミュニティ(IPLCs)の権利を保障する「公正な移行(Just Transition)」の実現に、いかに密接に結びついているのかを、その仕組みから根深い課題まで包括的に解説します。
用語の定義
一言で言うと、REDD+とは**「開発途上国が、自国内の森林破壊や劣化を食い止めることで達成した温室効果ガス排出削減・吸収の実績に応じて、経済的なインセンティブ(資金など)を受け取れるようにする国際的な枠組み」**のことです。
「REDD+」という名称は、その活動内容の進化を反映しています。
- REDD: もともとは「Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation(途上国における森林減少・森林劣化に由来する排出の削減)」の頭文字を取ったものでした。
- プラス(+): その後、より広範な森林活動を対象に含めるため、「プラス」が付け加えられました。これには、「森林保全(Conservation)」「持続可能な森林経営(Sustainable Management of Forests)」「森林炭素蓄積の増強(Enhancement of Forest Carbon Stocks)」、すなわち植林などが含まれます。
重要性の解説
REDD+の重要性は、これまで経済システムの外で「無料の公共財」と見なされてきた森林の生態系サービス、特に炭素貯蔵機能に、初めて明確な経済的価値を与えようとする点にあります。
これは、森林とその守り手である地域コミュニティに「給料を支払う」という考え方に例えることができます。多くの途上国では、森林は伐採して農地や牧草地に転換して初めて、短期的な経済的価値を生むものでした。そのため、森林は常に開発の圧力に晒されてきました。REDD+は、この力学を根本から変えようとします。「森林を伐採して得られる利益」よりも、「森林をそのまま保全することで得られる国際社会からのインセンティブ」の方が大きくなるようにすることで、森林保全を経済合理性のある選択肢へと転換させるのです。
この仕組みは、これまで資金が届きにくかった途上国の森林保全活動に対して、緑の気候基金(GCF)などの公的資金や、ボランタリー炭素市場を通じた民間資金を動員(Finance Mobilization)するための、極めて重要なパイプラインとして機能します。
仕組みや具体例
REDD+の実施は、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の下で合意された「ワルシャワ枠組」に基づき、一般的に3つのフェーズで進められます。
- 第1フェーズ:準備(Readiness): 各国がREDD+を実施するための国家戦略を策定し、森林の炭素蓄積量を測定・監視するための体制(森林モニタリングシステム)を構築し、関係者の能力向上を図る段階。
- 第2フェーズ:実施(Implementation): 策定した国家戦略や政策を実行に移し、具体的なパイロットプロジェクトなどを通じて排出削減活動を実施する段階。
- 第3フェーズ:成果に基づく支払い(Results-based Payments): 実際に排出削減・吸収を実現し、その成果が国際的なルールに則って測定・報告・検証(MRV)された場合に、その実績に応じて資金を受け取る段階。
成果の測定方法:
REDD+の核心は、「もし対策をしなければ、どれだけの森林が失われていたか」という**森林減少参照レベル(Forest Reference Emission Level, FREL)**を、過去のデータに基づき科学的に設定し、実際の森林減少率がそれを下回った場合に、その差分を「排出削減量」として算定する点にあります。
具体例:インドネシアにおける泥炭地林保全プロジェクト
- 背景: インドネシアの広大な泥炭地林は、世界有数の炭素貯蔵庫ですが、パーム油プランテーションへの転換のために排水・伐採され、大量のCO2を放出していた。
- プロジェクト: 民間企業やNGOが、地域コミュニティと協力し、泥炭地の排水路を塞いで再湿地化し、違法伐採を防ぐためのパトロールを実施。コミュニティには、アグロフォレストリーなどの代替生計手段を提供する。
- 成果: これにより、森林減少と泥炭地の分解によるCO2排出が「回避」された。この成果が、Verraなどのボランタリー炭素市場の基準の下で検証され、カーボンクレジットとして発行・販売される。
国際的な動向と日本の状況
2025年現在、REDD+はパリ協定の第5条にも明確に位置づけられ、気候変動対策の重要な柱として認識されていますが、その信頼性を巡る議論も活発化しています。
国際的な動向:
初期のREDD+プロジェクトの一部が、ベースラインの過大評価や、地域コミュニティへの利益還元の不備などをメディアや研究機関から厳しく批判されたことを受け、市場全体の信頼性(Integrity)向上が最重要課題となっています。この流れの中で、個別の小規模プロジェクト単位ではなく、州や国といったより広域な行政単位で排出削減量を管理する「管轄区域アプローチ(Jurisdictional Approach)」が、排出の漏出(リーケージ)を防ぎ、信頼性を高めるための主流なアプローチとなりつつあります。
日本の状況:
日本政府は、JICAなどを通じて、アジア太平洋や中南米、アフリカの多くの国々で、REDD+の第1フェーズ(準備)や第2フェーズ(実施)を支援する、世界有数のドナー国です。また、日本独自の**JCM(二国間クレジット制度)**の枠組みの中でも、REDD+を対象とした方法論を策定し、パートナー国と共に質の高いプロジェクトを形成・実施する取り組みを進めています。
メリットと課題
REDD+は、気候変動、生物多様性、貧困という複合的な課題に同時に取り組む大きな可能性を秘める一方で、その実施は極めて困難な挑戦です。
メリット:
- 大規模かつコスト効率の高い排出削減: 森林保全は、最もコスト効率の高い気候変動の緩和策の一つである。
- 豊かな共同便益(コベネフィット): 生物多様性の保全、水源涵養、土壌保全、地域社会の生計向上など、SDGsに幅広く貢献する。
- 途上国のエンパワーメント: 森林資源を持つ途上国が、気候変動の「被害者」としてだけでなく、解決策を提供する「主役」となる機会を創出する。
課題:
- 市場の信頼性(Integrity)の問題:
- 追加性: クレジット収入がなくても、その森林は守られていたのではないか?
- リーケージ(漏出): ある場所の森林を守った結果、伐採圧力が別の保護されていない森林に移るだけではないか?
- 永続性: 保護した森林が、将来の火災や政策変更によって失われてしまうリスク。
- 公正な移行(Just Transition)の問題:
- 土地の権利: プロジェクト対象地域の土地所有権が曖昧な場合、伝統的に土地を利用してきた先住民や地域コミュニティの権利が侵害される「グリーン・グラビング(緑の収奪)」のリスク。
- 利益配分: クレジットから得られた収益が、実際に森林を守る地域住民に公正に分配されない。
まとめと今後の展望
REDD+は、地球の生命維持システムである熱帯林を守るための、最も重要で、そして最も複雑な気候変動ファイナンスのメカニズムです。
要点:
- REDD+は、途上国が森林保全によって達成した排出削減成果に応じて、経済的インセンティブを受け取る国際的な枠組みである。
- 生きている森林に経済的価値を与えることで、公的・民間の資金を森林保全へと動員する。
- その成功は、排出削減量の測定(信頼性)と、先住民・地域コミュニティの権利保障および利益配分(公正な移行)という、二つの大きな課題を克服できるかにかかっている。
- 現在は、より信頼性を高めるため、国や州といった広域での「管轄区域アプローチ」が主流となりつつある。
今後の展望として、REDD+の価値は、単に炭素のトン数だけで測られるのではなく、どれだけ豊かな生物多様性を守り、どれだけ地域社会、特に最も脆弱な立場にある人々の暮らしを向上させたかという、共同便益の質によって、ますます評価されるようになるでしょう。ICVCMのようなイニシアチブが定める厳格な基準や、衛星技術の進化によるモニタリング精度の向上が、その信頼性を高める上で不可欠です。この壮大な挑戦の成否は、人類が気候変動と生物多様性の危機に、公正かつ効果的に立ち向かえるかを占う、試金石であり続けるのです。