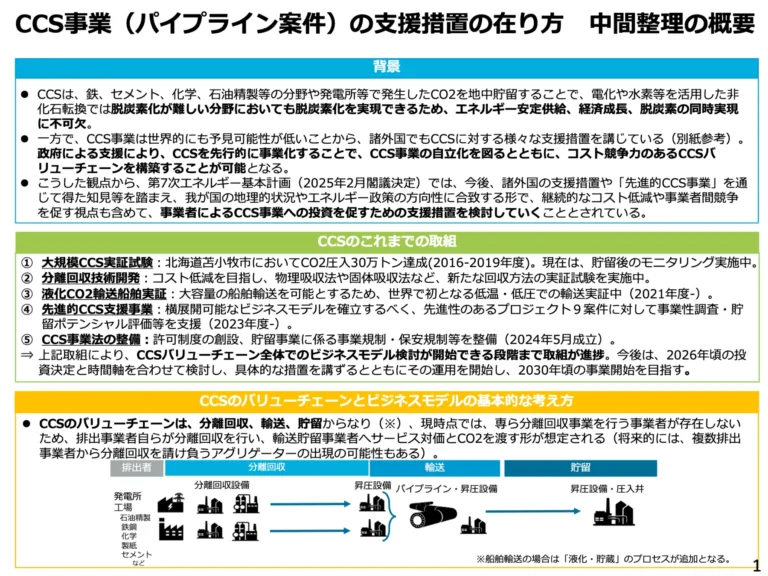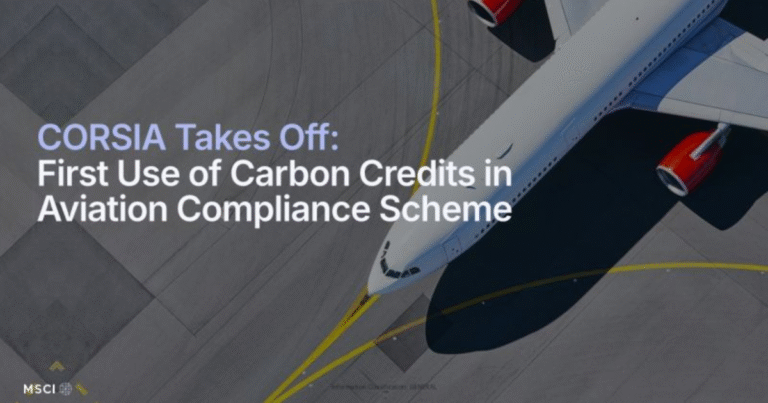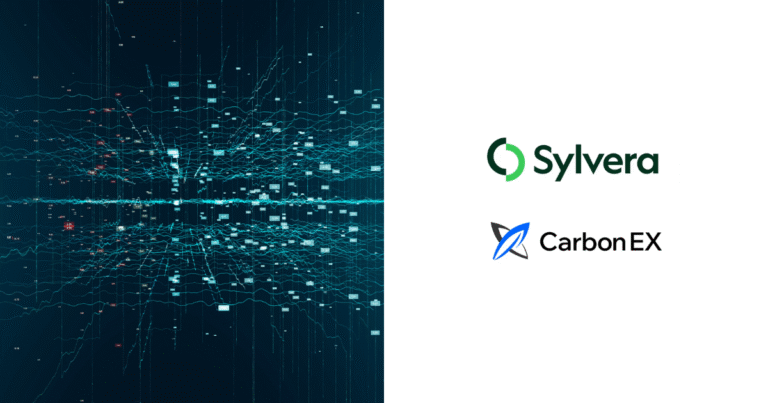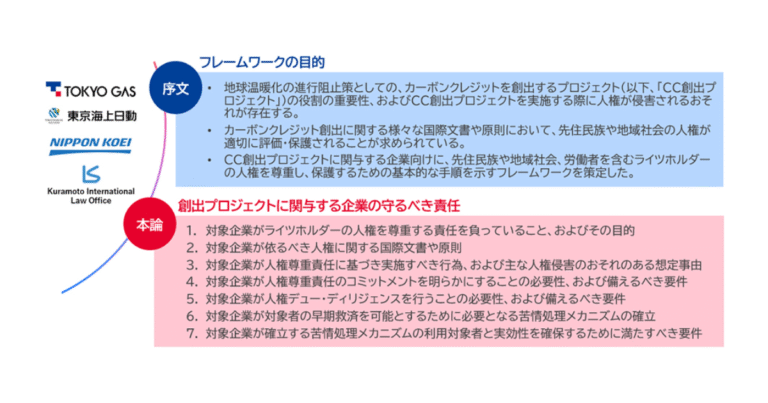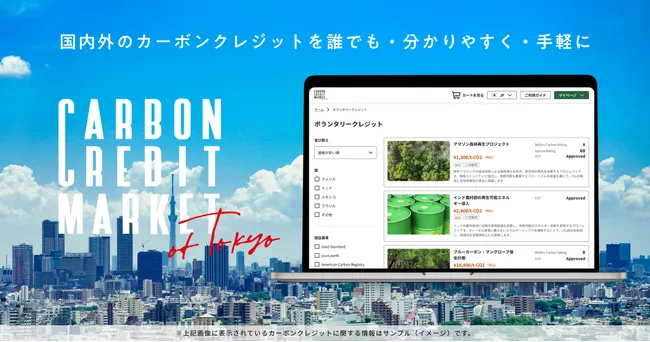神奈川県は11月27日、藻場の保全・再生活動とブルーカーボンクレジット創出の最新動向を共有する「かながわブルーカーボンシンポジウム」を藤沢市で開催する。漁業協同組合や企業、自治体が連携し、藻場再生を通じたCO2吸収の拡大と地域経済の循環を両立させるモデル構築を目指す。
同県は、海藻や海草などがCO2を吸収・固定する「ブルーカーボン」に注目し、県内でのクレジット創出を後押ししている。今回のシンポジウムはその理解促進を目的とし、県内の漁協や企業、研究機関、自治体などが参加する。
基調講演では、日本海藻協会の藤田大介会長(元東京海洋大学准教授)が登壇し、国内外の藻場再生の現状と課題、そして「磯焼け」と呼ばれる藻場の消失現象への対策を解説する。藤田氏は「藻場の保全は漁場の生産力向上だけでなく、CO2吸収や生物多様性保全にも資する」と述べている。
県環境農政局の脱炭素戦略本部室も登壇し、神奈川県が進めるブルーカーボンクレジット事業の仕組みを説明する予定だ。さらに、小田原市や三浦市、平塚市などで実施されている藻場再生活動の事例が、各漁業協同組合から紹介される。
午後の講演では、横須賀市経済部や三和漁協城ヶ島支所などが登壇し、県内でのブルーカーボンクレジット取得の具体的事例を共有する。藻場の再生活動を通じて創出されたカーボンクレジットを、企業が脱炭素経営の一環として購入する流れも紹介される見通しだ。
意見交換セッションでは、株式会社東京久栄の神尾光一郎氏をファシリテーターに、参加者が藻場保全の課題と今後の協働の方向性を議論する。
同県は、今回のシンポジウムを「SDGsの達成と脱炭素社会の実現を支える取り組みの一環」と位置づけており、今後もブルーカーボンを活用した地域主体の気候変動対策を推進する方針だ。