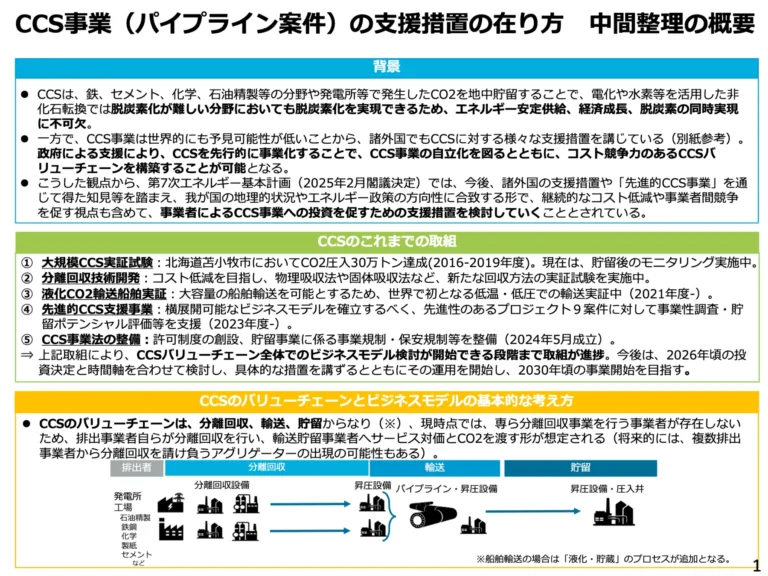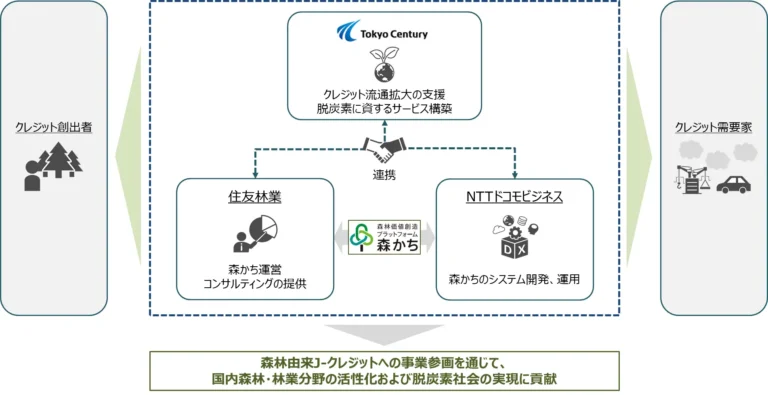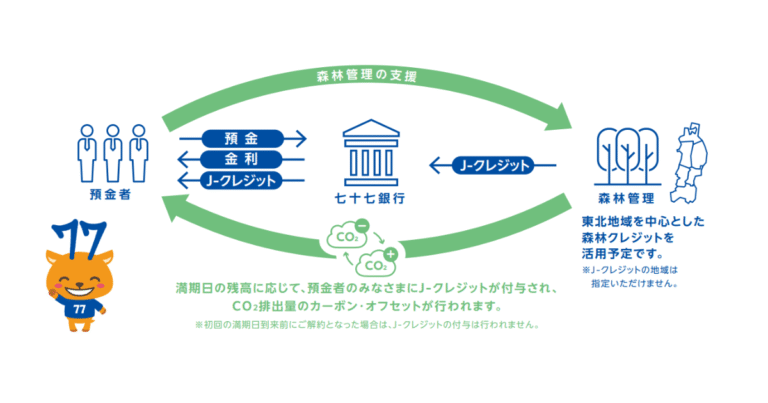国際標準化機構(ISO)と温室効果ガスプロトコル(GHGプロトコル)は9月9日、温室効果ガス(GHG)排出量の算定と報告に関する既存の基準を統合し、新たな国際標準を共同開発する戦略的パートナーシップを発表した。これにより、企業・投資家・政策当局が依拠できる「共通言語」としての排出量会計基準が整備され、カーボンクレジットや炭素除去(CDR)市場の信頼性向上につながる。
両者は、ISOの「ISO 1406Xシリーズ」とGHGプロトコルの「企業会計・報告基準」「スコープ2・3基準」などを統合し、二重ロゴで発行される国際基準を策定する。また、製品別のカーボンフットプリント基準の共同開発にも着手し、バリューチェーン全体の詳細データに基づく脱炭素経営を支援する。
ISOのセルヒオ・ムヒカ事務局長は「気候行動を効率的に前進させ、関係者の負担を軽減する新しい時代の幕開けだ」と述べた。GHGプロトコル運営委員長のジェラルディン・マチェット氏も「企業・製品・プロジェクトの算定基準を調和させることで、利用者にとっての複雑性を解消する」と強調した。
背景には、各国政府や企業からの「基準の乱立解消」要請がある。これまでISOとGHGプロトコルは並行的に基準を策定してきたが、算定範囲や検証指針に差異があり、企業や投資家に混乱をもたらしていた。今回の統合は、主要7カ国(G7)ビジネス界の意見集約組織「B7」や国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が求めていた流れにも合致する。
ISSB議長のエマニュエル・ファベール氏は「投資家にとって資本配分を左右する一貫性のあるカーボンデータが不可欠だ」と歓迎した。さらに、COP30ハイレベルチャンピオンのダン・イオシュペ氏は「統一基準は信頼できるネットゼロ移行を加速する」と指摘した。
両者の基準はすでに各国の規制や自主開示枠組みで広く採用されている。ISOは政府による法規制や検証制度の基盤となり、GHGプロトコルは世界の主要な開示イニシアチブで参照されている。今回の連携により、政策的な妥当性と技術的厳密性、実務的な使いやすさが一体化し、国境を越えたカーボンクレジット市場の信頼性を強化する。
両組織の専門家は今後、統合的な技術プロセスを経て新基準を策定し、各国の脱炭素戦略とCDR市場の発展を後押しする方針である。最初の成果は2026年内に発表される見通しで、11月に開催されるCOP30に向け、統一基準の動向が注目される。
SEO slug: iso-ghgprotocol-carbon-accounting-unified-standards-2025