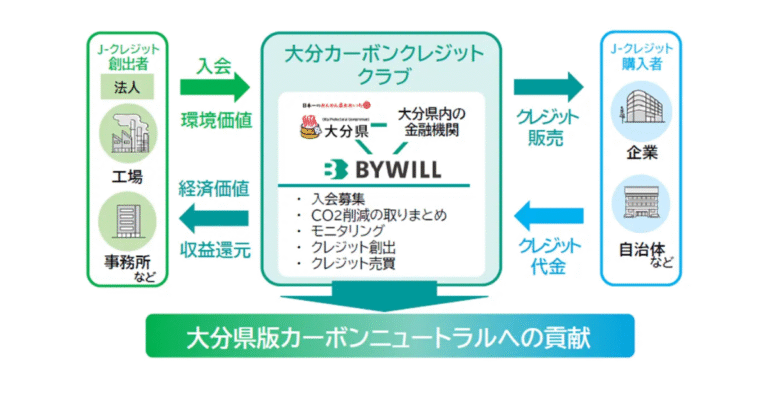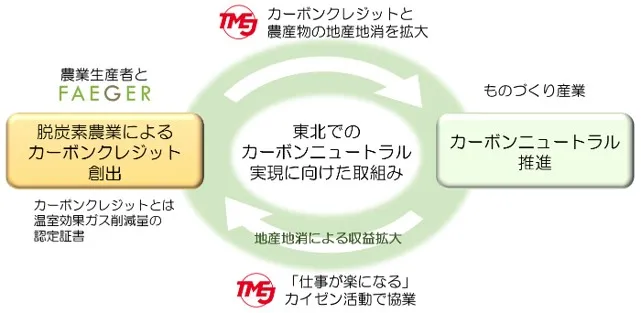漁業技術大手の古野電気は11月18日、神戸市の須磨海岸沖でSuma豊かな海ネットワーク(Suma豊かな海ネットワーク)と共同でブルーカーボン創出活動を開始した。同社が持つ魚群探知機の超音波技術を活用し、海中の藻場の生育状況を「見える化」することで、炭素除去(CDR)源としての藻場のポテンシャルを科学的に評価する実証実験に乗り出す。
ブルーカーボン活動のモニタリングに技術を適用
この協業の核心は、海洋・漁業分野で培ってきた古野電気の技術を、地球温暖化対策の重要テーマであるブルーカーボン生態系の健全性維持に転用する点にある。同社はSuma豊かな海ネットワークに魚群探知機を提供し、須磨沖の藻場を継続的にモニタリング・分析する。
ブルーカーボンは、藻場や海草、マングローブといった海洋・沿岸生態系が大気中の二酸化炭素(CO2)を吸収し、炭素として海中に固定するメカニズムを指す。この吸収・固定プロセスが、排出削減では対応しきれない大気中のCO2を直接除去するCDRの重要な手法として、国際的に注目されている。
今回の実証実験では、超音波で取得した藻の高さや分布を示すデータと、現場の漁師が持つ経験的知見を融合させる。これにより、藻場の成長状況や海洋環境の変化を定量的に把握し、ブルーカーボンによるCO2吸収量測定の信頼性を高める基礎データとして活用することが目指されている。
CDRの信頼性向上に不可欠な「計測・報告・検証」
CDRプロジェクトがカーボンクレジットとして市場で取引されるためには、その排出削減・吸収量が正確に計測・報告・検証(MRV)されることが極めて重要となる。特にブルーカーボンの分野では、藻場の状態やCO2固定量を継続的にモニタリングし、その長期安定性を証明する科学的手法が確立途上にある。
古野電気 常務執行役員 舶用機器事業部長の矮松 一磨氏は、「藻場の育成やブルーカーボンの促進には、目に見えにくい海の変化を捉えることが求められる。私たちの“見えないものを見る”技術が、持続可能な海の未来を築く一助となれば幸いだ」と、技術がMRVに果たす役割に期待を表明した。
一方、地域での活動主体であるSuma豊かな海ネットワーク 代表理事の若林 良氏は、「海藻の生育状況や分布を見える形にすることで、これまで気づけなかった海の“声”を感じ取れるようになる」と述べ、技術導入が地元の豊かな海づくりに科学的な根拠を与えると指摘した。
「Ocean 5.0」実現に向けた社会連携
この取り組みは、古野電気が掲げる2050年未来社会コンセプト「Ocean 5.0」実現に向けた「海を未来にプロジェクト」の一環である。「Ocean 5.0」は、持続可能性を模索する現代の「Ocean 4.0」からさらに進み、「海の恩恵をすべての生きるものが受け、さらに海へ恩返しする未来」を描くものだ。
海洋分野のリーディングカンパニーが、自社のコア技術をブルーカーボン活動におけるCDRの信頼性担保という新たな目的に活かす挑戦は、今後の日本の地域創生型カーボンクレジット創出に重要なモデルを提供する可能性がある。
参考:https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1741&dispmid=1017