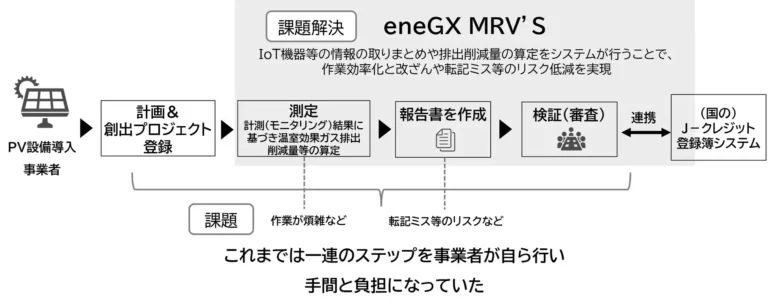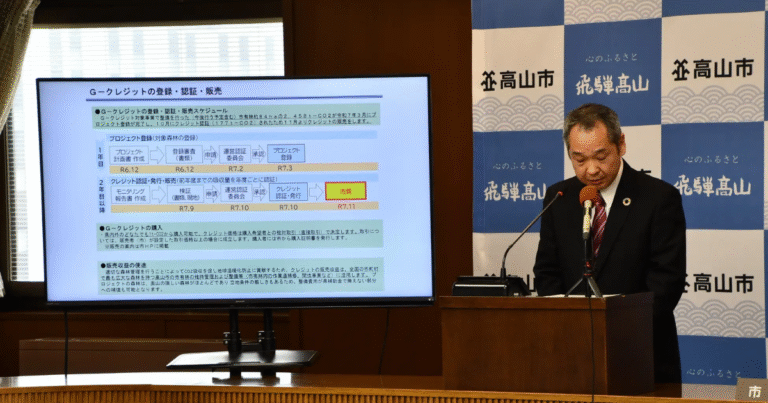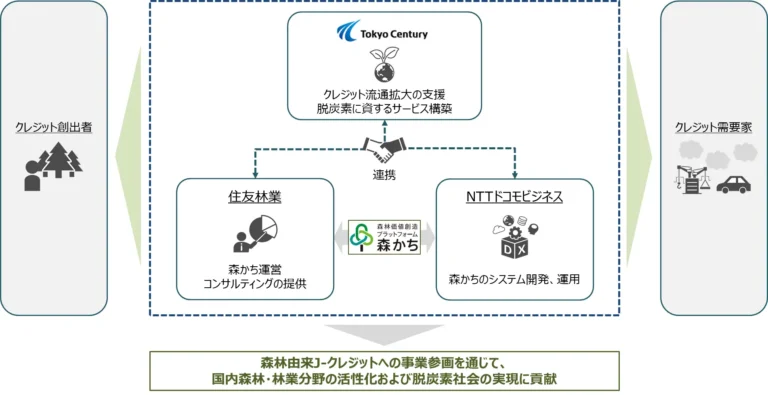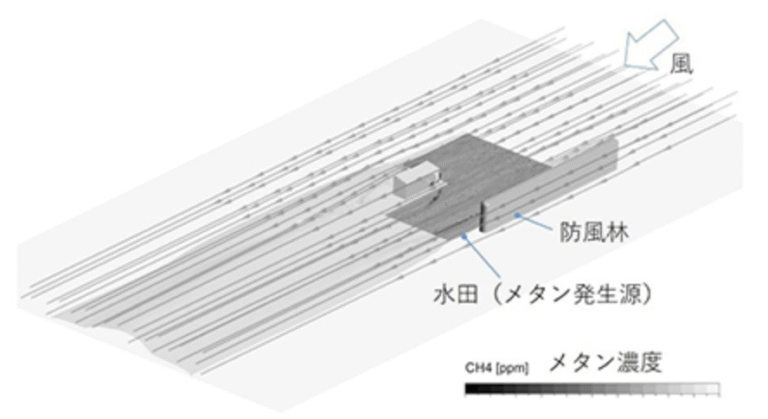経済産業省は9月17日、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(CCS事業法)に基づき、千葉県九十九里沖の一部海域を「特定区域」に指定し、試掘の許可申請の受付を開始した。これは2025年2月に北海道苫小牧沖が指定されて以来、国内で2件目となる。
今回の指定は、京葉臨海工業地帯など首都圏の大規模排出源からのCO2を貯留する「首都圏CCS事業」と密接に関連している。同事業は、2030年度に年間128万トン規模のCO2圧入を開始し、将来的には最大500万トンまで拡張する計画を掲げており、貯留候補地として千葉県外房海域を選定している。
事業計画によれば、製鉄所や発電所から回収したCO2をパイプラインで輸送し、九十九里沖を含む外房沖の帯水層に圧入する構想である。調査では、南関東ガス田に隣接する外房海域に優れた貯留層が存在する可能性が高いとされ、圧入シミュレーションの結果、目標とする注入量は達成可能と評価された。
また、CO2輸送については、年間約500万トンの輸送能力を持つ海底パイプラインの設置が検討されている。再昇圧設備を経て陸域から送られたCO2は、海底に埋設されたパイプラインを通じて水深15〜40メートルの海洋プラットフォームに送られ、そこから圧入井や観測井を掘削して帯水層へ貯留する仕組みである。
千葉県の熊谷俊人知事は「九十九里沖の指定は、全国最大のコンビナートを抱える千葉県にとってカーボンニュートラル実現への大きな前進だ」と強調した。経済産業省は今後、利害関係者の意見募集や都道府県知事との協議を経て試掘許可の可否を判断する。
首都圏CCS事業は、2030年代初頭からの商業化を視野に、排出削減とカーボンクレジット創出の双方を狙うものであり、日本のGX戦略の要となる。九十九里沖での試掘結果は、今後の事業化の可否を大きく左右するとみられる。
参考:https://www.pref.chiba.lg.jp/carbon/topics/ccs-tokuteikuiki.html