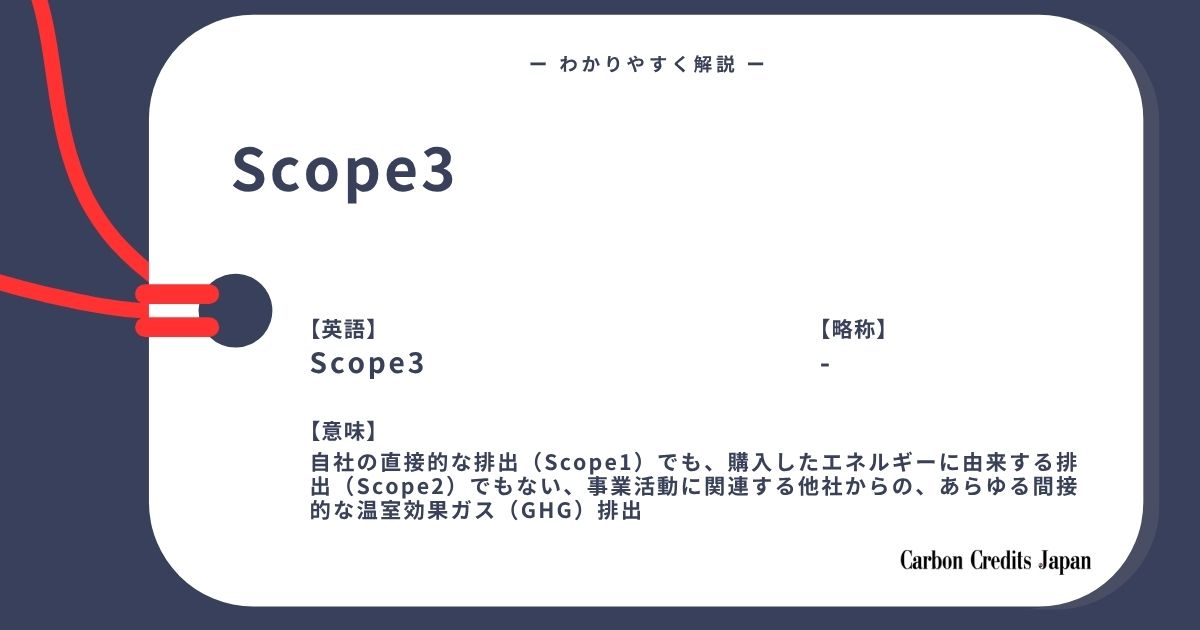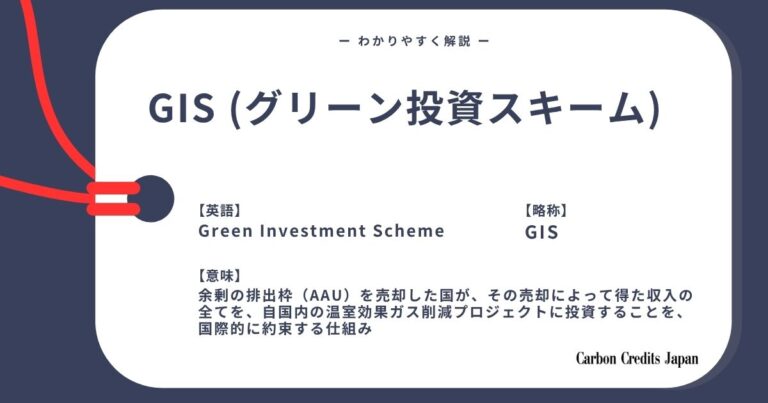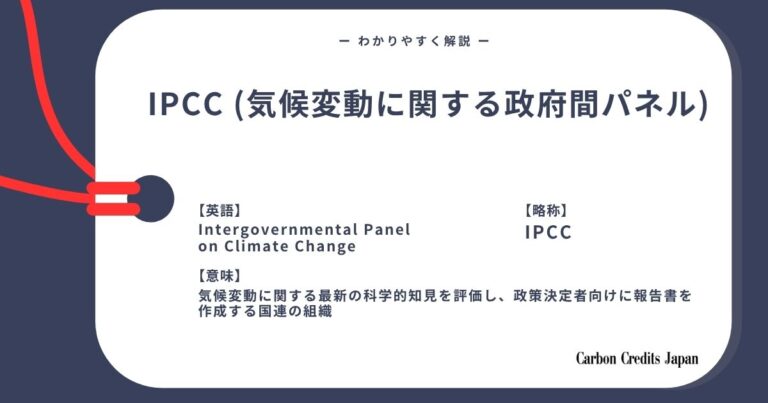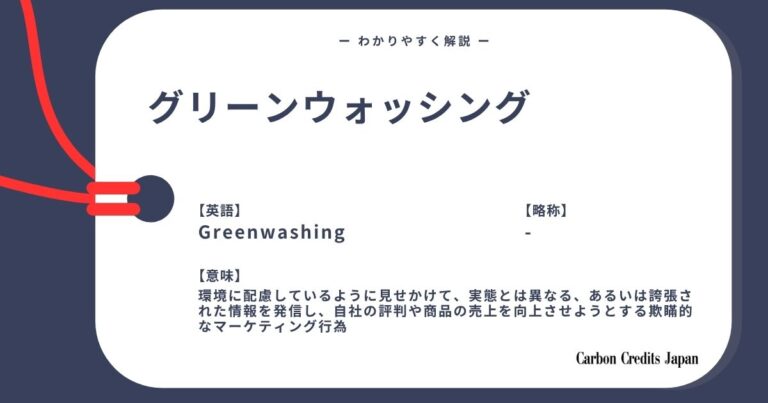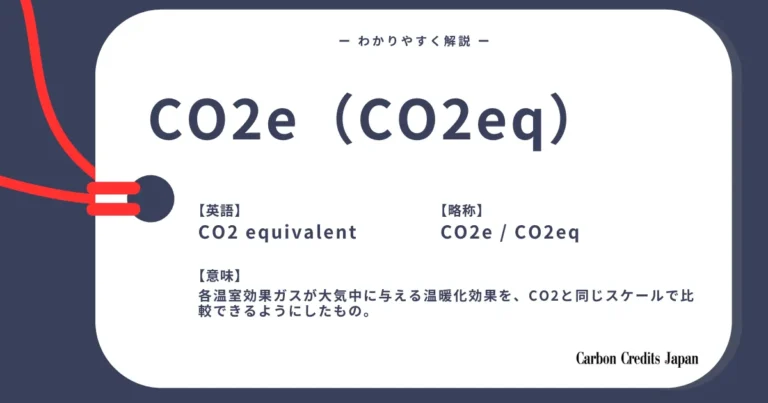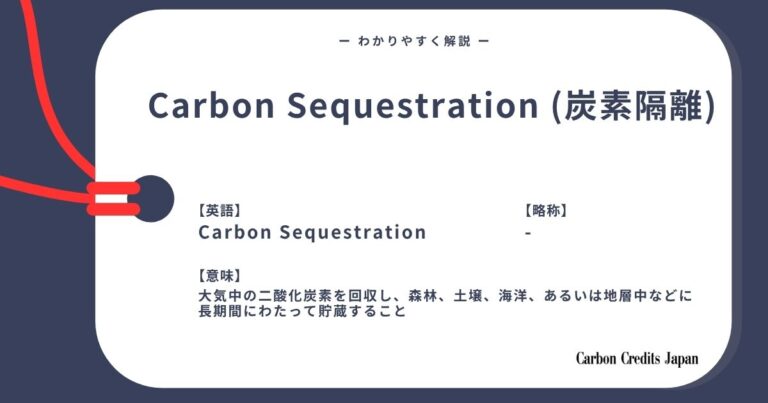はじめに
企業の気候変動への影響を全体像として捉える上で、避けては通れない、最も複雑かつ広範な領域が「Scope3(スコープ3)」排出量です。これは、自社の直接排出(Scope1)や、購入したエネルギーに由来する間接排出(Scope2)とは異なり、原材料の調達から製品の使用、廃棄に至るまで、事業活動に関連するサプライチェーン全体の排出を対象とします。企業の真の「カーボンフットプリント」は、このScope3にこそ隠されています。
本記事では、このScope3を「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から深く分析します。グローバルに広がるサプライチェーンの大部分が開発途上国に位置する現代において、Scope3の算定と削減が、いかにして途上国の産業の脱炭素化を促し、新たな資金動員(Finance Mobilization)と公正な移行(Just Transition)の機会を生み出すのか。その巨大な挑戦と、市場の信頼性(Integrity)を確保するための取り組みを解説します。
用語の定義
一言で言うと、Scope3排出量とは**「自社の事業活動に関連する、Scope1とScope2以外の、あらゆる間接的な温室効果ガス(GHG)排出」**のことです。
これは、GHGプロトコルによって15のカテゴリーに分類されており、自社の事業を基点として、上流(サプライヤー側)と下流(顧客側)の両方の排出を含みます。多くの企業にとって、Scope3は総排出量の70%以上を占めると言われており、その影響はScope1とScope2をはるかに上回ります。
重要性の解説
Scope3の重要性は、それが企業の気候変動リスクと機会が、自社の工場やオフィスの壁の外にこそ存在するという現実を、経営者に突きつける点にあります。
これは、氷山の一角に例えることができます。
- Scope1とScope2: 海面の上に見えている、目に見えやすく管理しやすい氷山の一角。
- Scope3: 海面の下に隠れている、巨大で、その全貌を把握することさえ困難な氷山の本体。
この水面下の巨大なリスク(例:サプライヤーが気候変動による物理的被害を受けるリスク、将来の炭素価格導入で原材料費が高騰するリスク)と機会(例:サプライヤーと協働してエネルギー効率を改善し、コストを削減する機会)を可視化するのが、Scope3の算定です。気候変動ファイナンスの観点から見れば、投資家はもはや、企業単体の排出量だけでなく、そのサプライチェーン全体の強靭性(レジリエンス)と脱炭素化への移行戦略を評価しています。Scope3への取り組みは、企業の長期的な価値創造能力と、気候変動に対する真の責任を示す、決定的な指標なのです。
仕組みや具体例
Scope3は、GHGプロトコルに基づき、以下の15のカテゴリーに分類されます。企業は、自社の事業活動に関連性の高いカテゴリーを特定し、その排出量を算定します。
上流(Upstream)の活動
- カテゴリー1:購入した製品・サービス: 原材料の調達、製造委託先での加工など。多くの場合、最大の排出源。
- カテゴリー2:資本財: 工場や設備の建設、機械の製造など。
- カテゴリー3:Scope1, 2に含まれない燃料・エネルギー関連活動: 購入した電力の送電ロスや、燃料の採掘・精製など。
- カテゴリー4:輸送、配送(上流): サプライヤーからの部品や原材料の輸送。
- カテゴリー5:事業から出る廃棄物: 自社から出た廃棄物の、社外での処理。
- カテゴリー6:出張: 従業員の出張(航空機、鉄道など)。
- カテゴリー7:雇用者の通勤: 従業員の通勤。
- カテゴリー8:リース資産(上流): 自社が借りている資産(オフィス、倉庫など)のScope1, 2排出量。
下流(Downstream)の活動
- カテゴリー9:輸送、配送(下流): 製品の顧客への輸送。
- カテゴリー10:販売した製品の加工: 中間製品が、顧客先でさらに加工される際の排出。
- カテゴリー11:販売した製品の使用: 販売した製品(自動車、家電など)が、顧客によって使用される際の排出。
- カテゴリー12:販売した製品の廃棄: 販売した製品が、寿命を終えて廃棄される際の排出。
- カテゴリー13:リース資産(下流): 自社が貸している資産の稼働。
- カテゴリー14:フランチャイズ: フランチャイズ加盟店の稼働。
- カテゴリー15:投資: 投融資先の排出量。金融機関にとってはこれが最大の排出源。
国際的な動向と日本の状況
2025年現在、Scope3排出量の開示は、任意から「義務」へと、その位置づけを急速に変化させています。
国際的な動向:
**国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)**が公表した開示基準(IFRS S2)では、企業の気候関連リスクを評価する上で重要性(マテリアリティ)がある場合、Scope3排出量の開示を実質的に要求しています。この基準は、世界各国の証券市場で採用が進んでおり、グローバルに事業を展開する企業にとって、Scope3の算定と開示はもはや避けて通れない経営課題です。
この流れは、開発途上国に位置する多くのサプライヤーに、自社の排出量を算定し、削減努力を行うことを促す、強力な波及効果を生み出しています。先進国のグローバル企業は、サプライヤーに対して、再生可能エネルギーへの転換支援や、省エネ技術の導入といった「サプライヤー・エンゲージメント」を強化しており、これが途上国への新たな技術移転と資金動員(Finance Mobilization)の形となっています。
日本の状況:
日本でも、金融庁が主導するコーポレートガバナンス・コードの改訂や、東京証券取引所のプライム市場上場企業に対するTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく開示の要請などを通じて、Scope3を含むサプライチェーン排出量の開示が、事実上の標準となりつつあります。
メリットと課題
Scope3の管理は、企業に新たな視点をもたらす一方で、その実践には多くの困難が伴います。
メリット(Scope3管理の):
- リスクと機会の可視化: サプライチェーン全体の気候変動リスクと、排出削減によるコスト削減機会を特定できる。
- ステークホルダーとの連携強化: サプライヤーや顧客と協働することで、より強靭で持続可能なバリューチェーンを構築できる。
- イノベーションの促進: 製品の設計段階から、使用時や廃棄時の排出量を考慮した、環境配慮型の製品開発を促す。
- 途上国への貢献(公正な移行): サプライヤーへの支援を通じて、途上国の脱炭素化と産業競争力の向上に貢献できる。
課題:
- 算定の困難さとデータの信頼性: サプライヤーから正確な排出量データを収集することは極めて困難であり、多くの場合、業界平均値などを用いた推計に頼らざるを得ず、データの信頼性(Integrity)に課題が残る。
- 影響力の限界: 巨大なグローバル企業であっても、無数のサプライヤー、特にその先の二次、三次のサプライヤーにまで影響を及ぼすことは非常に難しい。
- コスト負担: サプライヤー、特に途上国の中小企業にとって、排出量の算定や削減努力は、大きなコスト負担となる可能性がある。
まとめと今後の展望
Scope3排出量は、企業の気候変動への影響と責任が、自社の境界線をはるかに超えて広がっているという、現代のグローバル経済の現実を映し出す鏡です。
要点:
- Scope3は、サプライチェーン全体を対象とする、企業のGHG排出量のうち最も広範で、かつ影響の大きい部分である。
- その算定と開示は、国際的な情報開示基準の下で、事実上の義務となりつつある。
- Scope3の削減は、サプライヤー(多くは途上国に所在)との協働が不可欠であり、新たな気候変動ファイナンスと技術移転の機会を生み出す。
- 算定データの信頼性確保と、サプライヤーへの過度な負担が、今後の大きな課題である。
今後の展望として、Scope3の管理は、企業が気候変動対策の「リーダー」となるか、「追随者」に留まるかを分ける、決定的な試金石となるでしょう。優れた企業は、単に排出量を報告するだけでなく、AIやブロックチェーンといった最新技術を活用してサプライチェーンの透明性を高め、サプライヤーへの資金支援や技術協力に積極的に投資していくはずです。それは、自社のリスクを管理する受動的な行為から、サプライチェーン全体を、より公正で、より持続可能な形へと変革していく、能動的で創造的な挑戦へと進化していくのです。