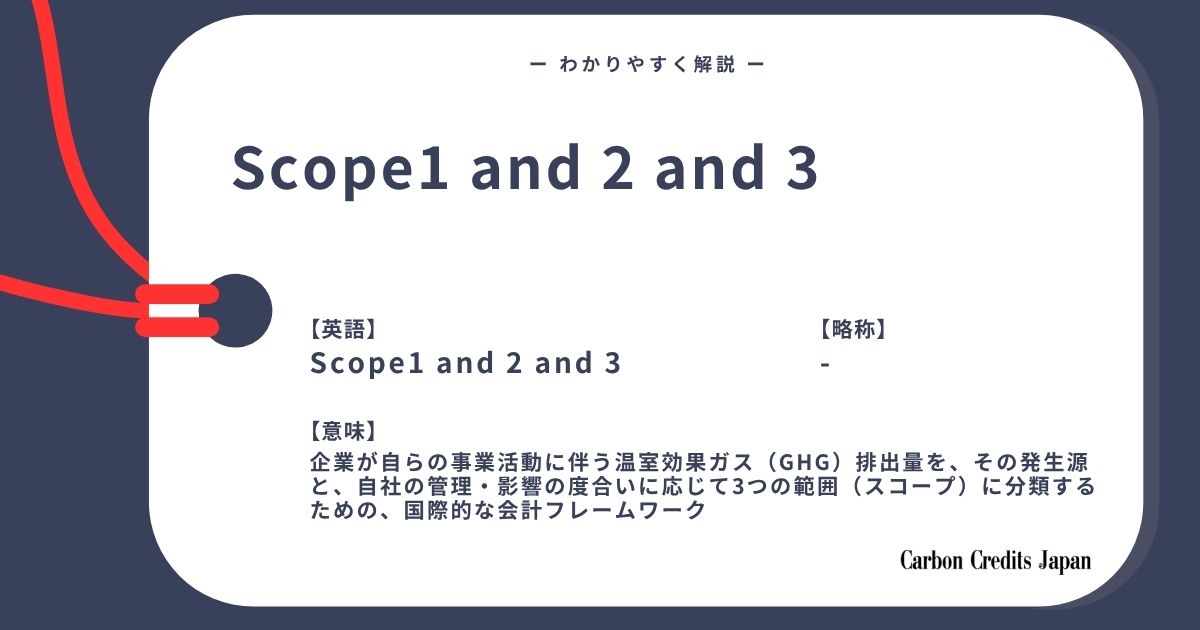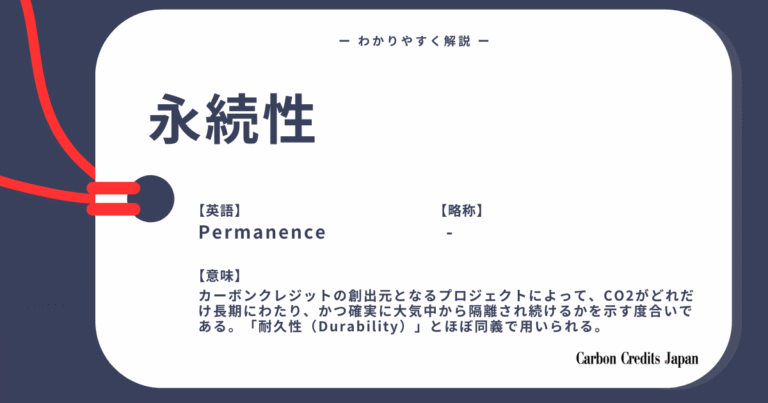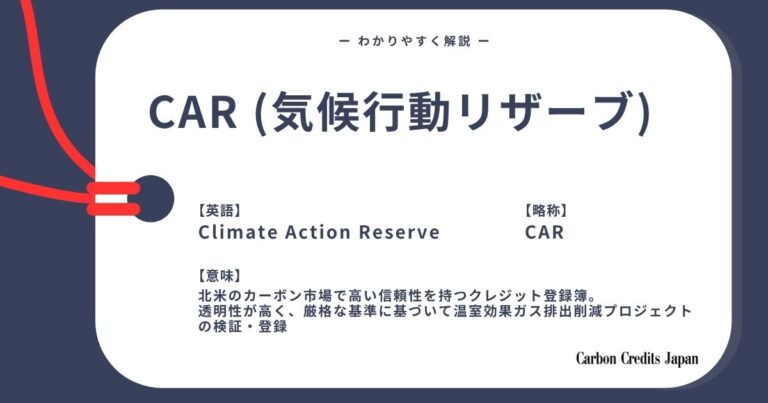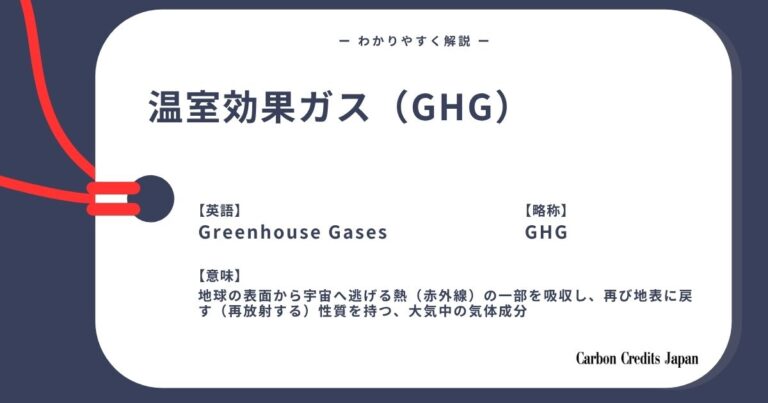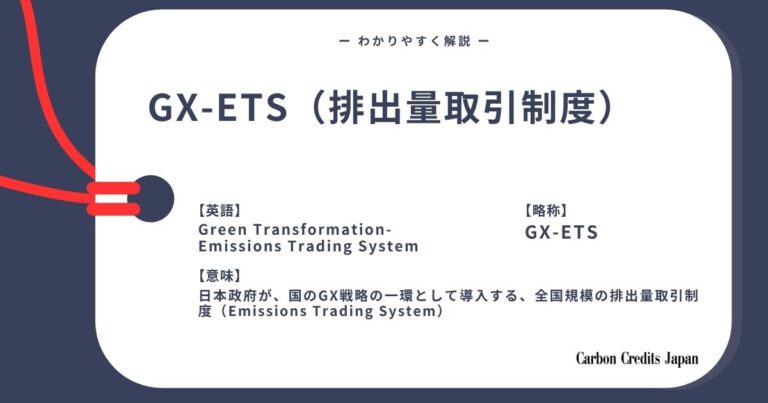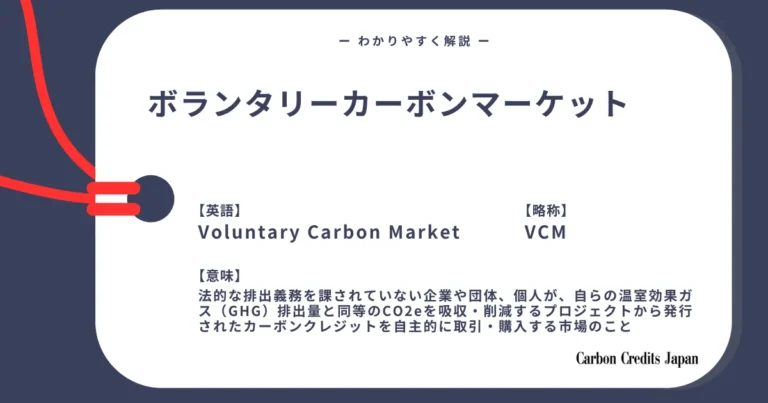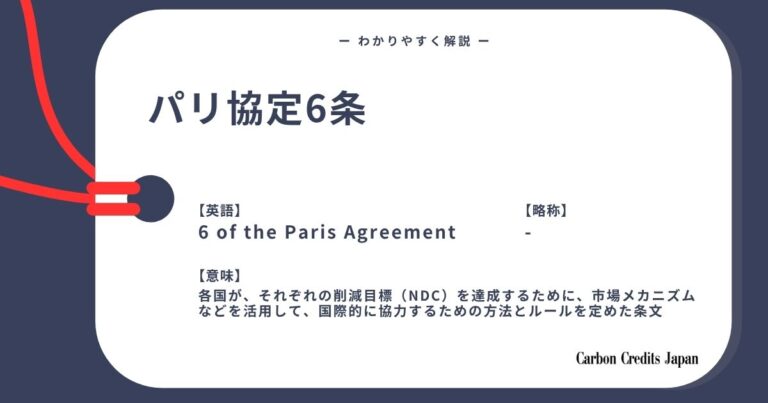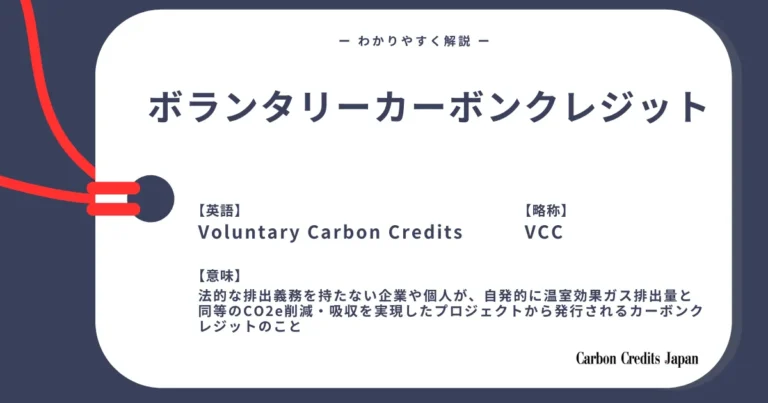企業のカーボンフットプリントという言葉を耳にする際、それが具体的にどこからどこまでの範囲を指すのか、疑問に思うことはないだろうか。自社の工場から排出される煙だけなのか、それとも製品の原材料が作られる過程や、顧客が製品を使用する際の排出まで含むのか。
本記事では、この問いに明確な答えを与える、温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告における世界標準「GHGプロトコル」が定める「Scope1, 2, 3」という分類について、その全体像と各スコープの関係性を統合的に解説する。
Scope1, 2, 3とは
Scope1, 2, 3とは、企業が自らの事業活動に伴う温室効果ガス(GHG)排出量を、その発生源と自社の管理・影響の度合いに応じて3つの範囲(スコープ)に分類するための、国際的な会計フレームワークである。
この3つのスコープは、企業の排出量を同心円状に捉えると理解しやすい。
- Scope1:企業が直接管理する、自社からの直接排出。
- Scope2:自社が購入するエネルギーに由来する、間接的な排出。
- Scope3:上記以外で、自社の事業活動に関連する、サプライチェーン全体からの間接的な排出。
なぜ3つのスコープに分類するのか
このフレームワークは、企業の排出量を体系的に理解し、管理するために不可欠である。分類の主な理由は以下の通りだ。
責任と管理範囲の明確化
企業は、自らが直接コントロールできる排出(Scope1)、電力の購入先を選ぶことで影響を与えられる排出(Scope2)、そしてサプライヤーや顧客との協働が必要な排出(Scope3)を、明確に区別して認識することが可能となる。
ダブルカウントの防止
社会全体で、同じ排出量が異なる企業によって二重に計上されることを防ぐ役割がある。例えば、ある電力会社のScope1排出量は、その電力を購入する企業のScope2排出量として計上されるため、明確な境界線が引かれるのである。
戦略的な削減計画の策定
この分類により、企業は自社の排出量の「ホットスポット」を特定し、どこから削減努力を始めるべきか、戦略的に計画を立てることが可能になる。
各スコープの詳細解説
Scope1 直接排出量(Direct Emissions)
事業者が所有・管理する排出源から、物理的に直接排出されるGHGを指す。自社の工場における燃料の燃焼、社用車の排気ガス、自社設備からの冷媒フロンの漏洩などが具体例として挙げられる。キーワードは「自社で直接コントロール」である。
Scope2 エネルギー由来の間接排出量(Indirect Emissions from Energy)
事業者が他社から購入した電気、熱、蒸気の使用に伴い、そのエネルギーの製造元で発生する間接的なGHG排出を指す。オフィスや工場で使用する、電力会社から購入した電力がこれにあたる。キーワードは「購入したエネルギー」である。
Scope3 その他の間接排出量(Value Chain Emissions)
Scope 1, 2以外の、企業のバリューチェーン全体から発生する、あらゆる間接排出を指す。多くの場合、これが企業の総排出量の最大の割合を占める。GHGプロトコルでは、15のカテゴリーに分類されている。
具体例としては、上流工程における「購入した原材料の製造」「従業員の通勤」「外部委託した輸送」、下流工程における「販売した製品の顧客による使用」「製品の廃棄」などが挙げられる。キーワードは「サプライチェーン全体」である。
フレームワークのメリットと課題
GHGプロトコルの導入には、メリットと同時に課題も存在する。
メリット
最大の利点は、企業の気候への影響とリスクの全体像を包括的に把握できる点にある。また、国際的に統一された基準であるため、企業間の比較可能性が高まる。さらに、サプライチェーン全体を巻き込んだ体系的な排出削減を促進する効果も期待できる。
課題
一方で、Scope3の算定には極めて高い複雑性が伴う。世界中に広がるサプライヤーから正確なデータを収集することは、多大なコストと労力を要し、多くの企業にとって大きなハードルとなっている。
また、コントロールの限界も課題である。企業は自社のサプライヤーや顧客の排出に対し、直接的な管理権を持たず、影響力を行使することしかできないため、削減活動の難易度は高くなる。
まとめ
本記事では、Scope1, 2, 3というGHGプロトコルのフレームワークが、企業の排出量を体系的に捉え、管理するための世界標準であることを解説した。
- 排出量は、Scope1(直接)、Scope2(エネルギー由来間接)、Scope3(その他間接・サプライチェーン)の3つに分類される。
- このフレームワークが、企業のGHGインベントリの基礎となる。
- 多くの企業にとって、Scope3が最大の排出源であり、その管理が重要となる。
- 企業の気候変動への責任は、自社の活動範囲を超え、バリューチェーン全体に及ぶものである。
このフレームワークは、企業の責任範囲を工場の煙突から原材料の生産地まで拡大させるものであり、サプライチェーン全体での脱炭素化を促進する基盤として機能している。