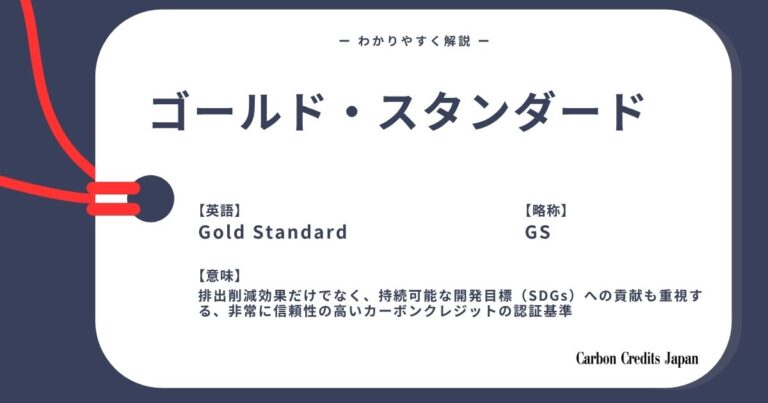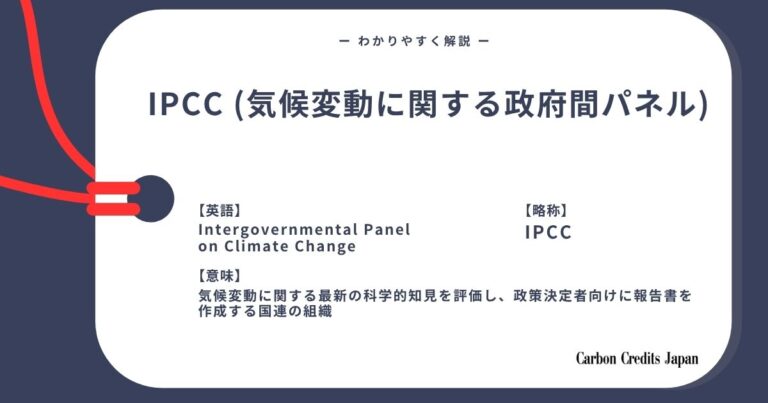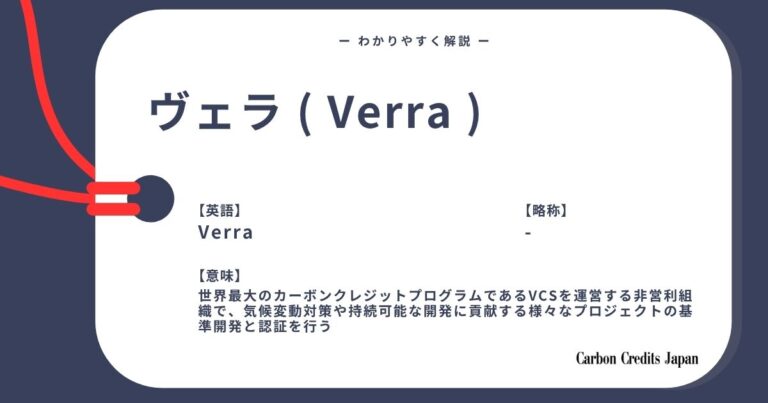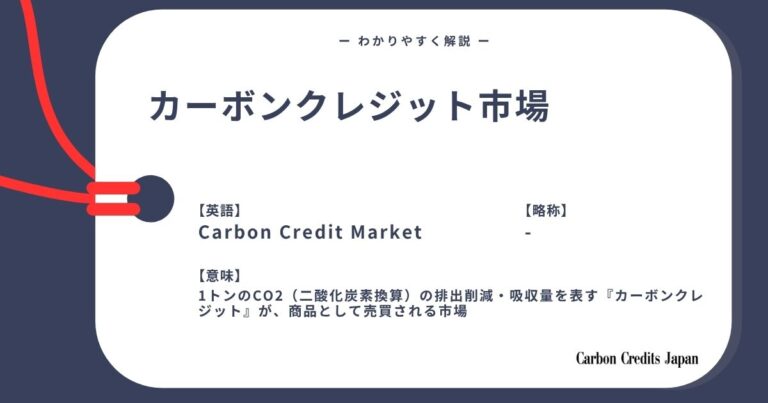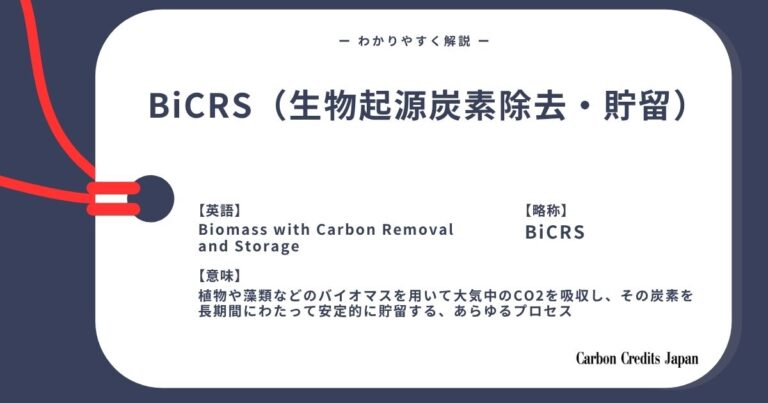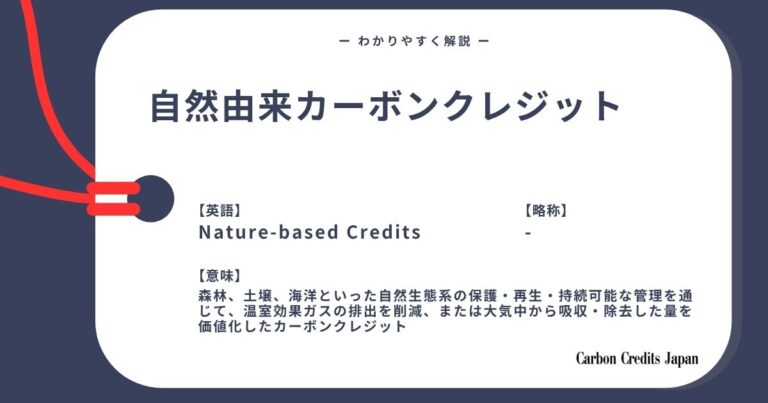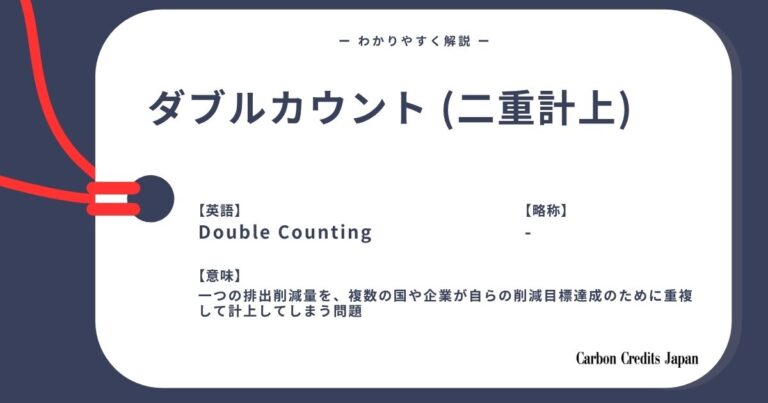気候変動対策は、単に未来の排出を「減らす」ことから、すでに大気中に存在するCO2を積極的に「取り除く(Remove)」ことへと、その重心を移している。この「ネガティブ・エミッション」を実現するための究極の技術として、世界中から期待を集めているのが、「DACCS(Direct Air Capture with Carbon Storage)」、すなわち「直接空気回収・炭素貯留」である。
本解説では、この最先端技術を「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から深く分析する。DACCSがいかにして、その高い信頼性を武器に、気候変動対策のゲームチェンジャーとなり、新たな官民の資金を動員しているのか。そして、この技術が将来、途上国の開発機会や公正な移行にどのような影響をもたらしうるのか。その壮大な可能性と、乗り越えるべき巨大な課題を包括的に解説する。
DACCSとは何か
一言で言うと、DACCSとは「大気中から直接CO2を回収(DAC)し、それを地中深くに長期間にわたって安定的に貯留(CCS)する一連の技術」の総称である。
これは、二つの既存技術を組み合わせたものである。
DAC(Direct Air Capture)直接空気回収
DACは、特殊な化学物質を用いて、どこにでもある空気の中から、濃度わずか0.04%の希薄なCO2だけを選択的に分離・回収する技術である。
CCS(Carbon Capture and Storage)炭素回収・貯留
CCSは、回収したCO2を、パイプラインなどで輸送し、地下1,000メートル以上の深部にある帯水層などに、数千年以上にわたって安定的に封じ込める技術である。
この二つを組み合わせたDACCSは、地球の炭素循環からCO2を純粋に取り除き、隔離することを目的とした、最も直接的で測定可能な「炭素除去(Carbon Dioxide Removal, CDR)」技術の一つである。
DACCSのプロセス
DACCSのプロセスは、DACプラントでの「回収」と、その後の「貯留」から成り立っている。
- 回収(DAC)
巨大なファンで大量の空気を吸い込み、特殊なフィルター(固体吸着材)や液体(化学吸収液)にCO2を化学的に結合させて捕捉する。その後、熱や圧力をかけてCO2を分離・精製する。 - 圧縮・輸送
回収された高純度のCO2は、液体に近い状態まで圧縮され、パイプラインや専用の輸送船で貯留サイトへと運ばれる。 - 圧入・貯留(CCS)
貯留サイトで、CO2は地下深くの多孔質な岩石層(帯水層や枯渇したガス田など)に圧入される。その上を、CO2を通さない固い岩盤(遮蔽層)が覆っているため、CO2は半永久的に閉じ込められる。
メリットと課題
DACCSは、究極の解決策であると同時に、究極の挑戦でもある。
メリット
- 最高の信頼性
除去量が正確に測定・検証可能で、貯留の永続性も非常に高いため、最も信頼できる炭素除去クレジットを創出できる。 - 場所の柔軟性
再生可能エネルギーと貯留サイトさえあれば、原理的にはどこにでも設置可能である。 - 土地利用効率
同じ量のCO2を除去するのに必要な土地面積が、植林などの自然ベースの解決策に比べて圧倒的に小さい。
課題
- 極めて高いコストとエネルギー消費
現在の除去コストは1トンあたり400〜1,000ドルと非常に高価である。また、プラントの稼働には大量のクリーンエネルギーが必要不可欠である。 - 技術と規模の未熟性
まだ産業としては黎明期にあり、気候に意味のあるインパクトを与えるためには、現在の規模から数百万倍にスケールアップさせる必要がある。 - 「モラルハザード」のリスク
「将来、DACCSで回収すればよい」という安易な考えが、現在の緊急な排出削減努力を遅らせる「言い訳」として利用される危険性がある。
まとめ
DACCSは、気候変動との闘いにおいて、人類が初めて手にする、地球の炭素循環に直接介入し、過去の排出を「取り消す」ための、強力かつ確実なツールである。
- DACCSは、大気から直接CO2を回収し、地中に貯留する、最も信頼性の高い炭素除去(ネガティブ・エミッション)技術である。
- その信頼性の高さから、企業のネットゼロ戦略において、最も高品質なカーボンクレジットの源泉として期待されている。
- 莫大なコストとエネルギー消費が最大の課題であるが、官民の巨額な投資によって、技術革新と市場創出が急速に進んでいる。
- その恩恵を、豊富な再生可能エネルギー資源を持つ途上国にも公正に分配していくことが、国際開発ファイナンスの大きな挑戦である。
DACCSは、広大な未利用地と、豊富な再生可能エネルギー(特に太陽光や風力、地熱)のポテンシャルを持つ途上国にとって、将来的に新たなグリーン産業を誘致し、高品質なカーボンクレジットを輸出する機会となり得る。
しかし、現時点では、莫大な初期投資と高度な技術、そしてCO2を安全に貯留するための地質学的条件と、それを管理する強固なガバナンスが求められるため、プロジェクトは先進国に集中している。この技術格差をいかに埋め、その恩恵を公平に分配するかが、国際開発ファイナンスの大きな課題である。