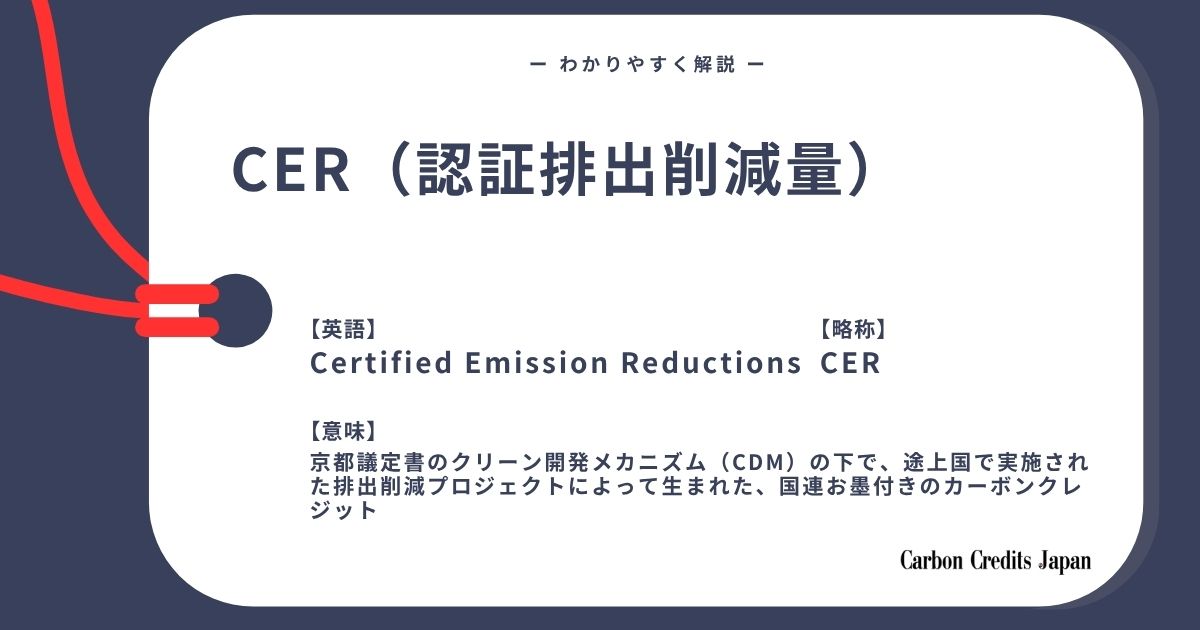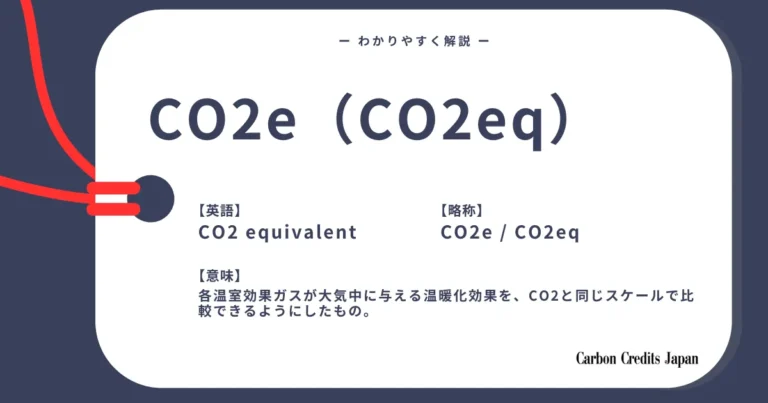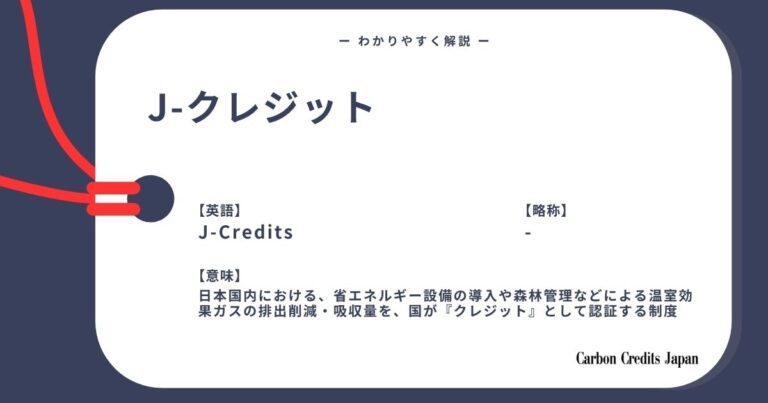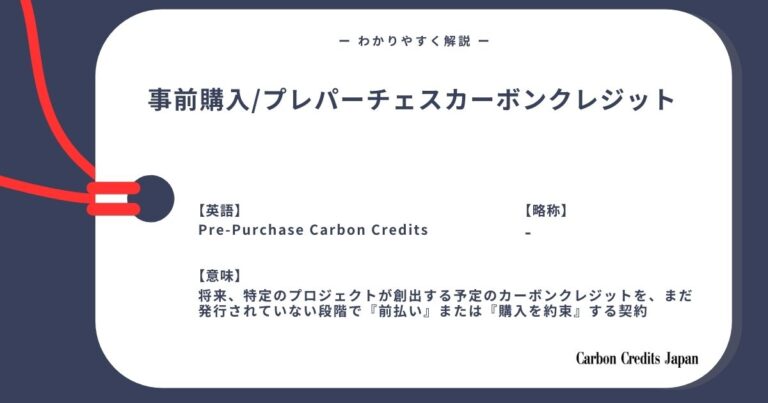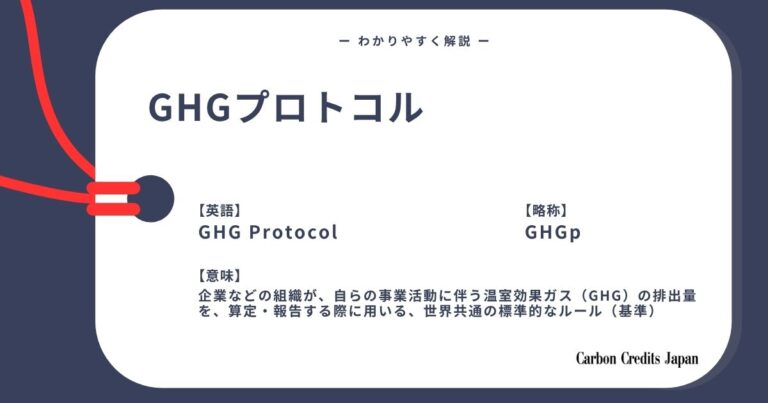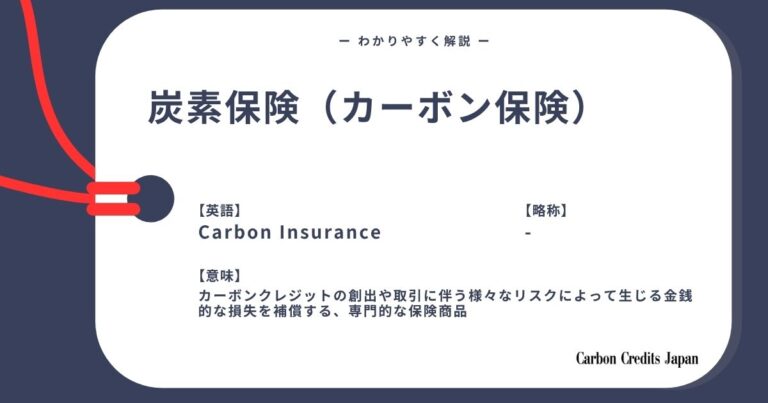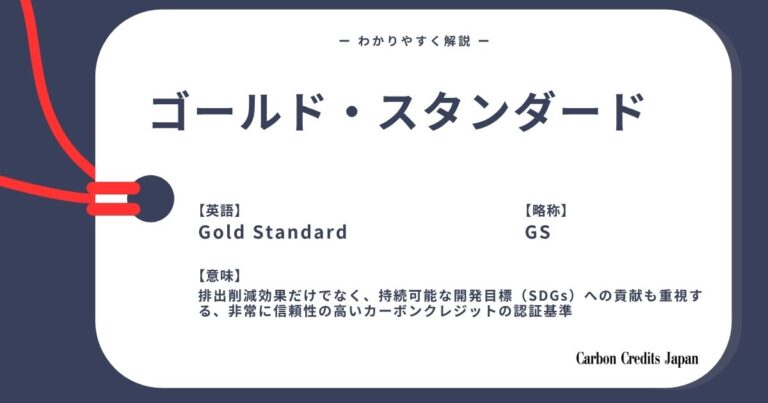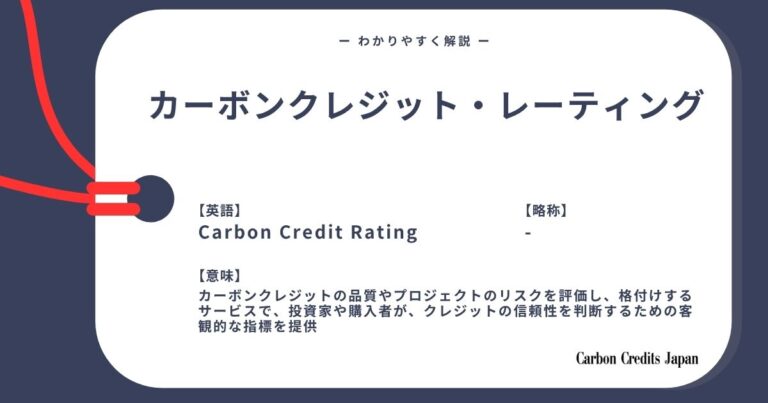今日のカーボンクレジット市場の議論を理解するためには、認証排出削減量(Certified Emission Reduction, CER)を知ることが不可欠である。これは、京都議定書の下で創設されたクリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism, CDM)から生まれた、いわば「第一世代」の国際カーボンクレジットである。
本記事では、「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から、このCERの歴史的な役割とその遺産を分析する。CERがいかにして、先進国から途上国への、前例のない規模の民間資金の呼び込みを可能にしたか。そして、その運用を通じて露呈した市場の信頼性を巡る深刻な課題が、今日のパリ協定下の市場設計や、公正な移行を巡る議論にどのような教訓を与えているか、深く掘り下げていく。
CERとは
CERとは、「京都議定書の下で、先進国の資金・技術支援により、途上国で実施された温室効果ガス排出削減プロジェクトから創出された、国連認証のカーボンクレジット」のことである。
1CERは、1トンの二酸化炭素換算(t-CO2e)の排出削減量に相当する。京都議定書で排出削減義務を負う先進国は、このCERを自国の目標達成のために使用することができた。その目的は、先進国に柔軟な目標達成手段を提供すると同時に、途上国の持続可能な開発を支援するという、二重の便益を創出することにあった。
CERの歴史的重要性
CERの歴史的重要性は、気候変動対策というグローバルな課題解決のために、史上初めて、先進国の民間資金を途上国へと大規模に誘導する市場メカニズムを制度化した点にある。
これは、国際的な「環境投資のパイプライン」を初めて建設した試みに例えることができる。このパイプライン(CDM)を通じて、先進国の企業は、自国内でのコストの高い排出削減の代わりに、よりコスト効率の高い途上国のクリーンエネルギープロジェクトなどに投資し、その成果(CER)をリターンとして受け取ることができた。
この仕組みは、京都議定書の「共通だが差異ある責任」という原則を具体化するものであった。つまり、歴史的に排出責任の大きい先進国が、資金と技術を提供することで、排出削減のポテンシャルが大きい途上国のグリーンな発展を支援するという、国際協力の新しい形を提示したのである。CERは、この協力関係の中で取引される「国際通貨」として機能し、気候変動ファイナンスという大きな市場そのものを創り出した。
仕組み(発行プロセス)
CERが発行されるまでには、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の下に設置されたCDM理事会の監督下で、非常に厳格で複雑なプロセスを経る必要があった。
負の遺産と教訓
CDMは8,000件以上のプロジェクトを登録し、20億トン以上のCERを発行するという規模を達成したが、その過程で深刻な信頼性の問題に直面した。
- 信頼性の欠如と追加性(Additionality)の問題
大規模水力発電や一部の産業ガス破壊プロジェクトが、「CER収入がなくても実施されたのではないか」という強い批判を受け、市場全体の信頼性を揺るがした。これは、排出削減がCER発行によって追加的(Additionality)にもたらされたかという、クレジットの根幹に関わる問題である。 - 社会的・環境的セーフガードの不備
一部のプロジェクトが、地域住民の強制移住や生態系破壊を引き起こしたとされ、社会的セーフガードの欠如が問題となった。「公正な移行」の視点が欠けていたとの指摘がある。 - 過度な官僚主義
複雑で時間のかかる国連の承認プロセスが、プロジェクトの実施を阻害し、非効率的であるという批判を招いた。
これらの「CDMの失敗」の教訓は、パリ協定6条下の新しい市場メカニズムの設計に深く反映されている。二重計上を厳格に防ぐ「対応調整」の導入や、人権・環境セーフガードの強化は、まさにCERの反省の上に成り立っている。
日本の取り組み
日本は、京都議定書の目標達成のためにCERを最も多く購入した国の一つであり、その取引経験は日本の気候変動政策に大きな影響を与えた。CDMのプロセスが非常に煩雑で時間がかかり、必ずしも日本の技術や相手国のニーズに合致しなかったという反省から、日本はより迅速で柔軟な二国間協力の枠組みとして二国間クレジット制度(JCM)を創設した。JCMは、CDMの教訓を活かした、「日本流のポストCDM」モデルと言える。
CERのメリットと課題
CERは、気候変動ファイナンスの歴史における偉大な実験であり、その功罪は明確である。
メリット
- 市場の創設
世界初のグローバルな炭素市場を創り出し、民間資金を途上国の気候変動対策に動員する道筋をつけた。 - 技術移転と能力構築
途上国にクリーン技術を移転し、炭素市場に関する多くの専門家や制度を育成した。 - コスト効率
先進国にとって、比較的低コストで排出削減目標を達成する手段を提供した。
課題
- 信頼性の欠如
追加性の問題が市場全体の信頼を揺るがし、グリーンウォッシングとの批判を招いた。 - 社会的・環境的セーフガードの不備
プロジェクトが地域社会に負の影響を与えるケースがあり、「公正な移行」の視点が欠けていた。 - 過度な官僚主義
複雑で時間のかかる国連の承認プロセスが、プロジェクトの実施を阻害した。
まとめ
CER(認証排出削減量)は、その歴史的役割を終えたが、その存在なくして今日の気候変動ファイナンスの議論はあり得ない。
CERは、京都議定書のCDMの下で生まれた、途上国での排出削減を価値化した初の国際カーボンクレジットであった。先進国の民間資金を途上国に動員するパイプラインを創設したが、追加性などの信頼性問題に直面した。その失敗の教訓は、より信頼性が高く公正な市場を目指す、パリ協定6条や現代のボランタリー市場の制度設計に深く活かされている。日本のJCMは、CER/CDMの経験を踏まえて設計された、日本独自のアプローチである。
CERの物語は、気候変動ファイナンスという複雑なシステムにおいて、信頼性がいかにその生命線であるかを我々に教えてくれる。現在、市場が厳格な基準(例えば、ICVCMの「コアカーボン原則」)を求めるのは、まさにCERが残した「二の舞は演じない」という強い決意の表れである。CERは過去の遺物かもしれないが、その教訓は、より効果的で、より公正な未来の気候変動ファイナンスを築くための、永遠の道しるべであり続ける。