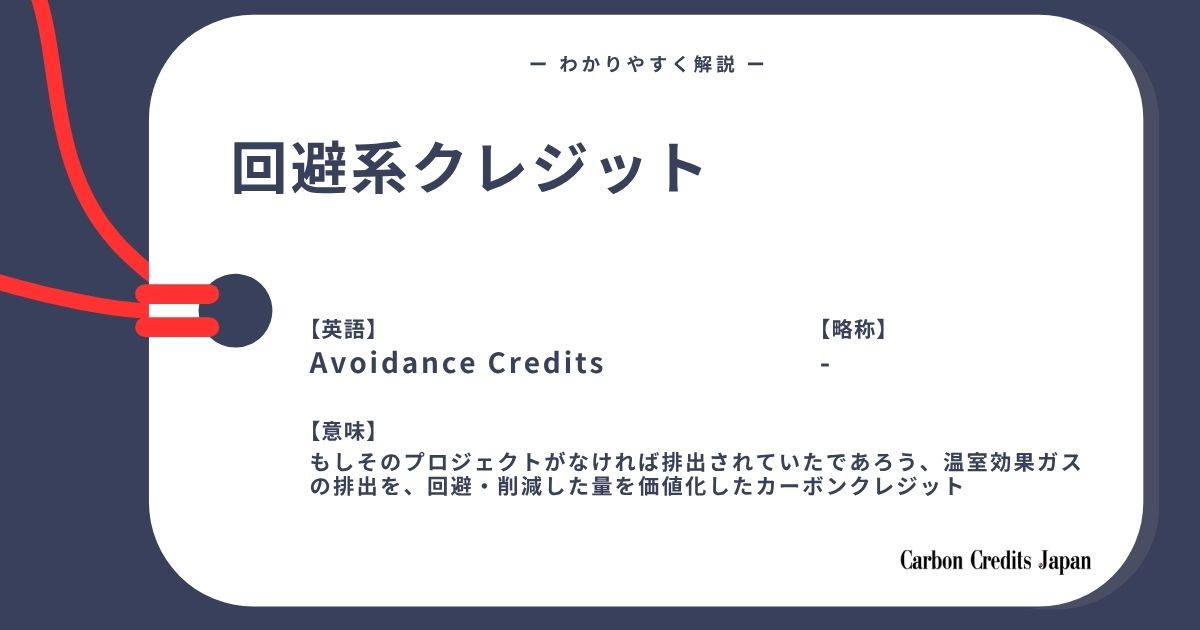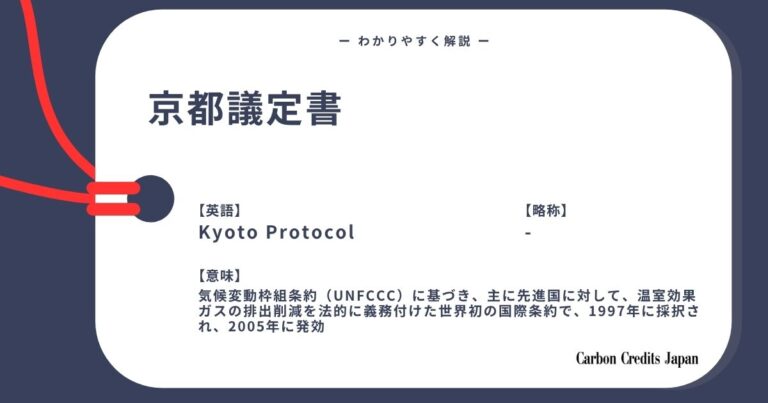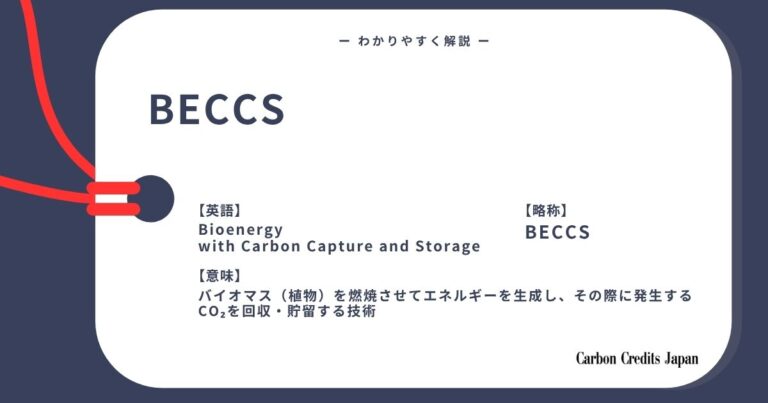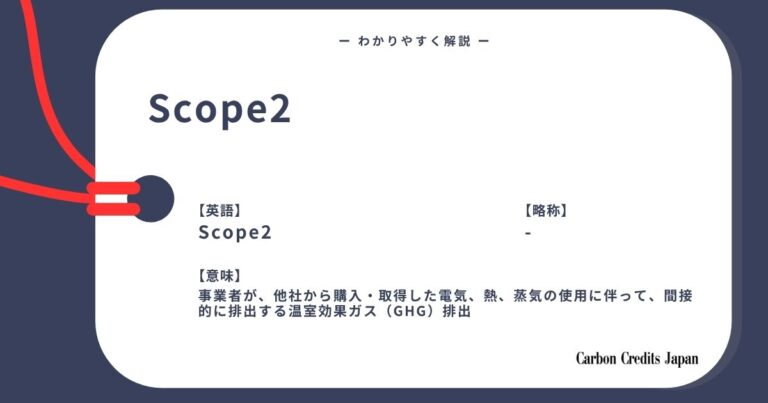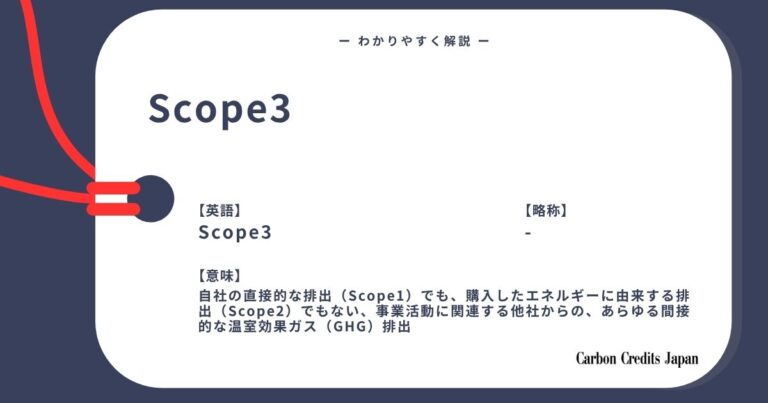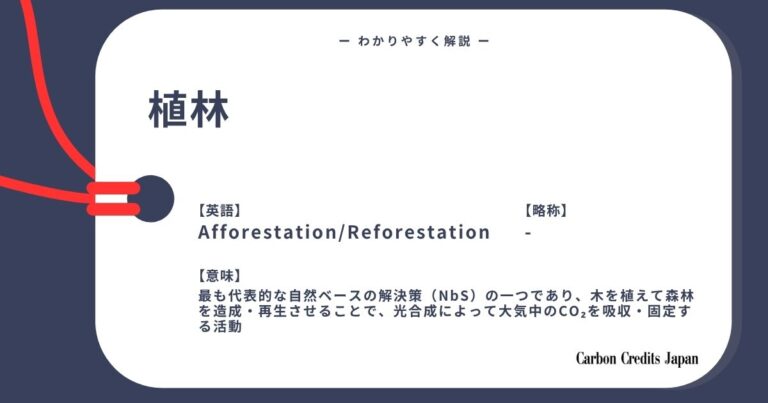気候変動対策には、大きく分けて2つのアプローチが存在する。
一つは、大気中のCO2を積極的に吸い取る「除去」の活動。もう一つは、そもそもCO2が大気中に出るのを未然に「防ぐ」活動である。カーボンクレジットも、この2つの考え方に基づいて分類される。
この記事では、カーボンクレジット市場において重要な役割を担う「回避系クレジット(Avoidance Credits)」について、その仕組み、重要性、そして除去系クレジットとの違いを解説する。
回避系クレジットとは
回避系クレジットとは、「もしそのプロジェクトがなければ排出されていたであろう温室効果ガスの排出を、回避・削減した量を価値化したカーボンクレジット」のことである。
この概念を正確に把握するためには、「除去系クレジット」との対比で理解することが極めて重要だ。両者の違いは、以下の通りである。
| 項目 | 回避系(Avoidance) | 除去系(Removal) |
| 活動内容 | 排出そのものを未然に防ぐ (例:森林伐採の停止、再エネ導入) | 大気中からCO2を物理的に取り除く (例:植林、DACでの回収) |
| 大気への影響 | 濃度がこれ以上悪化するのを防ぐ | 濃度を純粋に減少させる |
| 浴槽での例え | 蛇口を「閉める」ことで、 水かさが増えるのを止める行為 | 栓を「抜く」ことで、 水かさを減らす行為 |
なぜ回避系クレジットが重要なのか
回避系クレジットは、特に途上国における気候変動対策と、その資金調達において中心的な役割を果たしてきた。その理由は主に以下の3点に集約される。
大規模かつ費用対効果の高い削減
多くの場合、CO2を大気から除去する技術よりも、排出を回避する方が低コストであり、かつ大規模な削減を迅速に実現できる。特に森林保全(REDD+)などは、費用対効果の高い気候変動対策の一つとされている。
「今そこにある危機」への即応性
熱帯雨林や生態系は、一度失われると元に戻すことは非常に困難である。回避系プロジェクトは、かけがえのない自然資本が失われるのを「今」防ぐという、極めて緊急性の高い役割を担っている。
豊かなコベネフィット
多くの回避系プロジェクトは、気候変動対策以外の面でもプラスの効果をもたらす。例えば、クリーンクックストーブの普及は女性や子供の健康被害を減少させ、森林保全は地域コミュニティの生活基盤や生物多様性の維持に貢献する。
回避系クレジットの主な種類
回避系クレジットには、プロジェクトの内容によっていくつかの種類が存在する。
森林減少・劣化の抑制(REDD+)
回避系クレジットの中で代表的なカテゴリーである。途上国の森林が伐採されるのを防ぐことで、森林が蓄えている炭素が大気中に放出されるのを回避する仕組みだ。
エネルギー効率の改善
従来の非効率な設備を更新することで排出を減らす取り組みである。例えば、途上国において薪を使用する古い調理コンロを、燃料消費の少ない「クリーンクックストーブ」に置き換えるプロジェクトなどが該当する。
メタンガスなどの回収・破壊
CO2よりも温室効果が高いメタンガス(埋立地や家畜の糞尿などから発生)を回収し、燃焼させる取り組みである。燃焼によって比較的温室効果の低いCO2へ変換することで、より大きな温暖化インパクトを回避する。
「ネットゼロ」に向けた役割と議論
近年、企業の脱炭素目標として「ネットゼロ」が掲げられる中で、回避系クレジットの役割についての議論が深まっている。
科学的な「中和」との違い
科学的根拠に基づくネットゼロの定義では、どうしても削減しきれない排出(残余排出)については、大気から同量のCO2を除去する「除去系クレジット」で中和する必要があるとされている。論理的に、プラスの排出をゼロにするには、マイナスの排出(除去)が必要であり、ゼロの維持(回避)では釣り合わないためだ。
「貢献」としての活用
一方で、世界全体の排出量を減らすためには、自社のバリューチェーン外での削減活動も不可欠である。そのため、回避系クレジットは自社の排出を帳消しにする相殺(Offset)としてではなく、社会全体の削減を加速させるための「貢献(Contribution)」として位置づけられる傾向にある。
メリットと課題
回避系クレジットの特性を理解する上で、そのメリットとデメリットを整理する。
メリット
- 即効性と規模
費用対効果が高く、大規模な排出削減を迅速に実現できる。 - 社会的な意義
森林保全や途上国支援など、緊急性が高く、SDGsなどへの貢献度も高い。 - 市場の実績
これまでカーボン市場の流動性の多くを支えてきた実績がある。
課題
- 追加性の証明
「もしプロジェクトがなければ排出されていた」という仮定のシナリオ(ベースライン)を証明する必要があるため、その算定根拠には厳格性が求められる。 - 役割の区別
将来的なネットゼロ達成(除去による中和)と、移行期における削減(回避による貢献)の役割分担について、明確な理解が必要とされる。
まとめ
回避系クレジットは、排出を「未然に防ぐ」ことで気候変動の進行を食い止める、極めて重要なメカニズムである。
- 排出を未然に防ぐ(Avoidance)活動から創出される。
- 除去(Removal)系とは、大気への物理的な作用が異なる。
- REDD+やエネルギー効率改善などが該当する。
「除去」と「回避」は、どちらか一方が優れているというものではなく、気候変動という巨大な課題に立ち向かうための「両輪」である。途上国の自然を守り、世界全体の脱炭素移行を加速させるためには、回避系クレジットを通じた資金循環が引き続き不可欠である。