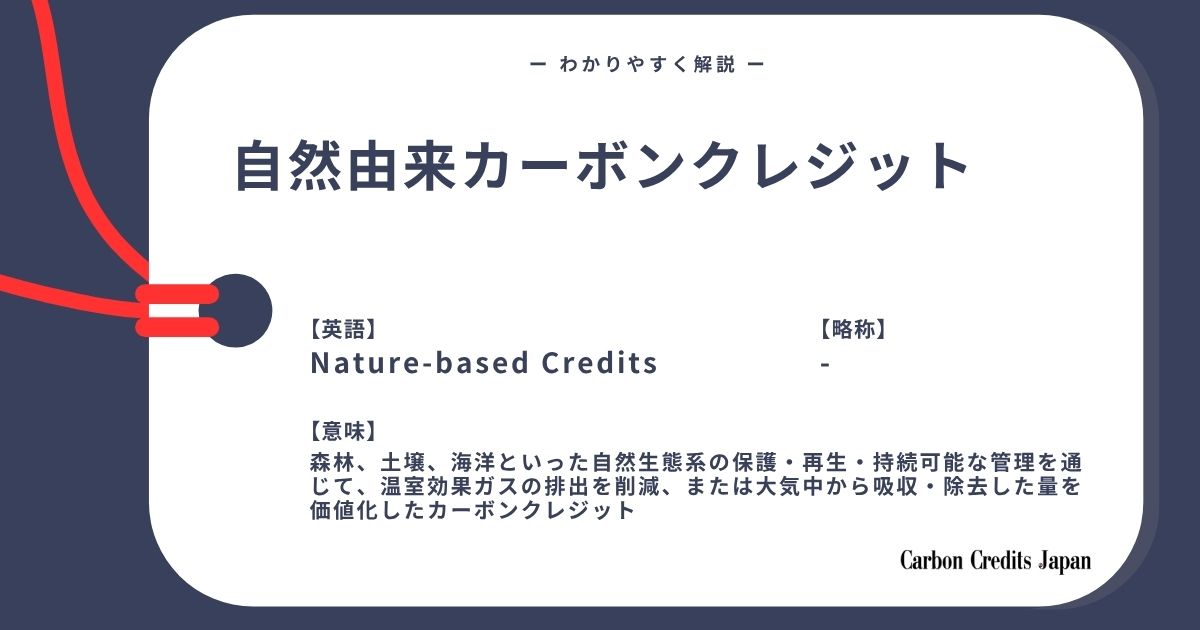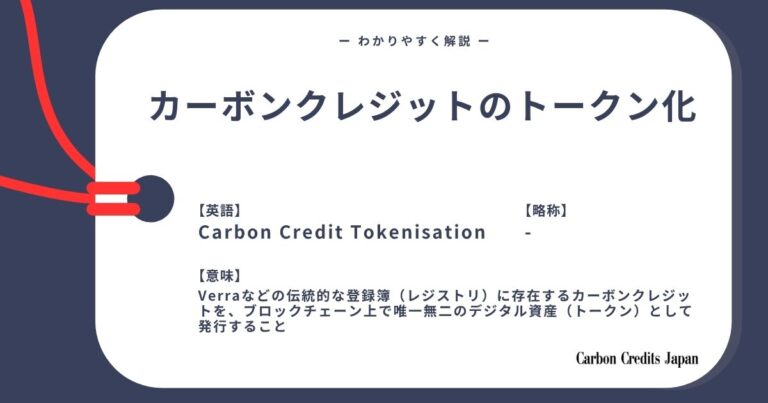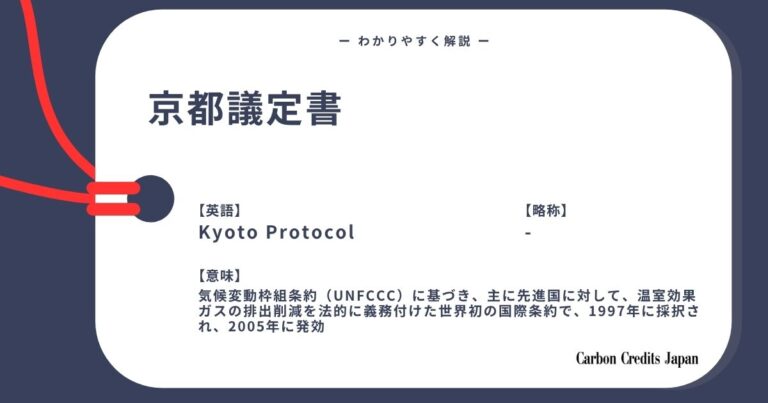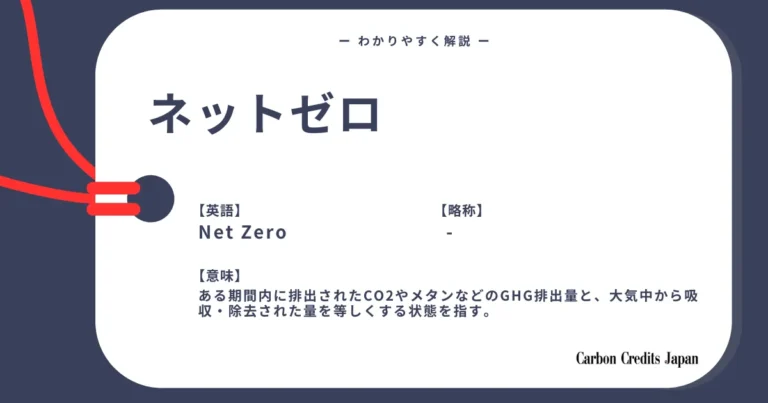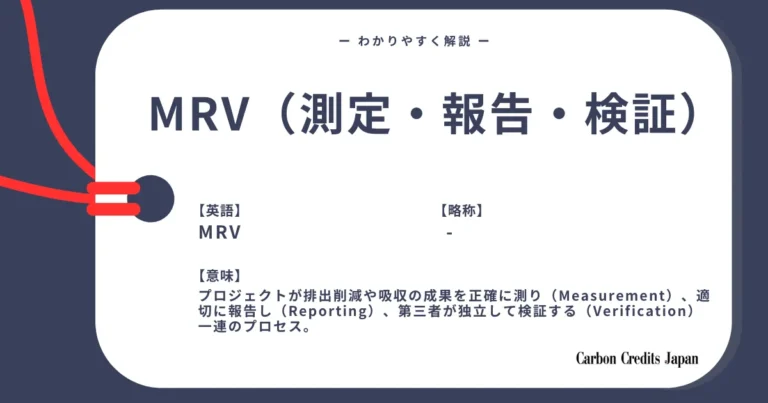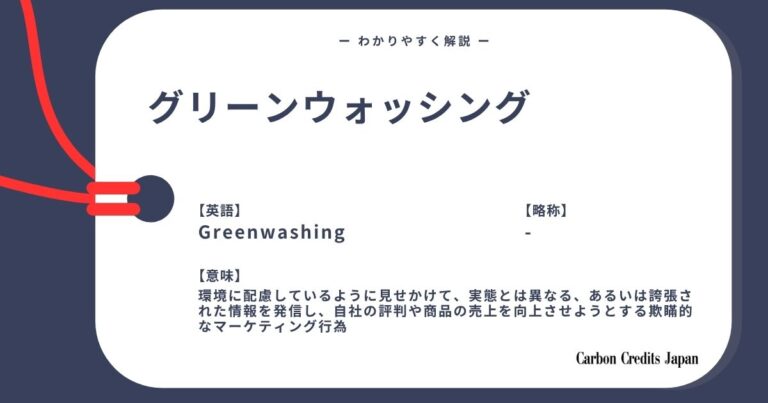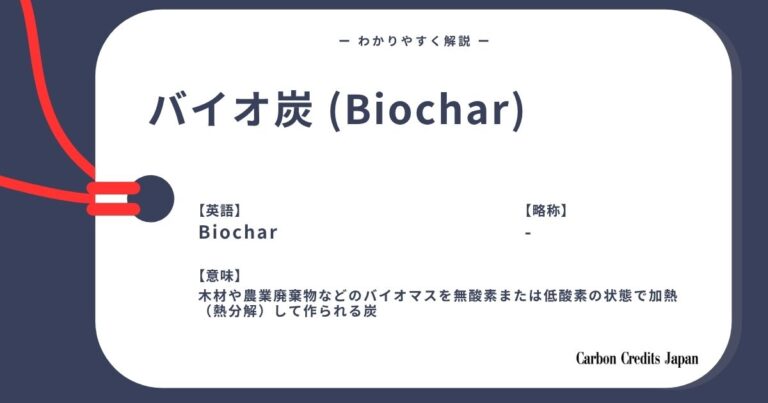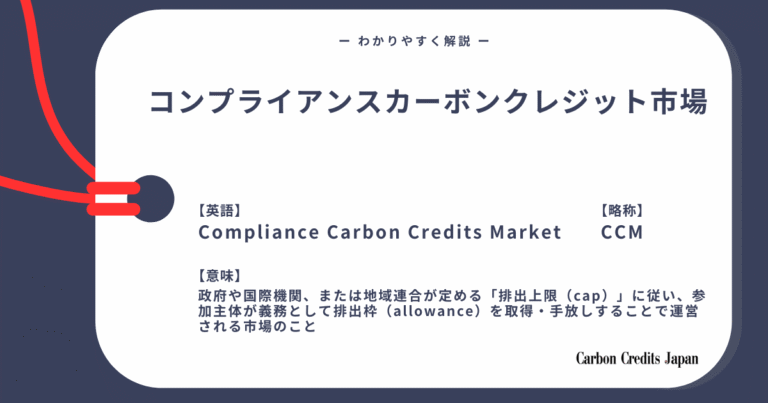はじめに
気候変動と生物多様性の喪失という、相互に深く関連する「双子の危機」に直面する中、その両方に同時に働きかけるアプローチとして「自然由来の解決策(Nature-based Solutions, NbS)」が国際社会の主流となりつつあります。そして、このNbS活動に民間資金を大規模に動員(Finance Mobilization)するための金融エンジンが、「自然由来カーボンクレジット」です。
本記事では、「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から、このクレジットの全体像を捉えます。森林保全から土壌改善、海洋生態系再生まで、多様な活動を含むこのクレジットが、いかにして途上国の持続可能な開発機会となり得るのか。その成功の鍵を握る市場の信頼性(Integrity)の課題、そして、活動の恩恵が先住民や地域コミュニティといった最も脆弱な人々に確実に届くための公正な移行(Just Transition)の重要性について、網羅的に解説します。
用語の定義
一言で言うと、自然由来カーボンクレジットとは**「森林、土壌、湿地、海洋といった生態系が持つ力を活用して、大気中のCO2を吸収・貯留、あるいは排出を回避する活動から創出されるカーボンクレジット」**の総称です。
これは、国際自然保護連合(IUCN)などが定義する「社会課題(気候変動など)に効果的かつ順応的に対処し、人間の幸福と生物多様性の両方に便益をもたらす、自然及び生態系の機能を保護、持続的に管理、回復するための行動」であるNbSを原資とするクレジットです。大気中からCO2を直接回収する技術(DACCS)など、工学的な解決策から生まれるクレジットと対比される概念であり、グリーンカーボン(陸域)とブルーカーボン(海域)の両方を含みます。
重要性の解説
このクレジットの重要性は、気候変動対策を、炭素という単一の指標から、生物多様性、水資源、食料安全保障、地域社会のレジリエンスといった、より広範な価値を包含する「統合的な投資」へと昇華させる点にあります。
これは、単なる「炭素の貯金箱」ではなく、「多岐にわたる配当を生む、生きた自然資本への投資ポートフォリオ」と考えることができます。例えば、途上国の熱帯林を保全するプロジェクトに投資することは、CO2吸収(=カーボンクレジット)という直接的なリターンだけでなく、
- 生物多様性: 絶滅危惧種の生息地を守る。
- 水資源: 流域全体の水源を涵養し、水質を浄化する。
- 地域経済: アグロフォレストリーやエコツーリズムといった、持続可能な生計手段を創出する。
- 先住民の権利: 伝統的な知識や土地の権利を尊重し、彼らを森の守り手としてエンパワーメントする。
といった、複数の開発目標(SDGs)に貢献する「共同便益(コベネフィット)」を生み出します。このコベネフィットの豊かさこそが、自然由来クレジットが投資家や企業を惹きつける最大の魅力であり、国際開発の文脈で極めて重要な意味を持つのです。
仕組みや具体例
クレジットの創出は、その活動領域の多様性に応じて、様々な国際基準や方法論に基づいて行われます。しかし、その根幹にあるプロセスは共通しています。
- プロジェクト設計: 地域の生態系と社会経済状況を深く理解し、炭素吸収とコベネフィットを最大化する活動を計画します。
- ベースラインの設定: 「もしプロジェクトがなかったら」というシナリオに基づき、炭素蓄積量の基準線を設定します。
- 実施とモニタリング: 植林、持続可能な森林管理、土壌改良などを実施し、炭素蓄積量の変化を衛星データや現地調査で継続的に監視します。
- 第三者検証と発行: 独立監査機関が、実績とベースラインとの差分(追加的な吸収・削減量)を検証し、VerraやGold Standardなどのレジストリがクレジットを発行します。
具体例:
- 森林保全(REDD+): アマゾンやコンゴ盆地で、商業伐採や農地転用の危機にある森林を、地域住民と協力してパトロールし、持続可能な森林管理計画を導入することで森林減少を防ぐ。回避された排出量がクレジットとなる。
- アグロフォレストリー: 中南米の小規模農家が、従来の単一栽培から、コーヒーの木とシェードツリー(日陰を作る木)を組み合わせて栽培する方法に転換。これにより、土壌の炭素貯留量が増加し、生物多様性も向上する。
- 土壌炭素貯留: アフリカのサヘル地域で、不耕起栽培や被覆作物の導入といった「再生可能農業」を実践し、劣化した農地の土壌有機炭素量を回復させる。
- ブルーカーボン(マングローブ再生): 東南アジアで、過去にエビ養殖池に転換されてしまった沿岸域に、地域コミュニティと共にマングローブを再植林する。
国際的な動向と日本の状況
2025年現在、カーボンクレジット市場では「質への逃避」が鮮明になっており、コベネフィットが豊富な自然由来クレジットへの需要が世界的に高まっています。
国際的な動向:
ICVCMが策定した「中核炭素原則(CCPs)」は、クレジットの信頼性を評価する世界的なベンチマークとなりつつあり、特に生物多様性や人権への配慮が厳しく問われています。また、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)の提言を受け、企業が自社の事業活動における自然への依存度と影響を開示する動きが本格化。これにより、サプライチェーン上の生態系保全に貢献する手段として、自然由来クレジットへの注目がさらに高まっています。世界銀行などの国際開発金融機関は、途上国における大規模なNbSプロジェクトのリスクを低減し、民間投資を呼び込むための基金を次々と設立しています。
日本の状況:
国内では、森林管理を対象としたJクレジットが、自然由来クレジットの代表例です。企業の間でも、自社の事業と関連の深い地域の生態系保全に貢献できるクレジットへの関心が高まっています。また、JCM(二国間クレジット制度)の枠組みを通じて、アジア太平洋地域のパートナー国と共に、マングローブ再生(ブルーカーボン)や森林保全(REDD+)といった自然由来のプロジェクトを形成・実施する動きが加速しており、日本の技術と資金が途上国のNbSを支援する重要な手段となっています。
メリットと課題
計り知れないポテンシャルを持つ一方で、その実現には数多くの複雑な課題が伴います。
メリット:
- 高いコスト効率: 多くの場合、技術的な解決策に比べて、より低コストで大規模なCO2の吸収・削減を実現できる。
- 豊富なコベネフィット: 気候変動の緩和・適応、生物多様性保全、貧困削減など、複数の社会課題に同時に貢献できる。
- スケーラビリティ: 地球上の劣化した生態系を回復させるポテンシャルは広大であり、吸収源対策の規模を大きく拡大できる可能性がある。
課題:
- 永続性(Permanence): 森林火災や病害、違法伐採などによって、一度固定した炭素が再放出されてしまうリスクをどう管理するか。
- リーケージ(漏出): ある場所の森林を保護した結果、伐採圧力が隣接する別の森林に移ってしまう現象をどう防ぐか。
- 測定・報告・検証(MRV)の複雑さ: 土壌や海底の炭素量を正確に、低コストで測定し続けることの技術的な難しさ。
- 社会・人権リスク(公正な移行): プロジェクトの実施にあたり、地域住民の土地利用権を侵害したり、クレジットからの収益が一部のエリートに独占されたりするリスク。先住民の権利(FPIC)の保障が絶対条件となる。
まとめと今後の展望
自然由来カーボンクレジットは、単なる排出量の埋め合わせツールではありません。それは、地球の生命維持システムそのものに再投資し、気候と自然と人間のための三重の勝利(Win-Win-Win)を目指す、新しい時代の気候変動ファイナンスです。
要点:
- 自然由来クレジットは、生態系の力を活用して気候変動と生物多様性の危機に同時に対応する金融ツールである。
- 豊富なコベネフィットが最大の特徴であり、途上国における持続可能な開発に貢献する大きなポテンシャルを持つ。
- 成功のためには、永続性や測定の難しさといった技術的課題と、地域コミュニティの権利を守る社会的な課題を乗り越える必要がある。
- 国際的な基準の厳格化と、企業の自然関連情報開示の動きが、質の高いクレジットへの需要を後押ししている。
今後の展望として、気候変動に関する国連枠組条約(UNFCCC)の下での国際的な炭素市場メカニズム(パリ協定第6条)と、生物多様性条約(CBD)の下での資金動員目標が、より一層連携していくことが予想されます。これにより、自然由来クレジットは、気候と生物多様性という二つの国際目標の達成を繋ぐ、重要な架け橋となるでしょう。その価値を正しく評価し、生まれた利益が最も脆弱な人々と生態系へと公正に分配される仕組みを構築できるかどうかに、私たちの未来がかかっているのです。