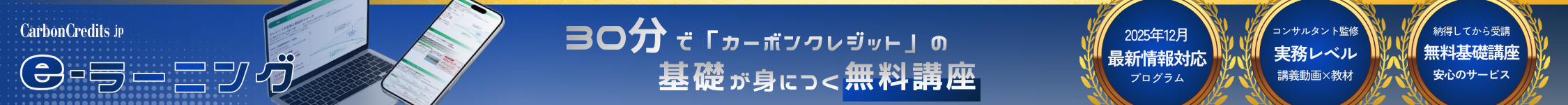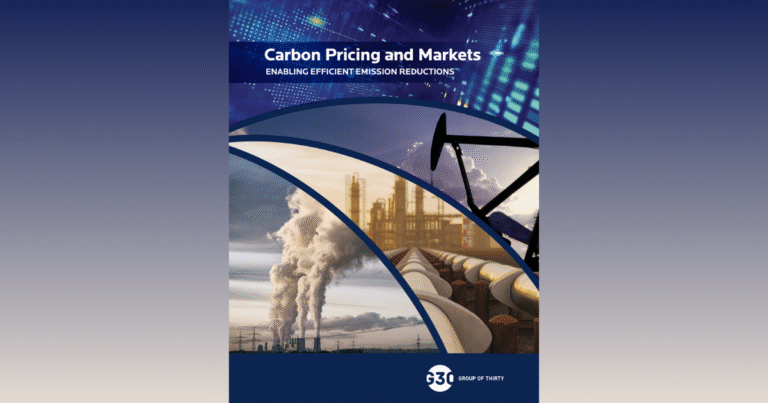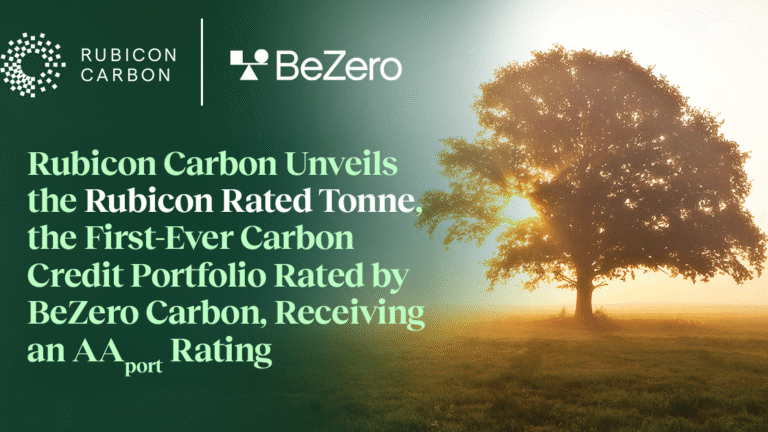米国発のカーボンクレジット・プラットフォームであるパッチ(Patch)、ボストン コンサルティング グループ(BCG)、およびオックスフォード大学ネットゼロ(Oxford Net Zero)は2025年9月、企業がネットゼロ目標と整合した「インターナルカーボンプライシング(ICP, 社内炭素価格)」を設定するための包括的なガイドラインを発表した。
世界でICPを導入する企業が3年間で約9割増と急拡大する中、本指針はICPを単なるリスク管理の指標から、高品質な炭素除去(CDR)クレジットへの資金循環を生み出す「実質的な投資エンジン」へと進化させることを提言している。
ICP導入企業が急増、実効性が課題に
気候変動情報開示を推進する国際NGO、CDPへの報告データによると、2024年時点でICPを利用している企業は世界56カ国で1,753社に達した。これは2021年の927社から89%の増加であり、マイクロソフト(Microsoft)や三菱商事など、世界のトップ500社の約半数が経営戦略に統合している。
しかし、多くの企業においてICPはいまだシャドープライス(投資判断時の仮想的な炭素コスト)にとどまっており、実際の資金移動を伴うリアルプライス(社内炭素課金)として機能していないケースも多い。ガイドラインは、ICPが実際の脱炭素投資や行動変容に結びついていない現状を指摘し、ネットゼロ達成に向けた実効力を高めるための「5つの原則」を提示した。
限界削減費用とCDR投資の「分岐点」
特筆すべきは、原則4「Committed(資金の戦略的投資)」において、ICPによって徴収した社内資金をどのように配分すべきかという具体的なフレームワークが示された点だ6。
ガイドラインでは、自社内での排出削減にかかる限界削減費用(MAC)と設定したICPを比較し、投資先を決定する手法を推奨している。
- MAC < ICPの場合
社内での削減対策(省エネ設備導入など)の方が安価であるため、内部削減に投資する。 - MAC > ICPの場合
社内での削減コストが炭素価格を上回るため、その資金を用いて高品質な外部炭素ソリューション(カーボンクレジット購入など)に投資する。
これは、削減困難な残留排出に対して、企業がどのタイミングでカーボンクレジットやCDRの購入に踏み切るべきかという経済合理的な基準を提供するものである。
特に、オックスフォード・ネットゼロ原則に基づき、従来型の回避系クレジットから、大気中のCO2を直接回収・貯留する「永続的な炭素除去(Durable CDR)」へのポートフォリオ移行を促している点が重要だ。
マイクロソフトとBCGの先行事例
本ガイドラインでは、ICPをCDR購入の原資として活用する先進企業の事例が紹介されている。
マイクロソフトは、全部門に対して炭素排出量に応じた社内炭素手数料(Internal Carbon Fee)を課金し、その収益を再エネ調達や炭素除去プロジェクトへの投資に充てている。同社は2024年だけで510万トン(5.1Mt)のCDRクレジットを確保しており、ボランタリーカーボンクレジット市場における最大のCDR購入企業となっている。ICPによる社内課金が、巨大なCDR需要を支える財布の役割を果たしている好例だ。
また、BCG自身の事例では、2030年に向けて100%高品質なCDRクレジットへ移行することを見据え、その将来コスト(推定80ドル/トン、約12,000円)や、持続可能な航空燃料(SAF)のコスト(300ドル/トン超、約45,000円)をベンチマークとして、社内炭素価格を階層的に設定している。これにより、将来のCDR価格上昇リスクを現在の経営判断に織り込むことが可能となる。
科学的根拠と価格の引き上げ
ガイドラインは、ICPの価格設定にあたり、以下の3つのアプローチを推奨している。
- 限界削減費用(MACC)
自社の削減対策コストに基づく。 - 政策主導型(ETS)
EU排出量取引制度(EU ETS)などの市場価格を参照する(2025年時点で約75ドル/トン、約11,250円)。 - 社会的費用(SCC)
炭素の社会的損害コストに基づく(185ドル/トン、約27,750円などの推計あり)。
さらに原則5「Catalytic(触媒機能)」では、時間の経過とともに価格を引き上げる「ラチェットアップ(野心の切り上げ)」の必要性を強調している。これは、枯渇性資源の価格が時間とともに上昇するというホテリングの法則(Hotelling’s rule)とも整合する考え方であり、企業は将来的な規制強化やCDR需給の逼迫を見越して、早期に高い炭素価格を社内導入すべきだとしている。
本ガイドラインが示唆するのは、ICPがもはや「形式的な環境対応」ではなく、「財務戦略」そのものになったという事実だ。特にCDR市場の観点からは、ICPが「企業の内部資金を炭素除去プロジェクトへと還流させるパイプライン」として機能し始めた点に注目すべきだろう。
日本企業においても、GXリーグでの排出量取引が試行されているが、多くの企業でICPはまだ投資判断の参考値にとどまっている。本レポートが示すように、社内課金(リアルプライス)としてプールした資金を、高コストなCDRやSAFの購入原資に充てる仕組みを構築できれば、日本市場におけるCDR需要も劇的に喚起される可能性がある。脱炭素予算をコストではなく「未来への投資」と定義し直せるかが、経営層の手腕問われる局面にある。