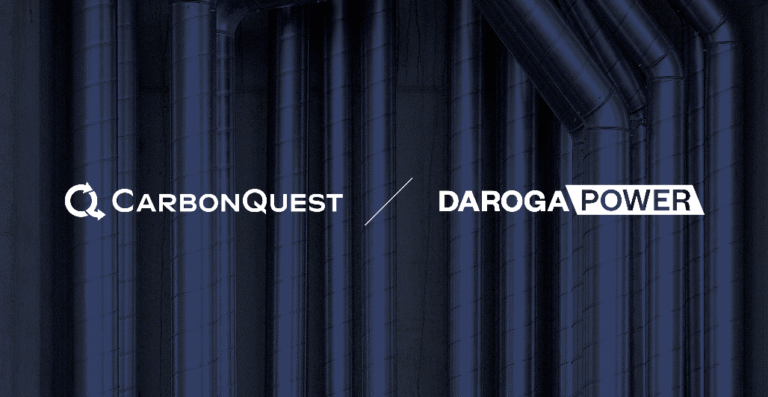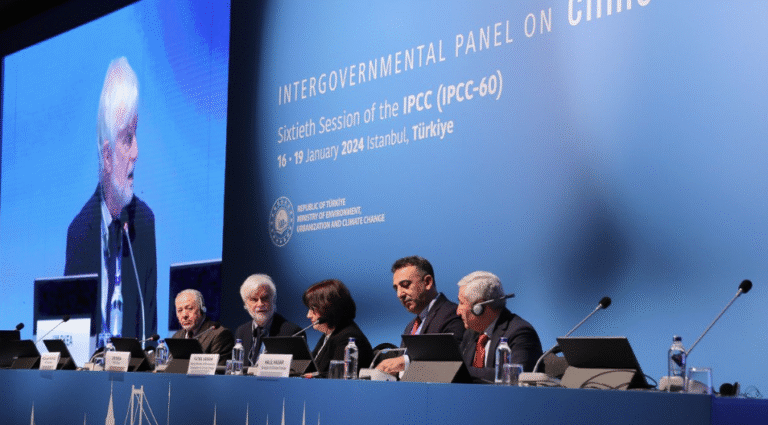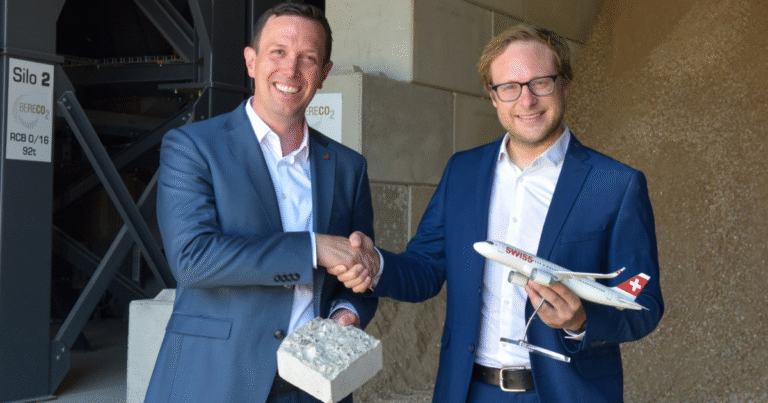CDR(炭素除去)に関わるステークホルダーや市民団体、学識者らが、エネルギー・気候変動分野の非営利シンクタンクであるRMIの主導でSBTi(科学的根拠に基づく目標イニシアチブ)の「企業向けネットゼロ規格 v2」草案に対する共同声明を6月3日に発表した。
SBTiは2025年3月にCDR導入方針を含む草案を公表し、意見募集を実施していた。
SBTiの草案では、企業が残余排出を埋め合わせるためにCDRを活用する3つの選択肢が提示された。これを受け、RMIらはCDR導入の原則や条件に関する6つの要点を共同声明としてまとめた。
第一に、CDRの導入目標は累積量ではなく年ごとの増加を基本とし、市場への明確な需要シグナルを送るべきとした。
次に、2030年以降、ネットゼロ目標を掲げる企業には中間CDR目標の設定を求め、早期にCDR導入を始めた企業にはその努力を認識すべきとした。
また、CDRの耐久性は排出されたCO2の大気中での影響と「同等(like-for-like)」である必要があり、ネットゼロ達成の10年前からの段階的導入を提案した。
CDRの質に関しては、独立した第三者による検証を義務付けるとともに、「追加性」「純負性」「逆方向のトレーサビリティ」「データの透明性」「持続可能性や環境・公平性の基準」への適合が求められるとした。
さらに、Scope3の航空排出(カテゴリ6に相当)に対しても中間CDR目標の設定を義務化すべきであり、Scope3への自主的な取り組みを行う企業を評価するべきだと述べた。
最後に、新興CDR技術の調達や投資を「バリューチェーン外の削減(Beyond Value Chain Mitigation)」として認め、イノベーションを後押しすべきとの提言も含まれている。
本声明には、政策立案、技術開発、民間セクターの各方面から広く賛同が寄せられており、今後のSBTiの最終版策定に向けた議論に大きな影響を与える可能性がある。