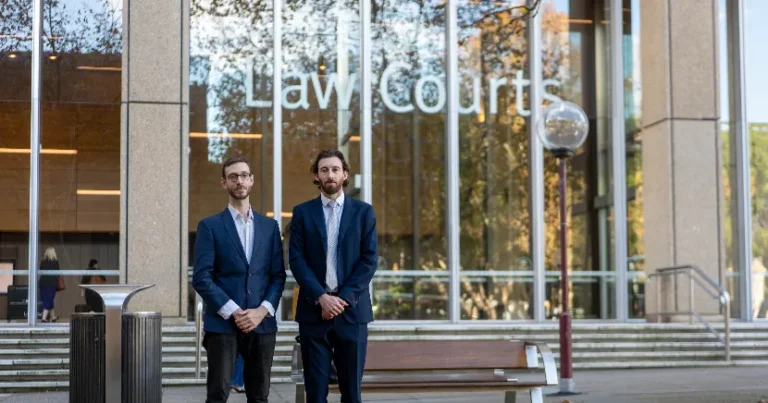ブラジルで開催中の第30回気候変動枠組条約締約国会議(COP30)にて、オーストラリアのクリーンテック企業MCiカーボン(MCi Carbon)が、炭素除去(CDR)技術の商業化に向けた重要な節目を発表した。
同社の実証プラント「マートル(Myrtle)」がニューカッスルで稼働を開始し、産業試験を行う準備が整った。この技術は、回収したCO2と産業副産物の鉱物残渣を反応させ、永続的に炭素を固定した(Carbon Embodied)建材として販売可能にするもので、従来のカーボンオフセットや地中貯留に依存しない「プロダクト・ファースト」モデルを通じて、セメントなど排出量の多い「削減困難なセクター(Hard-to-Abate Sectors)」の脱炭素化に、「永続性のあるCDR」という新たな道筋を提供する。
同社の実証稼働は、三菱UBCセメントなど日本企業との協業を背景に進められており、セクター全体の排出量削減を加速させることが期待される。
日本企業との連携で商業化を加速
MCi Carbonの共同創業者兼最高執行責任者(COO)のソフィア・ハンブリン・ワン(Sophia Hamblin Wang)氏は、COP30のオーストラリア・パビリオンで、マートル・プラントで製造されたコンクリートサンプルの実物を持参し、ブラジルと日本の顧客との間で実施された試用結果を紹介した。
同社は今年2月、日本の大手セメントメーカーである三菱UBCセメント(MUCC)から500万ドル(約7億7千万円)の出資を受け、提携を強化した経緯がある。三菱UBCセメントはこの投資に加え、伊藤忠商事との間で、MCiカーボンの鉱物炭酸化技術を日本市場で展開するための三者間覚書(MoU)を締結。この動きは、日本のセメント産業におけるCO2排出削減と、低炭素材料の開発を加速させる狙いがある。
CO2を素材に変える技術とCDRへの貢献
マートル・プラントは、鉱物炭酸化技術を用いて、年間約2,500トンのCO2を約10,000トンの建材へと変換する能力を持つ。これは、CO2をアルカリ性の材料(鉄鋼スラグや超苦鉄質岩など)と反応させて安定した炭酸塩を生成し、CO2を永続的に建設資材に封じ込める技術である。
セメント・コンクリート産業は世界の温室効果ガス排出量の約7〜8%を占めており、その排出量の削減は国際的な喫緊の課題だ。MCiカーボンの技術は、CO2を排出物としてではなく、付加価値のある製品へと転換させることで、将来的に販売可能な耐久性のあるカーボンクレジットの創出に貢献すると同社は述べている。同社は既に技術成熟度レベル7(TRL7)を達成したと表明しており、マートルを通じてパートナー企業にモデリングだけではない実世界のフィールドデータを提供し、排出量削減プロジェクトの融資可能性(Bankability)を高めることを目指す。
この技術の進展は、「バイ・クリーン」政策やインフラ脱炭素化の義務化が進む中で、低含有炭素(Low-embodied Carbon)建材に対する需要の高まりに応えるものだ。MCiカーボンは、この技術が産業排出物管理のあり方を根本的に変え、廃棄物としての処理ではなく、CO2を価値ある材料に変えるシフトを促す可能性があると強調している。
参考:https://www.linkedin.com/posts/activity-7394448626716073984-8lDm