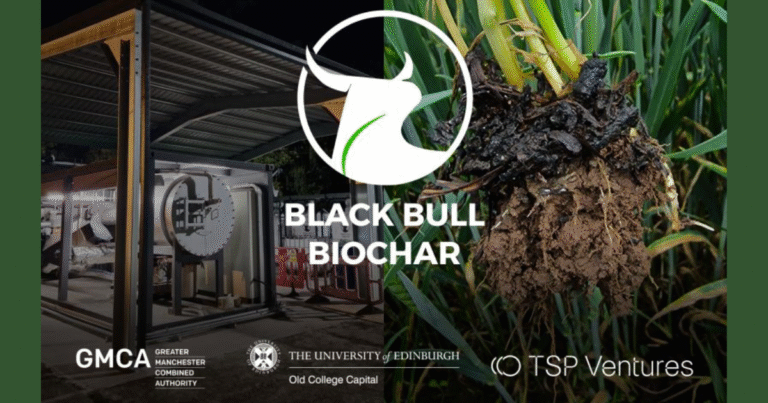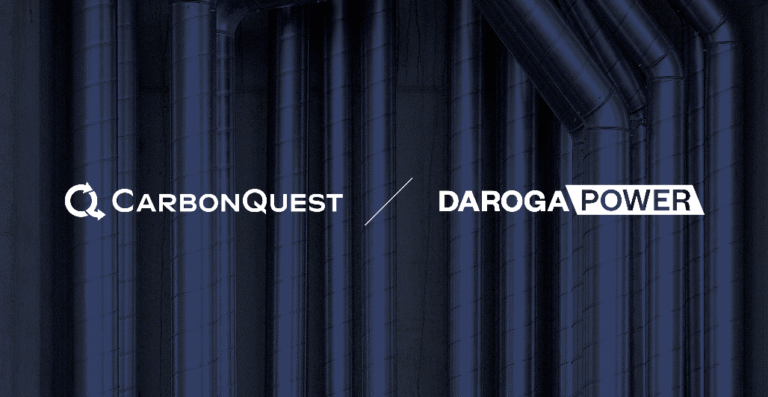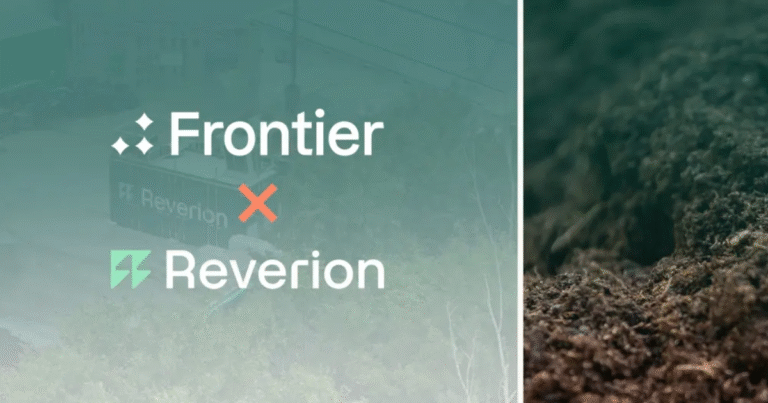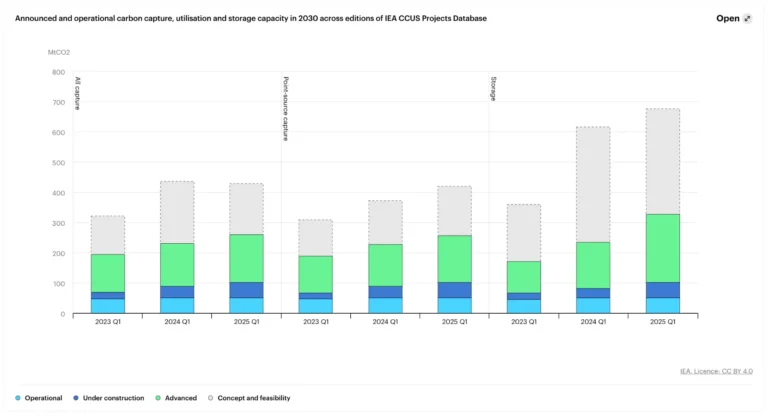本コラムでは、海洋からの直接的な二酸化炭素除去(Direct Ocean Capture and Storage:DOCS)の実用化を進めるIsometric社が、新たに公表したプロトコル案の内容とその意義について整理します。
DOCSとは、海洋を活用した炭素除去技術の仕組み
Isometric社が提案する「Direct Ocean Capture and Storage(DOCS)」とは、海水中に溶け込んだ二酸化炭素を回収し、耐久的に貯留する新しい炭素除去(Carbon Dioxide Removal:CDR)の手法です 。
このプロセスでは、電気的または化学的処理により海水からCO2を分離し、除去後の海水は再び海へ戻されます。このとき海水は再び大気中からCO2を吸収し、自然の炭素循環を促進する効果が期待されています。
プロトコルの特徴、科学的厳密さと実用性の両立
今回のプロトコル案は、DOCSによって実際にどれだけの炭素が除去されたかを精緻に測定するためのガイドラインであり、次の三つの観点において大きな意義を持ちます。
科学的根拠に基づく算定手法の提示
Isometricは、大気と海の間のCO2の動きを評価するために「Air-Sea Carbon Dioxide Uptake Module」というモデリング手法を導入しました。これにより、プロジェクトによるCO2吸収の効果が定量化されます 。
長期貯留の要件明示
除去された炭素のうち、評価対象となるのは大気から海へ再吸収されたCO2であり、その貯留は1,000年以上の耐久性が求められます。加えて、海水から除去された炭素についても、地質貯留などで同等の耐久性が確保されなければ、除去実績としては認められません 。
環境・社会的影響への配慮
プロトコルでは、事前の影響評価やモニタリング、地域住民との協議も義務付けられており、海洋生態系への影響や社会的受容性にも配慮されています 。
今後の展望、透明性と協働による制度設計
このプロトコル案は、Captura、CarbonBlue、SeaO2など、既にDOCS技術を開発・展開している企業の協力を得て作成されました。既にCaptura社は、商業的なカーボンクレジット販売にも成功しており、同技術への関心は急速に高まりつつあります 。
プロトコル案は2025年6月27日までパブリックコメントを受け付けており、今後の修正や改善を経て、実際のプロジェクト認証の基準となる見込みです。
海洋を活用した炭素除去は、気候変動対策の新たな選択肢として注目されており、今後の社会的受容性や制度設計の進展が期待されます。
参考:https://registry.isometric.com/protocol/direct-ocean-capture-storage/1.0/ctn_1JW977VXT1S0B2BR#calibration-and-validation