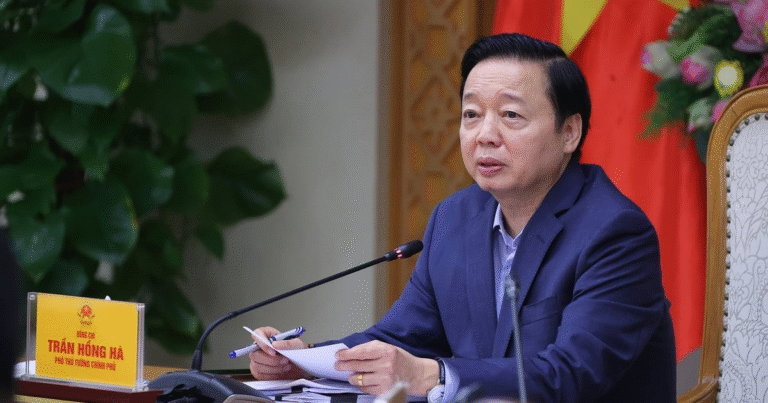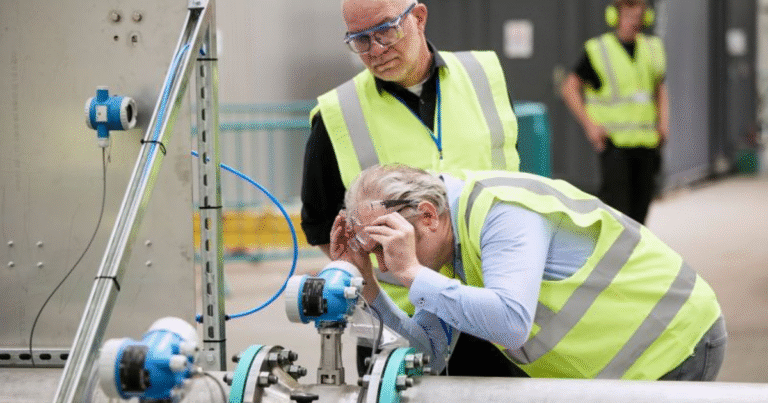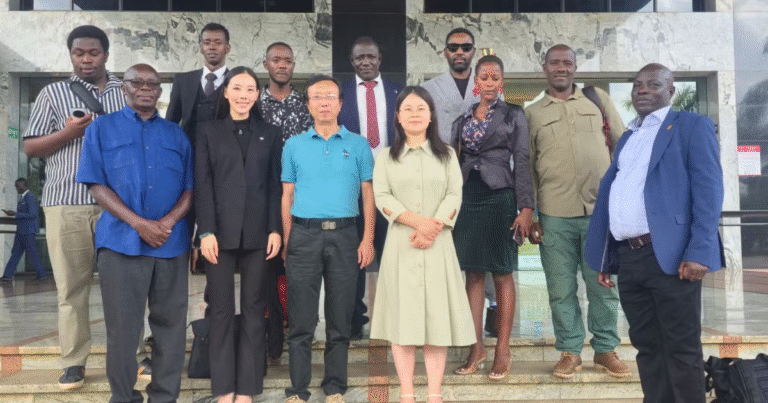インドネシア政府は、2030年までに最大134億トンの二酸化炭素換算(CO2e)カーボンクレジットを海外市場に販売する計画を正式に発表した。国際取引の再開を定めた大統領令を背景に、同国は11月8日、ブラジル・サンパウロで開催される国際排出権取引協会(IETA)のビジネス会合で主要買い手との協議に臨む。森林保全や再生可能エネルギー開発を通じ、外資誘致と温室効果ガス削減を両立させる狙いだ。
世界市場での「脱炭素資源」化 森林・再エネ・炭素除去を柱に
今回の計画では、134億トン分のクレジットが、森林保護、泥炭地再生、再生可能エネルギー、炭素回収・貯留(CCS)などのプロジェクトから生まれる。
インドネシアは約1億2,500万ヘクタールの熱帯林を保有し、年間約250億トンのCO2eを吸収している。同国は森林を「経済資産」として活用しつつ、保全資金を確保する新たな仕組みとしてカーボン取引を位置づける。
ラジャ・ジュリ・アントニ森林相は「投資家との信頼構築が最優先だ。国際的な認証機関との連携で市場の透明性を高める」と述べ、国際ボランタリーカーボン市場の監督組織であるインテグリティ評議会(ICVCM)と覚書を締結する方針を示した。
新制度の柱 国内市場の再活性化と国際取引の整合性
2023年に設立されたインドネシア証券取引所の炭素市場「IDXカーボン」は、開設初年度に約50万トン(約7億円)の取引を記録したが、2025年には取引額が10億ルピア(約1,000万円)台まで低下。政府はこの停滞を打破するため、10月10日に大統領令を発令し、国際取引を再開した。
新ルールでは、国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)または国際認証機関の基準に適合するクレジットの輸出を認める。また、「対応調整(corresponding adjustment)」を義務づけ、輸出分の排出削減量を国内インベントリから差し引くことで、二重計上を防ぐ仕組みを導入する。
経済効果は最大100兆円規模 地域還元も義務化
政府試算によると、1トンあたり平均15ドル(約2,250円)で取引された場合、年間収益は約127兆9,800億ルピア(約7.7億ドル=約1,150億円)に達する可能性がある。市場価格が上昇すれば、総額は最大67兆ドル(約10兆円)規模に膨らむ計算だ。
法令上、クレジット販売収入の少なくとも30%は地域政府と地元コミュニティに分配される。これにより、森林保護、持続可能な農業、エコツーリズムなどの事業が拡大し、数万人規模の「グリーン雇用」創出が見込まれている。
世界市場との価格差と信頼性課題 「実質的削減」をどう証明するか
インドネシア産クレジットの価格は、1トンあたり20ドル未満にとどまり、欧米市場での高品質クレジット(40〜80ドル)との格差が課題となっている。政府は国際需要を呼び込み、価格水準を引き上げる方針だ。
一方で、森林火災や違法伐採による「リバーサルリスク(吸収量の消失)」を懸念する声もある。このため、政府は予備クレジットを確保する「バッファ制度」を導入し、損失リスクに備える。また、ベラ(Verra)やゴールド・スタンダード(Gold Standard)といった国際認証機関との連携を強化し、透明性と信頼性の確保を図る。
地域競争の中で存在感拡大へ 「アジアの炭素ハブ」目指す
国際エネルギー機関(IEA)によると、世界が2050年までにカーボンニュートラルを達成するには、年間50〜100億トンのCO2除去が必要とされるが、現在の市場規模はその1%未満にとどまる。
このなかで、東南アジアの熱帯林を活かしたカーボン取引は「供給の新潮流」として注目されている。
ベトナムやマレーシアも独自のカーボンレジストリを整備中であり、今後、外国投資家に市場を開放する見通しだ。世界銀行は、透明性が確保されれば東南アジア地域全体で年間100億ドル(約1.5兆円)の収益が見込めると試算している。
展望 「信頼される炭素資産」への転換が鍵
インドネシアが提示した134億トンのクレジット販売構想は、気候政策と経済成長の融合を象徴する試みである。成功の鍵は、実質的削減の検証、価格の公正性、取引の透明化にある。
計画が着実に進めば、インドネシアは世界有数のカーボンクレジット輸出国となり、同時に森林保全と再エネ拡大の資金源を確保できる可能性が高い。
国際社会の信頼を獲得し、「排出削減の証拠があるクレジット」を継続的に供給できるかが、今後の焦点となる。