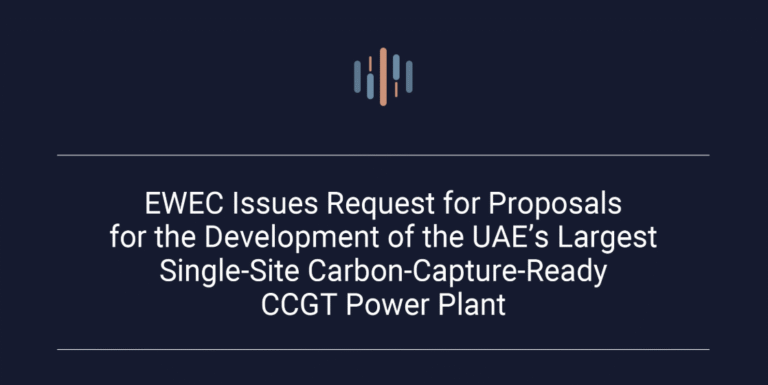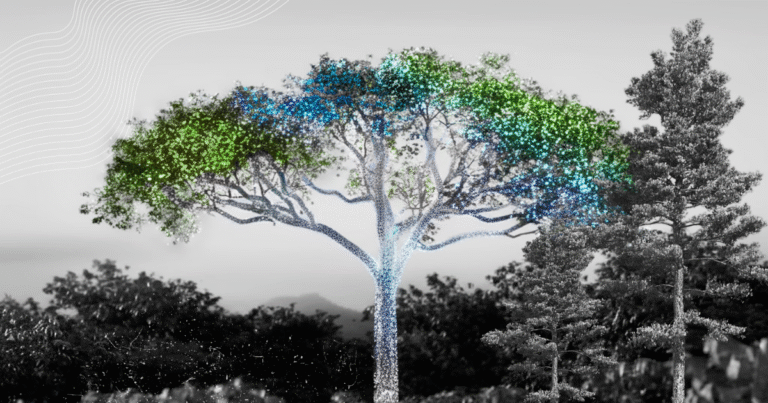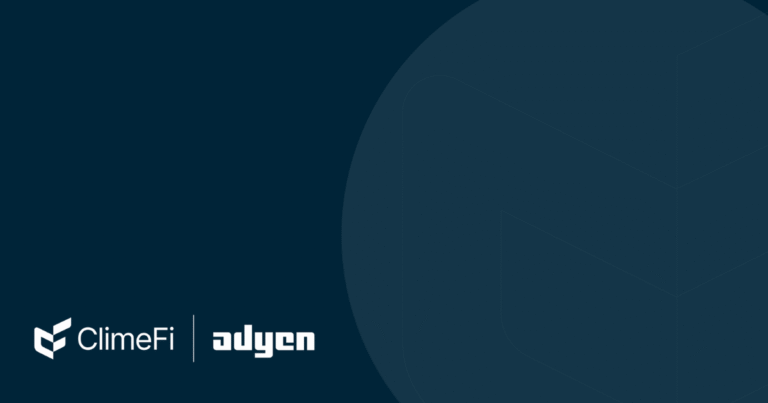ブラジル・ベレンで開催されていたCOP30は24日、温室効果ガス(GHG)排出削減量の国際取引を定める「パリ協定第6条」の運用ルールに関する最終文書を採択し、閉幕した。京都議定書時代の「クリーン開発メカニズム(CDM)」を2026年までに廃止することも決定され、国際炭素市場は新たなフェーズへ移行する。化石燃料の段階的廃止に関する政治的合意が見送られる一方で、炭素除去(CDR)分野では初の専用パビリオン設置や標準契約書「OSCAR」の発表など、民間主導の実装に向けた動きが加速した。
第6条の完全運用と京都メカニズムの幕引き
今次会合の最大の成果の一つは、長年の懸案であったパリ協定第6条(市場メカニズム)の技術的細則が決着したことだ。これにより、国家間でのクレジット取引(6.2条)および国連管理下の新メカニズム(6.4条)の本格稼働に向けた制度的枠組みが整った。
特筆すべきは、京都議定書に基づくCDMの扱いである。各国は2026年までにCDMを完全に「引退(retire)」させることで合意した。これにより、旧制度下のクレジットが抱えていた品質への懸念を払拭し、より厳格な基準に基づくパリ協定体制への一本化が図られる。
ただし、炭素除去の永続性や、一度貯留した炭素が大気中に放出された場合の「リバーサル(逆転)」に関する詳細なルール作りについては、一部の議論が先送りされた。
CDRの産業化、専用パビリオンと標準契約書「OSCAR」
COP30は、炭素除去(CDR)が「概念」から「産業」へと転換する分水嶺となった。会場内のブルーゾーンには、国連気候会議史上初となるCDR専用スペース「CDR30パビリオン」が開設された。ネガティブ・エミッション・プラットフォームが主催し、90以上の組織が参画したこの拠点は、パリ協定の目標達成にCDRが不可欠であることを外交的に位置づける役割を果たした。
実務面での大きな進展として、CDR取引の標準法的テンプレート「OSCAR(Open Standard Carbon Removal Purchase Agreement)」が発表された。 CDR市場のデータ分析を行うCDR.fyiなどの支援を受けて開発されたこのテンプレートは、価格設定、リスク配分、モニタリング、デリバリー条件などの契約条項を標準化するものである。これまで個別の交渉に費やされていた時間とコストを大幅に削減し、買い手とサプライヤー双方の参入障壁を下げることで、流動性の低いCDR市場の拡大を後押しすると期待される。
科学的根拠と「100億トン」の重み
ポツダム気候影響研究所のヨハン・ロックストローム所長(COP30科学アドバイザー)は会期中、産業界に対し次のように警告した。
「温暖化を1.7度以内に抑えるためには、年間100億トンのCO2を大気から除去することが極めて重要である。それなしでは、海洋循環の崩壊やアマゾンの熱帯雨林の消失といった危険な『ティッピング・ポイント』を招くリスクがある」
この発言は、削減努力だけでは不十分であり、ギガトン級の炭素除去能力の構築が急務であることを改めて市場に突きつけた。
森林保全と適応資金の動向
開催国ブラジルが主導し、熱帯林保全のための新たな資金メカニズム「トロピカル・フォレスト・フォーエバー・ファシリティ(TFFF)」が立ち上げられた。初期段階で67億ドル(約1兆円)以上を動員し、成果ベースの支払いを恒久化することを目指す。これは、森林由来のクレジットや自然由来ソリューション(NbS)への資金流入を安定化させる重要なインフラとなる。
一方、全体合意としては、気候変動への「適応」資金を2035年までに現在の3倍以上に増額することが盛り込まれた。しかし、COP29で設定された年間3,000億ドル(約45兆円)という目標額の再確認にとどまり、脆弱な国々が求めていた即効性のある資金提供とは乖離が残る結果となった。
政治的停滞と今後の展望
化石燃料の「段階的廃止」については、82カ国が支持したものの、産油国を中心とする反対により合意文書への明記は見送られた。 次の焦点は、トルコがホストしオーストラリアが議長を務めるCOP31に向けた政治的リーダーシップに移る。ブラジル政府は、エネルギー移行と森林破壊に関する2つのロードマップを発表したが、これらは法的拘束力を持たない。
市場関係者にとっては、第6条のルール確定とOSCARのような取引インフラの整備により、ボランタリーおよびコンプライアンス市場の双方で、高品質なクレジットへの需要と供給の構造がどう変化するかが、2026年に向けた最大の監視ポイントとなる。
参考:https://cop30.br/en/news-about-cop30/cop30-approves-belem-package1