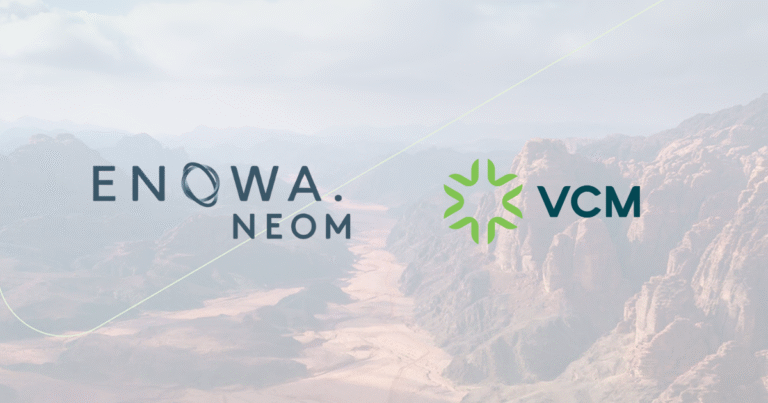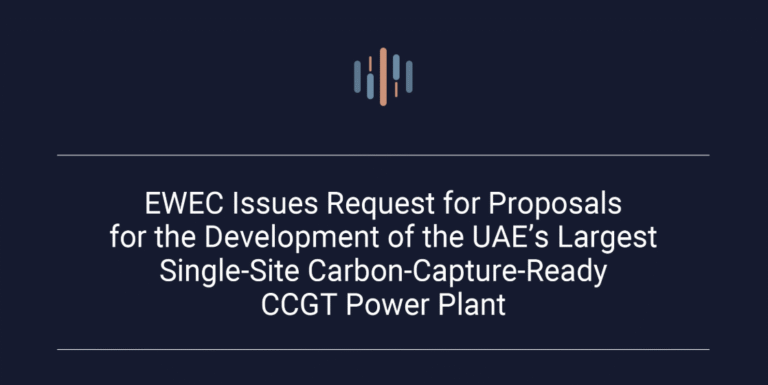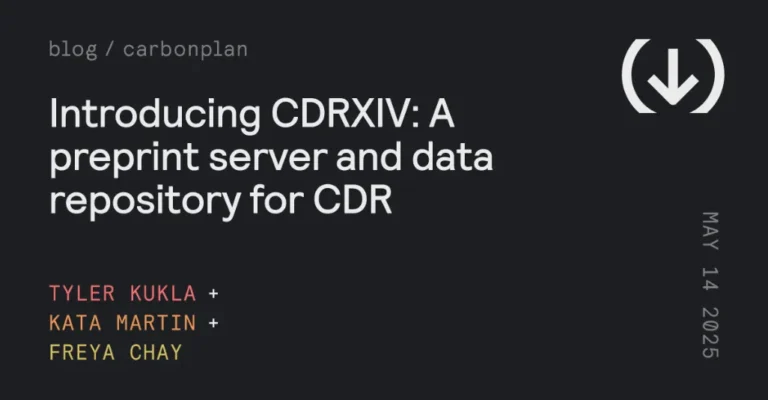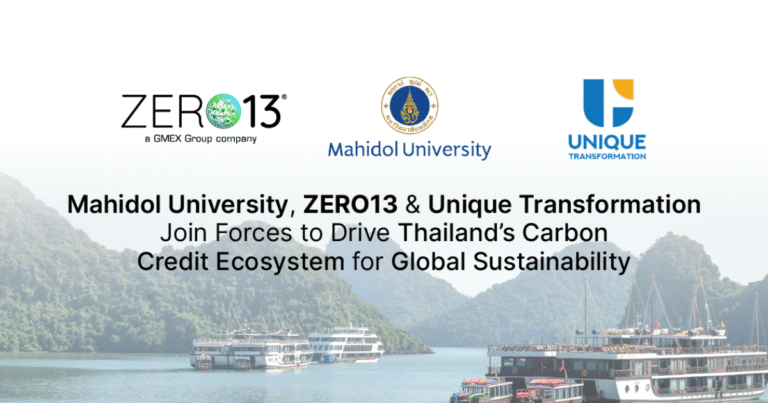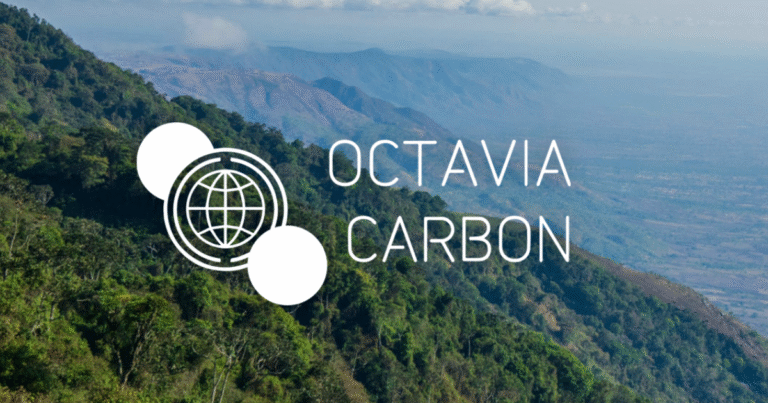米国の非営利団体シュミット・サイエンシズ(Schmidt Sciences)は9月25日、地球規模の炭素循環の不確実性を減らす研究拠点「バーチャル・インスティテュート・フォー・ザ・カーボン・サイクル(VICC)」の初回助成先を発表した。国際的な大学研究者による4チームに対し、今後5年間で最大4,500万ドル(約70億円)を拠出する。
このうちコロンビア大学と米海洋大気庁(NOAA)の研究者が共同主導する「COCO2(Constraining Ocean Carbon with Optimized Observing)」は、南大洋に自律型無人船(USV)を投入し、海洋の炭素吸収量を高精度に観測する計画である。現在、世界の海洋のうち炭素データが収集されるのはわずか約2%にとどまっており、シミュレーションと機械学習を組み合わせた観測設計により、海洋の炭素循環の定量化を進める。
コロンビア大学ラモント・ドハティ地球観測所のガレン・マッキンリー教授は「海は産業革命以降に排出された人為起源CO2の3分の1以上を吸収してきた。毎年、人類排出の約25%を取り込み、その規模は全世界のエンジニアードCDRプロジェクトの100万倍に達する」と指摘した。教授はさらに「海は大気中のCO2上昇を抑制し、気候変動を緩和する巨大な規制サービスを提供している」と強調した。
今回の助成対象には、中央アフリカ熱帯林の炭素フラックス解明、先進的な土地利用モデル、冬季の南大洋ロボット観測、永久凍土融解の影響評価なども含まれる。これらのデータは炭素会計の精緻化や自然災害リスク評価、エネルギー転換戦略に直結する。
VICCは2024年に研究提案を公募し、170件超の応募から25件を精査、最終的に4件を採択した。今後は湿地の排出や土壌炭素フラックス、新規観測技術なども対象とする新たな公募を2026年に予定している。
参考:https://fas.columbia.edu/news/columbia-will-co-lead-major-project-study-global-carbon-cycle