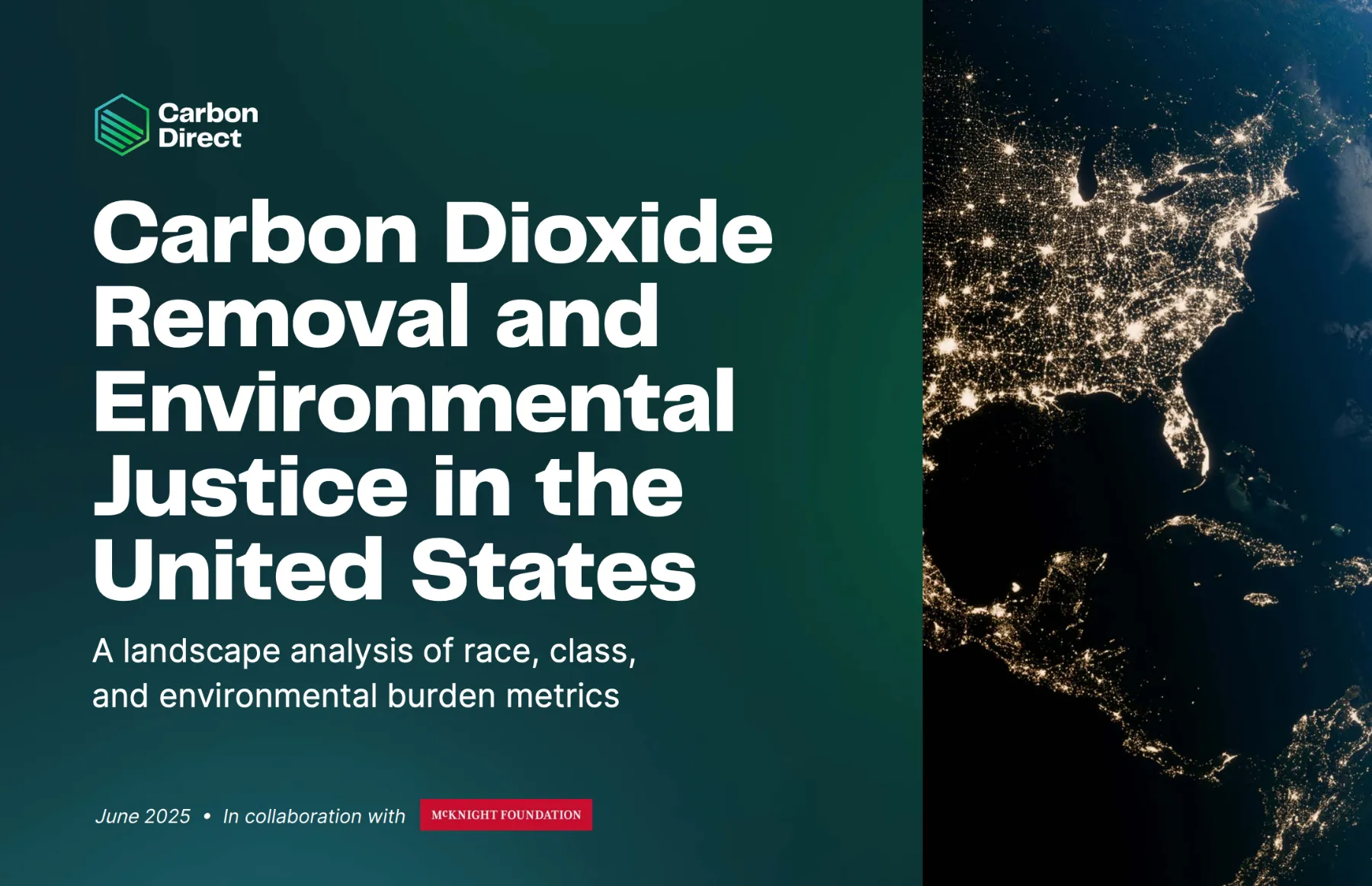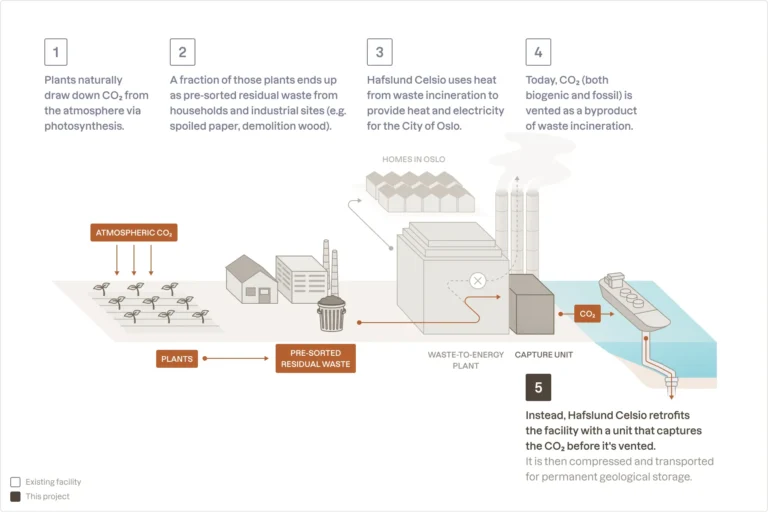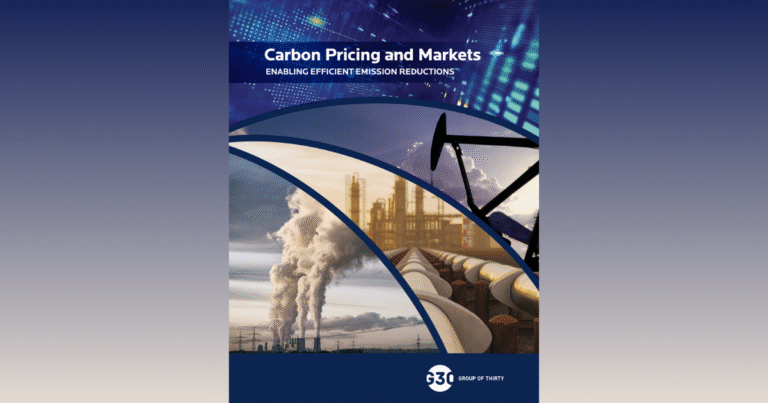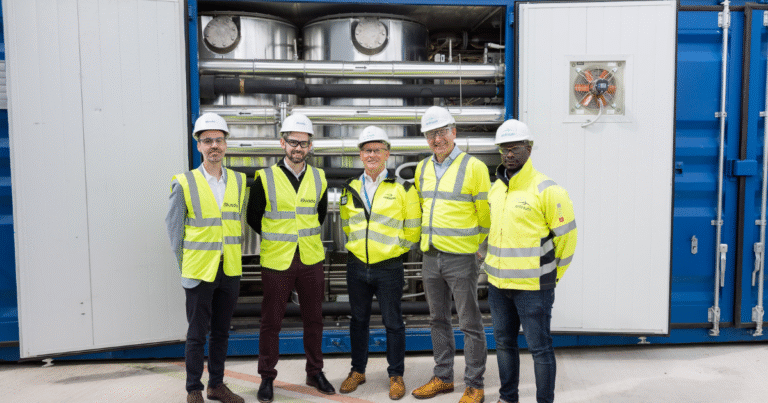カーボンダイレクト(Carbon Direct)は6月25日、マックナイト財団と共同で、アメリカ国内の炭素除去(CDR)プロジェクトが環境的に不平等な地域に偏っていないかを調査した初の包括的レポートを発表した。342件のプロジェクトを分析した結果、低所得層や有色人種が多く住む地域(いわゆるフロントライン・コミュニティ)への集中傾向は確認されなかった。
CDRは、大気中のCO2を回収・貯留することで気候変動対策を支える重要な手段である。だがそのプロジェクトが、社会的に脆弱な地域に集中していないかを問う声もあった。
今回の報告書『Carbon Dioxide Removal and Environmental Justice in the United States』は、CDRと環境正義(Environmental Justice)の関係に初めてデータで切り込んだものだ。分析対象となったのは、アメリカ国内でボランタリーカーボンクレジット市場(VCM)に登録された342件のCDRプロジェクトである。
プロジェクトの所在地情報と、米国環境保護庁(EPA)の「EJScreen」データを照合した結果、次のことがわかった。
第一に、CDRプロジェクトが低所得層や有色人種の多い地域に偏って立地しているという明確な傾向は見られなかった。これは、有害廃棄物処理施設など過去のインフラとは対照的な結果である。
一方で、自然系、ハイブリッド型、技術系(DAC等)を含む一部のプロジェクトでは、飲料水汚染や大気汚染のリスクが高い地域の近隣に立地しているケースも存在した。とくに先住民地域や都市部近郊などでは、環境負荷の高い条件が重なっていた。
カーボンダイレクトは、「CDR業界はまだ黎明期にあり、今後の制度設計次第で公平な成長を目指せる」と指摘する。そして、将来の立地や地域との関係づくりにあたっては、「その土地ごとの事情に応じた対話と利益共有が不可欠」と強調している。
さらに、現在のアメリカでは連邦政府によるCDR関連支援の先行きが不透明になっている。報告書は、フィランソロピーや民間投資家が積極的に支援することで、持続可能で公平なCDR事業の拡大を後押しできると提言している。
このレポートは、CDRプロジェクトの地域的な公平性を確保するための「出発点」として、政策立案や投資判断、地域住民との関係構築において今後の基準となることが期待される。