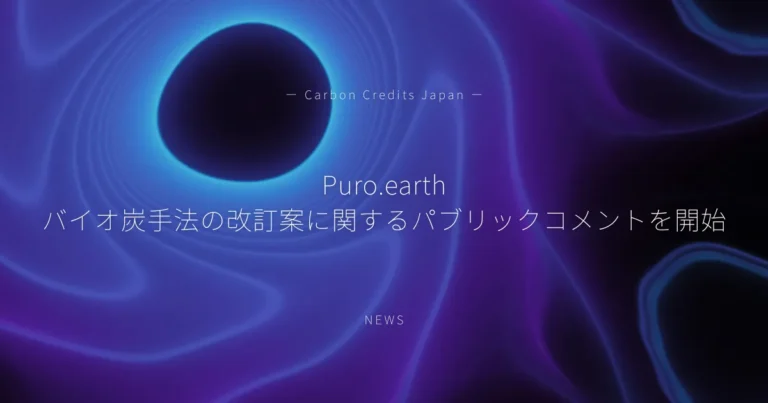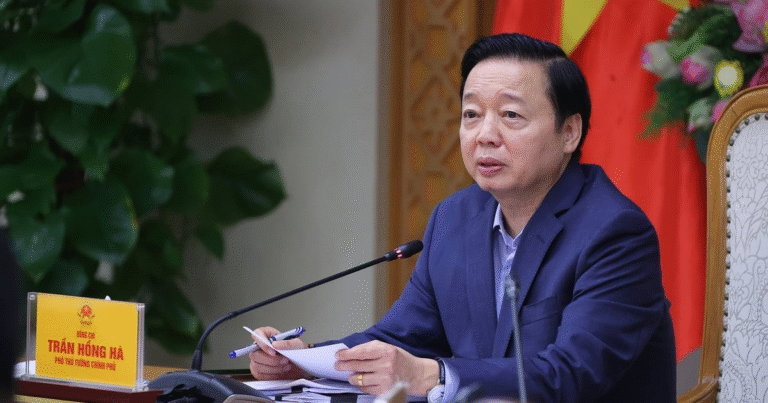米ミシガン大学とミネソタ大学の研究チームは10月20日、米国の都市における食肉消費が引き起こす温室効果ガス(GHG)排出量を初めて都市別に定量化した研究成果を、英科学誌『ネイチャー・クライメートチェンジ(Nature Climate Change)』に発表した。分析によれば、米国全体で年間約1,100万トンの食肉(牛肉・鶏肉・豚肉)が消費されており、これに伴う排出量は約3億2,900万トンのCO2に相当する。これは米国内の化石燃料燃焼(約3億3,400万トン)に匹敵し、英国(約3億500万トン)やイタリア(約3億1,300万トン)の年間排出量を上回る規模である。
研究チームは「Food System Supply-Chain Sustainability(FoodS3)」プラットフォームを活用し、全米3,531都市における牛肉・鶏肉・豚肉の消費と、それを支える農村部の生産・加工・飼料供給までを高解像度で結び付けた。これにより、各都市のカーボンフーフプリント(CFP)を可視化した。
主執筆者であるミシガン大学環境持続性学部のベンジャミン・ゴールドスタイン助教は「食肉消費の排出構造は地域によって大きく異なり、一律の排出係数では把握できない」と指摘する。たとえばロサンゼルス市は、10郡の処理施設から牛肉を調達しているが、その背後には469郡で育成された家畜と、828郡で栽培された飼料作物が関係しているという。
研究チームは、食肉消費由来の排出量を最大51%削減できる可能性があると推計した。具体的な方策として、食品廃棄の削減、牛肉から鶏肉や豚肉へのシフト、牧草地への樹木導入など自然ベースの吸収策の導入などを挙げる。
ゴールドスタイン助教は「都市の脱炭素政策はこれまで建築や交通に偏重してきた。だが、食料供給網の影響を可視化することで、都市と農村の炭素連鎖を結び直す新たな道が開ける」と述べた。
共同研究者でミネソタ大学のライリー・ペルトン研究員も「同じ量の肉を食べても、どこで生産されたかによって炭素負荷は大きく異なる。都市と産地の間で協働し、資金的インセンティブを設ける仕組みが必要だ」と強調した。
今回の研究は、都市別に食肉サプライチェーンを特定できる点で画期的だ。これにより、将来的には特定都市が排出削減努力や農村支援を行い、その成果をカーボンクレジット化する仕組みの基盤にもなり得る。都市の食生活起源の排出を定量化し、地域連携で削減するという発想は、炭素除去(CDR)やネイチャーポジティブ投資の新潮流とも合致する。
共著者であるミネソタ大学のジェニファー・シュミット主任研究員は「これは都市と農村の新しい対話の始まりだ。環境と経済の両立を目指すために、食を介した連携が鍵になる」と語った。
この研究成果は、米国内外の都市がCDR戦略やScope3排出の算定を拡張するうえで、重要なデータベースとなることが期待される。