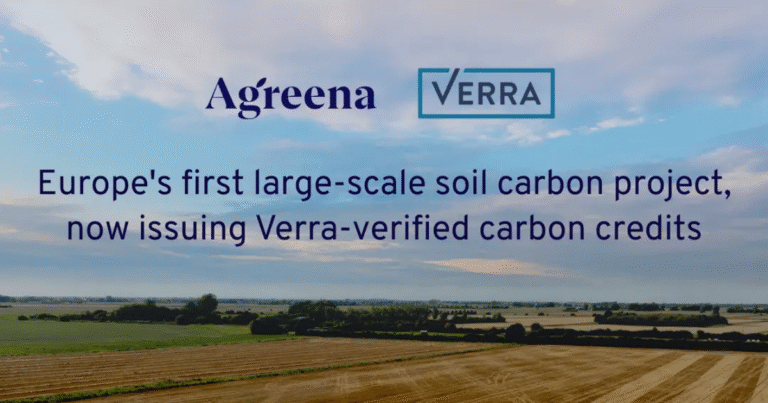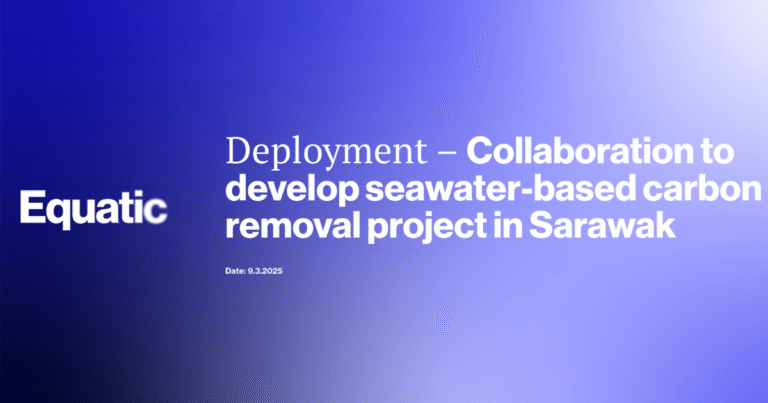オーストラリアの世界最大の鉱山会社、BHPが中心となり、アジアの製鉄大手やエネルギー企業、商社が協力して、二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)拠点をつくるための調査を始めた。調査はカナダのエンジニアリング会社、ハッチ(Hatch)が進行役を務め、2026年末までに具体的な戦略をまとめる。
参加するのは、アルセロール・ミッタル日本製鉄インド(AM/NS India)、JSWスチール、現代製鉄、シェブロン、三井物産など。特に削減が難しい製鉄などの産業を対象に、複数地域でCO2をまとめて回収し、パイプラインや船で北豪州やアジアの貯留地に運ぶ案を検討する。各社は最低1つの拠点づくりに関わり、コストや工程表、商業化の仕組みを作成する。
調査では技術だけでなく、国境をまたぐCO2輸送や貯留に必要な法律や規制の課題も整理する。成果は公表され、政策づくりや業界全体の参考にする予定だ。BHPのベン・エリス副社長は「アジアでは稼働間もない高炉が多く、既存設備を脱炭素化する技術が重要」と話す。
各社もそれぞれ削減目標を掲げている。AM/NS Indiaは「次世代のための責任」と強調し、JSWは2005年比で2030年までにCO2排出原単位を42%削減、現代製鉄は「国境を越えた知識共有」を重視。三井物産は2050年ネットゼロ、2030年までに30%削減を目標とし、シェブロンは「CCUSは不可欠」と評価する。
CCUSはすでに一部産業で実績があり、拠点をまとめて整備することでコスト削減や複数産業の同時脱炭素が可能になる。今回の調査は、アジア太平洋地域での大規模CO2削減への道筋をつける重要な一歩になるとみられる。
参考:https://www.bhp.com/news/media-centre/releases/2025/08/global-industry-leaders-launch-ccus-hub-study-to-accelerate-decarbonisation-in-asia