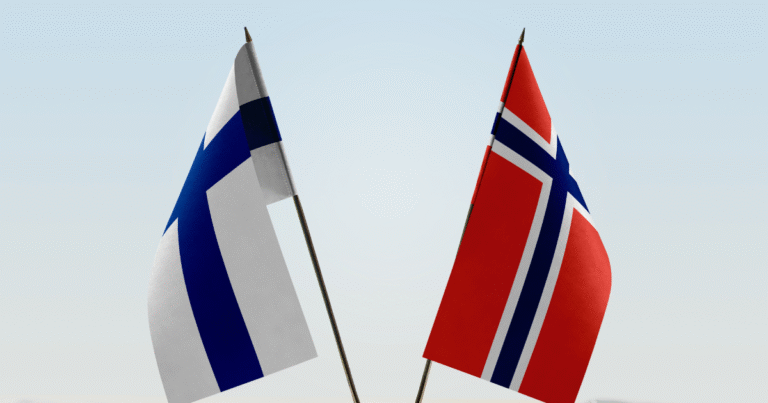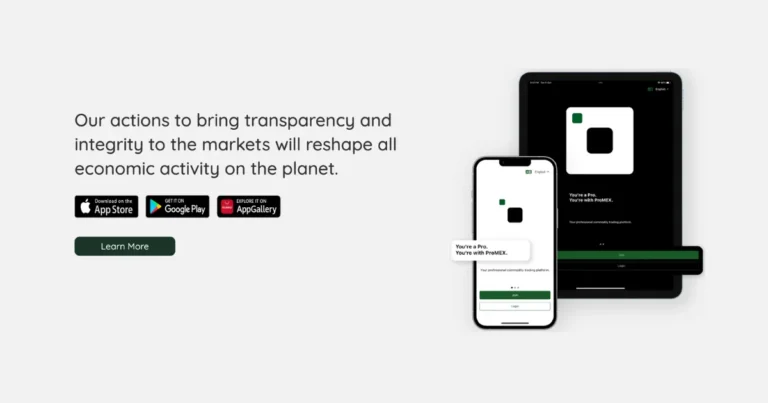農地にまく「石灰」が、実は大気中の二酸化炭素(CO2)を吸収している可能性がある。そんな驚きの研究結果が、イェール大学から発表された。これは従来の「農業はCO2を出している」という常識を覆す内容だ。
発表は10日、チェコ・プラハで開かれた地球化学の国際会議「ゴールドシュミット会議」で行われた。研究チームは、米国ミシシッピ川流域の120年分のデータを分析。石灰がCO2を出すどころか、むしろ吸収していることを明らかにした。
これまで、国際的な温室効果ガス(GHG)の計算では、「石灰は土壌の酸と反応してCO2を出す」と考えられてきた。しかし今回の研究は、「本当にCO2を出しているのは、肥料や大気汚染によって土壌が酸性になることが原因だ」と指摘している。
イェール大学自然炭素除去センターのティム・ジェスパー・スアホフ博士は「CO2を発生させるのは、酸が石灰と反応する時であって、石灰そのものをまいたからではない」と説明した。
農業で使う石灰は、土壌の酸性を中和し、農作物の育ちやすい環境を作るために使われている。このとき、土の中の炭酸と反応して「重炭酸塩」を作るが、これがCO2を安定的に土壌にとどめる役割を果たす。
ただし、肥料や大気汚染で酸が土壌に加わると、そこで初めてCO2が発生してしまう。研究チームは、1930年代以降の米国の農業データをもとに、「石灰によるCO2吸収効果は、理論上の最大値の約75%まで達している」と推計している。
この発見は、農業による炭素除去(CDR)の新たな可能性を示す。農業の炭素削減策として注目されている岩石風化促進(ERW)、つまり岩石を砕いて土壌にまく方法についても、「石灰岩を使う方が効率的な場合がある」と今回の研究は示唆している。
国際的には、IPCCの基準がいまだに「石灰はCO2排出源」としているが、研究チームは「農業政策を見直す時期が来ている」と訴えている。
参考:https://conf.goldschmidt.info/goldschmidt/2025/meetingapp.cgi/Paper/29785