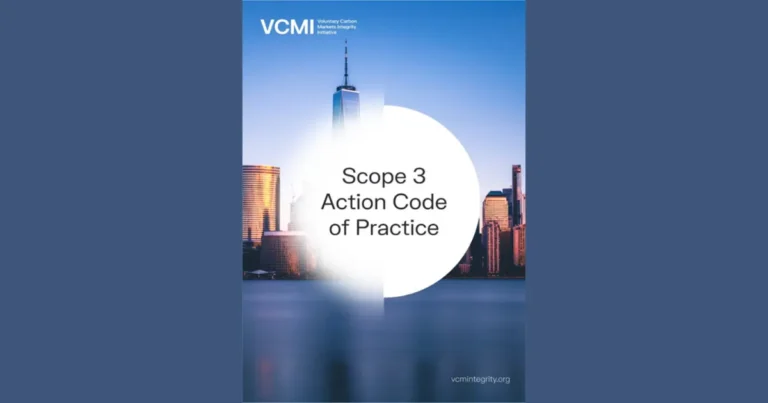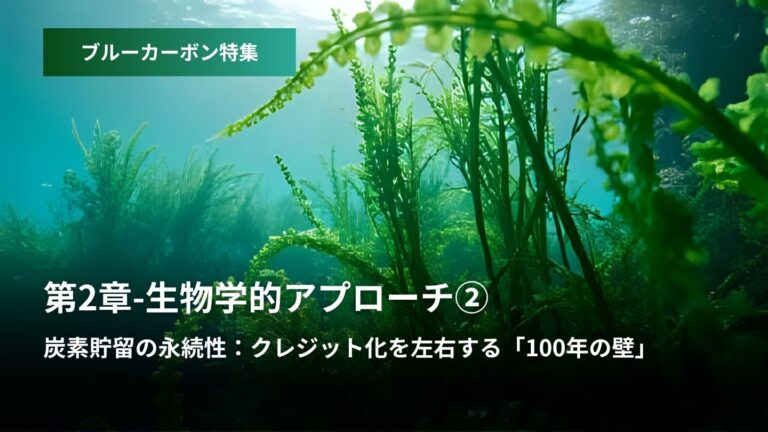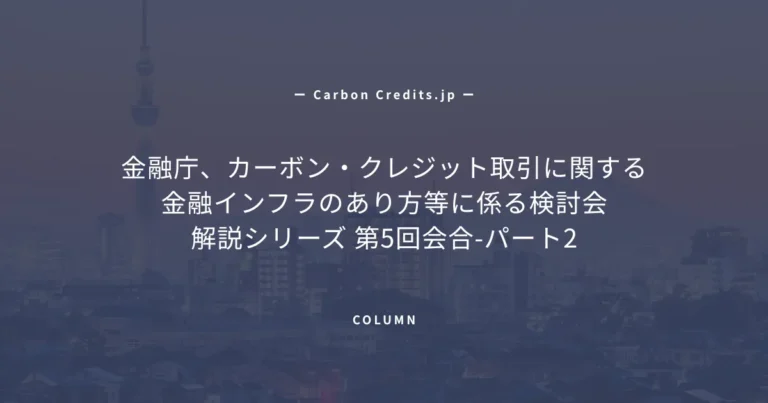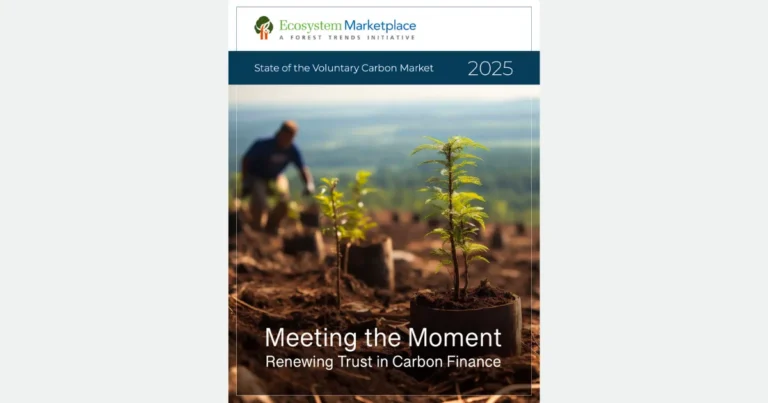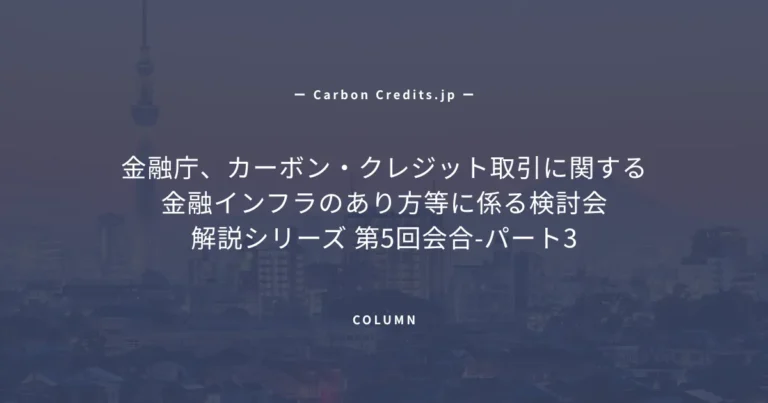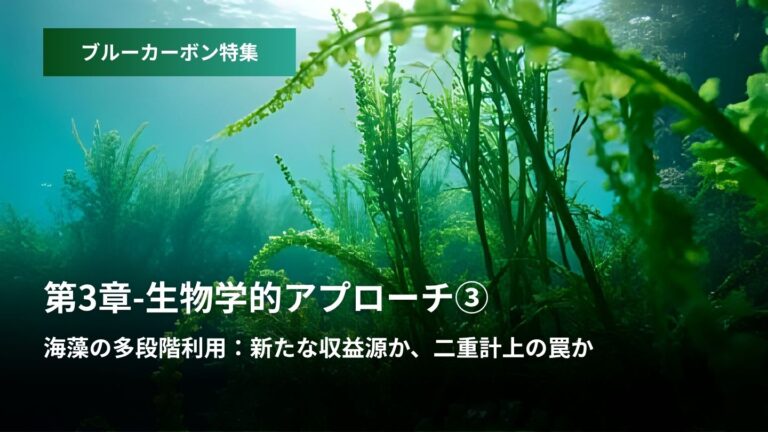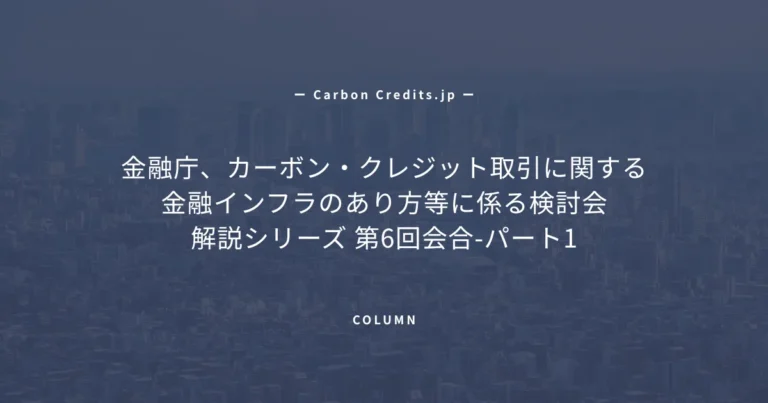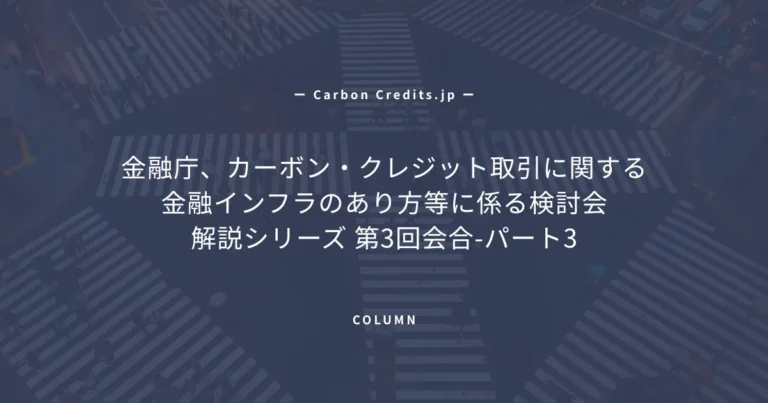国際的な森林保全型カーボンクレジット制度「REDD+(森林減少・劣化削減プラス)」の実効性を検証した新たな研究が、10月9日付の英科学誌『サイエンス』に掲載された。中国・深圳大学などの研究チームは、南米・アフリカ・東南アジアの12カ国で展開される52件のREDD+プロジェクトを分析し、全体の19%のみが報告された排出削減目標を達成したと明らかにした。一方で、低調な案件でも部分的な気候便益を示し、全発行カーボンクレジットの約13.2%が実際の森林減少抑制による実質的削減であったと推計した。
検証対象と手法 人工衛星データを基に「合成対照分析」
研究は、REDD+のうち「非計画的森林減少回避(AUD)」型に焦点を当て、Verraの「認証カーボン基準(VCS)」で登録されたプロジェクトを評価した。ブラジルやコンゴ民主共和国、カンボジアなどの事業データを衛星画像と地理情報に基づいて解析し、各プロジェクト地域と条件の類似する対照地を人工的に構築する「合成コントロール法(Synthetic Control Method)」を採用した。これにより、介入がなければ想定される森林減少量(カウンターファクチュアル)と比較する形で、実際の効果を統計的に評価した。
その結果、69の事業ユニットのうち21件(約3分の1)が統計的に有意な森林減少抑制を達成した一方、11件(約17%)ではむしろ森林喪失が増加していた。地域別ではブラジルとアフリカで比較的高い効果が確認された。
「過大評価」構造が依然 コロンビアで顕著な乖離
研究チームはまた、各プロジェクトの公式報告に記載された「基準森林減少率」が実測と大きく乖離していることを指摘した。52件中35%では、報告値が実際より10倍以上高く、削減効果を過大に算出していた。特にコロンビアでは、評価対象の12件中10件が「過剰クレジット」発行の可能性を示した。
全体として、2022年までに発行された264百万トン相当のカーボンクレジットのうち、実際に温室効果ガス削減と整合するのは約34.8百万トン(13.2%)にとどまると推定。既に9割以上が販売され、約1億2,700万トン分が企業や個人の排出相殺に使用されたが、真に追加的な削減量との乖離は5.6倍に上るとした。
改善策 基準設定と検証枠組みの再構築を提言
論文は、こうした「過剰クレジット」の主因として、過去の森林減少傾向を不適切に参照した基準地選定や、政策・経済要因の変化を反映しない単純モデルを挙げた。特にブラジルでは、ボルソナロ政権期(2019〜2021年)に森林減少率が倍増するなど、政治変動が影響した事例が観察された。
著者らは、対照地の設定において生態的・社会経済的条件を精密に一致させる手法の導入や、国ごとの政策サイクルを反映したモデル化を提案。さらに、単一プロジェクトへの依存を避けた「分散型ポートフォリオ」運用や、第三者機関による格付け制度の拡充を求めた。
日本市場への含意 信頼性確保が鍵
ボランタリー市場でREDD+クレジットを利用する日本企業にとっても、この研究は重大な示唆を与える。カーボンクレジットの品質格差を考慮し、購入時に「検証済みの追加性(additionality)」と「ベースラインの透明性」を精査することが不可欠である。今後、Verraなど認証機関の新基準や、国際的格付け機関による品質評価の進展が、信頼性の再構築に向けた焦点となる。