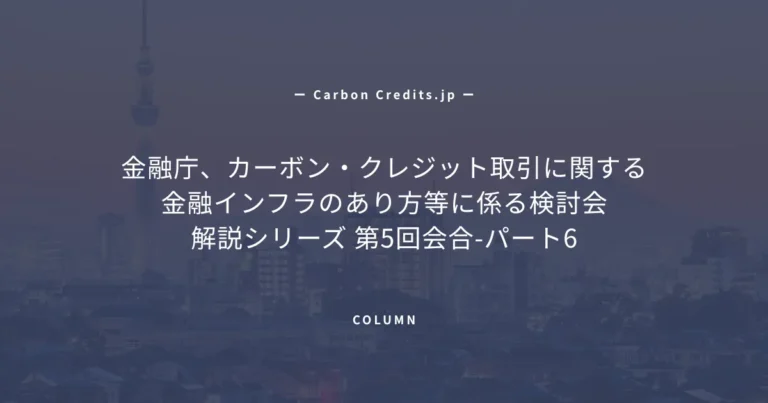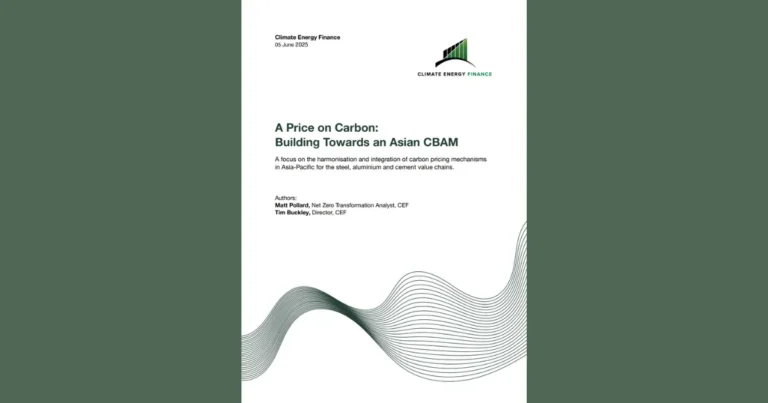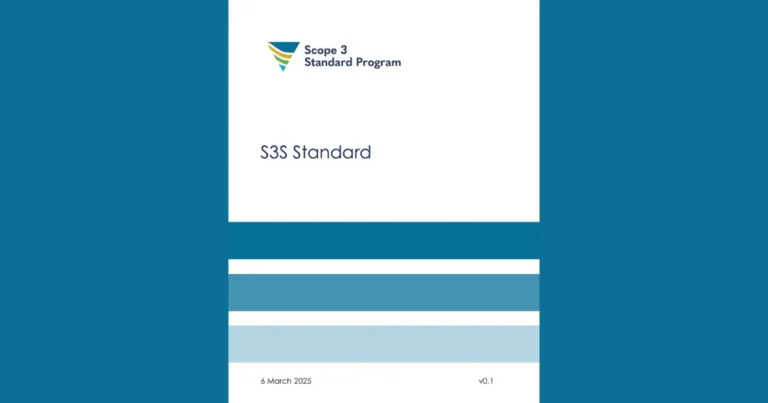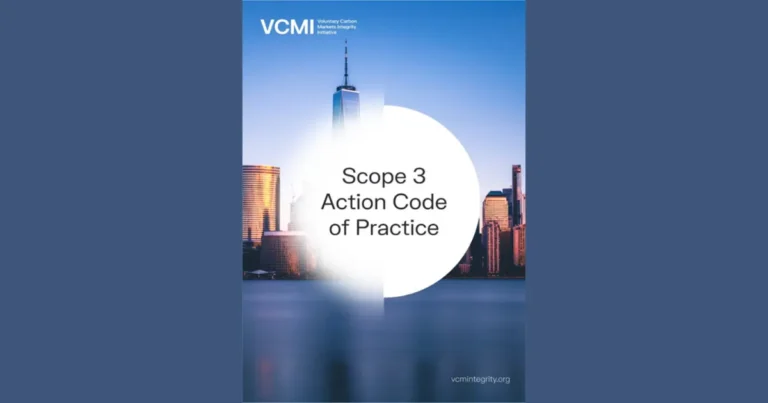2015年に採択されたパリ協定(Paris Agreement)は、すべての国が温室効果ガス(GHG)の削減に取り組むことを約束した初めての国際的枠組みである。それ以前の「京都議定書」では先進国のみが対象であったが、パリ協定ではすべての国が対象となった点が大きな違いだ。
この協定の中で第6条(Article 6)は、「国同士が協力して排出削減を進める仕組み」を定めている。例えば、ある国が他国の再生可能エネルギー事業を支援し、その分の削減量を国際的にやり取り(取引)できるようにする仕組みである。
つまり、「資金や技術を通じて協力しながら、世界全体でCO2を減らしていく」ためのルールが第6条である。
第6条の中でも重要な「第6条2項」
第6条の中でも特に注目されるのが第6条2項(Article 6.2)である。これは「協調的アプローチ」と呼ばれ、国と国が排出削減量をやり取り(取引)できる制度を指す。この削減量の単位は「ITMO(国際的に移転された緩和成果)」と呼ばれる。
これにより、ある国は他国の削減プロジェクトを支援することで、自国の削減目標(NDC)の達成にカウントできるようになる。
2025年から「実装段階」へ
2024年に開催されたCOP29(アゼルバイジャン・バクー)では、第6条の運用ルールが整備された。これにより2025年からは、世界各国で実際に運用が始まる「実装段階」に入った。
各国は次の3つのプロセスを順に実施している。
| プロセス | 内容 |
|---|---|
| 初期報告(IR) | 自国の制度や取引方針を初めてまとめた報告書 |
| 年次情報(AEF) | 毎年の取引や活動実績を電子フォーマットで報告 |
| 技術専門家レビュー(TER) | 専門家が報告内容を検証し、改善提案を行う仕組み |
国際排出取引協会(IETA)によれば、2025年秋時点でIRは17件、AEFは4か国、TERは6件(うち5件が公表済み)である。これは「第6条が実際に動き出した」ことを示す初期段階であり、国際協力による削減がいよいよ現実化しつつあることを意味する。
各国の制度整備、まずは「ルールと仕組み」づくりから
①権限機関(オーソライズ機関)の設置
取引を実施するためには、まず「国として誰が承認するのか」を明確にする必要がある。この役割を担うのが「権限機関(Authorization Authority)」であり、ITMOの発行・移転・承認を統括する。
地球環境戦略研究機関(IGES)の調査によれば、100か国のうち85か国が何らかの制度整備に着手しており、13か国が承認とトラッキングの両方を整備済みである。また、62か国が正式に権限機関を特定している。
つまり、世界の多くの国が制度基盤の構築段階に入っている状況である。
②トラッキング体制(レジストリ)の構築
排出削減量を正確に管理するためには、「レジストリ(Registry)」と呼ばれる電子台帳(登録簿)が必要である。これは削減クレジットの発行・移転・償却を記録するシステムであり、ダブルカウントを防ぐ仕組みとして重要である。
IGESによれば、13%の国が整備済み、35%が整備中である。レジストリが稼働することで、取引の信頼性がデータとして可視化されることになる。
③報告とレビューの運用開始
各国はIR・AEF・TERを通じて、定期的に取引の透明性を確保している。特にTERでは、専門家が報告内容を精査し、削減量の正確性や会計処理(対応調整:CA)の妥当性を確認する。IETAは、各国間で報告様式や定義にばらつきが見られることを指摘し、知見共有のための「野心対話(Ambition Dialogue)」の重要性を提言している。
二国間協力と実際の取引の動き
第6条2項の取引は、国と国の二国間協定(MoUや協力アレンジメント)を通じて実施される。IGESによれば、2025年時点で協定は99件に達し、関与する国は61か国にのぼる。代表的な例としては、日本の二国間クレジット制度(JCM)や、スイスの気候協力協定が挙げられる。
一方で、実際に削減量(ITMO)の移転が完了した取引はまだ4件のみであり、いずれもタイからスイスへの電動バス導入事業である。2023〜2024年に約31,000ITMOが移転されており、これは第6条市場の実動を示す初の成功事例であり、今後の拡大が期待される。
第6条4項(Article 6.4)との連携
第6条4項(6.4)は、国連が直接管理するクレジット制度であり、旧クリーン開発メカニズム(CDM)の後継にあたる。6.4メカニズムの仕組みで発行されるクレジットは「PACM(Paris Agreement Crediting Mechanism)」と呼ばれる。
最新の進捗は以下の通りである。
- 事前登録:1,041件
- CDMからの移行要請:1,508件
- ホスト国の承認:92件(約6%)
主な案件は南アジアおよび東アジア地域で、風力・水力発電が中心である。6.4メカニズムの拡大は、6.2市場に供給される高品質クレジットの基盤を形成するものである。
能力構築(キャパシティビルディング)
制度が整っても、運用を担う人材や技術が不足していれば機能しない。この課題に対処するため、UNFCCC事務局は各国の実施能力を高める「能力構築(Capacity-building)」を推進している。
2025年にはアジア・アフリカ・中東欧で地域ワークショップが開催され、90か国が参加した。また、各国の認定機関が集う「DNAフォーラム」やオンライン研修の拡充も進められている。
これらの取り組みは、各国の成熟度に応じて「基礎 → 制度整備 → 市場準備」という三層アプローチで段階的に行われている。
COP30(ベレン会議)での焦点
2025年11月にブラジル・ベレンで開催されるCOP30では、第6条の新ルールづくりではなく、実際の運用と改善に焦点が当てられる。特に「野心対話(Ambition Dialogue)」では、各国が実務経験や課題を共有し、制度の改善に向けた議論を行う予定である。
IETAは、正式な交渉再開は2028年以降になると見込んでおり、それまでの期間に各国が注力すべき課題として以下の4点を挙げている。
- IR/AEF/TERを一巡させ、報告と改善のサイクルを確立する
- レジストリを本格稼働させる
- 第6条4項の制度移行を進め、クレジット供給を安定化させる
- UNFCCCの支援を活用し、制度と人材を同時に整備する
これらの取り組みを通じて、信頼性の高い国際カーボン市場の構築が進展する見込みである。
COP30は、第6条が「制度設計から実践」へと移行する象徴的な会議となるだろう。
UNFCCC/CMA『Capacity-building for implementing Article 6』
IGES/A6IP『Article 6 Implementation Status Report 2025』
IETA『COP30 Policy Paper』