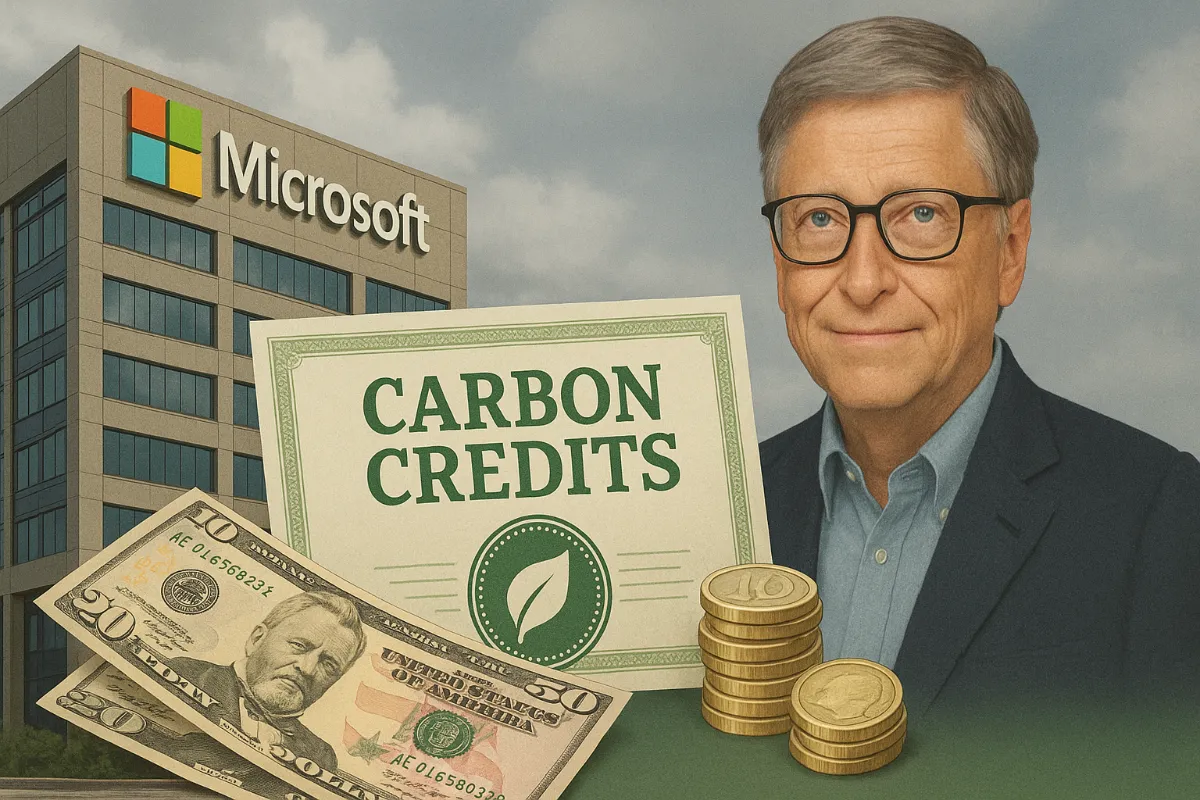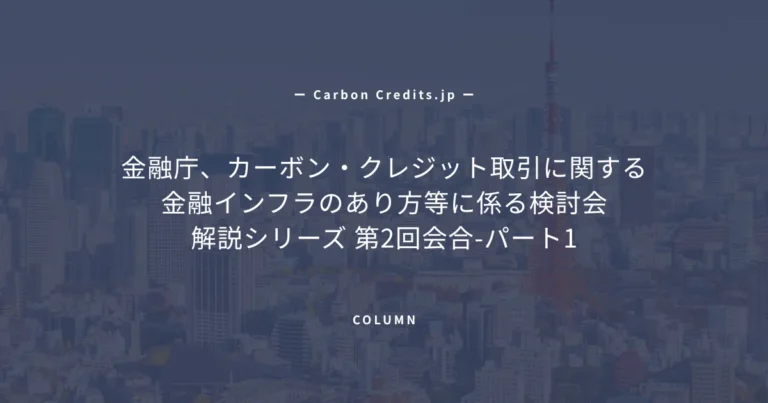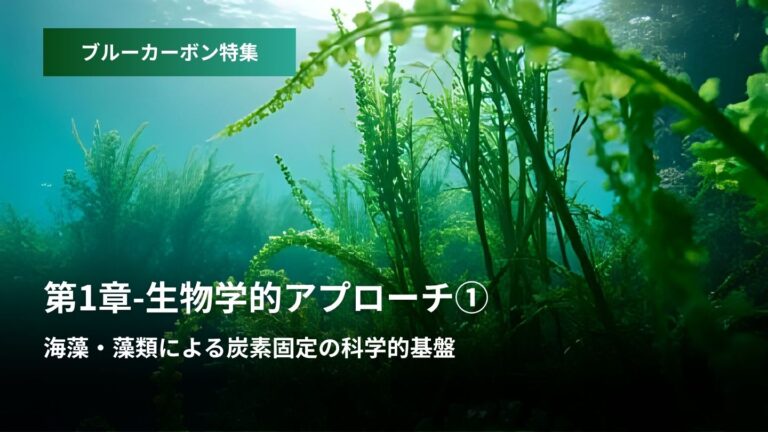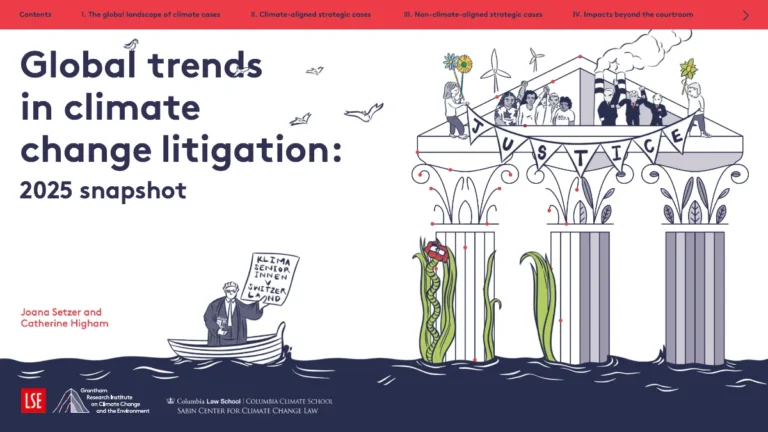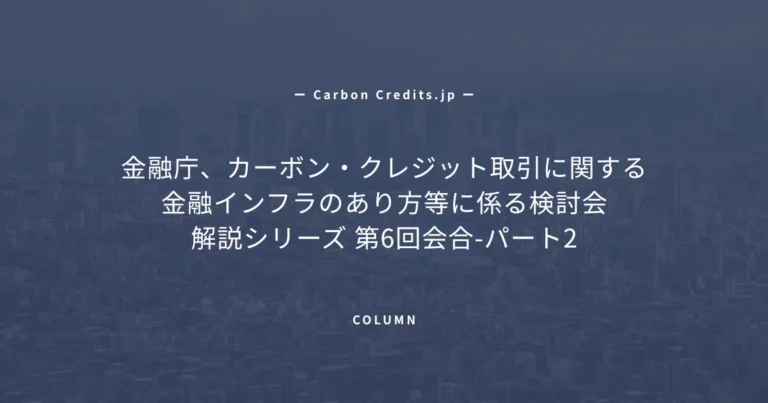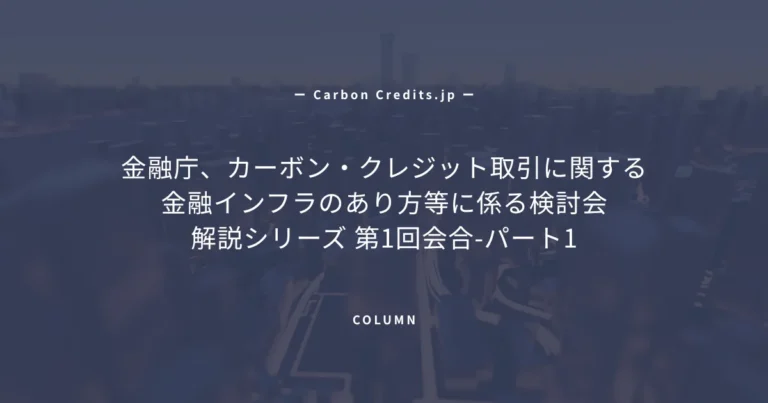先進企業としてのプレゼンス強化
2020 年に「2030 年までにカーボンネガティブ、2050 年までに創業以来の累積排出をすべて除去する」と発表したマイクロソフトは、気候対策をめぐる企業競争でいち早く最前線に立ちました。目標達成の柱は、自社排出の削減だけでなく、大量の高品質なカーボンクレジットを調達し、市場そのものを拡大させるというアプローチです。こうした大胆な宣言と実行力によって、マイクロソフトは「AIとクラウドの巨人」だけでなく「脱炭素のフロントランナー」というブランドイメージを確立しつつあります。
爆買いは「将来への投資」
同社は2024~2025 年だけでも、1PointFiveのDACプロジェクトからの50 万t CO2、Chestnut Carbonの森林プロジェクトからの700万t CO2、CO280のバイオ炭プロジェクトからの370万t CO2など、数百万トン規模のカーボンクレジット購入契約を重ねています。CDR市場全体で見ても、2024 年の耐久性除去クレジット購入の約8割がマイクロソフトなどのリピーター企業に支えられており、同社の取引は価格形成と技術コスト低減を牽引しています。
マイクロソフトが「爆買い」に踏み切る背景には二つの投資的観点があります。
第一に、耐久性の高い除去系クレジットは供給が限られ、将来的に価格が急騰するリスクが高いという先物買いの発想です。
第二に、大口オフテイク契約はスタートアップにとってデットファイナンスの担保となり、DACやバイオ炭の学習曲線を加速させる市場形成投資として機能します。
言い換えれば、同社はクレジットをコストではなく資本支出とみなし、長期的な環境価値と経済価値の双方を取り込もうとしているのです。
ビル・ゲイツ氏の思想と戦略への影響
マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏は著書『How to Avoid a Climate Disaster』で「イノベーションなしにネットゼロは達成できない」と繰り返し、Breakthrough Energyを通じてDAC、水素、グリッド最適化など、クライメートハードテック領域に資金を注いでいます。
2024 年にはCRSI(Carbon Removal Standards Initiative)の立ち上げを支援し、CDR技術の標準化と信頼性向上にもコミットしました。
ゲイツ氏の思想は、「市場を創り、その市場がさらに技術革新を呼び込む」というループを重視する点でマイクロソフトの戦略と軌を一にしています。同氏が率いる基金が関与する企業がマイクロソフトと長期契約を結ぶ例も増えており、技術革新と需要創出を同時にドライブするエコシステム戦略が見られます。
中立的に見たリスクと期待
もっとも、巨額購入をもってしても、同社のScope3の実排出は拡大を続けており、AIセンター新設による電力需要増とのトレードオフも指摘されています。また、耐久性や追加性の検証が不十分なプロジェクトが混在することで「市場全体の信頼性を毀損する」との批判も根強いのが現状です。一方で、マイクロソフトが先行需要を示さなければ「これらの技術がビジネスとして成立するタイミングはさらに遅れていた」という評価があるのも事実です。
マイクロソフトのカーボンクレジット大量購入は、単なる「排出の埋め合わせ」を超え、クライメートテックエコシステムへの戦略投資という側面が強いです。大胆な先行投資が市場を育て、価格を下げ、イノベーションの波を加速させる。そのシナリオが実現するかどうかは、同社自身の実行力と、市場全体の透明性を高めるルールメイキングの進展にかかっていると言えるでしょう。