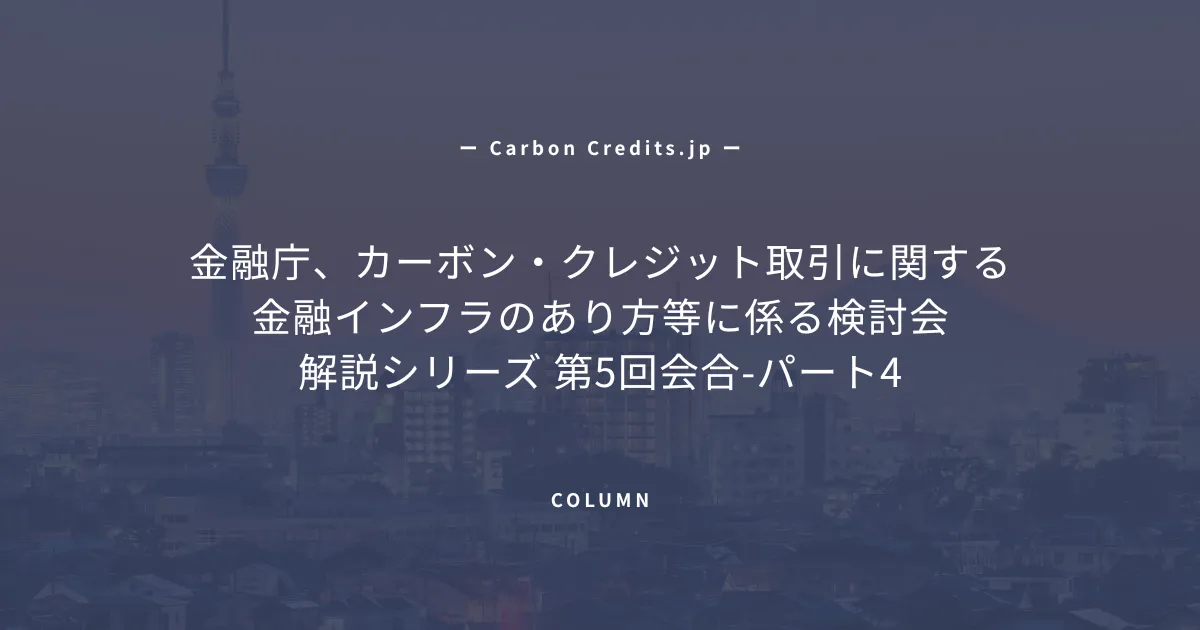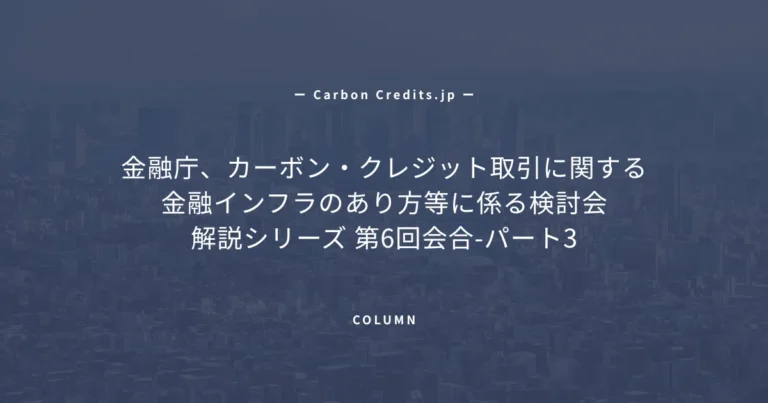金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第5回パート4
2025年2月25日に開かれた金融庁主催「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会(第5回)」では、国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)東京事務所長が登壇し、ボランタリーカーボンクレジット市場の健全な拡大に向けた同協会の政策提言と標準ドキュメンテーション策定の進捗を詳述した。
発言の核心は、
- ①グリーンウォッシュ抑止と市場信頼性向上を目的とした国際協調の強化
- ②各国でばらつくボランタリーカーボンクレジットの法的性質の明確化
- ③取引リスクを低減する契約書テンプレート「Verified Carbon Credit Transactions Definitions(VCC定義集)」の改訂
という三本柱だ。
これらは、日本で法的位置付けが曖昧なカーボンクレジットを扱う金融界にとって、取引コスト削減と信用リスク管理の両面で喫緊の課題解決策となり得る。
ISDAの提言
ISDAはまず、ISDAが掲げるボランタリーカーボンクレジット市場支援の基本姿勢を説明した。
同協会はIOSCOや欧州委員会(DG CLIMA)との連携を通じて、高品質カーボンクレジットの評価基準づくりやグリーンウォッシング抑止策を進めており、米国の「Principles for High-Integrity VCMs」策定にも参画している。
こうした国際枠組みの整合性確保は、市場流動性を損なわずに透明性を高める要諦だと強調した。
カーボンクレジットの法的性質
続いて焦点となったのが「法的性質」の論点だ。
ISDAは2021年以降、英国法、NY州法、独法、そして日本・仏・シンガポール法を対象に意見書を取りまとめ、ボランタリーカーボンクレジットを無体財産権とみなすアプローチと、契約上の権利束として扱うアプローチの長短を整理した。
その結論は国ごとに温度差があり、日本法では物権法定主義の壁が残るというものだ。
ISDAは「UNIDROIT作業部会が2026年前半に市中協議を行い、同年中に私法上の原則を確定させる予定」であり、日本も立法・ガイダンス整備で歩調を合わせる必要があると指摘した。
ボランタリーカーボンクレジットのリスク管理
リスク管理面では、ISDAが20年超にわたり排出量取引制度(EU ETSなど)向けに提供してきた標準契約スキームをボランタリーカーボンクレジット市場にも拡張した点が注目される。
2022年12月に初版が公開された「Verified Carbon Credit Transactions Definitions(VCC定義集)」は、ISDAマスター契約とひも付くスポット・フォワード・オプションで共通言語として機能する。
条項構成は一般定義、決済、無効化(Retirement)、VCC混乱事由などから成り、Force Majeureを補完する「VCC Disruption Events」で決済障害時の猶予や救済措置を明文化した。
さらに2024年2月公表のバージョン2.0では、①支払期日を「引渡し後2営業日以内」に短縮、②前払い条項を導入、③ICVCMのコアカーボン原則(CCPs)関連ラベルを追加するなど、市場実務に即したアップデートを実施。
次期改訂ではCORSIA適格クレジットへの対応が検討されており、航空分野の排出オフセット需要を視野に入れる。
まとめ
ISDAは締めくくりとして、「標準化された書式と法的確実性がそろえば、資本市場のプレーヤーが安心して気候リスク移転やファイナンスにVCCを組み込める」と述べた。
検討会の議論は、日本が抱える権利の対抗要件や倒産時ファイナリティといった国内特有の論点へと波及していく見込みだ。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事録.令和7年2月25日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事次第.令和7年2月21日