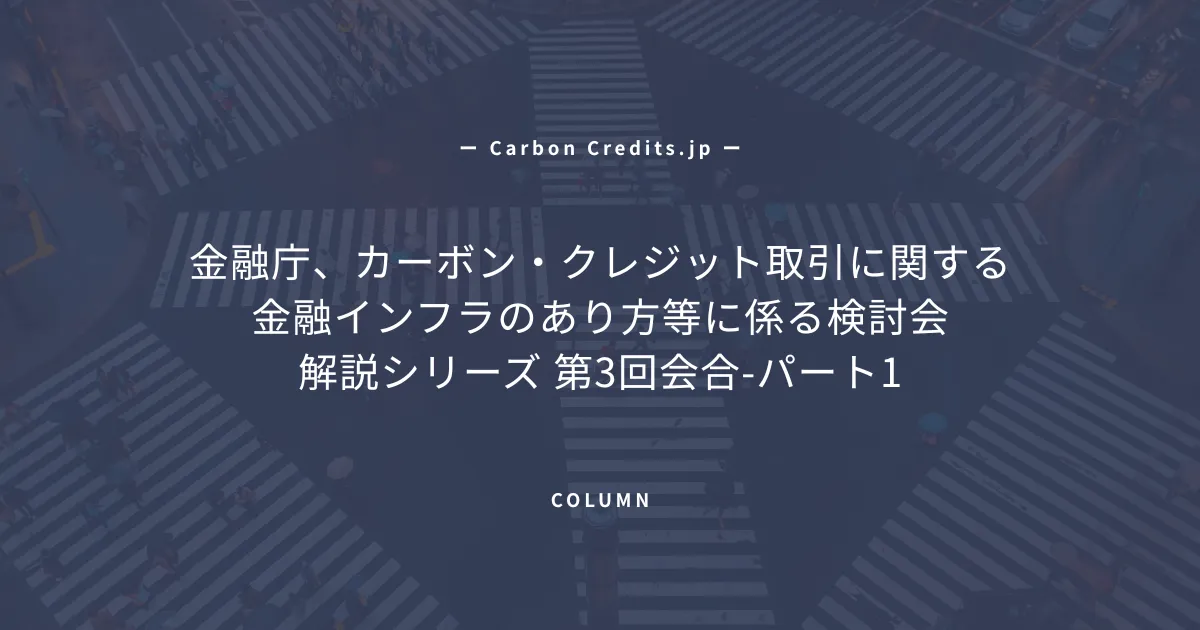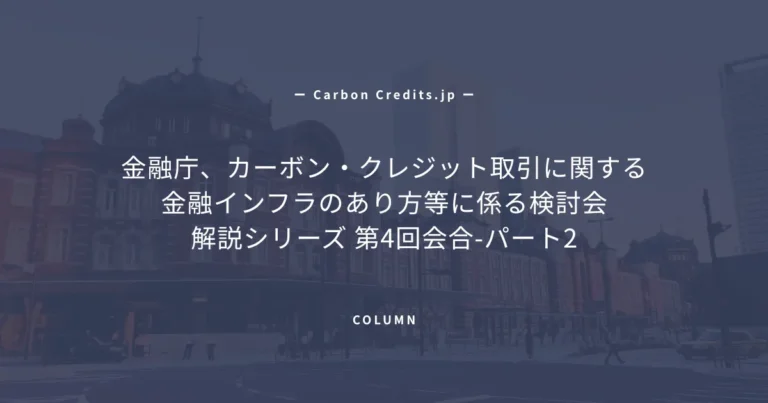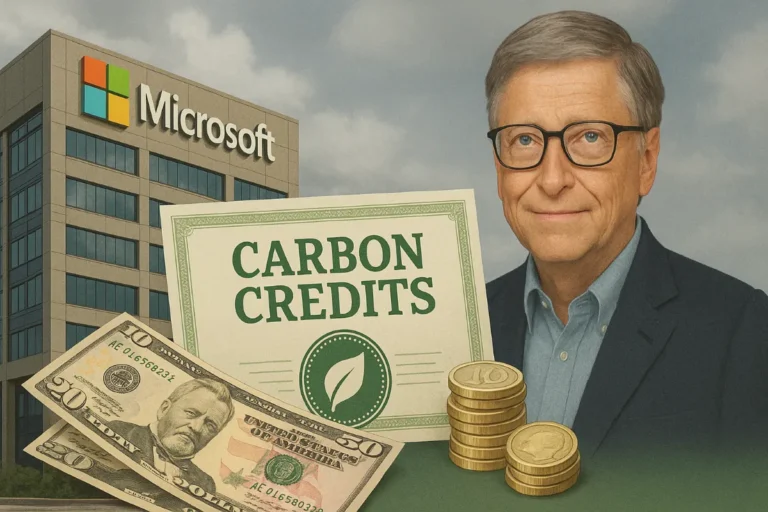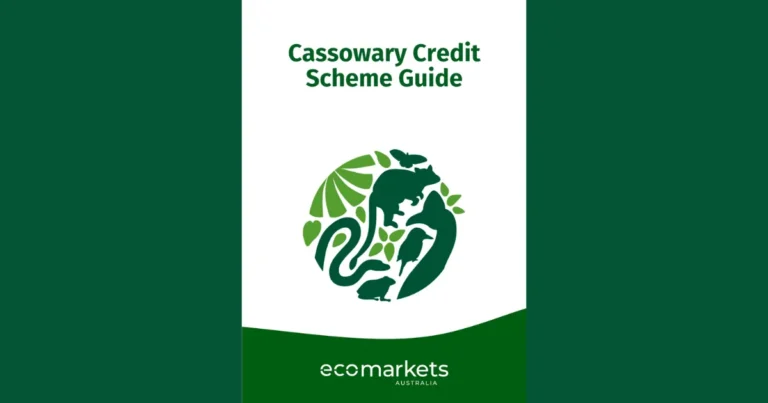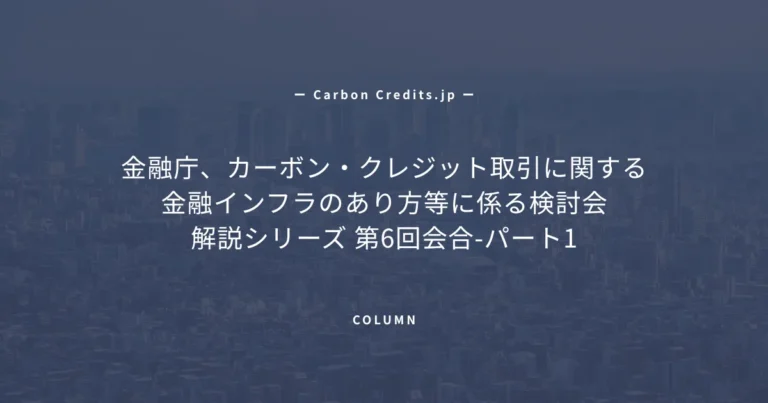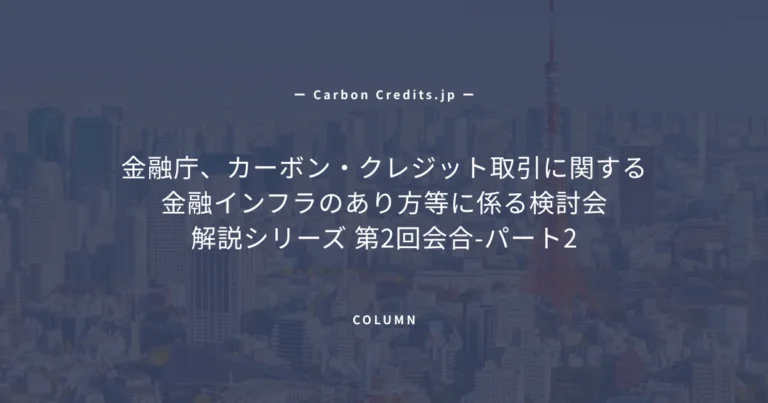金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第3回パート1
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、カーボンクレジット市場は国内外で急速に拡大しているが、一方で、市場の拡大に比例して、取引の透明性や健全性、投資家保護といった課題も浮き彫りになっている。
そこで金融庁は2024年6月より「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(以下、検討会)を立ち上げ、金融実務家・有識者とともに論点整理を進めている。本コラムでは、2024年11月19日に開催された第3回検討会の冒頭部分を中心に概要を整理し、今後の議論に向けたポイントを提示する。
第3回検討会の概要
第3回検討会では、
- ①前回整理しきれなかった「地域金融」と「テック活用」の論点を再確認
- ②COP29期間中に公表されたIOSCO Voluntary Carbon Markets Final Reportの要点を共有
- ③証券・商社・保険の3業界から最新ビジネス事例を聴取
- ④仲介者の役割や信用補完スキームを巡る課題の洗い出し
が行われた。
前回議論「地域×テック」の振り返り
冒頭、事務局が第2回会合の要点を整理した。
地域金融機関が取り扱う森林由来カーボンクレジットでは「売れ残りリスク」や「長期的な森林管理への信頼」が依然としてボトルネックであり、買手が地産地消やストーリー性を重視する傾向も確認された。
また、テクノロジー面ではブロックチェーンが透明性(改ざん不能台帳)、取引コスト削減(スマートコントラクト)、小口化(トークン化)といった価値を提供し得るものの、「誰でも台帳を閲覧できるのか」「償却(retirement)を自動実行できるか」といった具体実装を巡る疑問が残ることが指摘された。
IOSCO最終報告書
21のグッドプラクティス
続いて事務局は、2024年11月14日にCOP29会場で正式公表されたIOSCOVoluntary Carbon Markets Final Reportの全体像を説明した。
報告書は、規制フレームワーク、発行市場、流通市場、クレジット利用と開示の四領域で21項目「Good Practice」を提示されており、特に
- ①標準化の欠落
- ②情報アクセスの不足
- ③登録簿や評価機関における利益相反
- ④OTC偏重による価格不透明性
が市場の脆弱性として強調された。
また、どの法域でも「カーボンクレジット現物」を金融商品とみなすかコモディティとみなすかは定義が揃わず、国内外の「同等性」を確保しながら段階的に制度整備を進める必要があると指摘した点は、日本の立法作業にも示唆を与えるだろう。
仲介者(インターミディアリー)の現状認識
報告書によれば、世界の取引の大半は仲介者を介したOTCで、複雑なプロジェクト多様性や買手の専属契約志向が背景にあり、実際に日本でも証券会社、商社、銀行、ブティック型スタートアップが仲介や創出支援に参入しつつある。
メンバーからは「取引価格・量を開示する公的レポーティング体制がなければ、市場インテグリティは担保できない」との指摘があった。
投資家保護・顧客保護の論点整理
事務局はこの観点で二つの問いを提示した。
一つ目は「仲介者が増える中で、適合性確認や過剰販売防止など顧客保護をどう担保するか」。これに対してメンバーからは、①販売手数料の開示義務化、②適合性確認でのトランジション優先原則、③取引データのプレ・ポスト開示といった案が提案された。
二つ目は「信用補完スキームの質」を巡る議論。前払型オフテイク契約や保険が普及すれば創出前のプロジェクトに資金が流れやすくなる一方、引当不足や保険限度額不足が顧客リスクとなり得える。評価機関の利害がカーボンクレジット発行者と密接に結びつく構造も指摘され、「評価業者向けに、IOSCOが整理した利益相反ルールを国内でどう実装するか」が今後の論点として整理された。
まとめ
第3回検討会は、「仲介者主導のOTC市場」という現状認識と「IOSCOが求める透明・標準化市場」という将来像をつなぐ具体策を議論する場となった。
パート2では、大和証券、三菱商事、東京海上日動の取り組みの発表について整理する。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第3回)議事録.令和6年11月19日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第3回)議事次第.令和6年11月18日