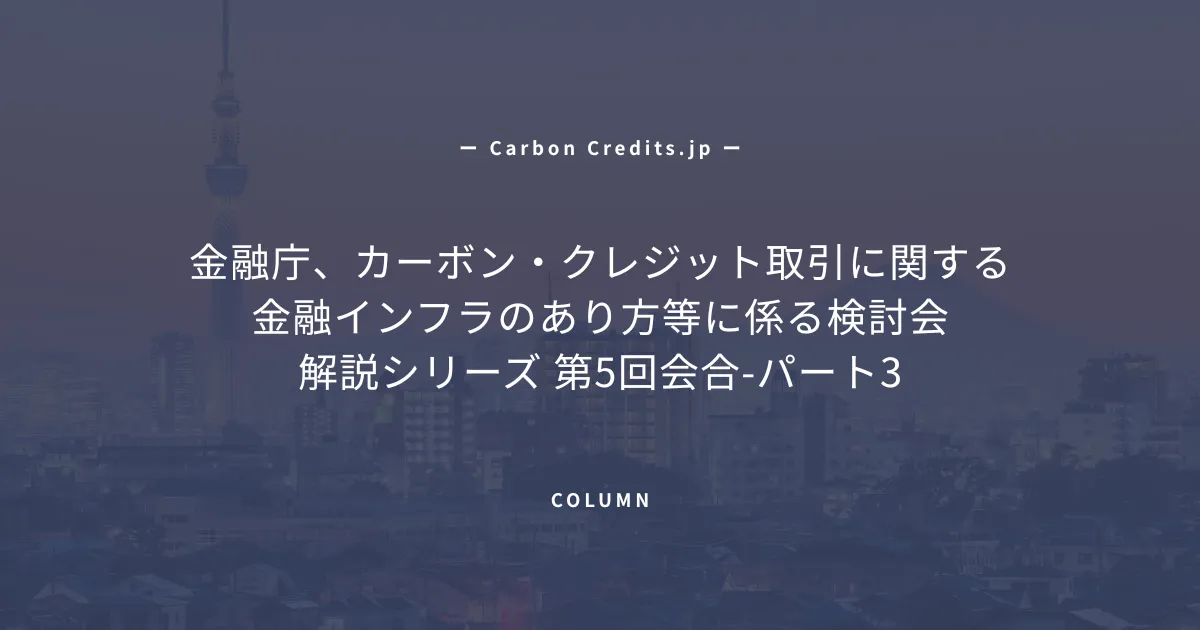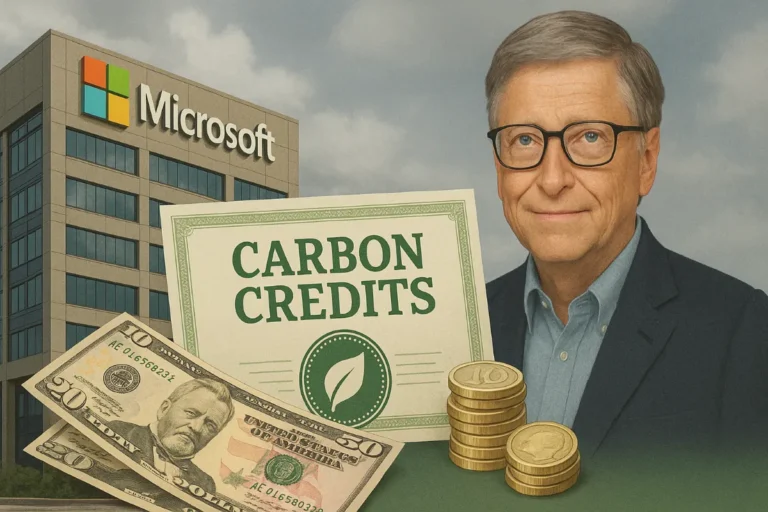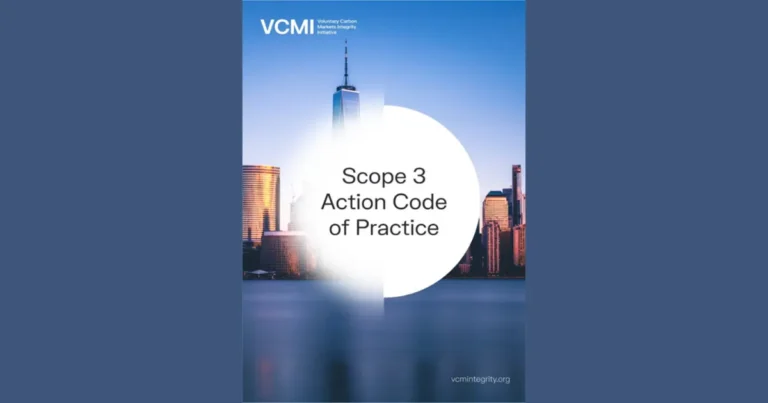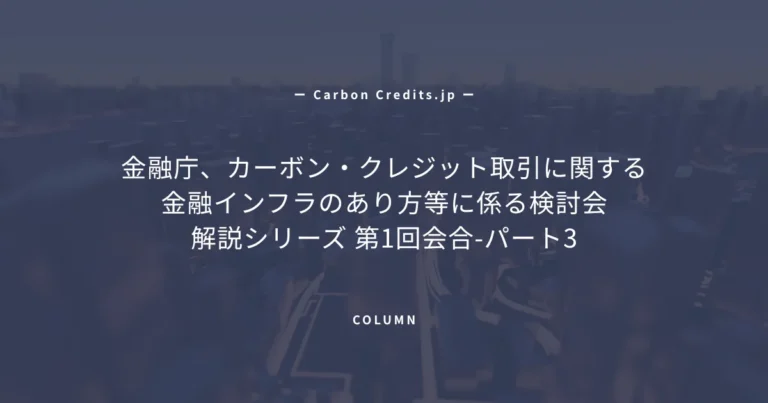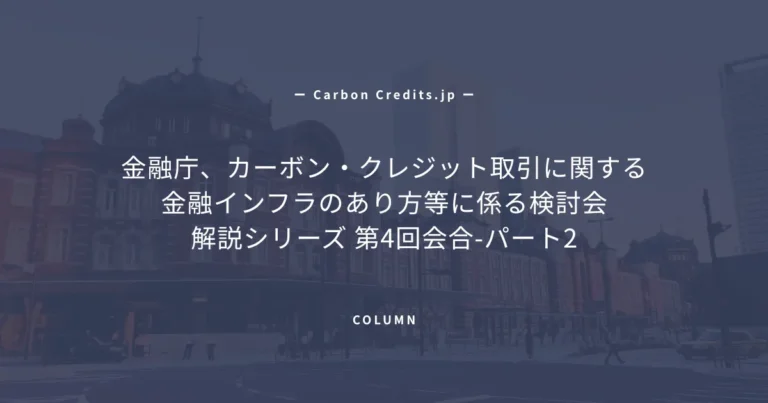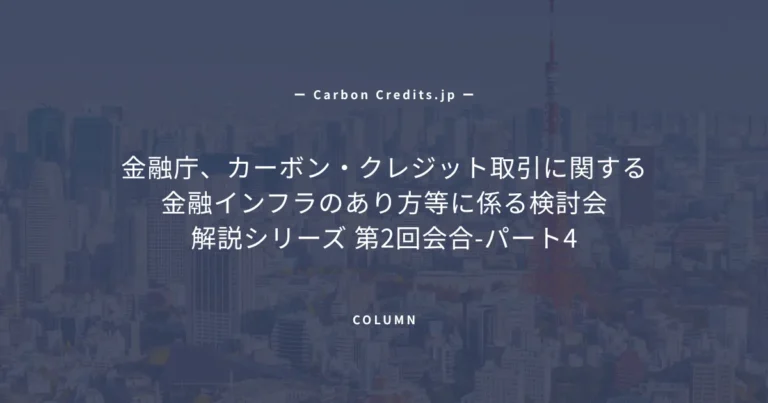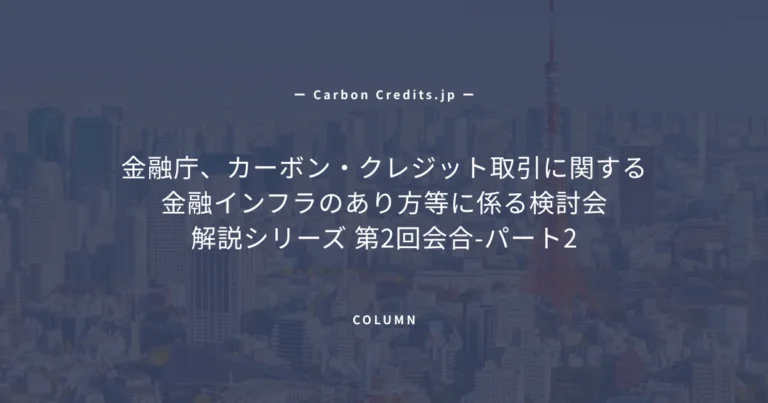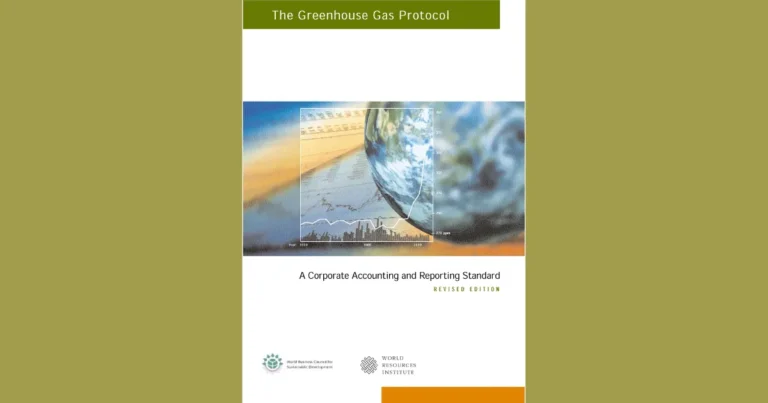金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第5回パート3
今回の質疑は、供給側の品質基準を担うICVCMと需要側の開示基準を担うVCMIという「両輪」に対し、委員が抱く根源的な疑問をぶつける場となった。以下では、各質問と登壇者の回答を軸に、課題構造を整理する。
CCPラベルはなぜ「3%」止まりなのか、追加性・メソドロジー更新の壁
まず焦点となったのは、ICVCMが市場全体の38%を審査済みであるのに、CCPラベル付きクレジットは3%に過ぎないという事実だ。
「認定失敗の主因は追加性か」というメンバーからの質問に対して、ICVCMは、
- ①評価中のメソドロジーが100超あるため数字は動的であること
- ②特定の市場セグメントを狙い撃ちに排除したわけではなく既存メソドロジーを逐一、二重チェックした結果であること
を強調し、とりわけ再エネ由来カーボンクレジットについては「途上国で追加性を証明し得る余地はあるが、従来手法では証明が弱い」と述べ、方法論刷新を促した。
REDD+承認の是非「排出回避」か「削減」か
ベースライン設定の恣意性が指摘されるREDD+が承認された理由これに対して、ICVCMは、VM0048、ART/TREES、JNRなどの改訂版メソドロジーのみを対象に、炭素削減実体が担保できると判断したと説明した。
続けて「カテゴリーとしてのREDD+を一括承認したのではなく、提出された手法単位で適格性を判断した」と強調し、パリ協定6.2条の国際移転(ITMO)とも整合するとの見解を示した。
CCPsとCORSIAの二層構造、統合の行方
CORSIAとの重複を問う質問に対して、ICVCMは「CCPsはCORSIA要件を包含しつつ、社会的セーフガードや恒久性評価など追加要件を課している」とし、両者は役割が補完的で、現時点での統合計画はないが「整合性の再検討には前向き」とした。
投資家インセンティブとグリーンハッシングリスク
根本座長はVCMIに対し「投資家やプロバイダーが高品質証明に取り組む動機」を尋ねた。
これに対してVCMIは、「企業にとっては財務的リスク低減とレピュテーション向上が最大の誘因であること」「メディアやNGOの監視が強まる中で曖昧な主張を避けて沈黙するグリーンハッシングが広がりつつあり、標準化枠組みの導入が信頼再構築の鍵になること」を指摘した。
VCMIのClaims Codeは、残存排出の10〜100%を補完するSilver/Gold/Platinum区分でカーボンクレジット利用量を定量化し、2026年以降はCCP承認クレジット購入を必須化する設計となっている。
米国政策の揺らぎと規制の準備運動
米国の政権交代やパリ協定離脱の影響について、ICVCMは「企業コミットメントは継続しており、CFTCやSECによる開示・上場指針にもCCPsが既に参照され始めている」と回答。
民間主導のボランタリーカーボンクレジット市場が「準規制→規制」へ段階的に移行する過程を見据え、標準化フレームワークを先に整備しておく必要性を示唆した。
日本のJ-クレジットはどう橋渡しするか
座長からの「国内制度(J-クレジット制度)とグローバル市場の接続」への提案要請に対し、ICVCMは「J-クレジット方法論をCCP適格へアップグレードし国際ラベルの取得を目指すこと」「需要側開示をVCMIコードに合わせ投資家信頼を得ること」「政府が供給・需要双方の品質基準を早期に示すことでグローバル資本を呼び込むシグナルとなること」を挙げた。
国内外のカーボンクレジット発行システムが完全に接続されなくても、共通品質ラベルがあれば流動性と価格発見を高められるとの認識を示した。
展望
質疑を通じて浮かび上がったのは、「追加性をいかに証明するか」「開示標準をどう法制度に埋め込むか」「J-クレジットを国際的ラベルで認定するルートをどう作るか」という三つの論点だ。
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事録.令和7年2月25日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)議事次第.令和7年2月21日