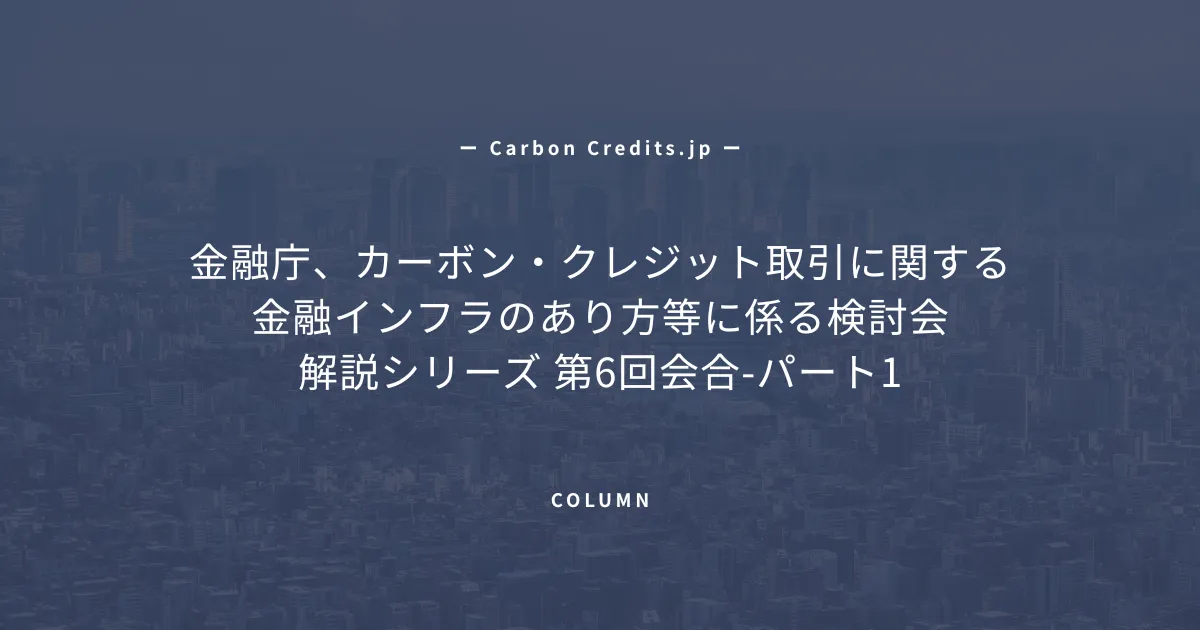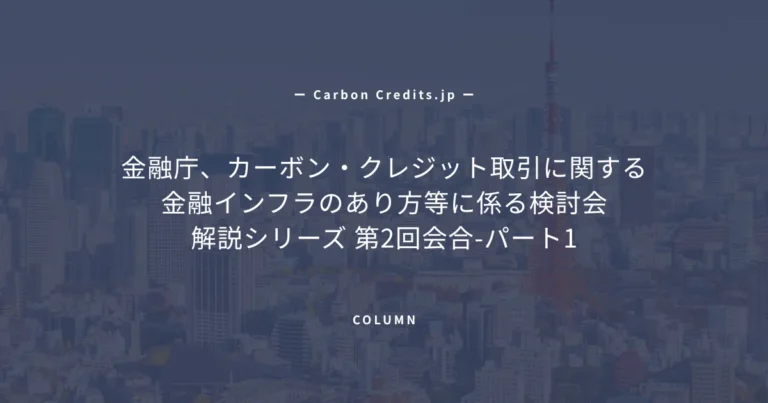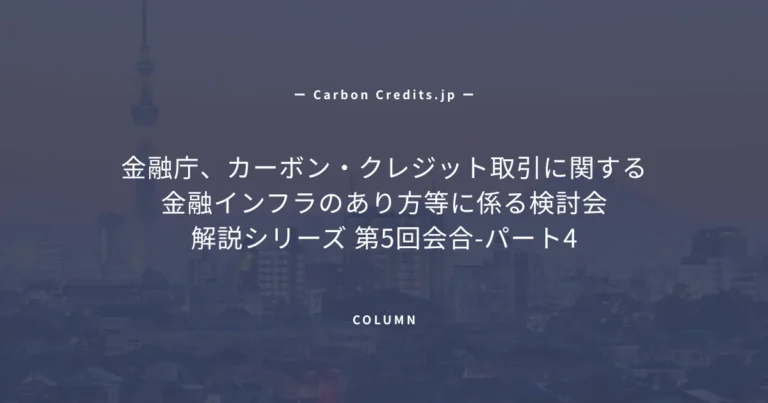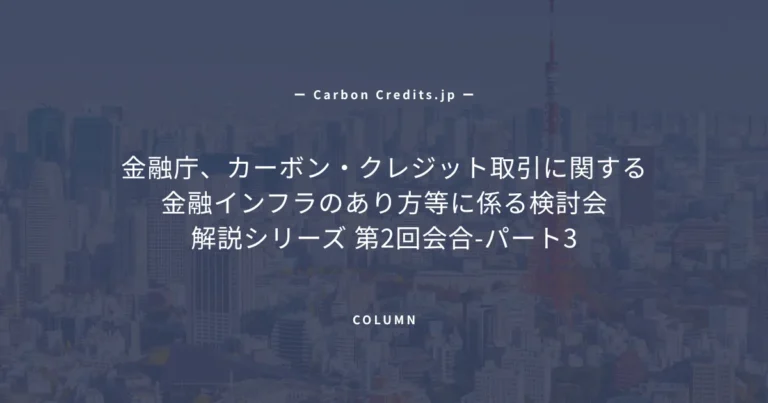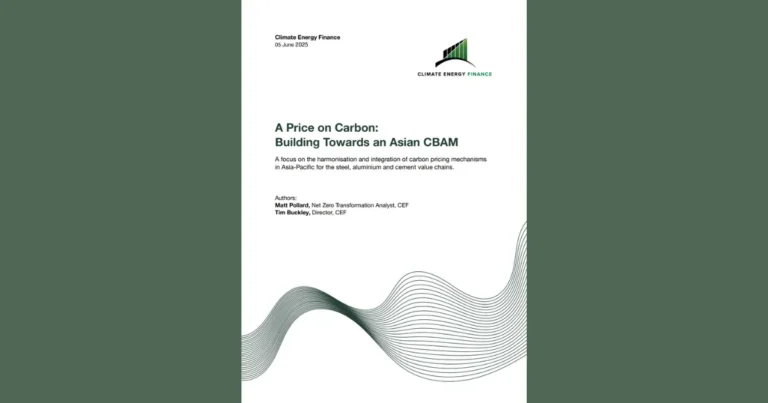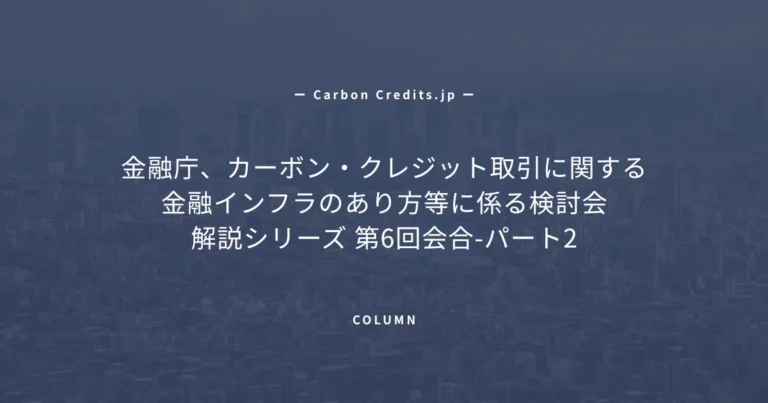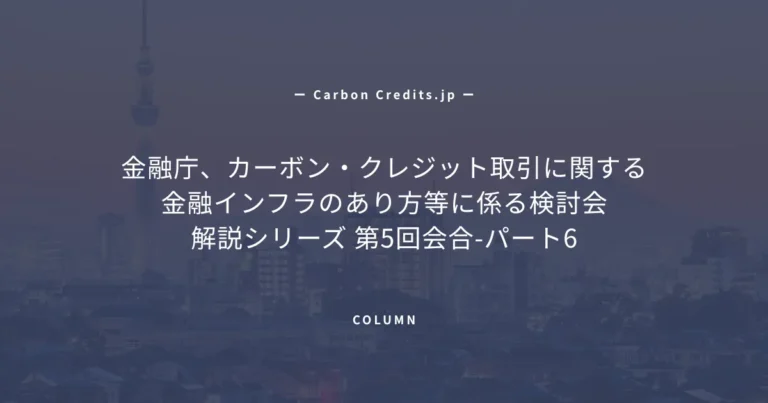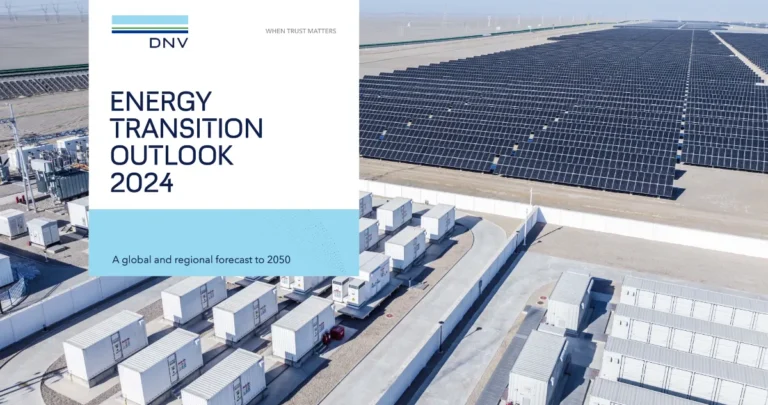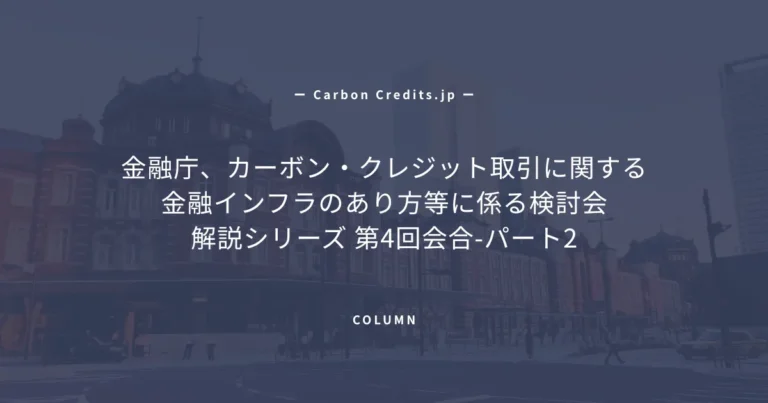金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ
第6回パート1
2025年4月11日に開かれた「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第6回)で、金融庁事務局は取引実態のストックテイクと論点整理を盛り込んだ報告書素案を提示した。
根本座長は「本日は素案の全体像を共有し、市場参加者拡大を見据えた活発な議論をお願いしたい」と呼びかけた。素案は5~6月に最終とりまとめを行い、将来的にハイレベル原則策定へ接続する工程を示している。
報告書素案の構成とねらい
素案は「取引実態把握」と「透明性・健全性向上に係る論点整理」の二部構成。
前半では国内外の金融機関・テック企業・取引所等からのヒアリングを基に、
- カーボンクレジットの組成方法(回避系・除去系 / 技術由来・自然由来)
- 信頼性(温室効果ガス削減への実質寄与)と共同便益(コベネフィット)生物多様性保全など
- 日本市場の現状(主にJ-クレジットと海外ボランタリークレジットを法人が現物取引。大企業中心で黎明期)
- 需給要因(カーボンオフセット利用や投資ニーズ、供給コストと価格見通し)
- エコシステム各機能(取引プラットフォーム、仲介、組成支援、保険・評価、テック活用)
を網羅的に整理した。
後半ではIOSCO報告書や米英の高位原則を踏まえ、論点を四つの視点に体系化している。
- 基本的事項:適切な情報開示、利益相反防止、法令遵守、取引参加者の知識・経験向上、関係者連携、法的性質・会計ルールの明確化。
- 取引仲介者・売主:買主の目的・理解度に応じた商品説明と顧客本位の業務運営、リスク管理。
- 取引所・インフラ:登録簿の正確性、公正なアクセス、オペレーショナルリスク・カウンターパーティリスク低減、商品・契約・データの標準化、デリバティブ取引を見据えた環境整備、評価機関のベストプラクティス。
- 買主:カーボンクレジット評価・保険の活用と自己責任による信頼性確認、カーボンオフセット利用時の詳細開示、まずは自社削減努力を優先する原則。
国内市場への示唆
素案は2026年度から本格稼働予定の排出量取引制度(GX-ETS)とは切り離しつつ、そこで取引量が一気に増える前に金融インフラ面で「信頼の土台」を築く必要がある、と強調する。
特に日本市場は現物中心で規模がまだ小さいため、「標準化」と「キャパシティビルディング」が成長の鍵になる。仲介者や評価機関のガバナンスも未整備な部分が多く、投資家保護の観点から早期の指針策定が望ましい。
国際的整合性と先行事例
国際機関IOSCOは2023年に21のグッドプラクティスを提示し、米CFTCはデリバティブ取引に関するガイダンスを、英国FCAはボランタリー・カーボン市場に関する高水準原則をそれぞれ公表している。
素案はこれらを参照しつつ、日本独自の制度・市場慣行との整合を図る構えだ。
今後のスケジュール
検討会は2025年5~6月に報告書を確定し、次段階としてハイレベル原則を策定する予定だ。
まとめ
第6回検討会は、取引実態と課題を整理した報告書素案を公開し、黎明期にこそルールメイクをとのメッセージを鮮明にした。
カーボンクレジット需要の急拡大と管轄環境の変化を前に、透明性と健全性を確保する金融インフラ整備が、日本のカーボンクレジット市場を国際競争力のあるプラットフォームへと押し上げる試金石となる。
最終報告の行方と、それを受けたハイレベル原則の具体化が、今後の市場参加者の戦略を左右するだろう。
次の記事:
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第6回)議事録.令和7年4月11日
参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第6回)議事次第.令和7年4月11日