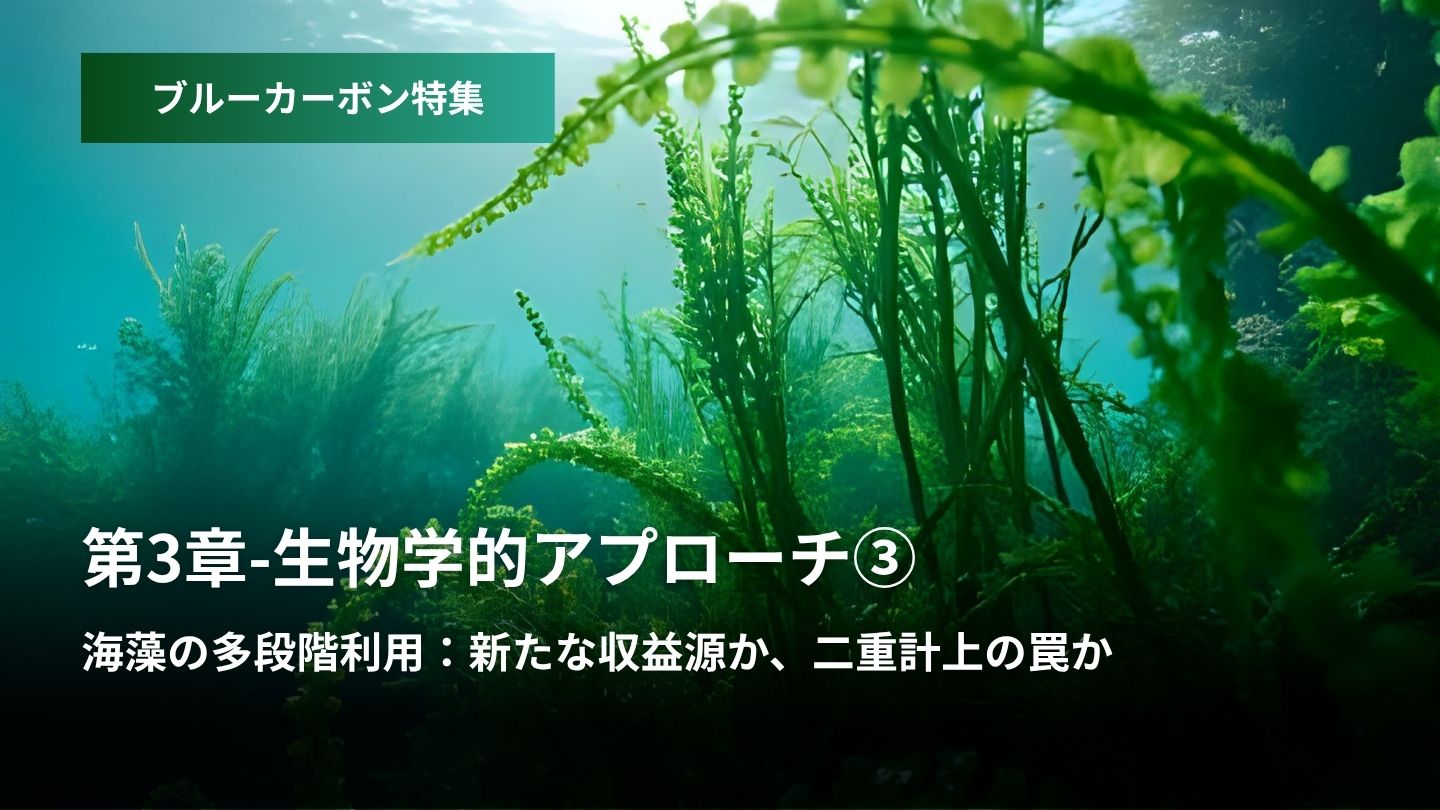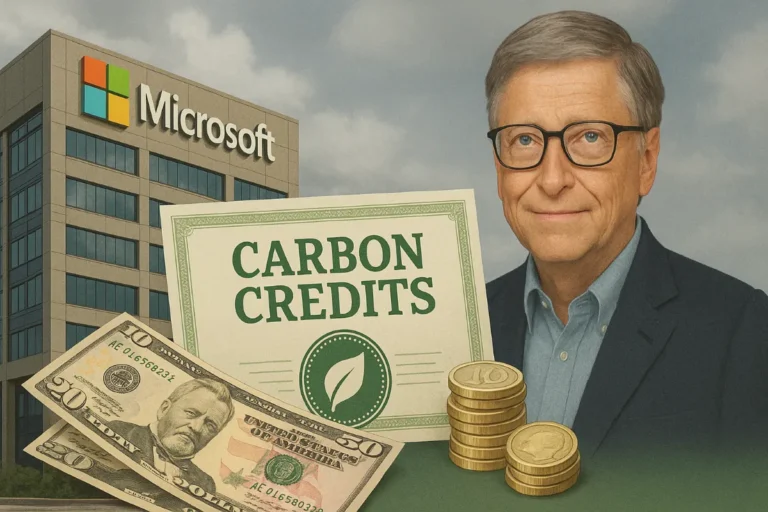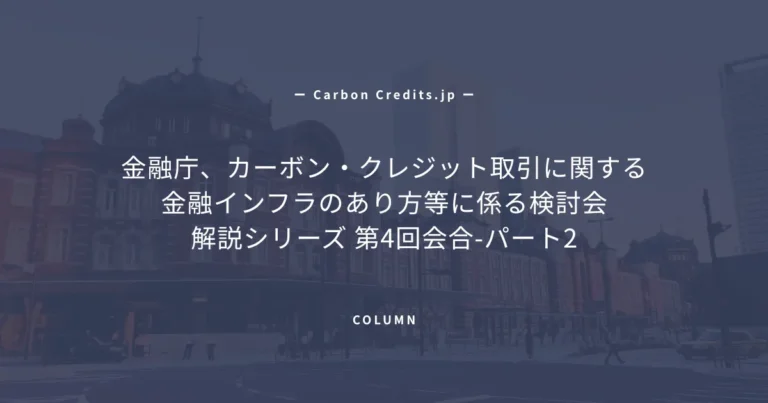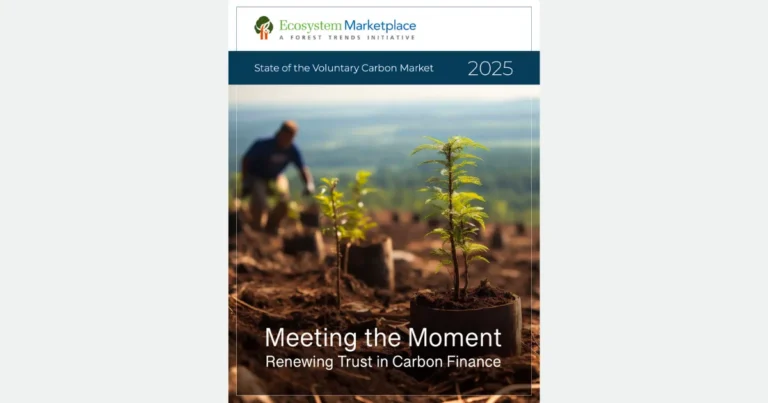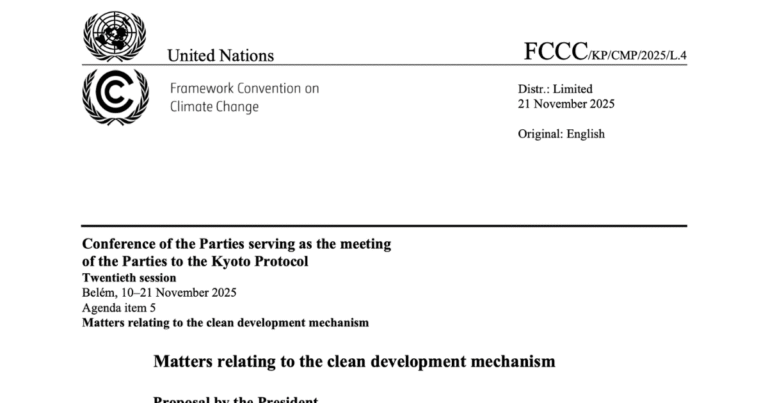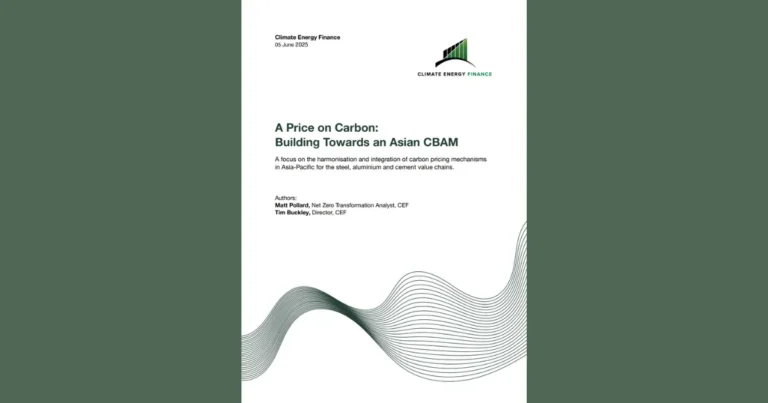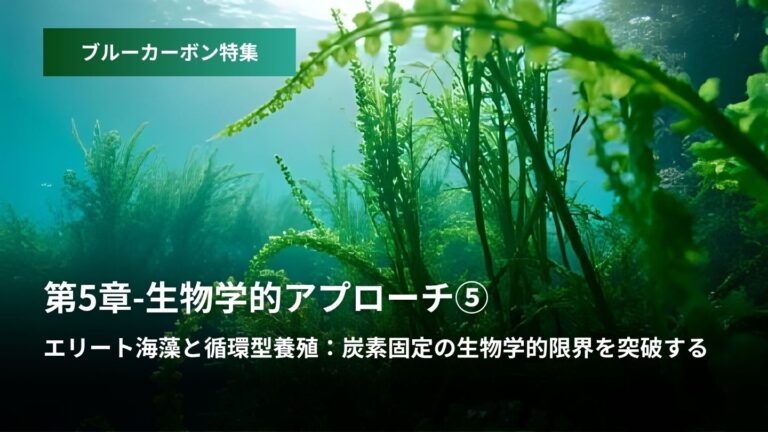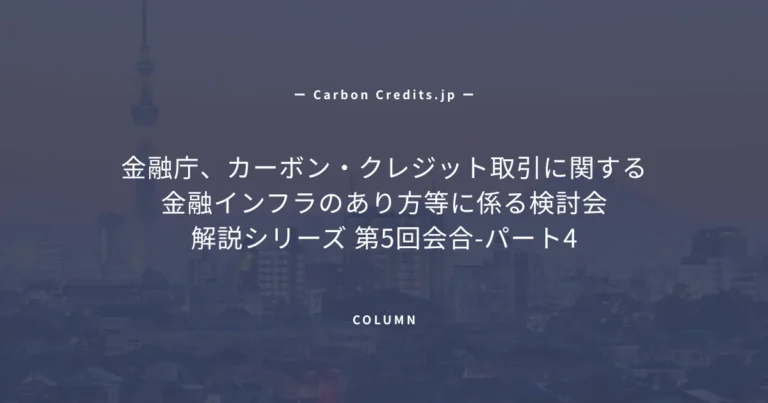【キーワード定義】
- カスケード利用(Cascade Utilization):資源を一度の使用で終わらせず、品質や価値に応じて多段階に利用すること。海藻の場合、食品→飼料→バイオプラスチック→燃料→土壌改良材といった流れが考えられる。
- ダブルカウント(Double Counting):一つの炭素削減・吸収量を、複数の主体(企業、国など)が自らの貢献として重複して主張・計上してしまうこと。カーボンクレジットの信頼性を根底から揺るがす問題。
- ライフサイクルアセスメント(LCA):製品やサービスが、原料調達から製造、使用、廃棄・リサイクルに至るまでの全段階(ライフサイクル)で、環境に与える影響を定量的に評価する手法。
【導入】
前章では、ブルーカーボンクレジット創出における最大の壁として、炭素貯留の「永続性」を証明する困難さを論じた。深海への沈降という自然プロセスに依存する方法は、科学的な不確実性とMRVコストの課題を抱えている。この課題への一つの回答として、収穫した海藻を製品化し、炭素を社会経済システム内に固定する「カスケード利用」が注目されている。
このアプローチは、新たな収益源を生み出す魅力的な事業モデルを提示する一方で、カーボンクレジット制度の根幹に関わるダブルカウントという極めて厄介な問題を引き起こす。本章では、この光と影を解き明かす。
【1. 科学的原理と国際的文脈】
カスケード利用の基本思想は、海藻が光合成によって固定した炭素を、大気中に再放出させずに、価値ある製品として活用し続けることにある。例えば、収穫した海藻をバイオプラスチックに加工すれば、その炭素は製品の寿命が尽きるまで固定される。また、家畜の飼料に混ぜれば、メタン排出量の削減効果も期待できる。さらに、最終的にはバイオ燃料として化石燃料を代替したり、バイオ炭として土壌に施用し、長期的な炭素貯留につなげたりすることも可能である。
国際動向
これは、欧州連合(EU)などが推進する「サーキュラーエコノミー(循環経済)」や「バイオエコノミー」の概念と軌を一にする。化石資源への依存から脱却し、再生可能な生物資源(バイオマス)の持続可能な利用を目指す国際的な潮流の中で、海藻は有望な原料として期待されている。
ただし、その利用が真に気候変動緩和に貢献するかを評価するため、国際標準化機構(ISO)などが定めるLCAの手法を用いて、サプライチェーン全体での炭素収支を厳密に評価することが不可欠となっている。
【2. カーボンクレジット化の論点】
海藻の製品利用は、事業性を高める一方で、カーボンクレジット化においては極めて複雑な会計規則と向き合わなければならない。
二重計上の罠
最大の問題がダブルカウントである。例えば、海藻由来のバイオ燃料を製造したとする。この場合、①海藻を育ててCO2を吸収したブルーカーボン事業者と、②そのバイオ燃料を使用して化石燃料の使用を削減した航空会社、この両者が「CO2を削減した」と主張できてしまう可能性がある。これはカーボンクレジットの信頼性を損なうため、ベラ(Verra)などの国際基準では固く禁じられている。
誰がクレジットを主張できるのか
一般的に、カーボンクレジットは「化石燃料を代替した」という排出回避、削減または除去活動に対して発行される。つまり、上記の例では航空会社側がカーボンクレジットを主張する権利を持つ。ブルーカーボン事業者は、海藻を「原料」として販売した対価は得られるが、固定・除去した炭素をCDRクレジットとして別途販売することは原則としてできない。
システム境界の設定
カーボンクレジットを申請するには、LCAに基づき、どこからどこまでをプロジェクトの活動範囲(システム境界)とするかを明確に定義する必要がある。海藻の育成から加工、輸送、最終製品の使用、廃棄までの全工程で発生するCO2排出量を算出し、それを差し引いた純粋な削減・吸収量を算定しなければならず、極めて煩雑な作業となる。
【3. 日本市場の展開と政策環境】
日本政府も「バイオマス活用推進基本計画」などを通じて、国内のバイオマス資源の利用を促進している。特に、既存の養殖技術を応用できる海藻は、食料安全保障とエネルギー問題の双方に貢献する可能性を秘めている。
日本市場
国内では、商社や化学メーカーが中心となり、海藻由来のバイオプラスチックやバイオ燃料の開発を進める動きが見られる。例えば、微細藻類ユーグレナはバイオジェット燃料としての実用化を目指している。しかし、これらの活動をJブルークレジットやJ-クレジット制度でどう評価するかについては、まだ明確な方法論が確立されていないのが現状である。
特に、異なる産業セクター間での排出削減量の帰属をどう整理するかは、今後の制度設計における大きな課題となっている。
現時点では、製品利用によるカーボンクレジット創出を目指すよりも、製品自体の付加価値(「環境配慮型製品」としてのブランディングなど)を高める戦略が現実的と言える。
【4. 経済的実行可能性とリスク】
カスケード利用は、事業の多角化と安定化に寄与する。
コスト構造と収益モデル
収益源がカーボンクレジット単体でなく、「製品販売収益+環境価値」となるため、炭素価格の変動に左右されにくい安定した事業モデルを構築できる可能性がある。しかし、製品化には高度な加工技術や大規模な設備投資が必要となり、初期コストは高くなる傾向がある。
市場リスク
製造したバイオ製品が、既存の化石燃料由来製品に対して価格競争力を持つかが事業の成否を分ける。技術開発によるコストダウンと、環境価値を価格に転嫁できるかが鍵となる。
会計上のリスク
前述の通り、カーボンクレジットの会計ルールは複雑で、将来的に変更される可能性もある。二重計上と判断され、期待していたクレジット収益が得られなくなるという規制リスクは常に念頭に置く必要がある。
【5. 今後の展望と次ステップへの布石】
海藻を価値ある製品へと転換するカスケード利用は、ブルーカーボンを持続可能な産業へと昇華させる大きなポテンシャルを秘めている。しかし、カーボンクレジットという観点では、ダブルカウントの問題を回避するための厳格な会計ルールが障壁となる。
このジレンマを乗り越えるには、二つの方向性が考えられる。一つは、より大規模に海藻を生産し、加工コストを抜本的に下げること。もう一つは、製品利用ではなく、より直接的で永続性が高く、かつダブルカウントの懸念がない炭素貯留方法を確立することである。
沿岸域での養殖には限界があり、より広大な沖合へと生産の場を移し、そこで収穫したバイオマスを安定した形で炭素として固定する。この「大規模化」と「新たな固定技術」こそが、次章で探求するテーマ、すなわち沖合養殖とバイオ炭化技術である。
【ブルーカーボンクレジット創出への接続】
認証スキームとの関係
本章の論点は、プロジェクトのシステム境界の定義とダブルカウントの回避に直接関わる。ベラなどの方法論では、LCAに基づき、プロジェクト活動が他の排出削減活動に与える影響を考慮することが厳しく求められる。製品利用を伴う場合、これは最も重要な評価項目となる。
カーボンクレジット発行プロセスにおける役割
この知識は、プロジェクトが除去と回避・削減のどちらに該当するのかを判断し、カーボンクレジットの算定方法論を決定する上で不可欠である。プロジェクト設計の初期段階でこの点を誤ると、後の検証プロセスで承認が得られなくなる可能性が高い。
次ステップとの関係
カスケード利用が直面する二重計上の複雑さは、よりシンプルで永続的な炭素貯留方法の必要性を示唆する。次章で扱う「沖合養殖」は生産規模の壁を、「バイオ炭化技術」は永続性とダブルカウントの問題を同時に解決しうるアプローチとして、これまでの課題に対する一つの解を提示する。