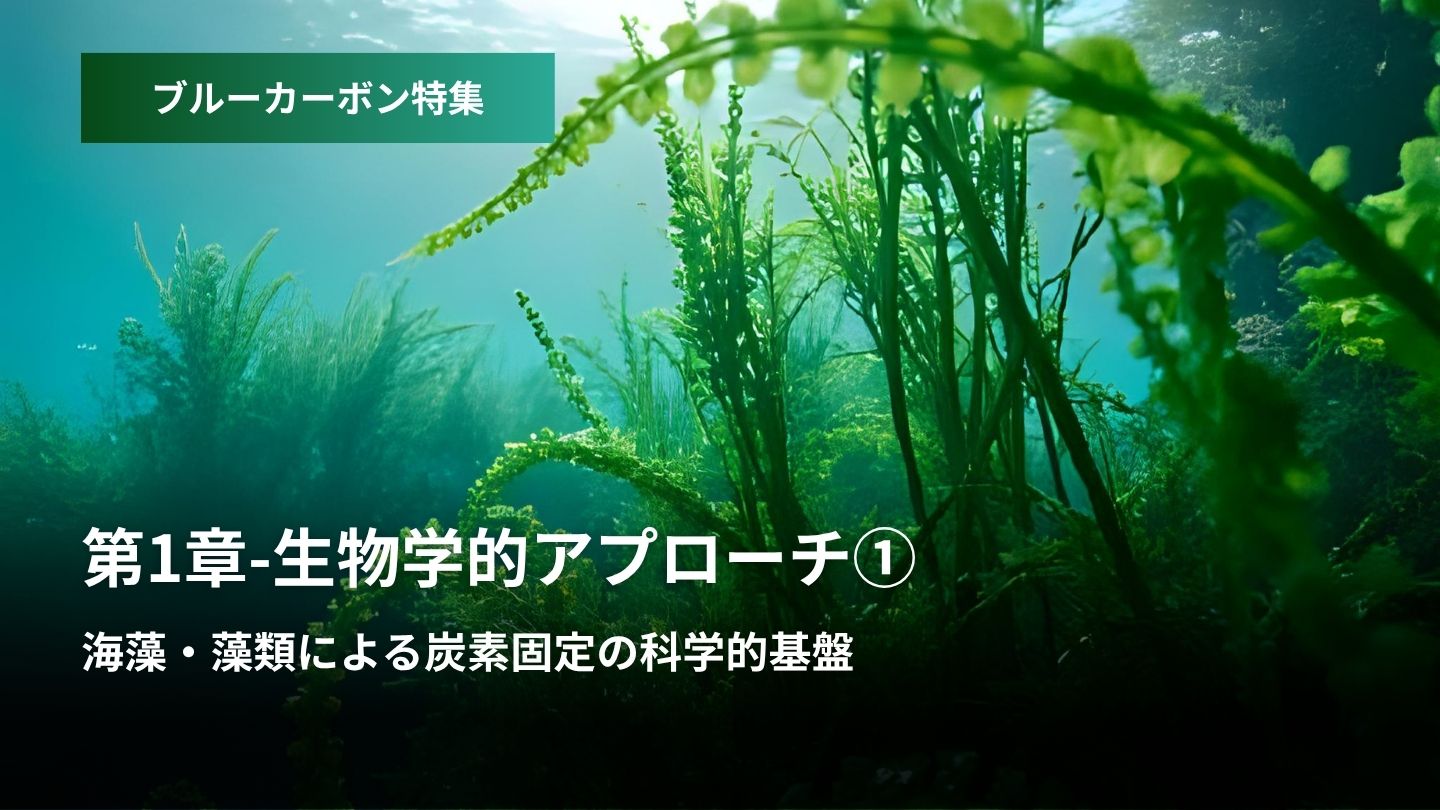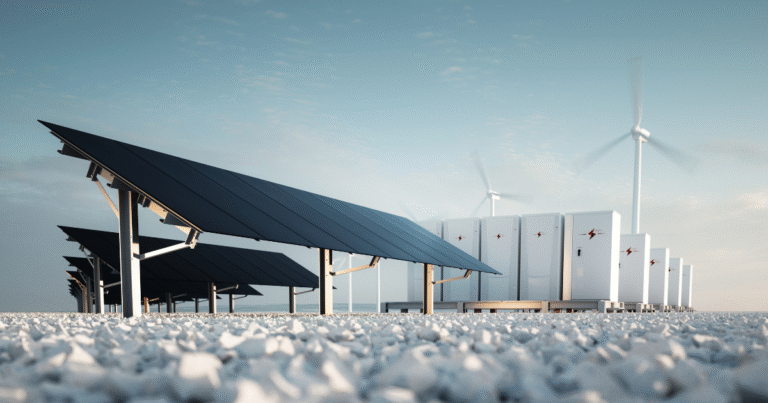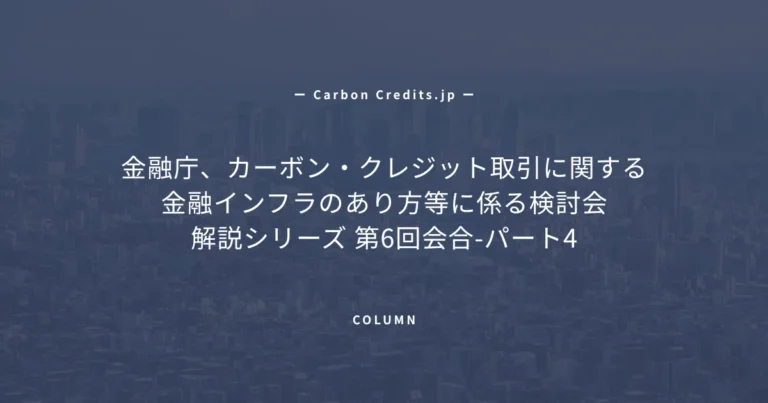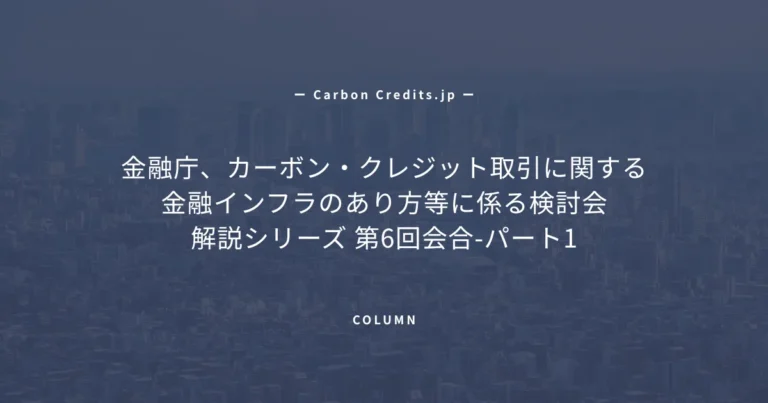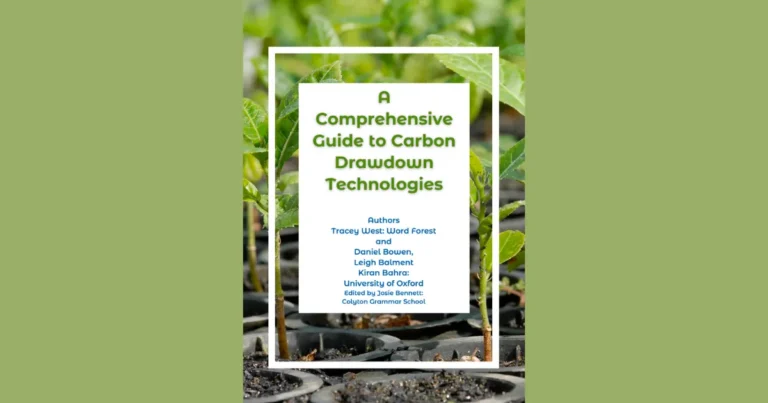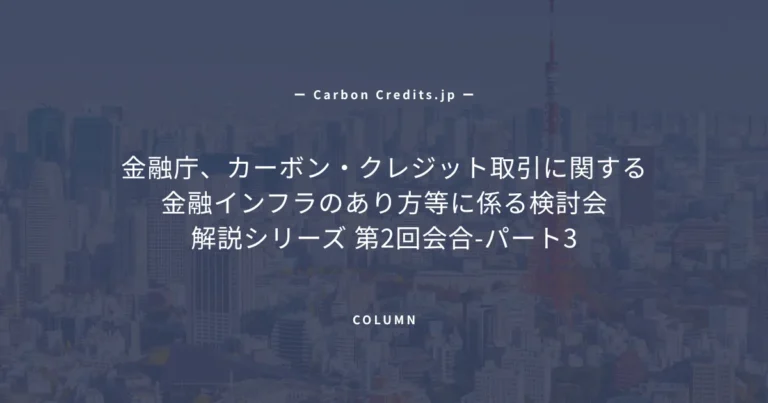【キーワード定義】
- ブルーカーボン(Blue Carbon):海洋生態系(マングローブ林、塩性湿地、藻場など)によって吸収・貯留される炭素のこと。
- 光合成(Photosynthesis):植物や藻類が、光エネルギーを利用して二酸化炭素(CO2)と水から有機物(炭水化物など)を合成する化学反応。
- 炭素固定(Carbon Fixation):気体である二酸化炭素を、生物が有機化合物へと変換し、体内に取り込むプロセス。
【導入】
気候変動対策が世界の最重要課題となる中、大気中の二酸化炭素(CO2)を吸収・除去する「ネガティブエミッション技術」への期待が高まっている。その中で、広大な海洋のポテンシャルを活かす「ブルーカーボン」は、自然に基づく解決策(NbS)の核心として、今やカーボンクレジット市場や国家の気候戦略において無視できない存在となった。
本連載では、ブルーカーボンクレジット創出の科学と実務を体系的に解説していく。
その第一歩として、本章では最も基礎となる「生物学的アプローチ」の出発点、すなわち海藻や植物プランクトンといった藻類が、どのようにしてCO2を吸収するのか、その科学的メカニズムと多様性に焦点を当てる。この炭素固定の第一段階を正確に理解することこそ、信頼性の高いカーボンクレジットを創出するための絶対的な前提条件である。
【1. 科学的原理と国際的文脈】
ブルーカーボンの根幹をなすのは、海洋生物による「光合成」である。特に、沿岸域に広がるコンブやワカメなどの大型海藻から、海洋の基礎生産を支える微細な植物プランクトンまで、多種多様な藻類がこのプロセスを担う。
彼らは太陽光をエネルギー源として、海水に溶け込んだCO2を吸収し、自身の体を作る有機物(バイオマス)へと変換する。この一連のプロセスが「炭素固定」である。
国際動向
IPCCの第6次評価報告書では、海洋が人為起源のCO2の約25%を吸収してきたと指摘されており、ブルーカーボン生態系の保全・再生が気候緩和策として重要視されている。また、アメリカ海洋大気庁(NOAA)は、これらの生態系が陸上林よりも単位面積あたりで高い炭素貯留能力を持つ可能性を報告しており、国際的な研究開発が加速している。
【2. カーボンクレジット化の論点】
藻類の成長による炭素固定は、カーボンクレジット化に向けた第一歩に過ぎない。そのポテンシャルを具体的なカーボンクレジット価値に転換するためには、国際的な認証基準が定める厳格な要件をクリアする必要がある。
測定・報告・検証(MRV)
最大の論点は、広大で常に変動する海洋環境において「どれだけの炭素が、いつ、どこで固定されたか」を科学的・定量的に測定し、報告し、第三者が検証できるかという点にある。生育速度、バイオマス量、炭素含有率などを正確に把握するモニタリング手法の確立が不可欠である。
追加性(Additionality)
プロジェクトを実施したことによって、ベースライン以上に炭素固定量が増加したことを証明する必要がある。単に既存の藻場を維持するだけでなく、能動的な藻場造成や養殖といった介入が求められる。
永続性(Permanence)
固定された炭素が、大気中に再放出されることなく、永続的に(通常100年以上)貯留されることが絶対条件となる。藻類が枯死した後の炭素の行方こそが、カーボンクレジット化の成否を分ける。この点は次章以降で詳述する。
【3. 日本市場の展開と政策環境】
四方を海に囲まれ、世界第6位の広大な排他的経済水域(EEZ)を持つ日本にとって、ブルーカーボンの潜在性は極めて大きい。古くから海苔やコンブ、ワカメなどの海藻養殖業が盛んであり、既存の技術や知見を応用できる土壌がある。
日本市場
政府は「みどりの食料システム戦略」などでブルーカーボンの活用を掲げており、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が中心となり、クレジット制度「Jブルークレジット」の運営が進められている。
これは、藻場の造成や保全活動によるCO2吸収量を認証し、カーボンクレジットとして売買可能にする国内独自の仕組みである。JAMSTEC(海洋研究開発機構)などの研究機関も、日本周辺海域における炭素循環メカニズムの解明や、効率的なモニタリング技術の開発を推進。
自治体や民間企業が連携し、全国各地で藻場再生の実証プロジェクトが始まっているが、その多くはまだ小規模な実証段階に留まっているのが現状だ。
【4. 経済的実行可能性とリスク】
海藻養殖をベースとしたブルーカーボン事業は、単なる炭素固定に留まらない多面的な価値を持つ可能性がある。一方で、事業化にはコストとリスクが伴う。
コスト構造
主なコストは、
- 苗の生産・育成
- 沖合での養殖施設の設置・維持管理
- 収穫
- MRV(特にモニタリングと第三者検証)にかかる費用
である。特に、科学的信頼性を担保するためのMRVコストがプロジェクト全体の収益性を大きく左右する。
収益性
収益源は、カーボンクレジットの売却が主軸となるが、炭素価格の変動リスクを伴う。そのため、収穫した海藻を食品、飼料、バイオ燃料、化粧品原料などへカスケード利用(多段階利用)することで、複数の収益源を確保し、事業の安定性を高める戦略が重要となる。
リスク要因
海水温の上昇や海洋酸性化といった気候変動そのものが、海藻の生育を脅かすリスクとなる。また、病害や赤潮の発生、台風による物理的被害も考慮しなければならない。
【5. 今後の展望と次ステップへの布石】
海藻や微細藻類が持つ炭素固定能力は、ブルーカーボンの巨大なポテンシャルを示す原点である。育種による高成長・高炭素吸収品種の開発や、沖合での大規模養殖技術など、炭素固定の効率を高める研究は今後さらに加速するだろう。
しかし、繰り返しになるが、炭素を固定するだけではカーボンクレジットとして認められない。重要なのは、その有機物(バイオマス)が最終的にどうなるかである。大気中にCO2が再放出されることなく、いかにして長期間、生態系に貯留されるか。この永続性の問いに答えることこそ、生物学的アプローチの核心であり、次章のテーマとなる。
【ブルーカーボンクレジット創出への接続】
認証スキームとの関係
本章で解説した「炭素固定メカニズムの理解」は、ベラ(Verra)やゴールドスタンダード(Gold Standard)などの国際認証スキームにおけるMRVと追加性の要件を満たすための基礎となる。プロジェクト設計書(PDD)において、どのような科学的根拠に基づいて炭素吸収量を算定するのか、その計算ロジックの根幹をなす部分である。
クレジット発行プロセスにおける役割
この知識は、プロジェクトのベースラインシナリオ(何もしなかった場合にどうなるか)とプロジェクトシナリオ(事業実施によってどれだけ炭素が追加で固定されるか)を設定する初期段階で不可欠である。また、モニタリング計画を策定する上で、「何を」「どのように」測定すべきかを定義する土台となる。
次ステップとの関係
本章は炭素の「固定」に焦点を当てた。しかし、カーボンクレジット化で最も厳しく問われるのは、次章のテーマである炭素の「貯留」、すなわち永続性の証明である。固定された炭素が、いかにして100年スケールで隔離されるかを理解しなければ、プロジェクトは成立しない。